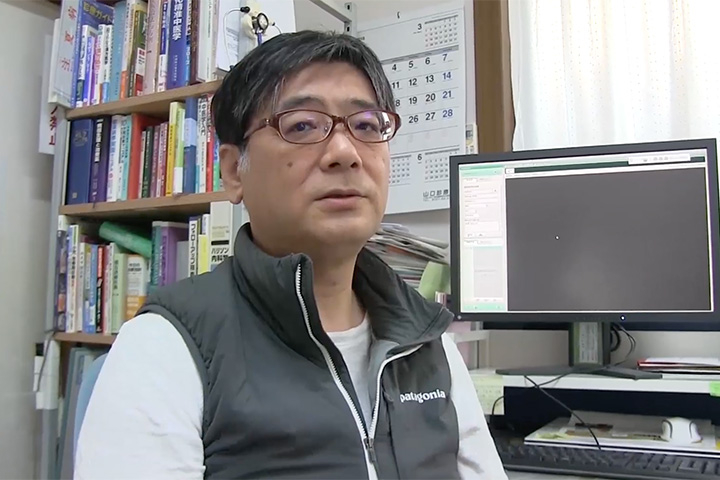▲熊本県山鹿市にある芝居小屋、八千代座での認知症の研修会の様子。最前列に講師の面々が並ぶ。「認知症」を語る講師それぞれの課題への共有と共感に満ちた聴衆である専門職の表情に浮かぶものは何か。「認知症」はここに届き、ここから積み上げられ地域社会を創り上げる。
熊本県山鹿市で、熊本県の介護専門職の研修会に参加してきた。
こうしたイベントなら、普通、公共施設のホールなどが一般的なのだろうが、今回は会場が山鹿市にある明治の芝居小屋、八千代座である。国の指定重要文化財だ。
この、地域の歴史的建造物での研修会だったことが、期せずして、今の認知症や認知症の介護専門職を取り巻く現実を考える視点を与えてくれたようである。
八千代座というのは、かつての参勤交代をはじめとする交通の要衝だった山鹿市が誇る文化財だ。一歩、八千代座の内部に踏み入ると、タイムスリップする。見上げれば天井絵は全て広告絵で、当時の地域産業の興隆がうかがえ、客席は昔ながらの枡席。花道が楽屋から舞台に伸び、舞台は回り舞台である。
その舞台で研修会が開かれたのだ。
主催と共催が、熊本県介護支援専門員協会と熊本県介護福祉士会で、この研修自体が、主任介護支援専門員更新研修でもある。つまりは華やかな八千代座の舞台であるが、ここでの研修は、ケアマネジャー、介護職、介護福祉士、社会福祉士といった専門職のそれぞれが、地域社会の現実とどう向き合い、動かしていくのかという切実な思いが込められていた。
舞台で語り合ったのは、地域包括支援センターの運営者や、高齢者施設の施設長など現場での指導的な立場の専門職であり、枡席にギッシリとつめかけたのも、それぞれの地域で認知症の人、高齢の人と向き合う専門職である。
この国は少子超高齢社会の只中で、確定的な展望を描くことができないまま、誰もが不安と怯えの中に未来を見つめている。
東京にいると、いつもどこかの会議室でこの課題への論評が行き交い、大きなホールでは著名な関係者によるシンポジュームが熱を帯びる。そのこと自体は大きな意味合いがあり、様々な声が時代に多大な影響力を持っていることは間違いない。ただ、大きな規模であるがゆえ、終わって「やれやれ、素晴らしい話し合いでしたねえ」の感想で閉じてしまう。評論の向こうに当事者性が沈み込む。
地域での話し合いは朴訥ながら、当事者が前面で評論は出番がなく、そこでの話し合いは直ちに地域の現実に結びつく。
熊本県の人口5万人の山鹿市の回り舞台の壇上で、地域の専門職が語るのは、自分史からだった。例えば・・・
「私が認知症と出会ったのは、20数年も前、鍵のかかっている痴呆棟だった。その時はそこに入るのも嫌だった。と同時にこれはどこか違うのではないか、と感じていた。その後、在宅訪問で生活の場の認知症高齢者の介護をするようになって、あの時のどこか違うという感じが、自分の中で明らかになったように思う」
枡席の同じ専門職の聴衆に向かって、小さく告白するように彼は語り、聴衆は身じろぎもせず聴き入る。東京の会議室での話し合いでは、「認知症とは」という語り口が多いが、ここ山鹿の舞台では誰もが、「私は」と始めて、認知症を語る。
図式的に言えば、「トーキョー」の「認知症」と、地域に向き合う専門職の語る「認知症」とは、同じ「認知症」でありながら、その背景も文脈も大きく異なる。
地域で語られる「認知症」には、常に現実の人の顔がある。あの村のおばあちゃんであり、前の区長さんだったり、酒屋の爺さんだったりする。
ここにあるのは、介護の原点とも言える関係性である。
それぞれの個人史が行き交う「地域」というのは、別の言い方をすれば「関係性」で成り立ち、それを当たり前の前提としているのが地域の暮らしなのである。
京都西陣で「わらじ医者」と言われ街の隅々までを巡りながら「地域医療」を確立し、世間の尊崇を集めた早川一光医師は、「地域」についてはこう語った。
「ひとりが一人と出会う。その関係をつなげていく。そこに支え支えられの思いと力が生まれる。そのつながりが「地域」を創る。地域は、人と人の「間」をつなげる。だから「人間」であり、人間のつながりが「地域」を創る。行政が作るわけではない」
以前、介護専門職の役割としては「入浴、排泄、食事」の三大介護が言われていたが、平成19年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正でその三大介護を、「心身の状況に応じた介護」とし、さらに「個人の尊厳」「自立」、そして医療や地域だけでなく「他のサービス関係者との連携」とてんこ盛りである。
専門職の裁量への期待ともいえようが、どうも「そこんとこ、なにとぞよろしくね」と、この社会の「共生」も「当事者性」も「地域社会」も、少子超高齢社会の課題全ての、専門職への丸投げのようでもある。
この社会を「トーキョー」的発想、つまりは行政主導でどこまで担うことができるのか。
「認知症になっても住み慣れた地域での安心の暮らし」の肝心の地域包括ケアは、単独高齢者、高齢者世帯の孤立や貧困へ届く機能うすく、結局特養やグループホームなどの入所型サービスへの依存だけが突出してしまっている。
「地域」の関係性の価値は目に見えず、あたりまえ過ぎて、「公共財」として地域の人に認識されることはあまりない。しかし、そこでの故郷の風景や顔なじみの人間関係の「財」としての豊かさは、計測不能なほどに大きい。東北地方というのは、経済指数で言えば、確かに豊かさは低いのかもしれない。しかしそこでの豊かな文化と人々の暮らしは、東日本大震災で失われた時、どれほどかけがえのないものであったのか、誰もが心に刻んだはずではないか。
地域の介護課題は重い。人材不足、待遇、過疎と財源、その中で研修会で語られた「認知症」は、人間のつながりの再生と維持であり、それはそのまま制度の限界を打ち破り、地域社会の再生への実践と覚悟となった。
「認知症」は、介護という分野の中だけで語るのでなく、自分たちの暮らす地域の中の現実と向き合うことでしか語れない。地域で語られる「認知症」は、目には見えない公共財である人と人とのつながりを前提としている。そこには制度施策のなかの「認知症」ではない「ジブンゴト」の息づかいがある。
専門職もまた課題はあるだろう。濃密な関係性は善意と思いやりの中、ともすれば本人主体を奪ってしまうことがある。認知症の人の声に耳を傾けながら、自身のケアを検証し続ける姿勢が必要だ。
八千代座で語られた「認知症」は、実は専門職だけでなく住民とともにいかに主体的に自分たちのコミュニティを作り直していくのか、「認知症」がその問いかけであるということだった。
「認知症」は当事者発信が大きく時代を切り拓いた。それを受ける形での「認知症」の地域発信が始まっていい。「認知症」は、こうした地域の実感から立ち上げ、専門職たちの地に足をつけた実践から地道に積み上げていく必要があるだろう。
明治に建てられた八千代座は、その後、時代から取り残され荒れ果てた。屋根に穴が開き、朽ちるがままになるかと思われた。心を痛め、起ち上がったのは高齢者だった。華やかだった八千代座を知るお年寄りにとって、それは自分たちの地域のシンボルであり地域再生の思いだった。そこに若者が加わった。世代を超えて八千代座をよみがえさせる取り組みは30年に及んだ。
コミュニティは、そこで暮らす誰もの主体的な取り組みの中で再生され、維持されていく。
八千代座で語られた「認知症」は、芝居小屋に宿る祖霊に見守られるようにして、それぞれの地域の専門職の胸に託された。
|第93回 2019.2.5|