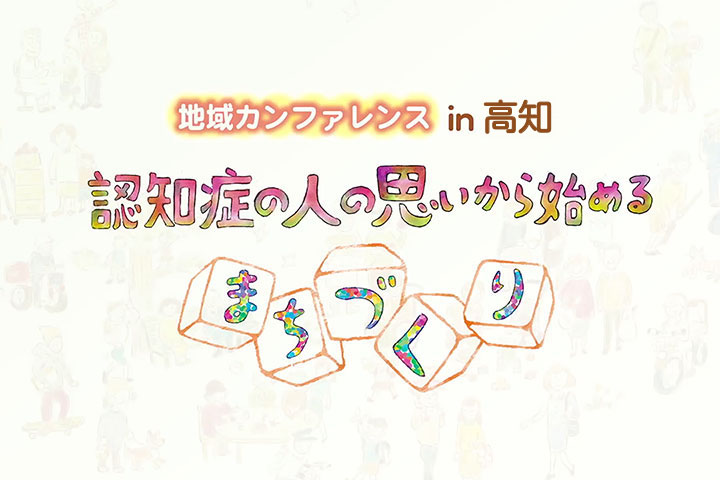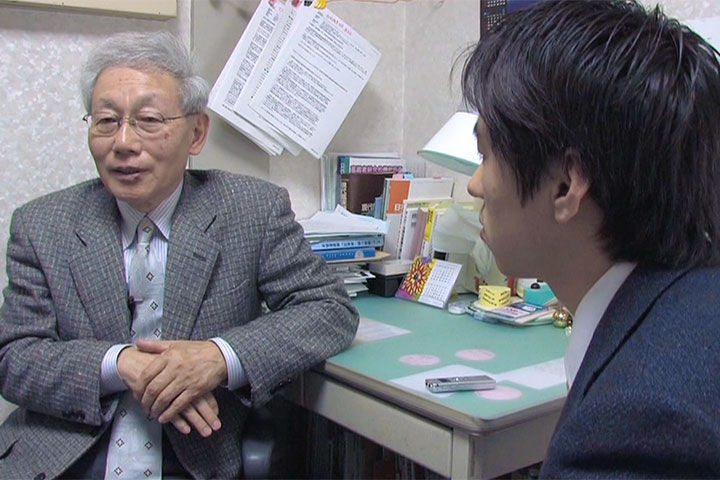▲ 認知症当事者勉強会の世話人会で熱く語る中島紀恵子さん。「認知症ケア」の生みの親と言っていい。中島さんは「学び」「学び合い」とよく言う。11月16日に三鷹で中島紀恵子さんとともに語り合う勉強会がある。「認知症ケア」の学び合いの場だ。
「コトバで語らなければ、カタチにならないのよ。もっと語り合ってコトバを探すの」
中島紀恵子さんは頬を紅潮させ、そう語った。
中島紀恵子さんは、この国に「老年看護」「認知症ケア」を創り出した最大の功労者の一人だ。1987年に「社会福祉士及び介護福祉士法」が出来た。現在のソーシャルワーカー、ケアワーカーの国家資格が定められた法律だ。なんせ、それ以前のこの分野の資格は社会福祉主事と保母の二つしかなかった。
法律はできたものの、では「介護福祉士」とはどんな存在なのか、教育や実践につながる理論が空白だった。そこで、「あなたは看護をやっていたのだから、介護も考えてほしい」ということで、当時、日本社会事業大学(厚生省立の大学で、社会福祉の東大とも称され、ここから多くの社会福祉の人材が輩出した)に老年福祉の教授として招聘されていた中島紀恵子さんに、国が「押しつけた」ということらしい。
「看護やっていたから、介護を考えろって何よ💢」と中島紀恵子さんは怒りながらも5年間、社会事業大学で懸命に、何もない地点から介護福祉の土台を創り上げたと、回想している。30年以上前のことだ。
だから、中島紀恵子さんの語る「認知症ケア」は、老年看護から、介護福祉、そして認知症へと、現実と歴史をぶあつく引き継いでいる。そこには常に「老い」や「生活の場」からの発想、介護と援助、自立といった「コトバ」自体に、この現実社会の底深くにまっすぐ降ろす碇の重みがある。
その中島紀恵子さんと「認知症ケア」を語り合った。仲間と開く認知症当事者勉強会の世話人会での語り合いだった。
今、なぜ「認知症ケア」なのか。
「認知症とともに生きる」時代は、認知症ケアにとっては自身を問い返すことになった。
認知症の人は、行政、医療や介護での、「支援や対策」の対象として語られるのではなく、主体を持った地域の同じ生活者と位置付けられた。
「介護」という言葉もまた、その庇護するニュアンスに敏感に反応し「ケア」とされ、社会と時代の変化のさまざな要素が「認知症ケア」に投影された。
新オレンジプランの、「認知症にやさしい地域づくり」「認知症の人とその家族の視点の重視」があり、そこに認知症当事者の発信がさらに盛んになっていく。
それを受けて、「認知症フレンドリー社会」「認知症とともに生きる」が熱気を持って提唱され、これこそがこの社会を拓くモデルであろうと、認知症の時代は、ケアモデルから共生モデル、コミュニティモデルへと大きく舵を切った。
では、そのとき「認知症ケア」はどこにいればいいのだろう。専門職はなにができるのだろう。
地域で「ともに生きる」というとき、認知症の人にとっては隣人や住民のさりげない振る舞いがどれほどのケア力であるか、暮らしの中での相互承認や地域参加感は、実は社会福祉の枠組みの介護や支援では得られないはるかに大きな力を、認知症の人々に実感させた。
そこにソーシャルワーカーを含む専門職のジレンマがある。
専門職としての「名のり」は、どこか認知症の人との関係性に距離を生むのではないか。
認知症の人と対等、水平な関係性の上に初めてその人との相互作用としてケアが成立するのではないか。その人の自立生活は、地域の生活の場という舞台がなければ持続しないとしたら、施設の「専門職」には何が期待されているのだろうか。
そのあたりのジレンマの深層は、私にはうかがい知れない。
ただ、断片的に聞こえてくる声にはこんなものもある。では、進行した認知症の人、あるいは寝たきりの人のケアをどうするのか、そのことを考えているのだろうか、といった声。
そうした身辺介護に比重が大きいケアは誰が担うのか。これまで家族が「扶養」という圧力で担わざるを得なかった家族介護を、介護の社会化のもとに、誰が担っているのか。専門職ではないか。「困った時の専門職」は、暮らしの安全保障であるはずだが、どこか自嘲も混じる。
「認知症とともに生きる」の美しい言葉は、その底で懸命に支える専門職と家族がいることで初めて掲げることができるわけで、ただ理念を笑顔で言い交わす人々は、結局「いいとこ取り」しているだけではないか。
いや、いくらなんでもこれは意地悪に過ぎる脚色なのであろう。
現実には、それぞれの専門職は精密に統合されたケアの形を模索している。専門職として先駆的な取り組みを展開する一群の人々は、ある時には「認知症ケア」の枠組みを外れ、自分を、認知症の人の「友人」として規定することから組み立てる。町田のBLG!の前田隆行さんがその筆頭だろう。
あるいは逆に、施設での専門職の中にはあえて「利用者」との関係性を、対等であるとか水平とかいう言葉に絡み取られることをいさぎよしとはしない人々もいる。
「利用者」がいて、その人の困難を解消する「専門職」がいるという「立場性」に立脚する。関係性というより機能主義であるかもしれない。
専門職としての専門職能が発揮されるのは、その明確な立場があればこそであるとする。ここでの立場というのは、もちろん支配被支配の関係ではない。あくまでも認知症の利用者の暮らしの支障を解消する「技量」を持つのが専門職とする。すでに言葉や表現でのコミュニケーションが難しい進行した認知症の人については、その人の「意思決定支援」につなげるための濃厚な「意思表出支援」の技能を駆使する。
その根源には、パーソンセンタードケアやバリデーションといった思想や技能が位置するとしてもいいのだろう。その人の思いをどうくみあげ、実際のケアをするか、それこそが専門職の機能であり、さらに言えば、拘束や虐待という負の現実の改善をも担うのが専門職だとする。それは、国家資格を持つものとしてのプロであるという矜持で、たかだかとしたプライドもうかがえる。
あるいは、こうした類型化には意味がなく、実践の現場での柔軟な組み合わせこそがチームケアの力とする人も多いだろう。
しかし、こうした現場裁量的な実践は、この社会総体に向かっては見えてこない。私たちは、認知症ケアの何に期待すればいいのか、地域は、認知症ケアのどこにつながればいいのか、そこがわからない。
一つには、認知症ケアの多義性があるだろう。それぞれがそれぞれの認知症ケアをイメージし、取り組んでいる。制度から語るか、認知症本人の視点から見るか、介護する家族の側から考えるか、医療や社会福祉の視点もある。多義は難しさであると同時に可能性だとしても、それでも社会総体から照射すれば、「認知症ケア」は見えていない。
少子超高齢社会の不可欠の資源が、制度行政と社会福祉関係者の中だけでしか語られていないのではないか。
だからこそ、中島紀恵子さんなのである。
中島さんは、30数年前、介護福祉と介護教育に心血をそそぐように創り上げ、そのことが自分の人生を変えたという。そこで獲得したのは、介護教育の現場で実践をどう言葉にするかということでもあった。
「受動」という言葉がある。ともすれば消極的態度とされる言葉だが、これを中島さんは、これこそが介護の秘訣だという。「受動」、受けて、そして動く。待って待ってそこから何かを受け止めつかんで、そして「動く」。これが介護だ、と。だから、「受動」と「能動」は相反する言葉ではない。ともに深く結びつく実践なのよ、とそう言う。
「人間」の言葉だ、と思う。人と人の「間」をつなげていく「人間」の言葉だ。
1983年に中島紀恵子さんが監修した記録映画「ぼける」がある。千葉の当時の呆け老人をかかえる家族の会のメンバーの暮らしの風景が展開する。中島さんはこの記録を撮るにあたって、撮影スタッフには「認知症とは」という語り口ではなく「生活の場」の記録としたいと注文している。
この記録映画を見た勉強会の参加者は、映像に流れる当時の認知症の人や家族の、厳しい現実に向き合いながらも、そのどこかハツラツとしたような明るさはなんなのだろうと、口々に語る。確かにこの映画を観るにつれ、そのタイトル、「ぼける」がそのまま「いきる」の感覚に重なっていく。
時代の動きの中で、何か大切なものを見落としてはいないか。
現時点の「認知症ケア」を切り出すだけでなく、歴史という時間軸をたどることで、これからの「認知症社会」が見えてくるのかもしれない。

▲ 1983年制作の中島紀恵子さん監修の記録映画「ぼける・痴呆老人と家族たち」より。現在の認知症の人と家族の会千葉県支部の全面協力があった。中島さんのもとからは、永田久美子さんはじめ多くの認知症ケアの指導者が生まれている。
|第120回 2019.11.6|