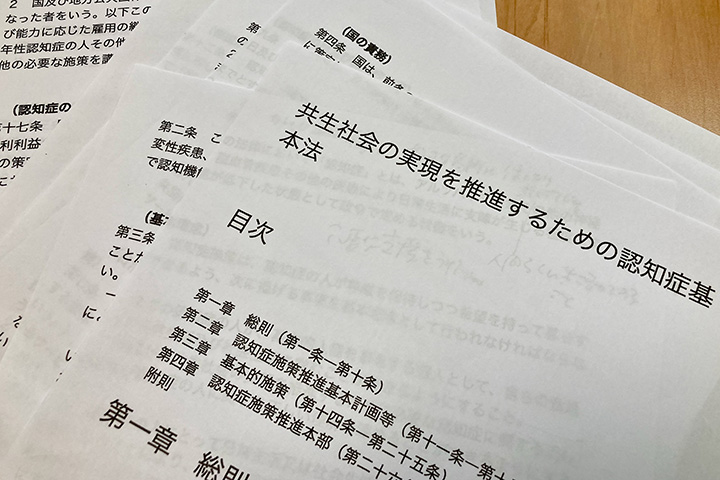▲ 仙台での認知症フォーラムの登壇者。仙台での認知症当事者と地域との活動は、丹野智文氏やいずみの杜診療所の山崎英樹医師たちと共に「認知症だからこそできること」を掲げている。丹野智文氏の右、中央のメガネの男性が鈴木理(おさむ)氏だ。下段左が、会場となった「仙台国際センター」。
「認知症だからこそできること」と言うフレーズをご存知だろうか。
今、認知症の人を中心に、このフレーズからさらに次の次元への社会発信がされている。しかし、この言葉はいきなり出てきたわけではない。
それ以前には、「認知症でもできることがある」と言う言葉があった。ひとつの言葉が、この社会の歯車をカチリとヒトコマ進ませ、「認知症でもできること」の言葉に背中を押されるようにして各地の認知症当事者の発信が起きた。
しかし、この言葉にもまた前史がある。
「呆けても心は生きている」である。
これは、2002年に認知症の人と家族の会が行った「家族を通じてぼけの人の思いを知る調査」から打ち出されたもので、それまでの「認知症になったら何もわからなくなる」と言う偏見を覆し、現在の「認知症観」を築き上げる基盤となった重要な言葉だ。
これ以降、2004年の「痴呆」から「認知症」への呼称変更、京都でのADI(国際アルツハイマー病協会国際会議)でのクリスティーン・ブライデンの講演、そして、全国各地で認知症の人が次々と登場してくるのである。
認知症の言葉が、実は認知症に関わる市民のグリーン革命につながったといっていい。
呆けても心は生きている
認知症でもできることがある
認知症だからこそできること
それぞれの言葉はそれぞれが個別の分断ではなく、しっかりと重なり合っている。
「認知症でもできることがある」は、認知症の人に勇気と自信を与え、それは当事者発信と、今の「自立と自己決定」を求める当事者性につながった。この言葉は全国に波及したが、その中で限界も見えてきた。
それは「認知症でも」と言う前節だ。そこにはやはり「認知症になったら何もわからない」と言うスティグマを前提としている。
それはかつて、障がい者活動を報じる際に、「障がいに打ち克って、見事な金メダル」とか、「障がいに負けずいつも笑顔」と言った見出しが踊ったのと同じ構造だ。当時のメディア自体が、ステレオタイプの無知の中、疑問も抱かずに慣用していた。
「障がいは打ち克たねばならないもので、障がいに笑顔はあり得ない」の偏見の潜在に当時は気づいていなかった。
同じことが「認知症」でも起きている。
「認知症でも」と「でも」の助詞で、「何もできない」という旧来の認知症観を前に据え、「にもかかわらず」できることがあるとするロジックは、俗に言えば、「認知症なのに、できることがあるなんて素晴らしいね」というようなもので、それは例外的で、その本人を「特別な人」としてしまいがちだ。
もちろん、注意しなければならないのは、「認知症でもできることがある」の言葉を否定するものではないと言うことだ。この言葉の喚起力、役割は依然として大きい。
ただ、どうだろう、
「認知症でもできること」
「認知症だからこそできること」
並べてみれば、明らかにメッセージの進化と深化がある。単に言葉の置き換えではなく、そのことをこの社会と私たちがどう受け止めるのかが必要だ。
「認知症だからこそできること」は、「デメンシア・エクスペリエンス・エキスパート(認知症の経験専門家)」とする海外での認知症当事者活動の成果を受け継いでいる。
では、この「認知症だからこそできること」とは、一体どういうことなのだろうか。
仙台の認知症フォーラムで、「認知症だからこそできること」をテーマとした。
宮城県名取市の施設で介護職員として働く鈴木理(おさむ)氏が登壇した。鈴木さんはこれまで施設のユニットリーダーとして活躍したキャリアを持つ。その後、若年認知症と診断されたが、今も介護職員として働いている。
鈴木さん自身は、進行する自分の認知症に、以前はできていた入浴介助や夜勤もできなくなり、いずれ自分は何もできなくなるのではと深い不安の中にいる。できることは、利用者の高齢者に声をかけては話し相手になることだけだ。やりとりがかみ合わなくても、毎日話しかけて、施設の中を回る。
施設長は、そんな鈴木さんを「なぜか、利用者のお年寄りは誰もが、鈴木さんには心を開く。鈴木さんだからこそできることだ」と語る。
鈴木理さんには最近気になっている利用者がいる。しばしば大声をあげるようになったお年寄りだ。どう対処すればいいのか、施設のカンファレンスで話し合いが持たれた。カンファレンスにも参加した鈴木さんは複雑な思いにかられる。いずれあんな風に自分も大声をあげるようになるのかと思う一方で、介護する側としていつの間にか、その人の大声をあげる原因探しばかりしている自分に気づく。
自分にできることはなんだろう。鈴木さんは、ある日いつものように、その男性の車椅子を押して外に出た。晴れ上がった秋空にその人は突然、ハーアッと大声をあげた。
でもその時、鈴木さんは、その大声を「なんて気持ち良さそうな声なんだろう」とごく自然に受け止めた。原因探しは、やめた。
それから、鈴木さんとその利用者の男性の関係は微妙に少しずつ変化した。いつのまにか、鈴木さんは、自分のことや悩みをゆっくりゆっくり話すようになった。
鈴木さんの話を聞いているのかどうかもわからなかったその利用者が、ある時、「どうしてそうなったの」と問い直してくれた。自分の話を聞いていてくれた。自分を認めてもらえたようだった。
それはとても嬉しかった、と鈴木さんは壇上でとつとつと語った。
「認知症だからこそできること」、この「できること」の捉え方に秘密がある。
ある意味で健常モデルの「できること」は、入浴介助や夜勤かもしれない。しかし、鈴木さんの、認知症専門家としての「できること」はそうした生産の言葉ではない。
一方的な「できること」の提供の図式ではなく、それは相互の分かち合いのようなものだ。「役に立つか立たないか」の価値観からも解き放たれた「人間」同士のふれあいといっていい。ピアサポートの姿といってもいい。
これが「認知症だからこそできること」なのである。
それはいわば、喪失の中から生み出すものだ。
私たち誰もの人生は、どこかの時点からは、喪失の旅路と言える。
「老い」と言う歳月は、ひたすらゆっくりと下り坂を歩むようにして、「喪失」と共にある。何かを喪失しながら、しかし、そこから生み出すものがある。
鈴木さんはそれを見出した。利用者との相互の気づきあいで、自分の「できること」を獲得し、自分と利用者の、互いの「自分」を取り戻す深い次元のピアサポートをしたのだった。
「老い」に向き合い、看護介護をこの国に据えた中島紀恵子氏は、ボーヴォワールの著「老い」の中の、「人間がその最後にもはや一個の廃者でしかないと言う事実は、我々の文明の挫折を示している(1972)」の一節を引用し、そこにこそのケアの必然を語る。
「認知症だからこそできること」は、「喪失」の中に新たに「人間」を生み出す。「老い」や「認知症」を「廃者」ではなく、挫折した文明を引き起こすようにして、まぎれもない「人間」であることを取り戻す力である。
そして、そのむこうに、私たちは人間という存在の「尊厳」や「権利」の地点までの確かな道筋を見出すはずだ。
そして、このメッセージは、これはそのまま「私だからこそできることがある」と読み替えることができる。
誰もが「私だからこそできることがある」を、認知症の人と共につなぎ合わせていく時、はじめて「認知症とともに生きる社会」の扉が、音きしませて開く。
鈴木理さんは今日も、利用者の男性の耳元で絶えずつぶやくように語りかけ、晩秋の空のもとで、その男性が目を細めて聴き入っているシーンが見られるはずだ。
「認知症だからこそできることがある」