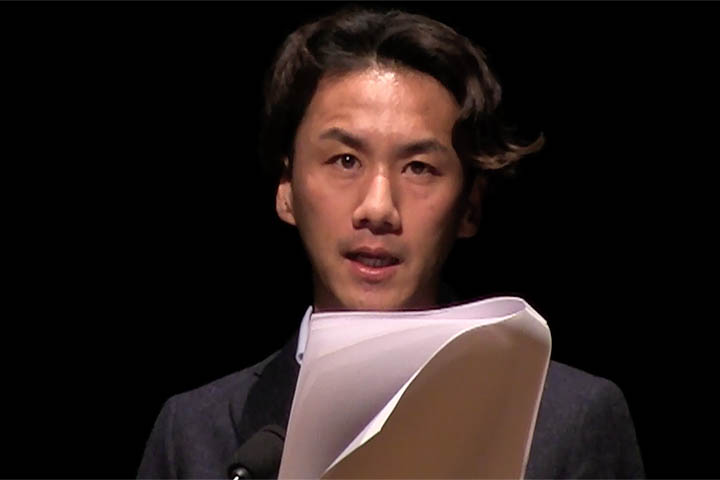▲下段、フォーラムパネリストの皆さん。左より、町永俊雄氏、オンラインで参加されたがん当事者の谷島雄一郎氏、がん研究センター名誉総長の堀田知光氏、愛知医科大学教授の三嶋秀行氏、NPOミーネット理事長の花井美紀氏。
オンラインでがんフォーラム「がんと生きる」を開いた。
テーマは、「情報」である。がん患者にとっては、「情報」は第二の医療といわれるほど大きな意味を持つ。
同時に情報はまた、副作用も持つ。がんと診断された時の大きな衝撃とそこから湧き上がる不安から、がん患者は必死の思いで情報を求めるが、不安は解消されるどころか、新たな情報で更なる不安を呼び起こすことも多い。
情報に振り回され、さらなる情報を追い求め、確かな情報がない大きな不安の中で過ごすがん患者の現実は今の新型コロナでの日々と重なる。
正しいがんの情報はどこにあるのだろう。
パネリストの国立がん研究センター名誉総長の堀田知光氏は、がん研究センターのがん情報サービスを推奨する。ここにあるのは科学的に根拠のある、現時点での最良とされる標準治療を中心としたがん情報だ。
しかし、ここでのがん情報は、予防や診断から治療、療養に至るまで網羅的であり、何より正確を旨としていることもあって自分の知りたいことにたどり着くのはなかなか難しい。予備知識や検索技術も必要だろう。
この情報社会では、がん患者も学ばなければならないとする声もある一方、がんは加齢リスクの側面もあるので、高齢のがん患者など、たちまち多くの情報弱者が取り残されてしまう。
フォーラムでのオンラインのアンケートでは、がん情報を得るのはネット情報とする人々が70%を超えた。
しかし、このネット情報に落とし穴がある。Googleでの「日米の肺がんに関するネット上の情報の違い」というリポートがあるが、これによれば、アメリカではおよそ50%が信頼のおける公的機関とNPOが発信元になっているのに対し、日本ではそうした公的機関やNPOは10%にも満たない。日本の場合多くを占めるのは個人、営利団体、医療機関の情報である。
そこに根拠の怪しげな療法やサプリなどの情報が紛れこむ。
堀田氏によれば、日本でもその後の法改正やweb管理での倫理規定などで、あからさまな「どんながんにも効く」とか「みるみる回復」といったフェイク情報は減ってきたものの、それだけにより巧妙化しているという。
全国に先駆けて12年前にがん体験者同士の情報サロン「ピアネット」を開設した花井美紀さんは、行政やがん拠点病院と連携しながら根拠のある情報へのアクセスを、がん体験者と患者が一緒になってパソコンで検索する取り組みもしている。
それはまるでネットでのワクチン予約ができず呆然としている高齢者の隣で、家族や若い世代が手伝うことによって予約が完了でき、高齢者に笑顔が生まれた光景と重なるようだ。
医療と患者とをつなぐはずの情報が、つながらない。正しい情報はただあればいいのではなく、そこにどうアクセスできるか、そのことはもう少し整備された方がいいのだろう。
繰り返すが、がんの正しい情報はがん情報センターに集約されており、随時最新情報にも更新され、現在での最も根拠と信頼性の高い情報と言っていい。
ただし、ここが難しいところなのだが、「正しい」ということは必ずしも「いいこと」とは限らない。がんを宣告された人の不安定で揺れ動く心情に、ときに「正しい情報」は冷たくそそり立つ壁のように感じられるという。近寄り難く、無防備に接すると自分の状態の深刻さに、かえって打ちのめされてしまう。「正しい情報」は本来はかけがえのない力になるはずなのだが、かなりの人が、「正しい情報」よりもネットの根拠のない情報にからめとられていく。
「ただ正しい情報をと言うのではなく、むしろ、ネット上の怪しげな情報に吸い寄せられてしまうがん患者の不安や弱さに、医療者は寄り添うべきだ」と発言したのは、愛知医科大学の三嶋秀行教授だ。
患者が根拠の薄い情報に飛びつくのは、患者の側のせつない願望に応える心地よい響きがあるからで、そこに踊る「回復」や「注目」「最新療法」などの惹句にあらがい難い磁力があると、三嶋氏は指摘する。
では医療者としては、そうしたネットに潜む罠にどう対応するのだろう。三嶋氏は、そのサプリや療法が、コストの負担や現在の治療に弊害が及ばない限り、そして、本人がそのことで少しでも安心できるのなら、「では、しばらくそれもやってみましょうか」と、認めるという。多くの患者は、ホッとした顔つきになるのだそうだ。いきなり、その情報は正しくないと否定したら、その時点で患者との対話が途切れてしまう。
患者の選択も認めつつ関係性をつなげていく中で、医療者と患者との間の空白を埋めるようにする。がんの医療にはそうした患者の側の不安や弱さを包摂することで、本来の治療が成り立つのであり、がんの「サポーティブケア」とは広義で言えば、こうした患者の不安に揺れる心情に伴走することでもあるとしている。
がん情報は単に無機的な用語の集合ではない。それはあるときは不安を和らげ、またあるときは絶望の淵を深め、またあるときは新たに医療に向き合い、生きる力ともなっていく。
そして、がん情報は医療と患者の間を行き交うだけではない。
「がんは万が一ではなく、二分の一」とは、日本対がん協会のキャッチフレーズである。
よく言われる「二人に一人ががんになる」とは、がんは誰でもなりうるとして、他人事ではなくがんを捉えようと言う意味合いで世間に流布している。
が、がんの当事者の側からすれば、世間の半分の人は、がんではない。となると、がんの人とそうではない人の間には超え難い分断がある、そんなことを感じる時があると言うのだ。
「寄り添いハラスメント」と言う言葉で問題提起したのは、大阪のがん当事者の谷島雄一郎氏だ。
希少がんのひとつ、ジストと診断された谷島氏は、がん当事者と周囲の人との間の溝に悩み、傷ついてきた。「がんばれ」とか「弱気になってはダメ」と言った言葉がそうだ。
谷島氏は、声をかける人の善意がわかるだけに、その言葉に傷つく自分の気持ちは抑え込み、それまで反論しなかった。
しかし、二人に一人ががんになる時代にこのままでいいのか。声をかける側は無意識に自分の善意に心地良くなっているだけなのではないか。
谷島氏は、あえて刺激的な「寄り添いハラスメント」の言葉を使って、がん啓発のウエブセミナーで提起した。これは大きな反響を呼び、同じ当事者からは共感の言葉が寄せられた一方で、がんではない人々からは「それなら、声をかけるなと言うことか」「寄り添いと言う言葉を大切に思ってきたのに、それをハラスメントとされるのには違和感を覚える」と言った声も寄せられた。
オンラインで参加した谷島氏は、「そうした声もよくわかる。だからこそ、どちらが正しいかではない答えのない問いとして提起した。自分自身、がん当事者になって自分のつらさや気持ちが「わかってほしい」と「わかってたまるか」の両極に揺れ続けている」と語る。
そして、押し出すようにして語った。
「結局、「わかりえない」と言うところから積み上げていくしかないのではないでしょうか。互いにわかりえないとすることで、何か本当の理解や共生が生まれてくるのかもしれません」
その人のつらさや困難の真実は安易にわかるものではない。むしろ、「わかりえない」と言う地点からまず自分を見つめ直すしかない。そこから、がんではない人の「がんと生きる」が立ち上がる。
「わかりえない」ことをわかることから確かな情報が生まれる。情報とは与えられるものではなく、互いの異なる立場にかけ渡すようにして私たち自身が生み出していくものなのかもしれない。