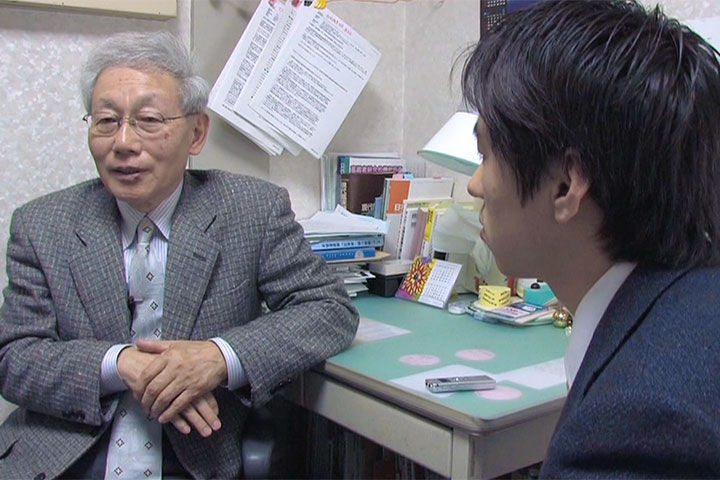▲多様性と共生の社会は、帆船の航海に例えられる。多様な乗組員が未来への羅針盤に進路を定め、力を合わせて帆を張り、風を呼び込み、嵐に危うく傾いても、そのレジリエンス(復原力)をもって立ち直り、未来へと航海を続けていく。
パラリンピックは、未曾有の感染爆発の中で、「やめたほうがいい」と示唆する専門家もいたが、なかば強行されるように開催された。
最大限の感染対策の徹底の中での開催は、矛盾するメッセージとなったと論評されている。
そのとおりだと思う。思うが、一方でそうした矛盾をはらみ、その脆弱さを露呈したこの社会にとっては、パラリンピック自体が持つ多様性と共生のメッセージが薄れてしまったのは、感染対策とこの社会の健全化双方にとって不幸な事態が重なったとしか言いようがない。
国際パラリンピック委員会では、パラリンピック開催に合わせて、史上最大のキャンペーンとされるWeThe15(ウイ・ザ・フィフティーン)を始めている。
WeThe15というのは、世界の15%の人々、12億人は障がい者で、その人々に対する差別をなくすことを目的とする人権運動としているが、コロナ禍でのキャンペーンは果たして実効的な展開をするのだろうか。
ここでの障がい者の捉え方はこれまで以上に多様で、国連のファクトシートには、障がい者の80%が途上国に暮らし、世界で最も貧しい人々の20%にはなんらかの障がいがあり、障がいを持つ女性と女児は虐待を受けやすい、などがあげられている。
日本に関わる項目としては、「平均余命70歳以上の国の国民は、平均で約8年間、すなわち人生の11.5%を障害とともに過ごすことになる」とある(国連権利条約事務局UN Enable)。
つまり、平均寿命が女性87歳、男性81歳を超える超高齢社会の日本にとっては、老いていく誰もが障害とともにある人生を歩むことになる。さらにそのことに自覚的でなければならないことに、認知症がある。
2025年には65歳以上の高齢者の5人にひとり、つまり20%が認知症となるこの国では、このWeThe15のまさに切実な当事国なのである。
認知症を、加齢に伴うリスクとしたり疾患の側面だけで捉えるのではなく、障害として捉えようという動きはイギリス・スコットランドを発祥として今や国際的な潮流として定着している。その背景にあるのが2006年に国連で採択された障害者権利条約で、ここでの障がい当事者たちの「私たち抜きに私たちのことを決めないで」の合言葉は、そのまま現在の認知症当事者たちに継承されているのはご存知のとおりである。
ただし、認知症を障害とすることは、まだこの国では一般的ではないし、誰もが受け入れるには至っていない。それは、認知症というレッテルに加えてさらにそこに障がい者というレッテルが貼られるという拒否感だろう。
このことは障害を持つ多くの人もまた抱く感覚であり、多くの人が自らを障がい者の枠組みで語られるのを否定する。パラリンピック自体も、かつての障がい者の大会から今や純然たるアスリートの祭典を名のり、そのように位置付けられている。
認知症の人や障害のある人が、障がい者とされることの否認感情には、認知症や障害が、いまだに疾患モデルの文脈で語られ「できない人」「わからない人」とされることへの強い抵抗感である。障害は社会の側にあるとする社会モデルがまだ根づかないこの社会が、さまざまな差別と偏見を生んでいる。だから、認知症を障害と捉えるかどうかは、現時点では結論的な見解を急ぐのではなく、むしろそのことで新たな視点を獲得できることに目を向けたい。
パラリンピックの開会式や競技を観て「感動した」「素晴らしい」という声が多く寄せられている。そして、そうした人々の思いの集積がこの社会を方向付けることになる。
ただし、とここでケチを付けようとは毛頭も思わないのだが、その感動や「素晴らしい!」の声の奥深くのどこかに、「障害があるのに」「障がい者なのに」という前提が潜んでいたり、あるいは無意識の、自分が障がい者ではない側、マジョリティの側にいることの安堵と優位感が隠されてはいないだろうか。
そして、パラ・アスリートを、身体能力に秀でたヒーローの側面だけで見るなら、一元的な価値での強くて秀でた「すばらしい」障がい者の姿だけが前景化してしまい、能力主義に絡み取られかねない。
しかし、そのことは否定されることではなく、むしろ率直で大切な感情だ。そこから自分自身の障害に対する意識のありように気づいていく。あらかじめの「あるべき」理念に基づいて考えるのではなく、手に汗握る観戦の中から気付いていくものがある。
その道筋はいく通りもあり、どう見なければならないかという定式はない。「素晴らしい!」と心揺さぶられた個々の体験が、どのように多様性と共生に育っていくのか。そこには対話と時間と継続が必要だろう。
時間をかけて「考え続けていく社会」と言ってもいい。正解があらかじめあるわけではなく、対話の中であちこちに模索し、引き返し、失敗しながら、それでも前に進む。多様性や共生はそうしたプロセスを経てはじめて育まれるものだろう。
これまで、差別の解消は主にマジョリティの側の課題とされてきた。社会の大多数であることは、様々な配慮と優遇を気づかないままに受容し、その余剰を思いや支援として、マイノリティのための福祉や差別解消に再配分してきたところがある。もともとマジョリティの側が按分した公正や平等であって権利の不在でもあった。
ところが、コロナ禍の中で浮かび上がったのは、マジョリティの側の深い不安と生きづらさだった。自分の困難やつらさを説明する言葉を持たないマジョリティは、互いを感染リスクと見て排除し、マジョリティの内部で互いを差別し、被害感情と孤立の度合いを深めていくしかなかった。
一方で、当事者研究で知られるように、マイノリティの人々は、自分たちの困難の専門家は自分たちであるとして、互いに語り合い共有し研究し、自分自身が持つ力を見出していく。
そこでは、マジョリティとマイノリティの構図は逆転し、今やマイノリティの当事者としての力がこの社会の多様性や共生を推進する確かな力となっている。
そのことを示すのが、新たなキャンペーンでの「WeThe15は、民族、性別、性的指向と並んで、障がい者をインクルージョンの課題の中心に据える」としたメッセージだ。
ここでのメッセージは端的に言えば、障害を超えた幅広い包摂である。
これまでの、障害のある人や認知症の人と「ともに生きる」というマジョリティの側からの共生提案だったのを組み直し、「人」の中に障害のある人も認知症の人も民族、性別、性的指向の人々が当たり前に含まれているという認識である。
基軸はマジョリティの社会にあるのではなく、「人間」に置く。そこに包摂されるのが多様な人々とその価値観なのである。
開会式の「片翼の小さな飛行機」の少女は、その物語を世界に示した。
片翼の飛行機の少女は、なんとか飛ぼうと試みるが、その度に飛ぶことをためらう。未知の世界に飛び出すことは少女の勇気全部をかき集めてもまだ足りない。
飛ぼう、ダメだ、無理だ、飛べない。大きな不安の小さな少女は、我が身を抱きしめて嘆く。少女は飛ぶためのその一歩を踏み出すことができない。
手を握りしめ、息を止めて見つめる私たち。ガンバレ、などとは言えないほどの少女の緊張が痛い。意を決して、少女は目を見開き、ぐいぐいと滑走路を突き進む。ついには、高々と飛び立つ片翼の小さな飛行機。
片翼の小さな飛行機はなぜ飛ぶことができたのか。少女はなぜ飛ぶことに踏み出すことができたのか。
そのことを考え続ける世界へと、あの小さな飛行機と少女は飛び立った。
閉会式にまたあの片翼の小さな飛行機の少女に会いたいものだと思うのは、私だけだろうか。
|第186回 2021.9.1|