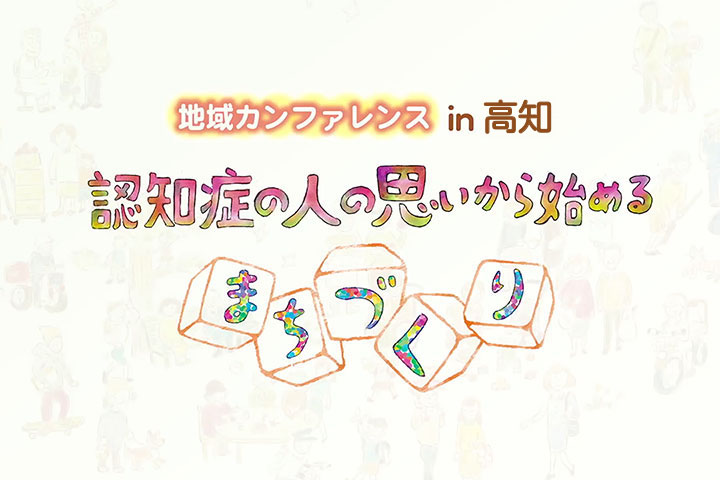▲ブックシェルフスピーカーの上に、小さな陶器の村を置く。壮大なオーケストラの調べが、村の人々の息づかいのようにも聴こえてくる。
認知症EYES始まって以来の画期的連載企画(?)の前回は、このコロナの日々で誰もがこの社会への違和感を持ちながら過ごしてきたのではないか、しかし、実はそこに感じた違和感こそが今一度、自分を含めた社会のあり方を再検討するヒントなのではないか、そして、そこでの中心的な視座としては「認知症とともに生きる」と言うことがコロナの日々にそのもろさを露呈してしまったのは何故か、と言うところまであちこちに脱線しながらも記してきて、そこで、第一回を終わっています。
これってあれです。よく連続ドラマなどで最初に「前回までは…(Previously On This Column)」というあらすじが出ますね。あれを一回やってみたかっただけなのですが、だったら前回、あんなにグダグダ書かずにこの要約で十分じゃないか、という読者もいるに違いありません。全くその通りで言葉もないのですが、しかしね、実はグダグダと書いたり語ったりすることって案外大切なのではありますまいか。
私は東京の下町の日本橋という職人横丁で生まれ育ったのですが、そこの住民は寄ってたかっておしゃべりなのです。女性はもちろん、男衆(これは、オトコシュといいます)もまたひどくおしゃべりで延々グダグダと話すのです。「要するに、なんだってえんだ」といいながらもグダグダが続くのです。
下町の言説にはグダグダと言った独自の情報の量と質が必要なのです。そこから何をいいたいのかを読み取る中で、地域共同体のコミュニケーションが担保されていきます。「結論は何かね」という冷たく言い放す言説が行き来するのは、多分、生活とは切り離された最大利益追求の企業言語です。
グダグダからその人の人格や惑いや価値観を読み取るのが、下町の暮らしを成り立たせていました。その蓄積が、「わかった、もう言うな、あとはまかせろ」といういい加減であたたかな相互信頼を生んでいました。そもそも、私自身、無駄のない人生だとか、失敗のない子育てといったことはあり得ないと思っていて、そもそもグダグダを削ぎ落とした暮らしって、なんとも味気なく私には想像できません。だから、グダグダの中を蛇行するようにしてこのコラムも進んでいきます。
グダグダが過ぎました。
「ともに生きる」の何が問われているのか。
この社会の「認知症」は、最初から大きな関心の中で語られてきました。国際会議やイベント、政府の国家戦略などで語られる認知症はいつも注目され、メディアで取り上げられてきたのです。
そこには二つの側面があって、一つは世界に冠たる超高齢社会であるこの国は早くから認知症への問題意識が濃厚でした。何しろ世界一の高齢化率なのですから、認知症への環境整備は、政策施策のレベルでは早くから焦点化されていたのです。
そのことが新オレンジプラン・認知症国家戦略の策定につながりました。これが成果の側面。もう一つの側面というのは、認知症は社会保障財源を圧迫することになるとして、常にこの社会の喫緊課題としてハンドルされてきたのです。だからどうしても、認知症は問題の文脈で語られてきてしまって現在に至っています。
難しいところなのですが、さらには私たちの側にこうした共生概念とどう出会ったのかも合わせ考える必要があります。
それは、この国の認知症への基本的な方向性や施策はお上によって私たちにもたらされてしまったのです。これはある意味不幸な出会いでした。出来合いの「ともに生きる」に私たちは出会ったようなものです。
この国の「認知症とともに生きる」がもろさを内包しているとしたら、それは自分たちで獲得したのではなく、理念を与えられてしまったことにあるのではないか、と言うことも考えてみたいのです。
例えば、2015年の新オレンジプランの冒頭の文を再掲してみます。
「認知症の人の意思が尊重され、住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができる社会の実現をめざす」
なるほど。いいね。でもここからスタートすることでいいのか、正直迷います。
端的にいえば、ここに掲げられている共生概念の裏には、要するに「こうではなかった」社会があったからですよね。認知症の人の意思が無視され、住み慣れた地域ではない収容と隔離の中で自分らしい暮らしを奪われ続けた歴史があったということです。
私たちの「ともに生きる」はそこからスタートしなければならないのではないかと私は思います。
何故こんなイチャモンのようなことを言うのかといえば、このコロナの日々に私たちの社会は相変わらず、異質の存在を排除する体質を持っていることを見てしまった気が私はしています。それはかつての痴呆症の人の隔離、収容、拘束の負の記憶を呼び起こしたとはいえないでしょうか。
今の「ともに生きる」のもろさというのは、共生概念を獲得する、あるいは闘い取るプロセスを持たないまま、与えられた「ともに生きる」を語ってきたところがあるのかもしれません。言われたからではなく、私たちは「こうありたい、こう生きたい」と言う私たち自身が据えた地点から「認知症とともに生きる」を再検討しなければと思っています。リスタートです。
私たちの「認知症とともに生きる」と言うのは、実は思わぬ地点からの発想も流れ込んでいるのかもしれません。
それは「認知症は治らない」と言う前提です。残念ながら、現時点では認知症の根治というのは相変わらず難しい。根治薬もいつもいいところまで行くらしいのですが、どうもその先あと一歩(かどうか私にはわからないのですが関係者はこう言ってました)のところで達成できない。
いや、言いたいのはですね。この「認知症は治らない、治すことができない」という現実へのBプランが、認知症とともに生きると言うことなのか、ということです。
治すことができない。となれば、(チッ、しょうがない)共生するしかないか、といった本音がありはしませんか。
では仮に認知症の根治薬が完成した暁には、「認知症とともに生きる」ということは必要なくなるのでしょうか。それは「認知症とともに生きる」ということが、認知症治療薬ができるまでの代替プラン、もしくはつなぎの理念ということなのでしょうか。
共生という社会モデルから、疾患としての医学モデルへの逆行なのか、あるいはこれを医学の大勝利として進歩とするべきなのか、どうも妙な感じがします。
ではもうひとつ、「認知症になっても安心の社会」という言葉もよく使われます。これまた自治体などの見出しに使われています。端的でわかりやすい共生理念と言っていいでしょう。しかし最近は主に当事者たちやそこに関わる人々からは別の標語も提案されています。それが「安心して認知症になれる社会」です。
もちろん、どちらが正しいのかと言ったことではありません。どちらの標語も大切な言葉です。しかし、この二つの標語には微妙ながら本質的な認知症観の変化が読み取れると、私は思っています。そこから見えるのは、認知症の現在地です。
「認知症になっても安心の社会」というのは、とてもわかりやすいのです。すっと誰もの心に馴染みます。でも、わかりやすさにはあやうさもあります。実はそれは、誰もの共有している「常識」に響くからです。その常識とは何でしょうか。
それは「認知症になっても」という前段の字句にあります。それは「認知症になると大変であり、つらく困難な暮らしになるはず」という思い込みです。この「思い込みという常識」を前提にして、この標語は成り立っています。つまりこの標語の根底を探ってみれば、それはこんなつぶやきも隠されているのかもしれません。
「本来は誰だって認知症にはなりたくはないだろうが、仮になったとしても、大丈夫、私たちがきっとなんとかしてあげよう。だから、安心してね」
そう、ここにあるのは確かに馴染み深い地域共生の合言葉であり、素朴な善意です。ですが、こうした心やさしい人々の心情には実は、認知症になると大変なのだという負の側面が刷り込まれていることに当の本人が気づいていないのです。そこが根深いのです。
つまり、「認知症になっても安心の社会」という言葉にはどこか、認知症になっていない側の発想が感じられるのです。そこにあるのは、「認知症になってしまった人」という他者性へのやさしさの擬態で、この言葉には「認知症にならずにすんでいる」側のマジョリティと健常性の無意識の優位、おごりが感じ取れないでしょうか。
対して、「安心して認知症になれる社会」ですが、ここにあるのは、認知症であろうとなかろうとユニバーサルな「安心の社会」を打ち出す方向性を示しています。社会が変わらなければならないというメタメッセージと言っていいでしょう。
つまり、「安心して認知症になれる社会」は、社会のあり方のパラダイムシフトに力点が置かれています。ここでの認知症は、そうした包摂の社会への変革をうながす駆動力としての位置付けであると、私はそう思います。
「認知症とともに生きる」なんて口に出してみると、なんとなく「ともに生きる」という言葉に引っ張られて心地よい「共生」のあり方に向かいがちですが、本当に見るべきはその背後にむっつりずっしりとうずくまる私たちそれぞれの「認知症観」の再点検なのです。ちょっとつらい点検なのです。共生というのは、あとで語りますが、実はイバラの道なのです。
「あなたも認知症になるのだから」という言葉で共生を語るのは、恫喝です。震えあがらせてから、「ともに生きる」メンバーに誘い込むのはどこか悪徳商法の勧誘です。言い過ぎだな。
認知症になっていない側から、認知症の人々へ恩恵や善意を滲ませて「ともに生きましょう」というのは、私はその人のやさしさには感銘しますが、実はそのやさしさに潜むのはその人自身の中のネガティブな認知症観なのです。
ではどう考えればいいのでしょうか。
よくわかりません。そう、言っておかなければならないのはここで私は正解を出そうとはちっとも思っていないのです。どう考えればいいのか、と自分に問いかけるようにして、自分の思考の道筋を歩いてみようと思っているだけです。皆さんの道筋と一緒であれば嬉しいし、違っていれば、そこでの対話はこの地域社会の新たな活力につながるかもしれない、そう思っています。
さて、どう考えればいいのか。
私は、だから、当事者の声を聴くこと、そして当事者の存在が何より必要だと思っています。しかし、この当事者の声を聴くということにも、深い再検討が必要だとも思っているのです。
それは…、あ、ここで次回に続くのです。
次回は、当事者と共生といったあたりについて語れるかなと思っています。どんなふうになるのかまだ私自身も分かっていないのですが、よろしければ、覗いてみてください。
ではでは、to be continued.(つづく)
|第204回 2022.3.14|