-

「認知症と共に生きる」は、新型コロナウィルスに真価を発揮するか
緊急事態宣言が出された。私の部屋から小さな児童公園が望めるのだが、そこの桜の満開過ぎて、風に花びらが舞い、梢には瑞々しい若葉が萌え出ている。
-

「新型コロナウィルス」が本当に問いかけていること、その脅威とは何か
この事態だからしょうがない、引きこもって読書三昧と思ってもどうも身が入らない。というか心が入らない。晴耕雨読というのが最高の充実の時間とされてきたのは、社会と個人の一定の安定が前提だったのだ。
-

新型コロナウィルスは、私たちの何を試しているのか
新型コロナウィルスによって、この社会のありようが一変した。私の親しい友人は、メールで「お互い生き延びよう」と呼びかけた。「生き延びよう」という言葉が私たちの日常の暮らしの中に入り込んだ経験は、戦時中の世代はともかくとして現在の私たちにはなかった気がする。
-

「認知症は社会をケアする」とはどういうことか
「まだまだ寒いわね。一人で暮らしているから、部屋はなかなか暖まらないでしょ。コタツに潜り込んでも、それでも体の芯がとても冷たい。ある時、気がついたの。寂しいからなの。寂しさって、冷えるの。身体も、そして心が冷えて冷えて・・」本人の声を聴くということは、自分の中の声を聴くことだ。
-

認知症は、老いのスティグマを解き放す
「老人」という言葉も悪くない。そんなふうに思った。普段、福祉的テーマでは「高齢者」という用語を使い、口語的な語りでは「お年寄り」と言うことが多い気がする。
-
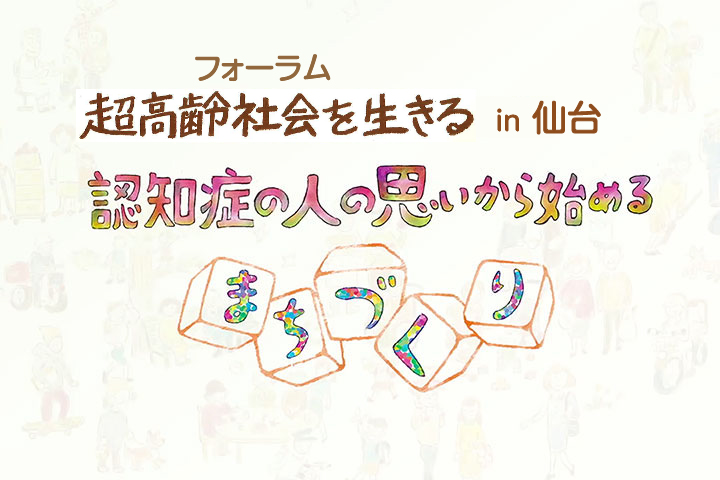
フォーラム超高齢社会を生きる in 仙台〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜
フォーラム超高齢社会を生きる in 仙台〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜
-

一挙掲載!認知症とともに生きるまち大賞
今年もまた東京国際フォーラムで「認知症とともに生きるまち大賞」の表彰式が開かれた。これまで、「認知症にやさしいまち」や「認知症とともに生きる社会」というのはいつもどこか、この社会の目指す姿として捉えられてきた。
-

認知症と地域・なつかしい未来を拓く「パートナーセンター・水平に支え合うしくみ」
東京世田谷の三軒茶屋で「パートナーセンター」の発足式があった。三軒茶屋というのは、渋谷のお隣なのだが、ガラリと雰囲気が変わる。
-

「認知症」を語らない
あえて、「認知症」を語らない。過剰に「認知症」を語ることは、「認知症」を問題化するだけだ。当たり前の認知症だから、語らない。認知症ではなく、切実な現実の「地域」をかたりあおう。
-

「無添加お弁当 二重まる 一番町」のこころみ その1〜青森県 八戸市〜
青森県八戸市内の県道沿いに、「無添加お弁当『二重まる』一番町」がオープンしました。二重まるが提供しているのは、共生型デイサービス(通所介護)。
-

認知症の人の「家族」の力 〜「認知症と共に生きる」ために〜
ブラームスのような秋の夕暮れ、灯火の下チクチクと文章を綴る。「しかし」とか「けれども」と言った逆接の接続詞をなるべく使わないようにして文をつなげていきたい。
-

認知症ケアは時代遅れなのか
三鷹で認知症当事者勉強会が開かれた。テーマは「認知症ケア」だった。案内文にはこう記されている。
-

くまモン電車の通る街角で〜顔見知りが安心と優しさを育む〜八景水谷4丁目認知症カフェ
熊本市北区にある八景水谷地区では、マンションの一室で「八景水谷4丁目認知症カフェ」が開催されています。
-

認知症の本人参画で、何が起こるのか
お盆前に令和元年の厚労省の老健事業、「認知症本人の意見を生かした認知症施策展開に関する調査研究事業」の検討委員会が開かれた。
-

「認知症とともによりよく生きる」を語る〜佐久総合病院・農村医学夏季大学講座での講演より
7月19日に、長野県の佐久総合病院での農村医学夏季大学講座で講演をしてきた。講演全体の最終部、「共生社会と対話」を語った部分を補筆修正した上で、コラムとして記したものである。
-
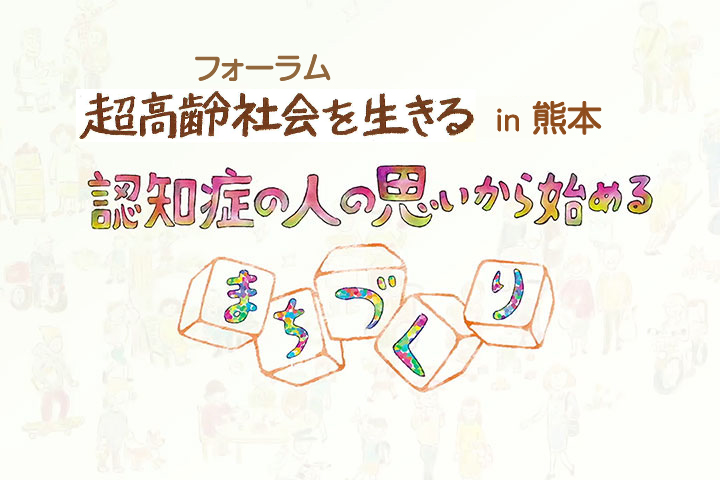
フォーラム超高齢社会を生きる in 熊本〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜
2019年3月3日、ホテル熊本テルサで「フォーラム超高齢社会を生きる in 熊本〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜」が開催されました。
-

「私」は語るべき「認知症」を持っているか
NHKラジオ深夜便の「認知症カフェ」に出演した時、ディレクターの佐治真規子が、最後にひとつお伺いしたいのですか、とちょっと改まって聞いた。「町永さんは、どうしてそんなに認知症に熱心なのですか」
-

「認知症予防」と「共生」
政府が5月16日に認知症の大綱案の目玉とした予防の数値目標を取りやめると、6月3日、各紙が報道した。
-
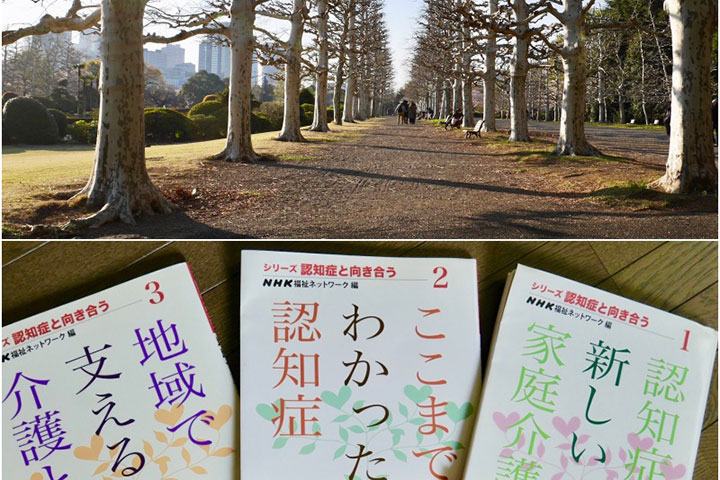
令和の時代の認知症
実は、元号が決まる前、ノーテンキに、新元号は「認知」で決まり、などと友人にメールしていた。一部で認知症のことを「ニンチ」と記号的に使う風潮にかなりの人が違和感を抱いていたはずだが、疾患名を離れて「認知」という単体の言葉をしげしげと眺めれば、これはなかなか味わい深い熟語である。
-
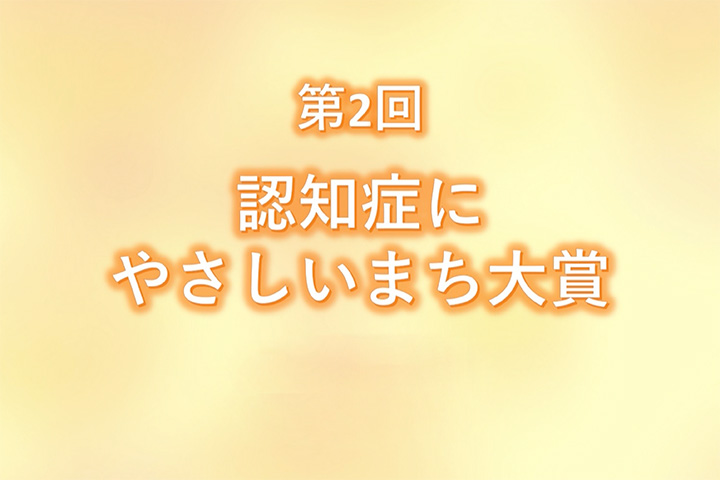
第2回 認知症にやさしいまち大賞
第2回 認知症にやさしいまち大賞