-
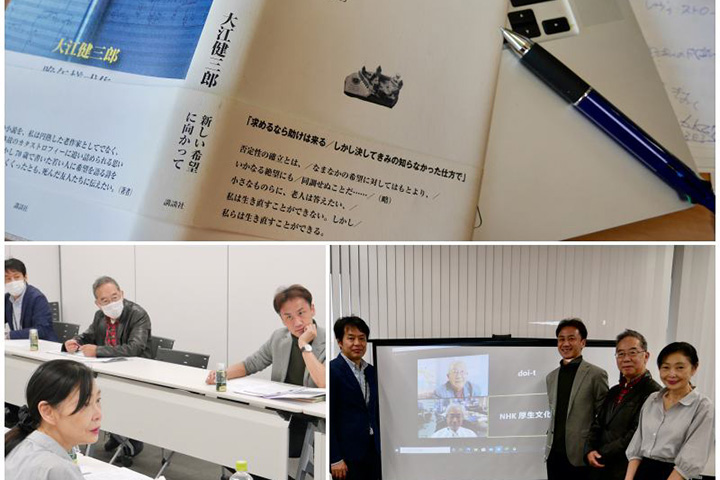
「私たち」の、認知症とともに生きるまち
今年の「認知症とともに生きるまち大賞」の選考委員会が開かれた。NHK厚生文化事業団の主催で毎年開催され、今年で4回目だ。
-

NHKハートフォーラム「コロナの時代に認知症を考える」 〜つながるためのオンラインはどうあればいいのか〜
8月30日にNHKとNHK厚生文化事業団の主催でオンラインフォーラムを開いた。タイトルは「コロナの時代に認知症を考える」である。
-

「影を慕いて 男性介護者の喪失と葛藤 」〜お父さん ありがとうを支えにして〜
正楽忠司さんが、若年性認知症と診断され5年前に亡くなった妻との日々を振り返ります。
-
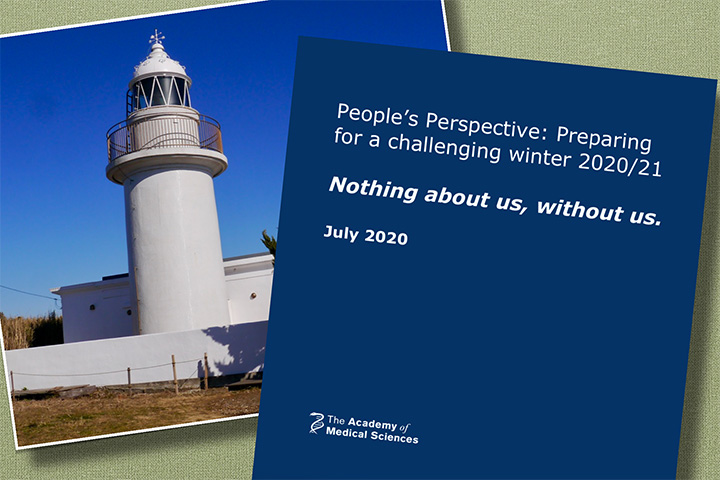
介護崩壊と「 安心して感染できる社会」
「介護崩壊を防ぐために」というオンラインの話し合いにずっとオブザーバーで参加している。こうした介護関係者の議論の場は全国各地で様々な形で行われているようだが、私は仙台の「宮城の認知症を共に考える会」のオンラインの場に参加している。
-
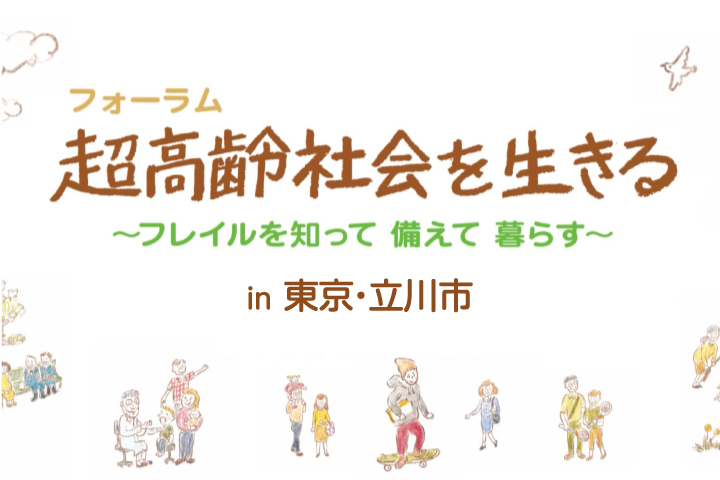
フォーラム超高齢社会を生きる ~フレイルを知って 備えて 暮らす~ in 東京・立川市
フォーラム「超高齢社会を生きる ~フレイルを知って 備えて 暮らす~」(東京・立川市)
-

私が 認知症の人にインタビューしない理由(わけ)
誰でもできるインタビューの技法というものがある。ふふ、企業秘密なんだがな。知ってます?これさえふまえれば、ともかくも世に言われる「インタビュー(らしきもの)」になってしまうのである。
-

「認知症を祝福する」 スコットランドの認知症活動をフィリー・ヘアと語り合う
「あのね、人生にはアイドリングストップが必要なんだよ」「あなた、燃費悪いものですね」といった会話が交わされたわが夫婦の緊急事態は収束に向かうのだろうか。
-
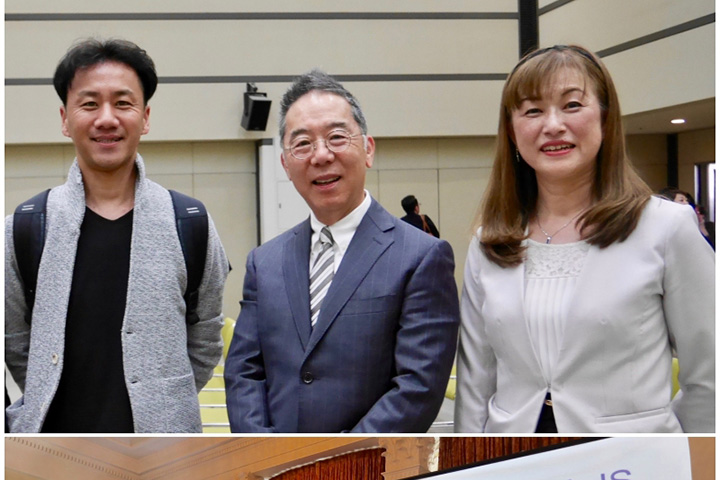
コロナの時代だからこそ、「認知症」にできること
このコラムでこのところ連続して、新型コロナウィルスがもたらしたこの社会の姿を追うように記してきました。この事態を考えるたびに気づいたことがあります。
-

「認知症」に、拍手を!
新型コロナウィルスの最前線で取り組む人々の奮闘で、私たちのステイホームが成り立っている。この最前線が決壊すれば、私たちのホームだけでなく、暮らしと命が崩壊していく。
-

認知症を障害ととらえる 〜認知症当事者と語り合う仙台リカバリーカレッジ〜
仙台のリカバリーカレッジに参加した。リカバリーカレッジというのは、認知症当事者がこの社会に参画するための、認知症当事者たちが主体的に開く対話と学びの場である。
-

スーザンのままで 〜結婚・来日・認知症を生きる〜
アメリカテキサス州出身の岩田スーザン・リンさん(68)は、23歳の時に岩田長太郎さんと結婚し来日。奈良県天理市にある長太郎さんの実家で暮らし、3人の娘にも恵まれました。
-

認知症の「希望大使」任命イベント 〜希望を引き継ぐ〜
1月20日に都心で認知症の本人大使「希望大使」任命式のイベントがあった。多くの関係者、そして認知症当事者も全国各地から集まり、メディア各社のカメラに囲まれた晴れやかなイベントだった。
-
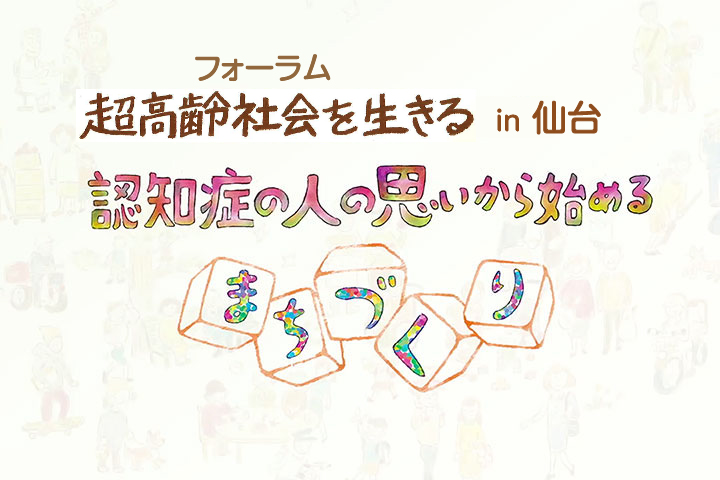
フォーラム超高齢社会を生きる in 仙台〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜
フォーラム超高齢社会を生きる in 仙台〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜
-

「認知症バリアフリー社会」を創る視点
今年は「認知症バリアフリー社会」へとなるのだろうか。去年4月に厚労省で、ご当地アイドルグループまで動員して、経済界、産業界あげて100近くの関係団体と共に賑やかに認知症官民協議会が設立された。
-

一挙掲載!認知症とともに生きるまち大賞
今年もまた東京国際フォーラムで「認知症とともに生きるまち大賞」の表彰式が開かれた。これまで、「認知症にやさしいまち」や「認知症とともに生きる社会」というのはいつもどこか、この社会の目指す姿として捉えられてきた。
-

認知症と地域・なつかしい未来を拓く「パートナーセンター・水平に支え合うしくみ」
東京世田谷の三軒茶屋で「パートナーセンター」の発足式があった。三軒茶屋というのは、渋谷のお隣なのだが、ガラリと雰囲気が変わる。
-

「認知症だからこそできること」から考える「できること」
「認知症だからこそできること」言うフレーズをご存知だろうか。今、認知症の人を中心に、このフレーズからさらに次の次元への社会発信がされている。しかし、この言葉はいきなり出てきたわけではない。
-

仙台で認知症当事者たちとリカバリーカレッジを開く
小さな集まりだった。小さいけれど、凝縮された想いに満ちた集まりだった。仙台のほっぷの森という就労支援などの草の根の福祉拠点が会場だった。その会場に三々五々、人が集まってくる。
-

花が憶えている 押し花アーティスト 川端信子さん(石川県七尾市)
石川県七尾市で暮らす押し花アーティストの川端信子さん。長年押し花教室を開催してきましたが、2017年にレビー小体型認知症と診断されてから徐々に幻視や物忘れなどの症状が進行し、教室を畳まざるを得なくなりました。
-

「認知症当事者」と「対話」する
仙台の「宮城の認知症をともに考える会」に行ってきた。ここのイベントには不思議な磁場があり、そのためもあってか、全国から人が集まってくる。その磁場とは、言ってみれば、「対話性」である。