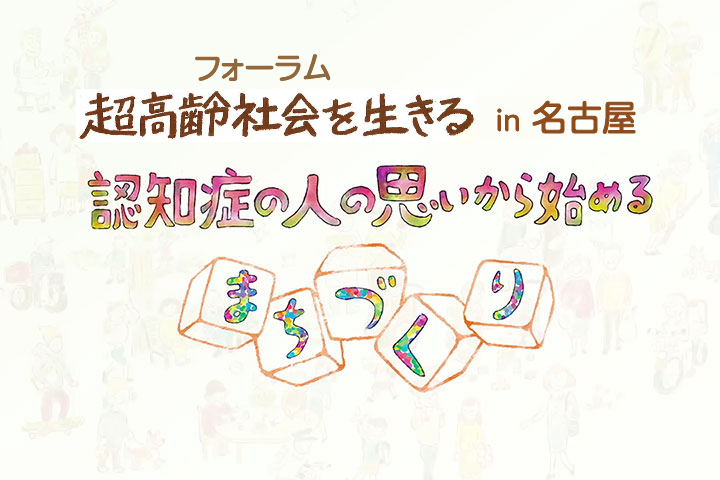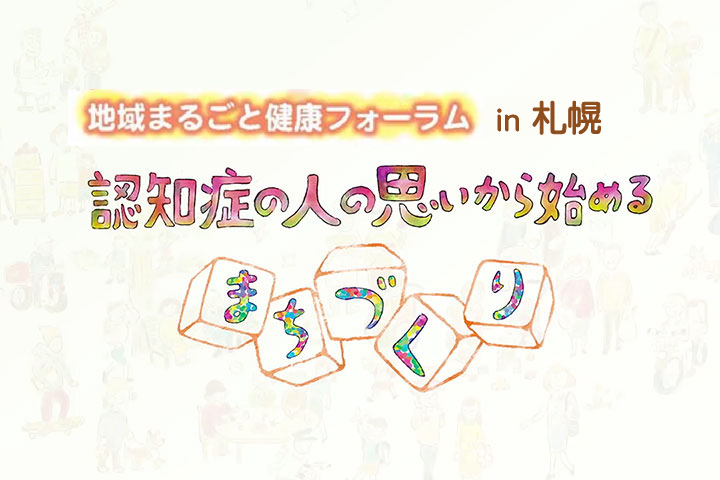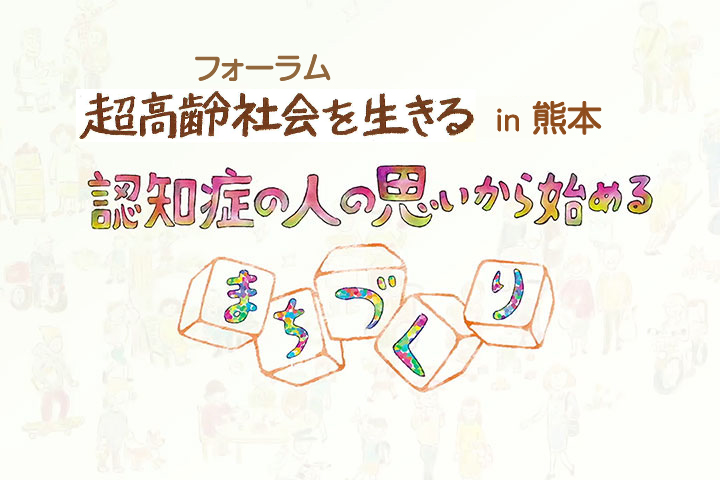▲整った家並みにひとりの子供が、輪島の空にたかだかと一枝を掲げている。物語と未来を感じさせる豊かさが、ここにある。その輪島が問いかけるものはなんだろう。(写真提供 小浦詩さん)
この大型連休には、多くのボランティアが能登半島の被災地支援に入った。
被災地の人々にとっては生活再建への大きな力になった。実際の瓦礫や家屋の片付けはもちろんのことだが、それ以上に、このように被災地に心寄せる人たちが続々と集まることに無形の支援を感じ取った人も多かっただろう。忘れられていない。
能登半島地震から4ヶ月が経った。
しかし、被災地に流れる時間に区切りはない。時間が経つことで改善したこともあれば、時間がより深刻で明らかになった課題を次々に押し出している。むしろ時間が、被災地の内側から見る現実と、被災地の外から見る現実との間の深いところに隔たりを作っているようにも見える。
以前、能登半島地震の発災直後からの、奥能登で在宅医療を担うひとりの医師の極限的な活動をたどったコラムを記したことがあった。
能登半島の先端部、奥能登にあって訪問診療に取り組んでいる「ごちゃまるクリニック」の小浦友行医師の活動である。
発災から現在に至るまで、私はメディアの震災報道とともに奥能登での小浦医師の発信を丹念にたどり続けている。そこで痛切に感じるのが、小浦医師の発信は時間が経つにつれ、彼の心情の振幅が大きくなっていることだ。その振幅が物語るものは何か。人々の内部で今なお続く「被災」に区切りはつけられない。
小浦医師の最近の投稿、震災から2ヶ月半ばには、このような思いの丈がぶつけられている。
頭のネジが外れそうです
輪島の風景は発災から大きく変わりません
復興ユートピアすら生じない
小浦医師自身、この状態を「既に被災後数ヶ月後の鬱・喪失期に突入しました」と分析的に報告する。かと思えば、満開の桜の写真とともにこんな心はずむような報告を載せる日もある。
入り口プランターのお花は満開です
ごちゃまるクリニックにスタッフの自己紹介を掲示しました。
私たちを少しでも身近にお感じ頂けると嬉しいです。
地域の人々とのつながりがかろうじて、日常を維持させている。小浦医師は「はれやかさも提供したい」と、クリニック入り口に花を植え、スタッフの笑顔の写真と親しみに満ちた自己紹介を掲示した。
だが、その診療は、今も駐車場に置かれた医療コンテナで行っている。
地区に水道は回復しているが、このクリニックでは配管が被害を受け通水していない。改修工事の目処も立っていない中、給水を受けながらの診療である。厳しい状況は依然続いている。
そんな中で、小浦医師は満開の桜とともに、コンテナでの診療を続けている。
被災地の人々に「晴れやかさを提供したい」とするその想いに痛ましささえ感じる日常は、被災地の瓦礫が残る非日常の中にある。
ただ、言っておかなくてはならないのは、この小浦医師の心情の振幅は自身の弱さの吐露として発信しているのではない。
実は小浦医師は富山大学時代に災害救命センターで働き、熊本地震では保険行政の支援に取り組んだ稀有の経験を持っている医療者だ。被災者の側の、揺れ動き迷走する想いを受け止め、そこから被災者支援を組み立てることを自身の信念としているように思える。
自身も被災者であるとする当事者性を身のうちに据えながら、同時にその当事者が支援と診療に当たるというのは、ひとりの人格を引き裂くようなアンビバレンツな思いだろう。
それが揺れ動く振幅となって、彼の報告に否応なくこぼれ落ちる。
あるいは彼の報告にまじり込むかすかないらだちの気配は、現在のメディア報道が見逃している被災地からの問いかけのむなしさから生まれているのかもしれない。
能登半島地震の復興が遅れている。その遅れは地理的不利が一因とされているが、それが全てか、と小浦医師はつぶやいている。
半島という狭く深い地域の中に、過疎地が孤立するようにして点在している。
能登半島地震はそうした地域に大きな被害をもたらした。道路は寸断され孤立し、物資も医療も支援が行き着かない。加えて寒さと高齢化、救命のための緊急の広域搬送をするしかないというこれまでにない被災状況だった。だから、これまでの震災の教訓が当てはまらなかった。
能登半島地震から4ヶ月ということで、朝日新聞にDMAT(災害派遣医療チーム)事務局の近藤久禎次長の談話が載った。近藤次長は、発災直後からのDMAT活動を担ってきたキーパーソンだ。
近藤氏は、物資や医療支援が届かない中で寒さや栄養不足による病気の悪化が懸念されるとして、命を救うための広域搬送を展開した。が、果たしてそれは最善であったかと自身に問うている。それにつづいて、このようにも語られている。
「人口減少社会における災害はただ単に命をながらえさせるためだけでいいのか。コミュニティーをすりつぶすような避難は幸せなのか。地元にできるだけ残れる選択肢を提示することが重要だった」(4/24 朝日新聞)
発災直後から現地に入ったDMATだけに、この見解は限りなく重い。
さらにこの談話では、復興を10年、30年で構想する中で、「この5年、確実に生きられない人が必ずいます。その人たちの最期をどうみとるのか」とも語っている。
こうした談話は震災現場のリアルからしか生まれてこないだろう。
しかし、このことはすでに小浦友行医師が、ずいぶん前、発災まもなくから切実な思いを込めて指摘してきたことだ。
小浦さんは、地域で暮らす幸せを創るための地域医療として2021年、奥能登に「ごちゃまるクリニック」を開業した。それだけに、高齢者を住み慣れた地域から引き剥がすような広域搬送、2次避難は大きなジレンマだった。
しかし、医療者としては救命第一である以上、2次避難を推奨しなければならない。1月8日以降の彼の報告は、そのジレンマに揺れに揺れていた。
例えば、1月11日の日付では、2次避難をすすめながらも、こうした文章をつづっている。
「それでも、敢えて地元に残るという方がいるのであれば、そして地元にいる他に選択がない方もいる。私たちは最期までそこにお付き合いをしていこう。それは本当に辛い選択かもしれない。とても私達だけではできないことだろう。今は信頼のある同志の到着を待とう」
この文尾にある「今は信頼のある同志の到着を待とう」とは、当然、小浦さんのネットワークの医療者たちの応援のことなのだろうが、同時にこれは私たちへの問いかけではないか、そんなふうにも読めるのである。
「私達だけではできない。同志の到着を待つ」とは、この社会をつくる私たちすべてが寄せる志の「到着」ではないのか。
能登半島地震の復興が語られ始めた頃、能登半島の過疎と高齢化、そして急速な人口減少に、そうした土地柄である以上、インフラの復旧は無駄であり、住民を移住させた方がいいとする議論もあった。
だが、日本史を大きく書き換えた歴史家の網野善彦は、かつて能登半島を中世日本史の原点とし、時国家の存在が示すように奥能登こそ江戸時代の日本海交易の要衝であり、東アジア世界と直接結びつく繁栄の地であったと見た。能登は辺境ではなく、中心だったのである。
私たちは地域を論じるとき決まってのように高齢化や過疎、人口減少などから考える。それは常に他者性の支援を組み立てるためのデータとして使われる。
しかし、地域の側から見れば、その土地には埋め込まれた記憶というものがある。現代はその忘却の上に地域社会のあり方を論じている。
奥能登のお年寄りは、死ぬまで故郷で暮らし続けたいと言う。それは年寄りの繰り言でも単なる情緒でもなく、その言葉の背景には豊かに層をなすその土地の記憶の継承がそう言わしめているのではないか。
被災地支援が経済合理性に基づく復興に傾くのは、ある意味当然かもしれない。しかし、それはあまりに短絡的な社会観であるのかもしれない。
そのことを含めて、能登半島地震の復興、支援をどう考えるのか。それはまず被災地の人々の揺れ動く心情を見つめることから始めるしかない。外の人が与える一面的な課題や希望から復興を立ち上げていいものだろうか。
小浦友行さんの発信するフェイスブックには、思い惑う切ない内容の報告の時は、決まってのように、能登半島の震災以前の穏やかな海岸風景や緑濃い田園の写真が載せられる。
そして小浦さんとともにクリニックを担うのが小浦詩さんだ。その小浦詩さんもまた、以前の輪島の風景とともに、子どもたちのいる写真を多く載せている。復興は、切実な未来の創造である。
その一葉の写真に、以前の本町通と思われる美しい輪島の家並みに、花の一枝を手にする子供の姿が映し出されている。ひとりの子がたかだかと掲げるちいさな花。
そうした風景を載せる輪島の人の心底には何があるのだろう。
しばらく目を離すことが出来なかった。
*参考:生きてます 街は壊滅状態です 〜能登半島地震:被災地の医師が見た「現場」〜
https://www.ninchisho-forum.com/eyes/machinaga_270.html