-

連携・協調・みんなが主役 〜10年を迎えた居場所ハウス〜
岩手県大船渡市末崎町の「ハネウェル居場所ハウス」は、東日本大震災から2年後の2013年に開設。津波による大きな被害を受けたこの地で10年にわたって、文字通り地域住民の居場所の役割を果たしてきました。
-

お盆の迎え火、そして送り火、夏の日々に想う
八月も半ばを越そうとしているが、実はこの稿を記しているのはお盆の最中で、私の育った東京の下町では、お盆にはどこの家庭でも迎え火、送り火をしていた。
-

岩手八幡平の農場の真ん中で「福祉」を聞いてきた 〜高橋和人が語るいのちの循環〜
先日、岩手県八幡平で認知症シンポジウムに参加してきた。東北も暑かった。「会場の八幡平の体育館には冷房がないのです」と、主催の市の担当者や地域包括の人が恐縮しながらあちこちに大きな業務用の扇風機を備え、至る所に飲み物のペットボトルが置かれて、そうしてシンポジウムが開催された。
-

秋田・地域ミーティングの奇跡 〜暮らしの中で語る「認知症とともに生きるまち」〜
秋田県の社会福祉会館で「地域ミーティング」を開いた。去年に続いて2回目である。コロナの日々の真っ最中だった去年、地域で何ができるか、まずはそこに住む人々の声を聴こう、去年開催した1回目は、そんな原点に立ち帰るような地域ミーティングで、大きな手応えがあった。
-

チャットGPTのあれこれを、素人の私があちこちに飛びながら考えてみた
このところ、騒然と言った感じで論じられているのが、チャットGPTである。生成AIとも対話型GPTとかいろいろ言われていてよくわからない。そのわからなさがまた、どこか説明のつかない不安にからみとられる。
-
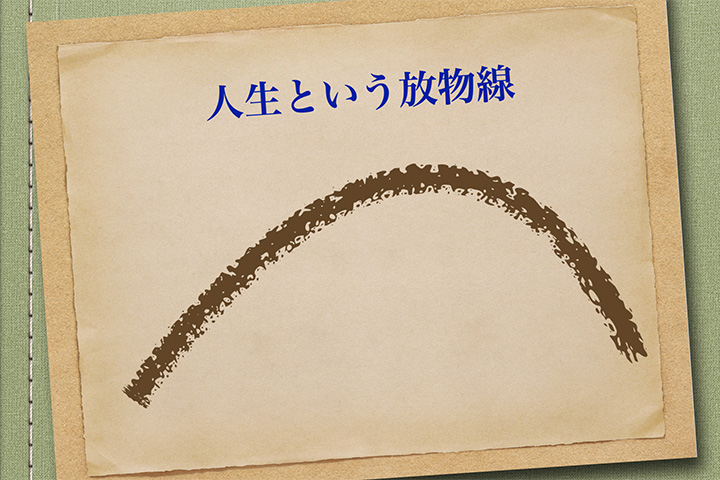
人生という放物線
コロナの日々もどうやらひと区切りの気分だ。こんな時こそ自分自身を振り返りたい。しかも俯瞰的に。いや、そんなに難しいことではない。画用紙に一気にぐいっと我が人生の曲線を描いてみる。
-

ちいさこべの社会へ 〜少子化対策に想う〜
山本周五郎に「ちいさこべ」というすがすがしい作品がある。舞台は江戸神田。大火で親もろとも、大工の老舗「大留」の一切合財を失った若棟梁、茂次が主人公だ。まっすぐな気性の茂次にとっては親を失うと同時に、老舗の再建が年若い自分にのしかかる。
-

君たちに何を伝えるか 〜成人の日に寄せて〜
成人が18歳からとなって初めての成人式が行われた。とはいっても、「20歳を祝う会」とするところも多く、18歳の成人式というのは少なかった。
-

長寿の未来フォーラム 記憶の見方が変わる 〜高齢者心理と認知症治療からひも解く〜
長寿の未来フォーラム 記憶の見方が変わる 〜高齢者心理と認知症治療からひも解く〜
-

よい年になりますように 〜福祉を発信する私たち〜
みなさん、明けましておめでとうございます。本年も、良い年になりますように。例年の決まり文句である。でも、決まり文句というのは、ある意味で長い歳月の中で洗い晒されて生き残った言葉だから、なにかの言霊を宿しているに違いない。
-

「まちづくり」とはどういうことか 〜「認知症とともに生きるまち大賞」に寄せて〜
今年もNHK厚生文化事業団の「認知症とともに生きるまち大賞」の受賞団体が決まった。その詳細はNHK厚生文化事業団のHPに掲載されており、またNHK Eテレのハートネットテレビでも放送の予定なので、全体はそちらに譲るとして、このコラムでは、このコロナの事態に改めてこの「まち大賞」が何を問いかけ、何を引き受けようとしているのかを見つめてみたい。
-

ボランティアという未来
新型コロナウイルスもまた新たな感染拡大の懸念も言われ、師走となって気ぜわしい中でただ気分だけが右往左往している。ここで深呼吸するようにして、さてこれからのこの社会をどうすればいいのか。
-

認知症学のススメ
秋が日毎に深まって庭の木々の葉が散っていく。ふと、「認知症学」といったものを提唱できないだろうか、そんなふうに思ったりする。
-

八王子「eまちサミット」〜いのち育むまちづくりを見る〜
11月3日の文化の日、八王子で「懐かしい未来」を語り合うような、そんなイベントが開かれた。これまでの未来社会といえば、20世紀の科学主義の中、ロボットと空飛ぶ自動車と空中都市といった風に常に新奇なもの、まだ見ぬもので描かれた科学の想像図でしかなかった。
-
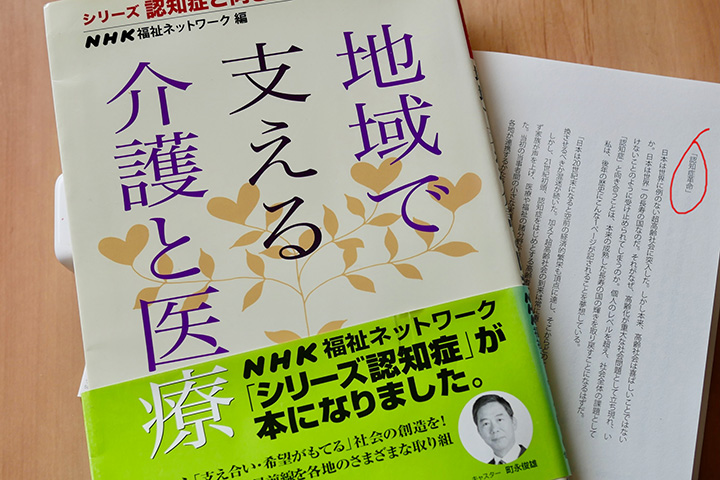
「認知症革命」はその後、どうなったのか
「マチナガさん、確か以前に認知症革命とか言ってましたよね」仲間との勉強会で、あるメンバーからそう言われた。議論の流れの中で、彼が「これは革命だな」と言ったことに対して、そう安易に革命という単語を使っていいのか、というようなことをつぶやいた私への反問だった。
-

夏の終わりに、人生という四季を思ったりして…
今年の梅雨明けを気象庁が、過去にないほど大幅に修正した。関東は6月の末に梅雨明けとされていたのが、「すまん、実は7月23日頃だったことにする(こんなふうにいいかげんに言ったわけではないが)」と、一ト月近くずらして修正したわけで、これほどの大幅な修正は過去になかった。
-

秋田の地域ミーティングがもたらした「成功」とは
秋田で地域ミーティングを開いた。コロナの日々でどうしても停滞していた地域がこれからどう動くか。どうあったらいいのか。コロナに覆い隠されていた課題をどう見つめ直すか。
-

「認知症と共に生きるまち」とコモンズ
今年も第6回の「認知症とともに生きるまち大賞」の募集が始まっている。このコロナの事態が始まった2020年には、果たしてどれだけの応募があるかと気を揉んできたが、確かに応募数は以前に比べれば減ってはいる。
-

喪失の時代と認知症の力
喪失の時代である。私たちのこの社会は、ひたすら喪失し続けている。繁栄を失い、人口を失い、若さを失い、子供を失い、地域を失い、未来を失うという喪失の社会の中に私たちはいる。
-

「認知症とともに生きる」ノート その7 「ともに生きる」とエイジズム
「認知症とともに生きる」ということは、改めてどういうことなのでしょうか。何か、同じことをひたすらくりかえし問い直しているようですが、大きな岩も指先で小さく小さく突き動かせば、やがて地響きたてて転がるかもしれません。