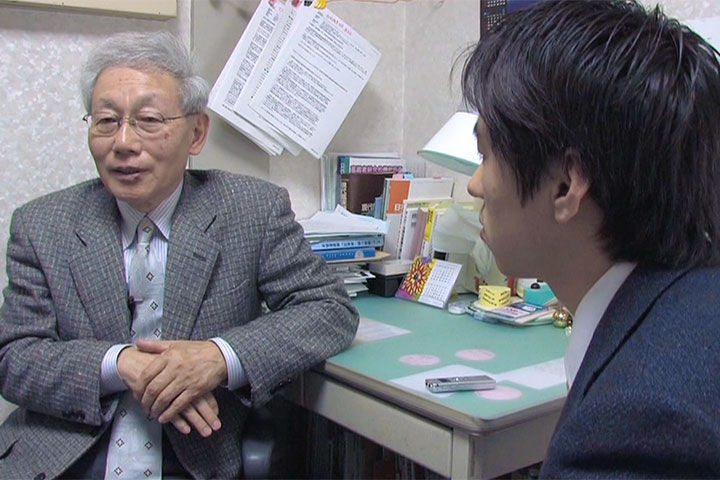▲中山道の奈良井宿。日本の原風景であると同時に、私たちのコミュニティの原型である。緊密な人々の関係性で時代の風雲を潜り抜け、現在に至るまで何か大切なメッセージを送り続けている。
八月も半ばを越そうとしているが、実はこの稿を記しているのはお盆の最中で、私の育った東京の下町では、お盆にはどこの家庭でも迎え火、送り火をしていた。
子供だった私には、きゅうりや茄子に割り箸の足を突き刺して、馬や牛にして一緒に飾るのが面白く、暮れなずむ頃には下町の職人横丁(私は貧しい表具職人の次男坊だった)のそれぞれの家の前のおガラに火をつけて煙がたなびくのが、何かのお祭りのようだった。
御先祖様が帰ってくるよ、おふくろにそう言われて夕暮れの横丁の空を見上げると、いつもと同じなのに、違った風景のようだった。
新盆の家があると、その家の迎え火に間を置いてからそっと加わり、「お帰りになりましたねえ」などとおふくろは声をかけていた。「はい」とだけ答える近所のいつものおばさんの声も、なぜか、いつもと違って聞こえた。
ご先祖様は私たちと共にいる、という感覚の共有はこうした街角の年中行事や祭りの中に組み込まれていて、子供たちはわけは分からなくても、何か自分の存在につながる漠然とした大きな存在があるらしいことを感じ取る。
自分のいのちはつながっている。亡くなった人を思うことは、いまを生きる自分を支えているとやがてどこかで子供達は気づく。年寄りは、自分が死んでも、子供達のいのちをどこかで支えることができるならと、そう思いながらお盆の迎え火、送り火を見つめる。
横丁は、学校では教えてくれないことを子供自身が感じ取り、時間と自分の中に醸成させる学びの場でもあったのだ。
この社会は情報社会だと言われる。
しかし、情報という明示化できる言語だけで説明される社会は、実は暮らしに潜在する力を振り落としている。悲しみや喜びの言語化される以前の未生の思いが流れる暮らしというものを、枯渇させてしまっている。
最近つとに思うのだが、あれこれをお話しする機会をいただいても、どうも「地域」とか「地方」という用語がなんとも馴染まない気がしてならない。
地域福祉、社会福祉を語るとなれば、この用語を使わざるを得ないのだが、使うたびに、スマナイ、この言葉しかなくて、と思ったりする。
「地域」という用語からは、私の育った街のおじさんもおばさんも御用聞きも消え去り、「地方」に至っては中央と地方の図式で、日本地図の片隅に追いやるような「地方」という語感に、東京モンの傲慢さにいたたまれない気がしてしまう。
いや、地域や地方という言葉自体が悪いのではない。だが、私の生まれ育ったあの下町の横丁は果たして「地域」なのであろうか、「地方」なのであろうか。
下町の暮らしはともすれば、ノスタルジアの中で、人情溢れる下町物語と商品化されがちなのだが、実際の下町暮らしというのは、体験者である私がいうのだからほぼ間違いないと思うが、実は陰口があちこちで囁かれたり、思春期の頃にはひたすらウザイ大人たちの価値観だけの封建的でわずらわしい街でしかなく、その頃の私は、郊外の庭付き一戸建てのサラリーマンの豊かな暮らしの洗練に憧れたりしたものだった。
しかし、その後、現実に郊外住宅地に住んで人生の大半を過ごしてきた今になって思うのは、戸建て住宅の中だけに囲い込まれた豊かさはいつも危うく、未来は不安と同居していて、かつての貧しい横丁の暮らしのノーテンキな豊かさとは決定的にどこかが違うということだ。
そして逃れがたく、あの面倒で濃密な人間関係が行き来する下町で、どうやら私の人格ができているらしい。
ウダウダと考える割に、ま、そんなもんだろうと投げ出したり、緻密というより雑でせこいところがあるのは、全てあの横丁の空気が育んだのである。
つまり、それは言ってみれば物事は一人で完結できはしないという街場の処世術である。世の中は誰かと誰かのひっきりなしの口出しの中で揉まれたり揺れたり、そうして、結局みんなの意見を聞くと言えばもっともらしいのだが、あちこちの顔を立て、顔色を窺い、そうしてどこか誰もがそれなりに納得できる合意点を探り当てる。
下町の寄り合いとは大体、こんなものだった。そうして締めはシャンシャンと手打ちして酒酌み交わしてお開きである。ひどいものだ、主体性のかけらもないではないか、と当時の私はそんなふうに下町の大人たちをみていた。若者の正義感からすれば当然だった。批判的であることが、自己の主体の確認だったのだから。
でもね、下町ってあるいは民主主義の素朴な形だったのかもしれない。誰もが口を出し、あーでもこーでもないとワイワイやって、訳知りに多数決とか言い出す輩がいれば、「ま、ま、まだ時間はあるから」「てやんでえ」とかで、時間と手間ひまをかけてそれぞれの落とし所に向かって話し合いを練り上げていく。
ここでの主体とは関係性の中に培われ、個人である前に共同体の一員なのである。
だから、病弱で内気だった私も、ひ弱な本の虫の坊主として、その存在はかろうじてご近所の誰からも認められていたのである。
下町というのは、どこかに上の町、お上といった権力構造が設定されていて、それはかつては城郭と武家屋敷で構成されており、時代がくだれば山の手の富裕層という経済強者の街があり、対して戦後の経済社会の勃興から取り残されたような経済弱者たちの下町は、そのか細い暮らしを守るため自然発生したのが、下町というコミューン(住民共同体)だった。
しかし、都市化と近代化によってそれまでの高齢者や赤子といった弱者を包摂する最小の共生単位であった家族は核家族となり、地域に根ざしての暮らしはサラリーマンの拡大で多くは寝るだけのベッドタウンになり、そのサラリーマンもまた企業の終身雇用と年功序列制によってなんとか企業の福利厚生が提供するセーフティネットにしがみついていたのが、ポスト産業社会で最後の拠り所の企業共同体も解体されたのである。
下町は、家内性手工業的な二次産業の職人の街だったから、かろうじて共同体の性格が残ったが、今、都市部の個人は剥き出しの個として、中間的セーフティネットを外され、帰属する共同体が失われた社会で、ただ生き延びるしかない。
その一方で、今この国で、共同体が生き生きと立ち上がっているところがあって(前回コラムの八幡平などがそうであるかも)、それはこの国の中心軸から離れた地域、地方なのである。そこでは個人は共同体の一員であることが、かつての家父長制などの前近代の負荷を組み替え、ふるさとの記憶や地域福祉と共に新たな共同体を作ろうとしている。
私たちの共同体を取り戻す。
この国の、はるかな海辺や山間地帯に息づいているオアシスのような新鮮な共同体の姿。そうした風景を、地域や地方ではなく、どう呼んだらいいのだろう。
ふるさと、あるいは風土と呼んでもいいのかもしれない。しかし、ふるさとや風土は、あまりにも湿った情緒の中に埋没し切った言葉で、果たして私たちの新たな社会システムがしっくりと馴染むだろうか。
だとすれば例えば、地域や地方ではなく「コミュニティ」の語をあてるというのはどうだろう。
かつて、アメリカの黒人運動指導者キング牧師は、その最後の著作とされる「混沌かコミュニティか(Chaos or Community)」の中で、人種差別や紛争が充満する時代の混沌を克服する社会に必要なのは「コミュニティ」であって、それは新たにつくりだすべき人類の理想的共同体であるとした。キング牧師は「コミュニティ」の創造に未来を託したのである。
今、各地で認知症のある人や障害のある人、子供達、高齢者たちとともにまちづくりや居場所づくりといった新たなコミュニティの創造が次々に生まれてきている。
それが今言われている地域福祉のデッドロック(ゆきづまり)を拓くケアリング・コミュニティ(ケアするコミュニティ)の概念ともつながり、パンデミック以後のこの国の新たな風景になろうとしている。いにしえより、新しい酒は、新しい皮袋に盛れ、と言うではないか。
お盆の送り火の夕になって、私が一緒に迎え火をした近所のおばさんのところに行こうとするとおふくろは、お別れだからね、と私を制した。
迎え火は、亡くなった近所のあのおじさんだから町内の人も一緒に迎えたが、新盆のお別れはその家の夫であり父なのだから、家族だけで送らせておあげ、おふくろはそんな意味合いを私に言ったように記憶するが、当時はそのところはよくわからず、今にしてなんとなくわかる気もする。
下町のコミュニティの底に流れるのは、実は誰もの物哀しい心情の共有だったのかもしれない。
深い哀しみを共にすることができるコミュニティ、共同体。それはどれほどの豊かさであろう。