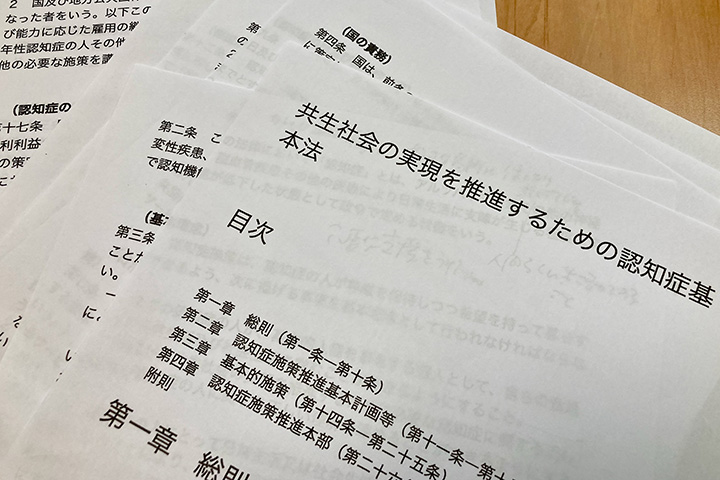いささか唐突ながら、キャロル・キングのタペストリーという曲をご存じだろうか。70年代の大ヒット曲だ。世代的には、これ聴くだけでたちまち「あの時代」が彷彿とする(泣く)。いや、別に回想法の話をするわけではない。
タペストリー、つづれ織りである。その歌詞には、 「わたしの人生は豊かで気高い色合いのつづれ織り」とある。
キャロル・キングは抑制の中、力強さも感じさせる語り口で、誰の人生もさまざまな人との出会いが織り込まれたひとつの物語だと歌う。 そう、人生は豊かに彩られた一編の物語。そして、その人生という物語の主人公は、紛れもなくあなた自身なのである。
誰の人生もかけがえのない一つの物語。しかし、その物語がいきなり奪われることがある。その一つが認知症である。 認知症と診断された途端に、「認知症の人」というレッテルが貼り付けられ、その人のそれまでの人生の物語が奪われ、「何もできなくなる人」「介護に大変な人」「困った人」として見られてしまう。 認知症の症状という今現在の断面だけが前景化して、それまでの「豊かで気高い色合いのつづれ織り」の人生の輝きと物語は喪失の中に色褪せる。
これは、認知症の当事者が訴えていることでもある。周囲の人々の善意と誠意の中で、「認知症になったのだから、精一杯お世話しなければ」という良かれとする思いが、実はその人の人生を奪ってしまっていることに気づくことは中々難しい。
ナラティブ・メディスンという言葉がある。ナラティブ・ベイスド・メディスンとも言われるのだが、ナラティブとは物語のことである。 つまり、医療に物語を取り入れようということで、なぜ医療に物語かというと、医療の現場では、医療者は医療者で自分の「治療の物語」を持っており、その物語に沿って患者に接する。 「熱はありませんか。咳は出ますか。お腹の様子はどうですか」といった具合に私達が接する医療者は、実は治療の物語に沿って患者の話を確認しているだけであり、ここには患者の物語は入り込む余地がない。 患者が「いや、センセ、うちの嫁がきつくてねえ」という物語を語ったところで「ほーほー、おナツさんも大変だねえ」と相槌を打ってもホントは聞いているわけではない。
ところががん医療のような先進医療であり、また深刻なケースも含まれる場合には、この患者の物語を聞き取ることが治療に大きな役割を果たすという。 先進医療であればあるほど、患者は医療者の物語の中に幽閉されてしまう。患者の、患者自身の物語を取り戻そう。医療がそうした動きを見せている。 その人の人生の物語を語ってもらうことで、医療に向き合う力を患者と医療者とが共有できるのだ。本来は、医療の中に暮らしが取り込まれるのではなく、暮らしの中にこそ医療はあるべきだ。 背景にはそうした新たな医療のあり方が見えている。ナラティブ・ベイスド・メディスン、物語を基礎とした医療。
認知症の人が自身の物語を各地で語り始めている。認知症になっても私は私であり、どんなに進行したとしても私の人生は続いていくという物語を。
認知症の人とそうでない人、そして医療者や全ての人が自身の物語を語りあい、出会いと共生のタペストリー、つづれ織りがこの社会に拡がるようになるといい。
|第24回 2015.11.30|