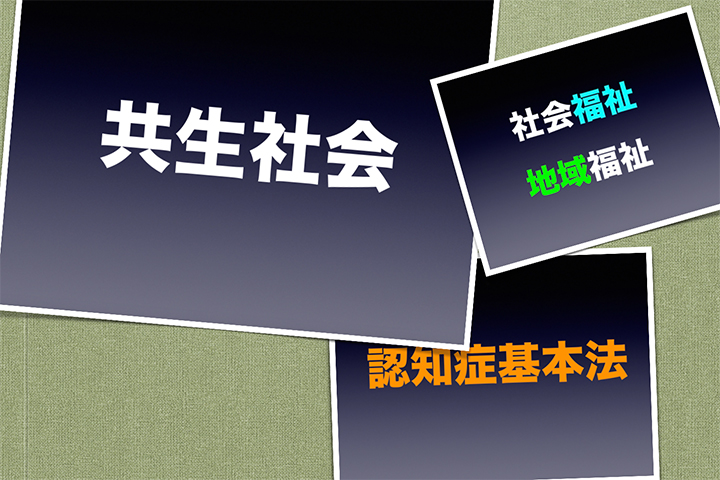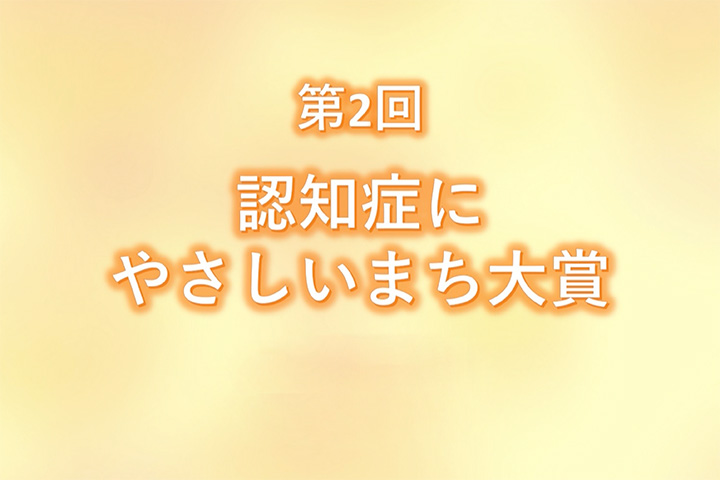▲「エリアアドバイザー Speaker’s Program」の会の皆さん。よく見れば見知った顔ぶれの参加者が多いはず。下段は、右から主宰の一人、木之下徹医師、丹野智文さん、山中しのぶさん(歌ってます)。この会は時代の当事者である。
東京の有明ベイエリアは、新しい街区である。空が広く、アリーナやビッグサイトなどのコンサートやイベントのための巨大施設が並ぶどこか未来的な空間だ。
同時に、「月は有り明けの・・」と枕草子にも夜明けの空に残る月の風情が愛でられているように、時代の夜明け、有り明けの地でもある。
そこのホテルを会場に毎年、「BSAP エリアアドバイザー Speaker’s Program」という会が開かれる。
全国から認知症医療に関わる医療者や看護師などがワイワイ、ゾロゾロと集まってきて、泊まりがけで語り合うという合宿のような会合だ。
会を特色づけているのは、集まる医療者はどの人も全国で認知症医療の新しい地平を拓いてきたよく知られた人たちであること、それに加えて、認知症の当事者である丹野智文さんと高知からの山中しのぶさんもスピーカーとして登壇することにある。
当然ながら、ここでの認知症当事者は「患者」でも「被支援者」でもない。当事者は特別扱い的な客員として招待されているわけでもない。
ふだん、丹野智文さんたち当事者が地域で講演すると終わって必ず地域の人々に囲まれるが、ここでは丹野さんや山中さんを医療者たちが囲んで質問攻めにする。ここでの当事者と医療関係者はフラットで互いに熱心に語り合う仲間である。
こうした医療者と認知症当事者とが一緒になって、それぞれの専門性、当事者性を語り合う場というのは実は多くはない。新しい有り明けの月、時代を拓く夜明けの月なのだろうか。
だが、月と太陽は同時に輝くことはない。これを認知症環境の成熟地点と見ることもできるかもしれないが、かといって、ここでの医療者と当事者が晴れやかに「共に生きる」といった調和に安住しているわけではない。その底では常に揺れ動く両者の関係性を互いに意識し確認しながら語り合いが進んでいく。
「医療はどうあったらいいのか」「私は何ができるのか」そのような密度と流動の会合である。
今年のテーマは「診断後支援としてのピアサポート」である。
やや深部からの視角で見れば、この二つの熟語、診断後支援とピアサポートは、どうもあやうい均衡に並んでいるように思える。それはどういうことだろうか。
それには「ピアサポート」と「診断後支援」という二つの言葉の成り立ちから見ていく必要がありそうだ。
ピアサポートとは、北海道浦河での精神障害者のコミュニティでの当事者研究を受け継いでいる。当事者の抱える理不尽な不安や絶望を、医療や福祉の専門家に委ねるのではなく自分たちで研究対象として捉え直し、同じ経験を持つ仲間とその意味や対処の仕方を探り当てることが当事者研究である。当事者の側に経験専門家としての力があるとするところから当事者研究は起動する。
当事者研究が新たな研究領域と社会知を生むに至ったのは、それまでの精神医療や専門性との関係性を衝撃的なまでに捉え直すことにつながったからだ。
当事者研究に当初から関わってきたソーシャルワーカーの向谷地生良氏は、当事者研究に専門家である自分はどう接すればいいのかを自問し、そこに技法以前の「私はなにをしてこなかったのか」という実践的援助論を獲得する。それは精神障害の当事者と共に「どうしたらいいのだろう」と途方に暮れる経験に、徹底して「ともに弱くなる」ことから始まったと語っている。
「なにもしないという支援」のあり方であるとか、「ともに弱くなる」という自らの専門性や権威を手放すとするあり方は、そのまま認知症医療の「診断後支援」へ示唆するところは大きい。
ではなぜ、診断後支援としてのピアサポートなのか。その双方の接点を探ってみる。
そも、ピアサポートとは、ピアという同じ立場だからこそ、互いのつらさや困難を語り合えるとする当事者性の力に依拠する。
とすれば、ピアサポートを診断後支援として医療の枠組みの中に置くイン・クリニックピアサポートは、設定時点でピアの当事者性を侵襲してしまわないのだろうか。父権主義的医療が顔を出さないか。
診断後支援とピアサポートのあやうい均衡というのは、ここにある。
今一度、北海道浦河での当事者研究の現場の言葉に立ち返るなら、向谷地生良氏は当事者研究は、自身の困りごとを「問題」としてその「解決」を目指すといった直線的な取り組みではないとしている。
自分の困りごとを「問題」とした時点で、それはたちまちマジョリティの側、つまり健常の側の発想に絡み取られ、自身を問題化し、その「解決」は、自身の当事者性を明け渡すことにもなりかねない。
解決ではなく、捉え方、立ち位置の変更を探り当てるのが当事者研究である。捉え方を変えることで、その問題は自身に属するのではなく社会の側にあることに気づき、その変更を求めることで、解決ではなく解消の可能性を示す社会変革につながる。
認知症医療がピアサポートに関心を向けるのは、そこにある。
診断の告知が「早期診断、早期絶望」という空白の期間しかもたらさないとした10年前の藤田和子さんの告発のような提起に、認知症医療の側が誠実な自己検証を重ねて辿り着いたのが、この診断後支援とピアサポートなのである。
ここ50年来の認知症史を紐解いても、原初、認知症医療は治すことができないとするところから歩み出し、敗北の医療ともいわれた苦渋を呑み込むようにして、「治す医療」から「支える医療」の模索を絶やすことはなかった。認知症医療は当事者とつながることで、治す医療から支える医療へ、さらには、より良く生きる医療へと進化と深化の道筋を歩んだ。
それは認知症ケアの充実につながり、当事者発信の背中を押し、そして今日の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に流れ込んでいる。
もちろん、医療の側の課題は依然として根深いものがあると指摘する声もある。そのことを踏まえるなら、むしろ、医療がピアサポートという発信点を自らイン・クリニックに内実化することで、常に当事者のまなざしに自己検証されることを引き受ける覚悟を示したと言えないだろうか。
その意味で改めて、認知症医療がここに至るまでの道筋は確認しておいた方がいいだろう。
被災地などの福祉の現場にたたずむと、つらさと困難の只中にいる人々から、専門家はやって来て、そして去って行く、という怨嗟にちかい声を聞くことがある。それは絶望を倍加する、と。
専門家たちは、嘆きの人々にやさしい声をかけつつ他者性の振る舞いに終始し、いくつもの見解と指導を示し、そして難しげに顔を振りながら去っていく。それは支援の擬態であり、嘆きに加え孤立と不安を植え付けるだけだ。
これはかつての認知症の診断の姿である。「あなたは認知症です。残念ながら治りません」
告知、宣告。病名を伝える単語はいつも恐ろしげに響く言葉をまとう。病名を告げるだけでなく、その瞬間、名前も人生も尊厳も全て奪われ「認知症の人」とされ、昨日と変わりない自分の日常は、たちまちに不安、孤立、絶望に取って代わる。
認知症と診断される人が最初に出会う他者が医療者であるのに、その人は「去っていく専門家」なのだった。
医療者もまた知らなかったのである。クリスティーン・ブライデンが知性に満ちた言葉を連ねて訴えるまでは、疾患としての認知症は知っていても、診断される「人間」を知らなかったのである。(心ある)認知症医療者たちは自らを詰問するような検証を重ねた。
今この会に参加した多くの人々も参加している「認知症当事者勉強会」は、その前身を「認知症当事者研究会」とし、その発足の会ではひとりの認知症医療者が、それまでの薬剤処方に頼っていた自らの医療を慚愧に満ちた告白をしたことが印象に残っている。
認知症医療は自らの権威を手放すようにして前向きな無力感を自覚するところから当事者性を内包することになったのである。
今の「診断後支援」はそうした認知症医療の人格性に基づいている。彼らはその過程で「医療は、認知症の人に何ができるだろう」という自己審問を今、「医療は、認知症の人と何ができるだろう」とさらに拓いた。ここに診断後支援とピアサポートが接続したのである。
医療は当事者の側に立つ。
認知症医療の診断後支援は、私たちは立ち去らないという医療者たちの宣言であろう。
2日にわたる合宿のような会合は、夜になるとホテルの一室に集まっては痛飲し語り合いを続ける。
医療者、医学生、専門職、メディア、行政者、本人、誰それも一緒になって語り合いは深更まで続くのが常である。誰もが当事者なのである。
診断後支援という医療用語は、本来、診断自体が支援であるべきで、「診断後支援」は「診断支援」ではないかという含みがある。そこにピアサポートがある。
「あなたは認知症です。これまでずいぶん大変だったでしょう。今はさまざまな手立てが見えてきています。それにあなたはあなたであることに変わりはありません。診断されていまは混乱しているかもしれませんね。
このクリニックではピアサポートをしています。そこにはあなたと同じ境遇の人がいます。よかったらそこでまず今のお気持ちを話してみたらいかがですか」