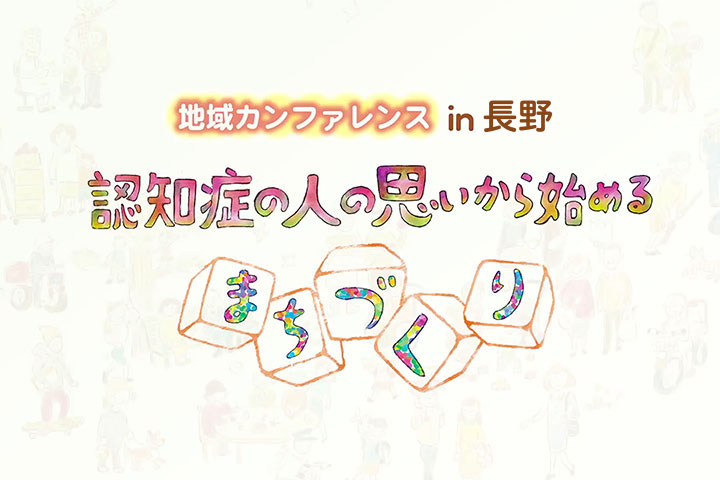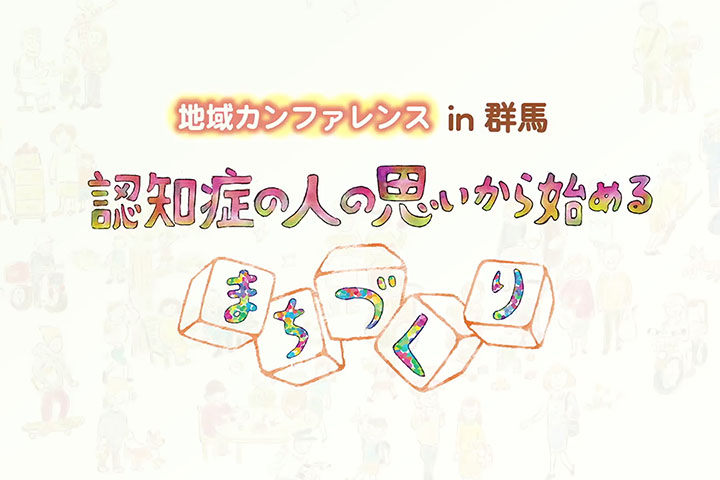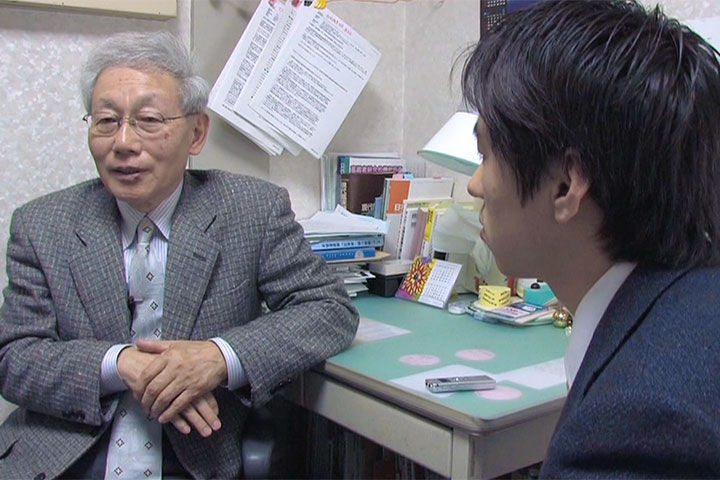▲ボランティア情報の機関紙。ささやかな冊子だが、各地の息遣いを感じる内容で読み応えがある。新たな視点でのボランティア社会こそ、これからの社会システムかもしれない。
新型コロナウイルスもまた新たな感染拡大の懸念も言われ、師走となって気ぜわしい中でただ気分だけが右往左往している。
ここで深呼吸するようにして、さてこれからのこの社会をどうすればいいのか。師走の宵にふとそんな思いに駆られても、いつもその辺りからその先に進むことができないでいる。
「これからのこの社会は・・」という設定自体に実は無理がある。ここには主体も客体もあいまいで、ここにあるのはただ茫漠とした気分だけで、今の不安の単なる言い換えでしかない。
「これからのこの社会」、確かなことは何ひとつわからない中を私たちは暮らしている。
私は地域福祉や認知症、がんといった医療、あるいはまちづくりなどの地域活動にささやかな関わりを持っているので、さまざまな団体から機関紙や報告書が送られてくる。
そのひとつ、全国社会福祉協議会の地域福祉部には全国ボランティア・市民活動振興センターがあって、私はここの運営委員をしていることもあり毎月ボランティア情報という冊子が届く。
せいぜいが10ページほどの体裁ながら、毎回ここには、ぎっしりと全国各地からのボランティア活動の取り組みが報告されている。
この冊子には漠然とした不安に塗りこめられた「これからのこの社会」への確かな展望が示されていると、私は思う。展望と言っても、眺め回す他者性のまなざしではなく、地域の中から、地域という現場を引き受け、あるいは引き受けざるを得ない人々の生の声で綴られている。
この社会は今どのように動いているのか、動き出そうとしているのか、その最前線がこの冊子には息づいている。
毎回、心動かされるのは、ここにあるのは活動報告ではあっても、その行間から溢れるのは「思い」である。地域への郷土愛であると同時に、この社会のありようへの切ない思いがあり、何より、自分を含めた「人間」への深い思いが否応なく溢れ出ている。
たとえば直近の11月のボランティア情報には、特集として中高校生のボランティアの取り組みが報告されている。そこにはこれまで「支援の受け手」として捉えてきた中高生世代を、主体的なボランティア活動の「担い手」として捉え直している。
山形県南陽市での中高生のボランティアサークルが発足したのは1999年、始まりは福祉科や看護科に通う高校生三人が「授業での学びを地域で実践したい」と、南陽市の市社協をひょっこりと訪ねたのがきっかけだという。いかにも地域の包容を示すようなあたたかなエピソードである。
こうして出来たボランティアサークルに中学の時から参加していた一人の少女がいた。中学高校とボランティア活動を経験したその少女はその後、市社協に入職し今度はその中高生のボランティアサークルを担当している。少女の成長物語がそのまま地域の成長となっている。これからの私たちのこの社会の希望の姿のひとつだろう。
あるいは佐賀県みやき町の事例報告では、福祉を学ぶ高校生が講師となって小学生や高齢者を対象とした介護講座をおこなっているとある。講座を開くにあたって高校生たちは事前に何度もデモンストレーションを練習した。入浴介助や排泄介助など、説明役と高齢者役に分かれての練習は教師や教育の現場を変え、若い世代にとっては何よりの高齢者理解であり、当事者性の獲得だったろう。
何ひとつ確定的なことは言えないこの社会で、ただひとつ確かなことはいずれこの社会は若い世代が担うことになるということだ。だとしたら、いつまでも「大人」の側ばかりが、この超高齢社会の怯えをガラガラとかき回すだけでなく、いっそ若い世代の声を聴き、地域に彼らの参画の場がもっとあっていいのだろう。
「地域包括ケアシステム」「地域共生社会」は、少子超高齢社会という「これからのこの社会」を見据えた社会システムであることは間違いない。しかしこのシステムは、施策理念という上から下へと降りてくる途中に浮遊し、地域の現実に行き着く前のどこかで霧散してしまいがちだ。
ボランティア情報に載せられた地域の声は、いわば、「地べた感覚」の現場のリアルであり、成果成功だけではなくそれと等分に、地域からのクレームや、ボランティアに対して「かわいそうな人にやってあげる」といった旧来の福祉観の壁を打ち破れない悔しさや、取り組みでの失敗の数々もまた共有すべき重要な情報として記されている。私は、むしろこうした声の貴重さこそもっと可視化されていいと思う。
そして災害は常に大きな試練である。今年3月のボランティア情報では、東日本大震災から11年の特集を編んだが、その中での南三陸町社協での報告では、身近に命を落とした人が多数いる中での被災者からの言葉を取り上げた。その被災者は震災10年の昨年、周囲から「節目ですね」と何度も言われたことに違和感を持ったという。
「時間としては確かに節目ですが、私は「継ぎ目」だと思うのです。被災者は一人ひとりが異なる歩幅で、一歩進んでは二歩下がるということを繰り返してなんとかここまで来られたのです」
うなだれてうなだれて顔をあげる。ひとりの被災者の言葉も重みもさることながら、この言葉を受け止めた社協の担当者の感性もまた、大きな気づきと使命を自身に刻みこむ。
これからのこの社会は、それぞれが異なる歩幅で一歩進んでは二歩下がり、それでも確かに前に進む。「節目」などという区切りなく命は続く。涙振り払い、命を落とした人のためにもそのように生きねばならない。
この被災者の言葉に、「社協は変わらねばならない」とこの女性担当者は記すが、それはそのまま変わらねばならないこの社会への一歩なのだろう。
ボランティアには互酬性がある。
誰かが誰かを助けてあげる、ということがボランティアではいささかもない。ボランティアをすることが、自己肯定であり自分と社会の「育ち」の力であることは、このボランティア情報の全国からの報告から読み取れる。ボランティアがこの社会を変える。
そうしたことを世に問うた一冊が、今から30年前の1992年に出版された「ボランティア・もうひとつの情報社会」(岩波新書)である。著者は福祉関係者ではなく、情報学のフロンティア、金子郁容氏だった。
当時、私はこの新書に大変に新鮮な思いで接したことを今も印象深く覚えているが、その内容はこの時代性の中、また注目されていい記述が含まれている。
それはボランティアと、バルネラブル(vulnerable)との関係性についてである。
このバルネラブルという単語は日本語にはない概念と言ってよく、あえて言えば脆弱性、傷つきやすさ、ひ弱、とされている。
金子郁容氏は、このように記している。
「ボランティアは、ボランティアとして相手や事態に関わることで自らをバルネラブルにする。
どうして、あえて自分をバルネラブルにするのか。それは、問題を自分から切り離さないことで「窓」が開かれ、頬に風が感じられ、不思議な魅力ある関係性がプレゼントされることを、ボランティアは経験的に知っているからだ」(P.112)
どうだろうか。文章の含意が広く、わかりにくいと言えばわかりにくいが、金子郁容氏はあえて解説や論理ではなく、体験することの感覚の力に託しているところがある。
そして、ここでのバルネラブル(ひ弱、脆弱)という言葉が、昨今再び注目されている。
それは私たちは「弱い存在」なのだということだ。社会福祉の分野では、「弱さの公開」こそが、真に勁い(つよい)社会であるとも言われている。あるいは作家、箒木蓬生氏の「ネガティブ・ケイパビリティ」の著作であるとか、これまでのポジティブ一辺倒の社会の生きづらさからの脱却としての「弱さ」の再定義がされている。
そのことを30年前、まさにバブル景気への挽歌のように著した金子郁容氏の「ボランティア論」は、今巡りめぐって、3年にわたるコロナの事態のこの社会の新たな指針でもあるように思える。
バルネラブルな私たち。ひとりでは生きられない私たち。
そのひ弱な存在が、互いに認め合い与え合うようなボランティアという互酬性の行き交う関係性に、それぞれがそれぞれの異なる歩幅で小さく歩み続ける。
それが、「これからのこの社会」という未来なのかもしれない。