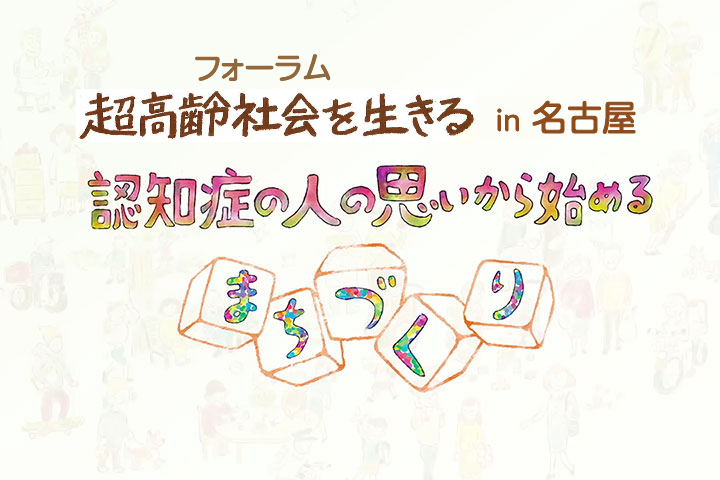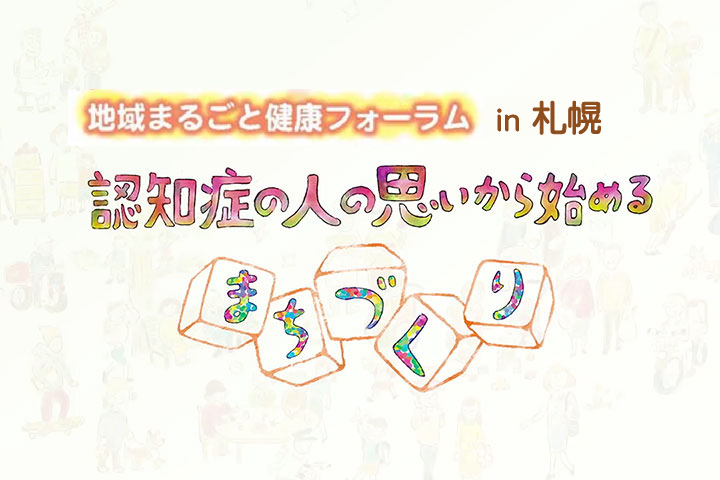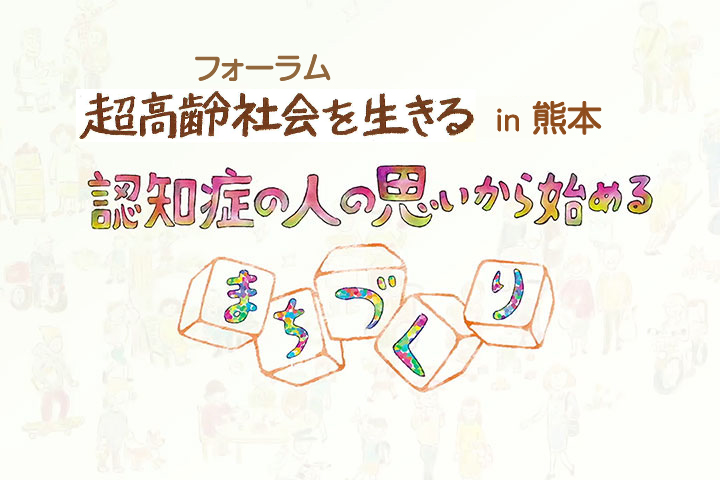▲最近はサブスクリプションで聴くばかりですっかりCDにご無沙汰している。手前に小澤が指揮した「ノヴェンバー・ステップス」の懐かしいCD。聴くたびに心がシャンとする。
小澤征爾さんが亡くなった。
私にとっての小澤さんの音楽は、書斎に置かれたオーディオ再生を通して、コーヒーを飲みながらや読書をしながら、あるいは何かをパソコンに打ち込みながら聴いていただけで、私自身はなんの専門性も持たないしがない音楽ファンのひとりにすぎない。
それでも、神経がささくれていたり、何事かに思い惑う時に、小澤さんが紡ぐ音の世界にひたることでどれだけ助かったかわからない。ありがとうございました。
食道がんから復活し、ニューヨークのカーネギーホールで自ら創設したサイトウ・キネン・オーケストラを振ったブラームスの交響曲第一番は、演奏終わるや、ブラーボーの嵐とスタンディングオヴェイションがうねりのように高まり押し寄せ、「奇跡のニューヨークライヴ」と言われた。
2010年9月のサイトウ・キネン・フェスティバル松本では、病気療養中でドクターから10分以内ならという許しを得てのチャイコフスキーの弦楽セレナーデの第一楽章だけを振った7分半の映像がある。これはもう魂の音楽だな。映像で見ると小澤征爾の存在そのものが音楽の具現で、途中に小澤のうめくような声や鼓舞するような声も入り、ただもう圧倒される。これもまた「奇跡のセレナーデ」とか「復活のセレナーデ」と呼ばれた。
いやいや、素人の私が小澤さんの音楽についていくら語ったところで、たいして意味はない。
私がここで言いたいのは、次のことである。
かつて小澤征爾さんはあるドキュメンタリーで、恩師である斉藤秀雄の言葉としてこんなことを語っていた。
「オーケストラというのは、最初は四人から始まった。
第一バイオリン、第二バイオリン、ビオラとそしてチェロという室内楽の弦楽四重奏を起源としている。では、そこから100人規模のオーケストラがどのようにして生まれていったのか。
室内楽には指揮者はいない。指揮者のいない中でどうしたのか。
それは互いに目を合わせ、他の奏者の旋律を聴き取り、互いの呼吸、息遣いを合わせ、そうすることでオーケストラに育ち、シンフォニーが世に響き渡った。」
このことを小澤征爾さんは熱っぽく語り、そしてそれは当然、小澤さんの音楽の本質でもあるのだが、私はこの言葉を聞きながら、これこそは私たちの地域社会でのまちづくりの本質ではないか、咄嗟にそんな想いが浮かび上がった。まちづくりとは、地域社会というオーケストラを奏でることだ、そんな突飛なイメージも浮かんだりした。
そう言えば小澤さん自身も、1992年から長野県松本市で毎年夏に「サイトウ・キネン・フェスティバル松本(2015年より、オザワ・キネン松本・フェスティバル)を開催し、今やすっかり国内外に定着している。小澤さんは、まさに「楽都・松本」としてのまちづくりの実践者なのである。
だが、このコラムの文脈でのまちづくりは、地域の「ともに生きる」という暮らしの中のまちづくりであって、当初は小澤さんの芸術観と世俗のまちづくりとを勝手につなげるのはいささかおこがましいような気もしていたのだが、どうも改めて考えると小澤征爾さんの松本での取り組みと、地域の小さなまちづくりの根っこは同じ風土と思想に根ざしているようである。
いうまでもなくオーケストラを構成する楽器となれば、弦楽器、金管木管楽器、打楽器とそれぞれ個別の音色と個別の役割を持つ。その多様性に満ちた楽器群が、互いの音と旋律を懸命に聴き取り音色をかさね、息遣いを合わせまなざしを交わし、100もの奏者と楽器の音がハーモニーとなりひとつの壮大なシンフォニーとなっていく。それがオーケストラというものだ、小澤さんはそのように語ったのだ。
それは先日開催された「認知症とともに生きるまちづくり大賞」のまちづくりの人々の取り組みと大きく重なり合う。
まちという舞台に、認知症だけではなく、いわばさまざまな個性という楽器を持つ人々が集い、互いの声を聴き、息遣いを合わせながらそれぞれの音色を重ね合わせるようにして暮らしの日々を奏でていく。日常というシンフォニーを響かせる。
確かにあの「まち大賞」に集まった人々の関係性は、固定したものではなく自然で、暮らしの中を流れる笑いや哀しみの音楽的な広がりや、フォルテ、ピアノ、アンダンテなど緩急のリズム感にあふれている。ともに暮らす、ともに生きることのリズムと言ってもいい。
社会学の創始者のひとりとされるG・ジンメルは、社会とはどのようにして生まれたのかをジクジクと考えめぐらせたドイツの哲学者である。
彼はそれを、それぞれの個人が互いに心から他者に働きかける相互作用によって成立するとした。ジンメルは、個人が他者に働きかける「心的相互作用」という関係性の構築が社会であるとし、そのプロセスを「社会化」としたのである。
ま、厳密に言えばこの「心的相互作用」についてもさまざまな解釈があるのだが、でもね、この「心から他者に働きかける相互の関係が社会をつくる」って、なにか響くところがないだろうか。この一節だけでも、はるかな時空を越えて現在の私たちへのメッセージと捉えることができるし、あるいはどこかで、小澤征爾さんの語ったオーケストラという音楽空間の成立とも響きあう感じがする。
そう言えば、前のコラムで「認知症の本人の声を聴くことは、実は自分の声を聴くこと」と書いたのだが、「あのさ、そこんとこもう少し」と親しい仲間から言われた。
「あのなあ、私のスタンスは、答えではなく問いを立てる、ということなんだからね」とかゴニョゴニョ言ってその時はお茶を濁したのだが、まあ、しかたない、私なりの思いを言えば(答えではない)「聴くこと」というのは受動ではない。それこそが互いの心的相互作用であり、「聴くこと」は、「自分」に向き合い発見する極めて積極の能動なのである。
「認知症の本人の声を聴くこと」は、それはそのまま自分の中の弱さや不安や、思考の歪みや無知偏見と向き合うことになったり、あるいは自分の可能性や強みや、さらには思いがけずまだ見ぬ自分と出会ったりすることになる。
「認知症の人の声を聴く」というのは、別に認知症の人のために何かをしてあげましょうということではない。認知症を自分のこととして考えましょうという説教でもない。
他者へ心から働きかけることで、自分を見つめ、自分を発見し自分の理解への一歩になる貴重な経験なのである。
いったん大きく息を吸い込むようにして自分に向き合った時、果たしてあなたは、自分の声を持っているのだろうか。誰かの声を自分の声と錯誤して、その声で自分を規定しているのではないか。
認知症の人が認知症を語る時、「わたしは」と語り始める。
認知症ではないとされる私たちが認知症を語る時は、「認知症とは」と語り始める。
認知症を生きる人たちは、「わたしの物語」の主人公である。認知症ではないとされる私たちは、「わたしの物語」を持っているのだろうか。「わたし」はどこにいるのだろう。「わたし」はどこにいってしまったのだろう。
ジンメルは、心から他者に働きかけることが社会となると捉えた。
心から他者に働きかけるには、「わたし」という誰とも取り替えがきかない「個」がなくてはならない。「わたし」という楽器を持たなくてはならない。
フラッシュモブというパフォーマンスがある。
街角で通行人に紛れて楽器を持つ人が突然演奏を始めると、次々にあちこちから楽器を抱えた人が加わり、やがて見事なアンサンブルとなって、立ち止まった人々がいつしか熱心な聴衆となり、そして盛大な拍手喝采の中に演奏が終わると、またもとの雑踏に戻っていく。
あれはどこか、私たちの、「他者への心からの働きかけ」という潜在する願望が成り立たせているサプライズに違いない。
小澤征爾さんは1967年にニューヨークで、武満徹作曲の「ノヴェンバー・ステップス」をニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団で初演し、絶賛を浴びた。
尺八と琵琶とオーケストラの協奏曲といういわば西洋音楽の他者である和楽器との心からの相互作用といった異色の編成で、そのどこにも旋律的主題を持たない11のステップという音楽だ。
わたしは「ノヴェンバー・ステップス」を聴くたびにいつも「わたし」の深いところが揺さぶられるような想いがする。精神の弾力を取り戻せるような気がする。新鮮なこころの共振をもたらす音楽である。
作曲した武満徹さんは、ノヴェンバー・ステップスのCDのライナーノートに箴言のようなコメントを寄せている。
「オーケストラに対して、日本の伝統楽器をいかにも自然にブレンドするということが、作曲家のメチエであってはならない。むしろ、琵琶と尺八がさししめす異質の音の領土を、オーケストラに対置することで際立たせるべきなのである」(※メチエ:表現技法)
「まず、聴くという素朴な行為に徹すること。やがて、音自身がのぞむところを理解することができるだろう」
こうした言葉に自分の思考を濃くしていくと、芸術家の言葉とは決して崇高に漂うのではなくむしろ、わたしたちの日々の暮らしの感覚にピッタリと響いてくるような気がしてならない。
|第272回 2024.2.15|