-
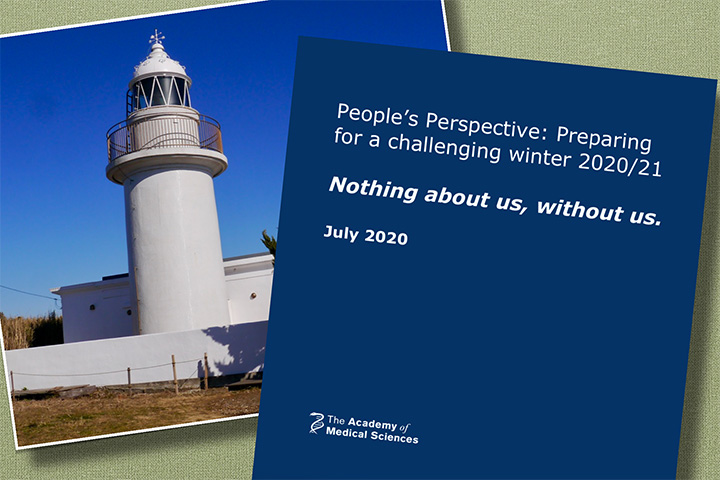
介護崩壊と「 安心して感染できる社会」
コラム「介護崩壊を防ぐために」というオンラインの話し合いにずっとオブザーバーで参加している。こうした介護関係者の議論の場は全国各地で様々な形で行われているようだが、私は仙台の「宮城の認知症を共に考える会」のオンラインの場に参加している。
-

「認知症」を読む。医師 木之下徹の一冊
コラム診察室では白衣でなく、一年中着慣れた(ヨレヨレとは言わない)Tシャツ、その大柄な身体を申し訳なさそうに幾分かがめるようにして認知症の人やその家族と接するのが、木之下徹医師のスタイルだ。
-
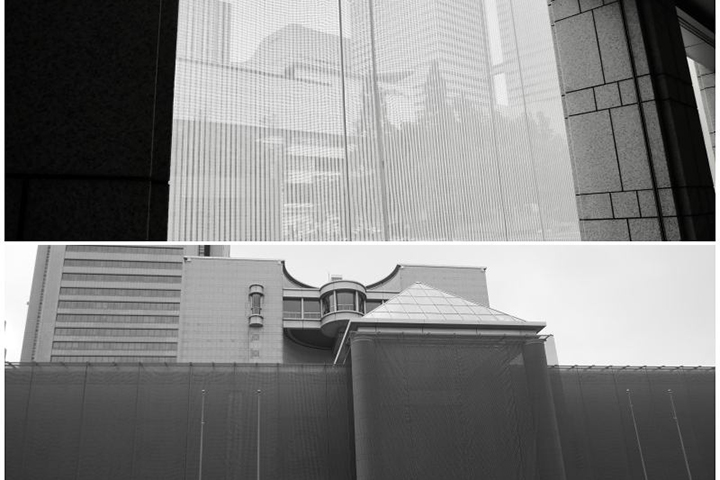
「認知症」という不安、その希望
コラム7月24日は芥川龍之介の河童忌、近代文壇の光芒となった稀代の才能がみずからの命を絶った日だ。「ぼんやりとした不安」という謎めいた言葉を遺して。
-
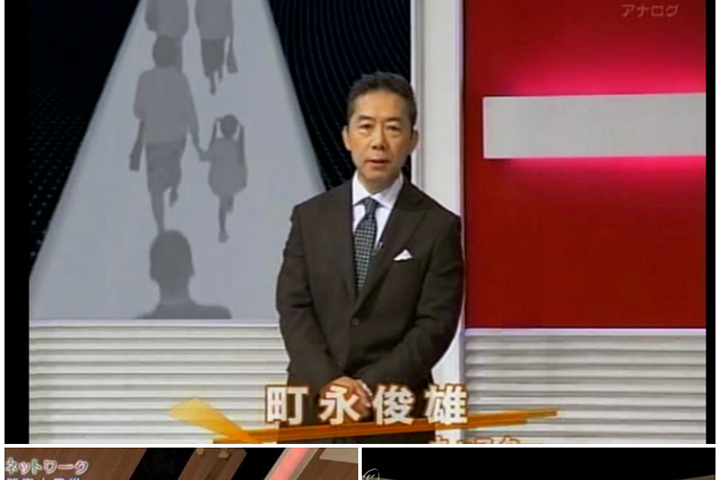
私の、「福祉ジャーナリスト」誕生の記
コラム私の今の肩書は、一応「福祉ジャーナリスト」というものである。どこかエラそうに聞こえてしまう以上に気恥ずかしい。 だから、名刺を出しながら「福祉ジャーナリストのマチナガです」と思いきり反り返って自分から名のることは、まずない。
-

私が 認知症の人にインタビューしない理由(わけ)
コラム誰でもできるインタビューの技法というものがある。ふふ、企業秘密なんだがな。知ってます?これさえふまえれば、ともかくも世に言われる「インタビュー(らしきもの)」になってしまうのである。
-

認知症当事者が「語る」ことと「聴く」社会
コラム「語る」ことと「聴くこと」、これは認知症の当事者活動の核だけでなく、あらゆる市民的活動を推進させていく私たちの力でしょう。
-

「認知症を祝福する」 スコットランドの認知症活動をフィリー・ヘアと語り合う
コラム「あのね、人生にはアイドリングストップが必要なんだよ」「あなた、燃費悪いものですね」といった会話が交わされたわが夫婦の緊急事態は収束に向かうのだろうか。
-
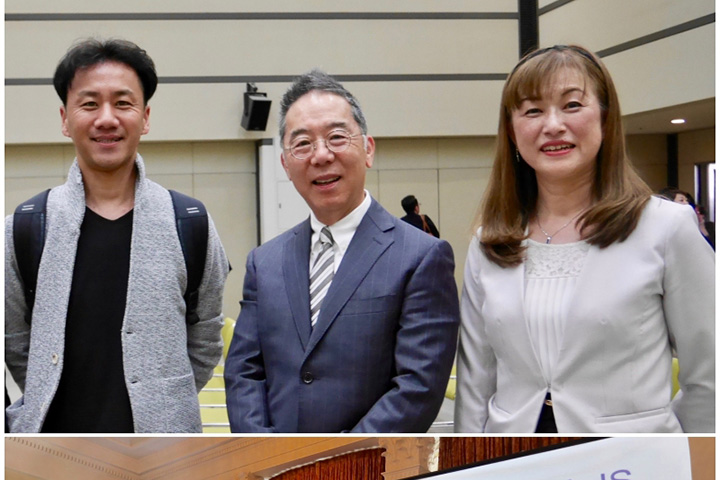
コロナの時代だからこそ、「認知症」にできること
コラムこのコラムでこのところ連続して、新型コロナウィルスがもたらしたこの社会の姿を追うように記してきました。この事態を考えるたびに気づいたことがあります。
-

コロナの時代に老犬とともに立ち止まる私は、この世界の片隅に何を見ることができるのだろう
コラムうちの愛犬は15歳のトイプードルだ。はるかな老犬である。プードルという犬種はひたすらノーテンキなキャラクターで、陽気にまとわりついては愛玩犬の全ての要素を振りまくようにして私の日々に彩りを添えてくれた。
-

緊急事態の延長と「今、私たちができること」
コラム緊急事態が延長されることになった。これで閉じこもるようなステイホームがさらに続くことになる。これまで人との接触を避け、不要不急の外出を控えることで、なんとかこの事態の収束につながるようにとがんばってきた人々の中にも、糸が切れるように自粛疲れが出始めたのだろうか。
-

「認知症」に、拍手を!
コラム新型コロナウィルスの最前線で取り組む人々の奮闘で、私たちのステイホームが成り立っている。この最前線が決壊すれば、私たちのホームだけでなく、暮らしと命が崩壊していく。
-

新型コロナウィルス、その最後の防波堤はだれか
コラム私は長くメディアの世界で過ごしてきて、幸いすぐれたスタッフ、仲間に囲まれて、多くの至らなさ失敗を重ねつつも、とりあえず、まあまあ、やりがいや手応えのある人生だったと思っている。
-

「認知症と共に生きる」は、新型コロナウィルスに真価を発揮するか
コラム緊急事態宣言が出された。私の部屋から小さな児童公園が望めるのだが、そこの桜の満開過ぎて、風に花びらが舞い、梢には瑞々しい若葉が萌え出ている。
-

認知症を障害ととらえる 〜認知症当事者と語り合う仙台リカバリーカレッジ〜
コラム仙台のリカバリーカレッジに参加した。リカバリーカレッジというのは、認知症当事者がこの社会に参画するための、認知症当事者たちが主体的に開く対話と学びの場である。
-

新型コロナウィルスの感染者と認知症当事者が見た おなじ風景
コラム今回の新型コロナウィルスの事態で、今なお感染してしまった人の姿がほとんど見えていません。見えていないというのは、実際に見えるか見えないかではなく、その存在がこの事態に可視化されていないということです。
-

「新型コロナウィルス」が本当に問いかけていること、その脅威とは何か
コラムこの事態だからしょうがない、引きこもって読書三昧と思ってもどうも身が入らない。というか心が入らない。晴耕雨読というのが最高の充実の時間とされてきたのは、社会と個人の一定の安定が前提だったのだ。
-

新型コロナウィルスは、私たちの何を試しているのか
コラム新型コロナウィルスによって、この社会のありようが一変した。私の親しい友人は、メールで「お互い生き延びよう」と呼びかけた。「生き延びよう」という言葉が私たちの日常の暮らしの中に入り込んだ経験は、戦時中の世代はともかくとして現在の私たちにはなかった気がする。
-

認知症がほほえんだある町の特別な、そしてあたりまえのいちにち
コラム2月15日に東京都町田市で「まちだDサミット2」が開催された。認知症をテーマに東京郊外の町田市が、認知症の資源の全てを結集させて取り組んだ大掛かりなイベントである。
-

「認知症は社会をケアする」とはどういうことか
コラム「まだまだ寒いわね。一人で暮らしているから、部屋はなかなか暖まらないでしょ。コタツに潜り込んでも、それでも体の芯がとても冷たい。ある時、気がついたの。寂しいからなの。寂しさって、冷えるの。身体も、そして心が冷えて冷えて・・」本人の声を聴くということは、自分の中の声を聴くことだ。
-

認知症は、老いのスティグマを解き放す
コラム「老人」という言葉も悪くない。そんなふうに思った。普段、福祉的テーマでは「高齢者」という用語を使い、口語的な語りでは「お年寄り」と言うことが多い気がする。