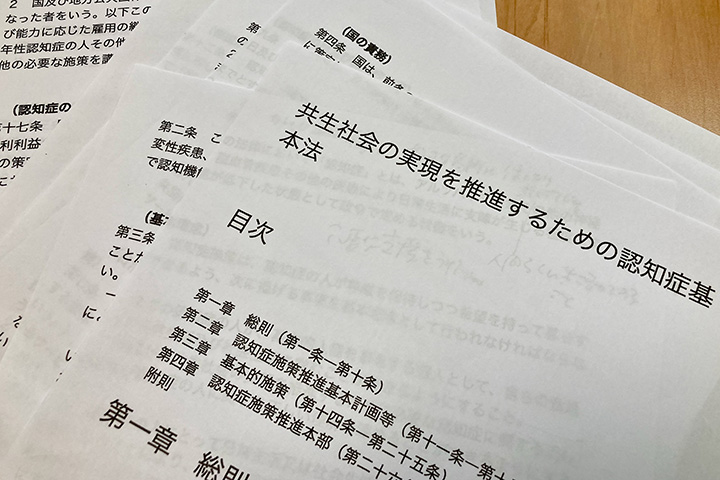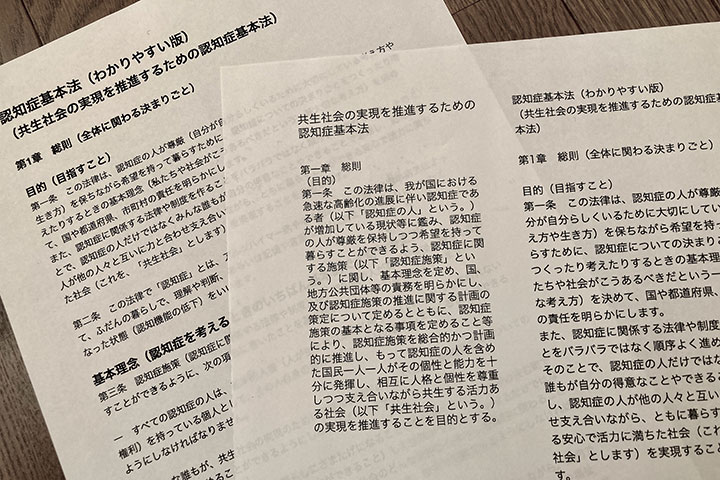▲6月の空。詩人は、「おうい雲よ」と語りかけ、「どこまでゆくんだ」と呼びかけて、じっと耳をすませたに違いない。語りかけ、耳かたむけることでしか、この世界の在りようは見えてこない。心込めて語っているか、そして聴いているか。
「語る」ことと「聴くこと」、これは認知症の当事者活動の核だけでなく、あらゆる市民的活動を推進させていく私たちの力でしょう。
ほとんど誰にもできて、ほとんどの誰もがなかなかできていないのもこの「語る」と「聴く」と言っていいのかもしれません。考えてみれば「語る」と「聴く」という二つの言葉は右手と左手のように明らかに別の言葉なのですが、互いに意識し離れることができません。
それは目的語をつけて他動詞として雄弁になることもあれば、単独の自動詞としてひっそりと主語を磨いたりします。
「語る」は能動性の言葉で、対して「聴く」は、受動の言葉と捉えられがちですが、実は当事者活動での「聴く」は、この言葉に能動の性格をどれだけ注ぐことができるかにかかっています。単に聴くだけ、ということはあり得ず、そこから多様な能動が派生していくことが当事者活動といってもいいのかもしれません。それはまるで自分の右手と左手をガッチリと握りあわせるようにして。
いうまでもなく当事者活動は「語る」ことから始まりました。
当初の「認知症になると何もわからなくなる」という地点からの発信はどんな営為であったのか。認知症の本人にとって、それははるかな階段をひとつずつ踏み上がるような果てしない挑戦でした。ある認知症当事者はこんなふうに語ります。
最初に聴衆の前で語るとき、震える背中をそっと押し出すようにして一緒に登壇してくれた人がいた。その人は原稿を共に目で追い、つかえればさりげなくその部分を指差し、大丈夫、私がいるからという風にうなずいた。その次の機会には、その人は隣にいてくれてしっかりと見守った。その次にはもう少し距離をとり、やがてその人は舞台袖のいつでも見えるところにいて、そしてついには、その人は聴衆と共に会場の一番後ろにいて胸の前で手を握りしめて聴いていた。
このプロセス全てが「語る」ということです。語ることを共にする。これが新たな支援の形を創り、パートナーシップの原型を生んだのです。
一方、認知症の当事者の発信が成立したのは、そこに「聴く人」がいたからです。
「語る」ことは「聴く」ことで成立し、「聴く」ことは「語る」ことを支えます。
改めて「聴く」こととはどういうことか。
私は平成29年度の厚労省老健事業の認知症の理解を深める普及・啓発キャンペーンで、4人の認知症当事者の「本人座談会」のDVD映像を作成しました。その解説にこう記しました。
「ここでの認知症の人の発言は、すべての認知症の人を代表しているわけではありません。皆さん一人ひとりが違うように、このDVDでの認知症の人もまた、一人ひとりが違った地域の違った境遇の中でそれぞれの暮らしを営んでいます。
このDVDは、認知症について何らかの「答え」を提供するものではありません。むしろ、認知症の当事者からの「問いかけ」ともいえるでしょう。それぞれの答えは、皆さんの側にあります」
ここでは、当事者が語ることを「聴く」ことを記しているのですが、この「問い」と「答え」は、共鳴する二対の音叉のように「語る」と「聴く」に響きあうのです。
これまで認知症の当事者はこんな風に語ってきました。
「認知症になってもできることがある」
これは当事者発信のごく初期に語られたことです。少しでも認知症のことに関わった人ならすでに常識なのかもしれませんが、初めてこの言葉を「聴く」とき、人々はどう感じたのでしょうか。
背景には当時の「認知症になると何もわからなくなり、できなくなる」という偏見がありました。今でもあります。となると、「認知症になってもできること」とは何か。それは世間の側に「認知症になるとなにもできない」とされていたことへの反論です。
そこからさらに一歩踏み込んで「認知症になってもできることがある」としています。
この平易な訴えの深さは、「できなくなる、つまり生産性だけで人間存在を語るのか」という告発の鋭さを懐の奥に呑んでいます。この短いフレーズは、「できる、できない」という次元を突き抜けて、私たち人間の存在の根本を問いかけるのです。ここには「認知症」を超えた普遍の問いかけがあり、当事者だからこその「語る」力がほとばしります。
こうした当事者の「語る」ことに向き合った一群の人々にとっては、それは我が身を震撼とさせる体験でした。当時、私もその場にも居合わせていましたが、当事者の声を聴いたとき、当事者の声を聴いたものとして何を語るべきか、誰もがほとんどうろたえたのです。
それまでの「認知症問題」として捉えるのではなく(問題化するのは、ある意味簡単でした。その解決策を他者として語ればいい)、同じこの社会の一人の人間として語るべきことは何か、そのことが問われていると誰もが聴き取ったのです。
「聴く人」はその場に安住はできません。聴くことは、自分の内に語るべき何があるのか、と自己審問を重ねざるを得ません。思えば、そのとき「聴く」側にいた人々がその後の当事者活動を切り拓き、そこから支援の形の検証や、パートナーシップであるとか、水平の関係、権利という言葉を練り上げ、生み出していったのです。
それはいわば、「聴く」人は、自分自身との対話をするようなものです。「聴く」べきは、認知症というより「人間」を聴くということなのではないか、という気づきでもありました。
ポストコロナが言われ始めていますが、確実なことは経済対策で発動した未曾有の赤字国債増発を抱えての国家運営になるということです。未来の巨額のツケを抱え込んでのポストコロナです。そして明らかになったことは、社会的弱者に対する医療や公衆衛生のセーフティネットの脆弱です。今後こうした社会保障政策はより危うくなる予測も出ています。
と同時に、この事態で明らかになったことがもうひとつあります。それはどこかで聴くことの選別があったのではないか。私たちが聴いていたのは誰の声であったのか。本当に聴くべき声に耳を傾けていたのか。自粛の中で沈み込んだ声は誰が聴いていたのだろう。医療や介護の現場では、「命の選別」の現実が押し寄せていたと報告されています。
それは報じられる過程で、医療現場の逼迫、混乱、崩壊という大きな言葉でくくられてしまいましたが、瀬戸際でなんとかなんとか切り抜けられたのは、制度が支えたのではなく、命を守る現場の医師や介護専門職たちの「人間」が支えたのです。私はそう思います。
それは当事者たちの声を聴くことの経験を積んだ人間の力です。
今後、この国も含めて世界経済がどのような道筋を進むのか、その予測は難しいでしょう。であれば、だからこそ、経済の枠組み以外の社会システムとしてのくらしのレジリエンスが必要です。それは、「聴く」ことから組み上げる社会といってもいい。
世間には「聞く耳持たない」という言葉があります。文字通り、「聞かない」のです。聞いたフリだけです。聞く耳持たないというのは、関わりだとかつながりだとか対話という民の側の働きかけを遮断する心ない言葉です。シカトです。
この国のある人々は、たぶん、聞く耳を持たないのです。耳という器官はアベノマスクを引っ掛けるところとしか認識していないのだと思います。
ですから、私たちの側でしっかりと、地域社会での聴く耳の感度を整備していくしかありません。
これからのこの社会は、「聴く社会」になることが求められています。当事者の声を聴く。弱い声を聴く。対話は、聴く人がいることで始まります。
誰かの声を聴く人が必ずいる社会、この社会のこれからは、そのような風景の中に描かれると思っています。