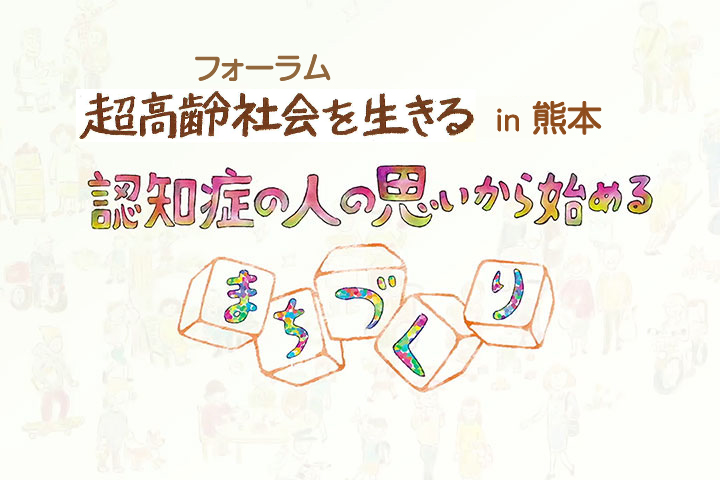▲季節はゆっくりと過ぎてゆく。港の公園では、人々がそれぞれのベンチに間隔をとって座り、同じ雲と空と海を見つめている。誰もが、同じこの社会を見つめている。やがて、いつの日か、ベンチから立ち上がり戻るべきところに歩みだす時、この社会は私たちの望む社会になっているだろうか。
私は長くメディアの世界で過ごしてきて、幸いすぐれたスタッフ、仲間に囲まれて、多くの至らなさ失敗を重ねつつも、とりあえず、まあまあ、やりがいや手応えのある人生だったと思っている。
が、それでいながらその渦中にあってどこか、そこに「これは虚業に過ぎない」といった思いがふいとよぎることがある。
深夜、放送センターの長いリノリウムの廊下をコツコツと歩いているときや、スタジオの重い扉を押して、テレビカメラに囲まれた照明の中に歩み入るときに、さっと影が横切るようにそんな思いにとらわれる。なぜ「虚業」と言った足元が揺らぐような不確かな思いがよぎるのだろう。
私の父親は東京の下町で表具職人としてその一生を終えた。戦後の貧しく無名の、数多な庶民の一人にすぎない。
息子の私から見れば、無学で無頼の人生の人だったが、贔屓の旦那衆には「知足堂さん(屋号だった)なら確かだ」と言われるぐらいにそれなりの腕はあったらしい。
貧乏暮らしでも、仕事に使う刃物や刷毛や和紙の吟味にはうるさく、酔っ払って帰ってきても深夜、裸電球の下、砥石に向かって刃物を研ぎ続けたりした。
注文を受けた書や画は、いったん仮貼りした作品の前で、表装の構想を練るためだったのだろう、腕組みをしては仁王立ちに睨み続けていた。
1925年築の早稲田大学図書館(今の会津八一記念館)は、当時、東洋一と言われた図書館専門建築だが、その大階段ホールの漆喰塗りをした左官職人が、工程最後の日、妻とまだ小さな息子を大理石の床に正座させ、妻子の見つめる中、丸天井を仕上げのコテで塗り終えたという逸話が残る。
私からその話を聞くと、父はその話がたいそう気に入って、わざわざ私とその図書館のホールを観に行ったことがあった。父なりに、その左官職人の仕事に対する心映えに共感し、意気に感じるところがあったのだろう。
つまりは、私の中に虚業に対して「生業」と言った言葉がどこかに刷り込まれていたのかもしれない。生業、なりわいということになるのだろうが、職人の感覚で言えば、おのれの身体感覚を通過させた手応えをもたらすものといったところだろうか。
それは単に仕事を指すだけではなく、生き方の思想と技法のようなものらしい。
頭脳だけ、観念の中だけでの空回りは、「料簡が足りない」とか「間尺にあわない」と言った独特の言い回しで切って捨て、学生になった私との論争にもなった。
生業というのは、文字通り、生身の人間の生き方であり、「てめえの暮らし」と地域に結びついていて、そこから離れた仕事というのは全て道楽なのである(父は赤貧の中、子供の給食費は滞留しても、暇があれば下手な小唄や謡をうなった)。しかし、その道楽も生業のためには必要で、いかに幅広い道楽から絞りあげることで生業を充実させることができるかという、ほとんど自己正当化の手順を踏む。
いかにも勝手な論理である。
そう、勝手なのである。暮らしというのは勝手が許されるところがあってはじめて、実は生き生きとした毎日を作る。子供は勝手な生き物で、女の勝手は暮らしの充実で、男の勝手は勝手だろ、という無茶苦茶な地点から創り上げてきたのが下町の風景なのである。
確かに近代の知性からすれば愚かしく、無駄や失敗やぶつかり合いの空間である。しかし、それがどれほど、生き生きと笑いと涙の、活力溢れた創造的空間であったことか。自分たちが創り上げた自分たちの共同体であることか。
落語の世界に接した人なら、そんな舞台は容易に想像できるだろう。
その「生業」の思想、感覚は、今、地域活動にそのまま注ぎ込まれていると私は思う。
実は、2月にこの事態になる直前まで、荒川と町田の、地域や認知症の人との活動に参加していた。そこでの人々誰もが当たり前に自発的に駆け回り、ふるまい、語り合っている光景を目の当たりにして、ここには確かに生業の感覚が息づいていると思った。
理念から引き降ろした行動ではない。頭脳や観念から生まれた活動ではない。誰かと何かを作り上げていくワクワク感。この方がいいのだという素朴にして勝手な思い。
失敗や無駄を、喜びややりがいに転化させることができるのは、自分だけではない繋がりがあるからだ。そのような失敗と無駄の暮らしと人生を歩んできたからだ。
失敗や無駄がなにひとつない人生などあり得ないことを経験として知っているし、失敗してもやり直せる人生の方がずっといいことは、地域の人が誰もがわかっている。
そこには、「共に生きる」とか「認知症にやさしい社会」と言う造語以前の、身体感覚の「生業」が備わっている。
今、新型コロナウィルスに、連日ネットやテレビに登場する人々の正論合戦がにぎやかに展開されている。確かにそれぞれの発言はきっとどれも正しいのだろう。が、多分、誰の発言も地域に息づく人々の生業感覚には届いていない。
この事態での正論は、結果を伴わない中で空転せざるを得ない。
何が正しいかの結果は常に未来になって初めて分かるしかなく、二週間後の感染者数の増減をはじめとして、おそらく一年後くらいまでその結果の正しさは検証されないだろう。
あともう一つ、口角泡を飛ばす論者の盲点は、この事態を収束に導くのは、実は論者ではなく、この国の一人ひとりの選択的行動の側にあるということを忘れている。
この事態を乗り切るためには、一人ひとりがSTAY HOME、接触をしない行動を選択することにかかっている。接触を避ける、不要不急の外出はしない、ということは何もしないことではなく、極めて積極的な抑制行動だ。
それがどんなにつらく、しかし重要なことかは地域のつながりの中に暮らしを創り上げた人々だけが知っている。
これまで福祉は誰かがやってくれるもので、生活者とは、常に福祉や施策のエンドユーザーと位置付けられ、サービスを受ける側の側面でしか見られてこなかった。
ところが、この事態で、これまで従順なだけとみなされてきた生活者が、市民として立ち現れ、自分たちの行動が、この国の命運を握っていることに気づいたのである。
それはこの社会が初めて、生活者、市民の側の行動の行使によって動かされる時代的体験を持つ。誰かがやってくれる社会ではなく、自分たちが直接関わるしかない事態なのである。
だとしたら、この事態で国が目を向けるべきは、経済対策での経済や企業だけでなく、何より社会の基盤を担う地域活動への支援策ではないか。最もつながりが必要な認知症の人や、子供たちや独居の高齢者などが今どのような思いで過ぎていく春を見つめているのか、その想像力は対策に織り込まれているのだろうか。
医療現場だけでなく、介護施設で高齢者、認知症の人と向き合う人々は、そこを「命の現場」として感染リスクと暮らしの共生接点をなんとか探り続けていることがわかっているのだろうか。
いつの日か、この事態が収束する時、この国の回復を担うのは、大企業などではなく間違いなく地域社会でつながりを築いてきた名もない多くの「生業」の人々なのだ。そのことを思い続けている。
|第137回 2020.4.23|