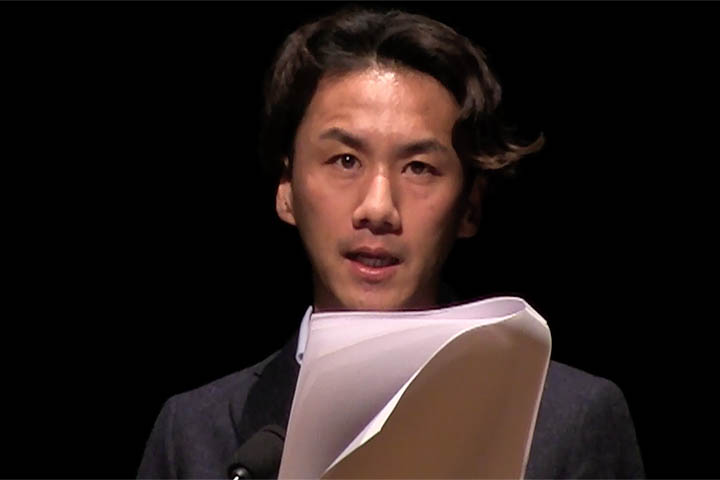▲この事態に巣ごもり生活である。もちろんそれどころでない人も多い。しかしそれは分断ではない。同じこの事態の経験を共有しているという稀有な状況に私たちはいる。そのことが無意味であるはずがない。つながりは、物理的な接触はなくてもより確かなつながりを生む、それが誰もが同じ状況を経験するということ。
うちの愛犬は15歳のトイプードルだ。はるかな老犬である。
プードルという犬種はひたすらノーテンキなキャラクターで、陽気にまとわりついては愛玩犬の全ての要素を振りまくようにして私の日々に彩りを添えてくれた。
その犬も15歳ともなれば、人間にすれば80代半ばとされる。耳は遠くなり、寝込んでいるところを二回三回と声を張って呼ばないと起きてこない。
散歩に行くのも、かつてのようにぴょんぴょん跳ね回る愛嬌は影を潜め、のっそりやれやれといった感じでつきあってやるという風情である。
外に出ると、この頃、彼はなぜかじっと立ち止まって周りを見回すのである。幼犬の頃からのなじみの風景を、初めてゴラン高原に降り立った牧羊犬のようにしてじっと見つめている。風に吹かれながら、見慣れているはずの風景のずっと向こうを見透かし、何か大切なことを見逃してはいないか考え込むようにして、ただ立ち止まる。
リードを引っ張っても小さな4本の足を踏ん張ってそこにとどまり、まだ確かめなければいけないことがあるかのようにふっと顔をあげ足踏み替えて、別の方角をまたじっと見つめる。
この、家族に愛されることだけで生き延びてきたバカ犬が、なにか思慮深い挙動を示しながら、ありふれた郊外住宅地の風景に、ここはいったいどこだろうとはるかな向こうを見つめ続けて物思いに沈んでいる。
この老犬の人生観(といったものがあるとすれば)に、何が起きたのだろう。
地上高十数センチの彼の視点からはこの世界はどのように見えるのだろう。何か底深い変化の未来なのか。それとも崩壊の予兆を嗅ぎ取ったか。私には不思議でならない。
私もまた、この小さく老いた生き物と連帯して物を思い、日々の時間をうっちゃるようにして過ごさざるを得なかった。老人と老犬の日々だ。
しかし、私にとっては必要な時間だったのかもしれない。愛犬のように風に吹かれながら目をすがめ、正義の声が行き交うコロナ論争の向こうに、本当はこの社会に何がもたらされようとしているのかを見透かそうとしてきたのかもしれない。
あるいは、今この世界では、梢に止まってざわめく鳥たちや夕方散歩に行き交うラブラドールやダックスフントの目配せ、水槽に泳ぐ金魚の気泡のつぶやき、公園のベンチで所在なく過ごす老人のため息、その誰もがこの風景の向こうに何かを感じ取り見出そうとしているのかもしれない。
世界は密やかに語り合っているようだ。
そのようなまなざしでこのコロナの時代を見透かすと何が見えるか。
緊急事態の解除の地域が示された。
これで、この事態に失われた日常を取り戻すことができるといった言葉がメディアに踊る。
でも待てよ、果たして「日常」というのはそんなふうに失われたり取り戻したりする交易品なのだろうか。「あたりまえの日常」と定型語として語られるが、そもそも日常というものは社会の組成としてあたりまえに準備されているわけではない。日常というものは、りんごの芯を手際よくくり抜くようにして暮らしから分離できるわけがない。
日常はあたりまえの所与のものとして存在するのではなく、それは人々の営みの中で必死に築き上げてきたかけがえのない想いや涙やつながりの集積なのだ。
日常はとても壊れやすく、それはいつも非日常と隣り合わせだ。しかし同時に、非日常とのせめぎ合いで、日常の輪郭はくっきりと輝くこともある。
今回のコロナウィルスの事態での自粛行動とは、その非日常と日常の辺縁をきわどく辿ることで、自分たちの日常こそが、私たち自身の大切な福祉ストックであることを確認したのである。
日常は、私たちのものだ。日常を失うと気安くいうが、それは暮らしの簒奪そのものだ。日常を誰かから与えられたり奪われたくない。
前回のコラムでこの事態は、私たちすべてが共通の経験をすることになった。それは私たちにとって稀有の一億総当事者経験ではないかと記したら、関西に住む古くからの友人の女性がこんなメッセージを寄せてくれた。
「一億総当事者。戦争以外にはなかったことですね。数々の自然災害の時はそれでもまだ一部だった。どんな状況下にあっても、何事もないように日常生活を送ること、それがいまの私たちに唯一できること」
なるほど。彼女はおおらかな感受性で地域活動や介護体験の中に自分の暮らしの彩りにも気を配る人だ。彼女には確かな世界観が据えられている。
確かにこの国は、この事態を国難と呼び、ウィルスとの戦いを呼びかけ、私たちも自粛行動や新しい生活様式に「動員」されているのかもしれない。
その彼女のメッセージに私が唐突に思ったのは、あの「この世界の片隅に」である。
あのアニメ映画の原作となった漫画家のこうの史代氏はそのあとがきに、「誰もかれもの「死」の数で悲劇の重さを量らねばならぬ戦災ものを、どうも理解できない」とし、「そこにだって幾つも転がっていた筈の誰かの「生」の悲しみやきらめきを知ろうとしました」と記している。
感染者の数でこの事態を量ることは専門家知見としても有効なのだろうから、ここでは特段のコメントはない。しかし、それが全てでもないはずだ。このコロナの時代の世界の片隅に、「生」の悲しみやきらめきで造り上げ守ろうとしている「日常」の力はどう算定されているのだろう。どう支援されているのだろう。
私はこれまでずっと認知症や地域福祉の当事者や現実のあれこれと共に歩んできた。
だから、どんなに愚かしく錯誤を繰り返すとしてもどこまでも生活者の側に立ち、互いの肩を抱くようにして応援していきたい。
生活者というのは、自分のことで精一杯なのだ。その中でなんとかそれぞれが手を差し伸べるようにしてつながっていかなければ、その精一杯の自分を見失ってしまう。だからあちこちで、語り合ってぶつかり合って嘆きあって、そんなことを積み重ねて地域を創り、それが社会になり、この国の「命と暮らしを守る」力になってきた。
生活者の語ることはいつも曖昧で繰り返したり、言い直したりする。そこには断定することはなく、つぶやくようにどうだろうか、と言い、自信なさげにそうだねえと繰り返し、でもやってみようよとうなづきあい、そのような声が積み重なって誰ものきらめきとなって、そこから立ち上がるのが、私たち自身の地域と暮らしというものだ。
それはデータを駆使し数値を積み上げ、確定的な課題を切り出し、冷たく光るカミソリのように切れ味のいいソリューションを提示する施策システムとは対極にある。
そして、今この国のコロナ対策は音を立てて経済対策へと雪崩を打っている。
メディアには、とても優秀なのだろうが、どこか貧相なイメージの経済閣僚ばかりがウロウロと登場し、私たちの暮らしの所轄のはずの厚労省担当者は、アベノマスクの不備の釈明だけに追われている。
閣僚の誰もがマスクで顔の半分を覆って発言し、それは意地悪く見れば具合よくごまかしの表情を隠す有効な手段になっているように見えてならない。マスクの陰に、私たちはごまかされ続けているような気がしてならない。
もちろん、働くことができなければ収入もなくなるわけだから、経済対策での補填は大切な社会活力の維持だろう。
しかし世の中を動かしているのは企業などへの有償労働だけではない。地域を循環する人々の活動や思いは、今静かにアイドリングを続けている。地域の人々が代わる代わるに、燃料を継ぎ足すようにそっと現場に顔を出し言葉を掛け合っている。
しかし、そのことにはなんの補償も補填もない。小さな声や弱い人々に寄り添う人々は今この事態に、活動ができない。互いに分かち合い与え合う無償行動の休業にはなんの補填もない。
いちばんの社会活力なのに。
今、出口が語られてきた。その出口はどんな社会につながっているのか。とんでもないところへの出口になりはしないか。
この世界の片隅で懸命に今を暮らす人々は、今、何をじっと見透かしているのか。
そのことを想え。