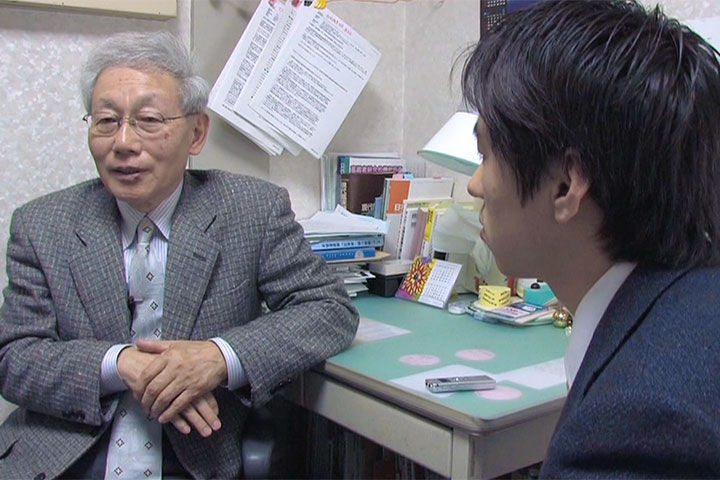▲新型コロナの事態は、今や社会不安として膨らみ、私たちは身を縮めて引きこもるしかすべはないのだろうか。これまで地域活動を重ねて作り上げた共生社会のつながりは分断され、無力なのだろうか。今回のウィルスの事態は、実は地域で築き上げてきた、つながりや自分ごと、私たちにできること、その全ての真価が試されている。そのように考えられないだろうか。
新型コロナウィルスによって、この社会のありようが一変した。
私の親しい友人は、メールで「お互い生き延びよう」と呼びかけた。「生き延びよう」という言葉が私たちの日常の暮らしの中に入り込んだ経験は、戦時中の世代はともかくとして現在の私たちにはなかった気がする。しかしこの場合、「生き延びよう」という切実な言葉がまことにぴったりとはまる。そういう事態なのだ。
私たちは生き延びなければならない。お互い、生き延びよう。
新型コロナウィルスのもたらす恐怖に近い不安は、見えない敵であるということだろう。
しかも、見えない敵はどこにいるのかわからない。電車で隣に座った人か、打ち合わせの会議室にいたあの人か。疑心暗鬼の中では、敵はますます強大な存在と恐怖をもたらすだろう。
私たちは試されている。
ウィルスは敵だが、その感染者までを敵とみなしたとたんに、私たちはウィルスに敗北する。生き延びる手立てを放棄したことになる。
敵としてのウィルスの手強さは、私たちの互いのつながりあいを嘲笑うようにして切り離していく事だ。次々とイベントや集まりが中止となり、交通機関での移動も外出も控えるしかない。暮らしの中の人々の交流が途絶え、地域と街のにぎわいがひっそりとし、身を潜めて暮らすようになっていく。
この事態に対する一番の難しさは、みんなで力を合わせ、一人ひとりの力を結集させることで百人力にすると言う古典的戦術がとれないことだ。だって、敵はどこにいるのかわからず、私たち自身も集まっちゃいけないのだからね。みんなが街角に集まって、手に手にスコップや棒切れやチェーンを振り回しても、どうにもならないのは誰もが分かっている。
では、私たちにできることはないのだろうか。
今、メディアが盛んに口角泡を飛ばすようにして語る、対策、自粛、中止、防止、批判など、その一切合切を含めて、このことに関してはただただ充実させ、一日も早く良い方向に向かって欲しい。
その一方で全く別の視点から、私たち一人ひとりがこの事態に試されている。私には、鳥肌が立つような思いで、その感覚がジワリと押し寄せている。
私たちは、これまでそれぞれの地域で「つながりあい、共に生きる」という暮らしの中の感覚を息づかせ、確かな社会の変革を推し進めてきた。地域福祉とカテゴライズすればどこか精彩を失う取り組みも、自分たちの暮らしの中に取り戻し軽やかに展開させることで、市民活動の大きな成果を見せてきた。少子超高齢社会の壁を突き抜ける可能性さえ見せている。
では、この事態に、その「つながり」は力となるのだろうか。交流が途切れ、つながりが凍結されてしまったこの事態には、「つながること」は無力になってしまったのだろうか。
それぞれが離れていてもつながっているという確信を持ち、それを信じ、その気配を感じ取ることだ。たとえ今、つながりの全てが分断されたとしても、夕空に浮かぶ雲に託すような願いとして、「私たちはつながっている」と確信を持って言えることが必要なのだろう。
私たちが試されているというのは、私たちが地域で取り組んで来たつながり合い「共に生きる」ことへの活動が、果たして本物であるかどうかということが試されている。
果たして、「つながること」は、共に生き延びるための力になっているのだろうか、と。
もうひとつ、このウィルスは私たちの共生社会のための重要なテーゼである「自分ごと」をも容赦なく審問する。私たちの言い募る「自分ごと」は機能するのか、と。
敵はウィルスであって、感染者ではない。
しかし一方で、感染拡大を防ぐことがいちばんの手立てであり、今のところこれしかない。
となると、私たちにとって感染者とはどういう存在なのか。それは否定される人なのか。加害の人なのか。
だが、感染者を否定した瞬間に、私たちは頼みの綱の共生社会のつながりを、我が手で断ち切る事になる。
テレビの中では感染者はいつも数字で表され、その数字が増え続けていく事態を私たちは固唾を呑んで見つめつづけている。無機の数字の増加は恐怖と不安だが、「自分ごと」を掲げる私たちはためらうことなく、感染者は自分のことであると自分に言い聞かせ、数字の向こうの感染者の暮らしと不安へ、私たちの想像力と共感の幅を広げられるか。「自分ごと」の想いを届けられるか。
私たちの側の困難は、ウィルスも見えない敵であるが、感染者もまた見えない存在なのである。
感染対策の鉄則は、感染者と接触を避けることである。人混みやイベントの忌避はそのためだ。私たちは、感染者を遠ざけ見えない存在にするしかない。
だが、私たちはそこにもう一つの鉄則を加えることができる。
「接触はしないが、排除はしない」という鉄則を。
敵はウィルスであって、感染者ではない。そのことを実体化するために私達は、「接触はしないが、排除はしない」と言う語法の背反を乗り越える「自分ごと」が問われている。
ここでの「排除」はつながりの断絶だが、「接触しない」というのは、つながりを前提とした一時停止であるはずだ。
語の解釈としていかに無理くりであっても構わない。何より、「つながり」があること、つながりは切れていないことを共有し信じることを優先する。
「自分ごと」とは、どこかにいる他者である感染者とのつながりは、たとえ一時的に機能停止しても、どこまでも維持されていることが、自分と感染者の間で信じられていることだ。私たちが積み上げてきた共生社会の底力を示す時だ。
私たちがこの事態を生き延びることができるかどうかは、ひとえにここにかかっている。
また、社会全体もこのウィルスをまるで黙示録的な災厄として捉え、社会の中に取り込む新たな共生モデルが発想できていない。
政治家がこの事態の終息を言うたび、字幕には「終息」の用語が当てられるが、それでいいのだろうか。終息とは完全制圧である。この世からウィルスのひとかけらも許さないと言うのは、エビデンスベースでもありえない。
今、長期化する中で目指すのは、「収束」であるべきではないのか。
事態を誰もが受け入れられる段階にまで、まずはこの混乱を収めることである。
今、世界は国境を越えて開かれ、移動と交流を盛んにすることが新時代につながるという合意と、それを受けてこの国もまた地域が開かれ、つながり合うことを目指してきた。
だが、このウィルスは疾病対策をすり抜け、この開かれつながり合う社会にやすやすと入り込んだ。
このウィルスは世界は閉じよ、と警告しているのだろうか。私たちのつながりはリスクの回廊なのだろうか。
この事態の終息宣言をしても、いつかまた必ず同じような事態が起こるだろう。
世界は開かれているという原則の選択をしており、私たちの暮らしもその前提でつながる社会の構築に向かっている。となれば、強権発動の制圧よりもむしろ、つながる共生の真価を旗印にするしかない。
終息宣言をするための最終戦争に突入するより、私たちはつながり合う社会の強さを確かめ、個人と社会に「抗体」を植え付け、どこか共存する道筋も探りたい。
この社会はいく層ものレイヤーが重なっている。単層の共生社会で浮かれるのではなく、底深く異質なものとの遭遇が今後もありうることの想定を、社会の深層に据え付けるしかない。
想定外を想定内としなければ、この社会は回復しないのはあの大震災の貴重な教訓だったではないか。
今、私たちは、自分たちのつながりがまだまだ弱いのか、それとも、つながっている強さを確かに手にしているのか、よくわからない。いずれにしろ、この事態を生き延び、試練を乗り越えた時、私たちのつながる力を再び確かにつなぎ合わせていくしかない。
そのために、お互い、今は生き延びようではないか。
|第132回 2020.3.2|