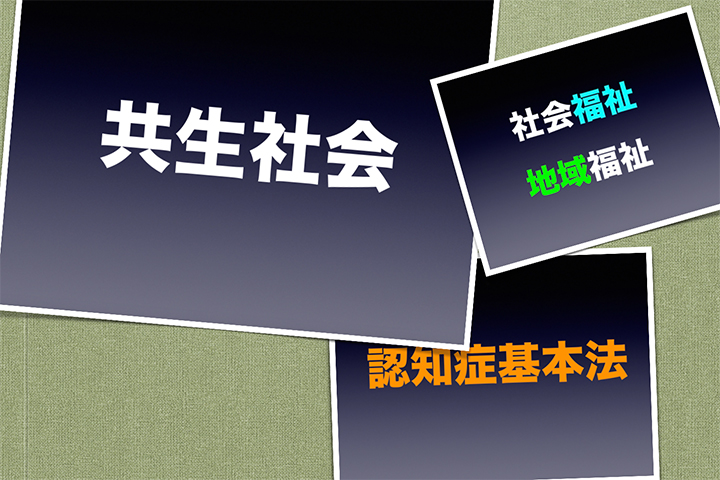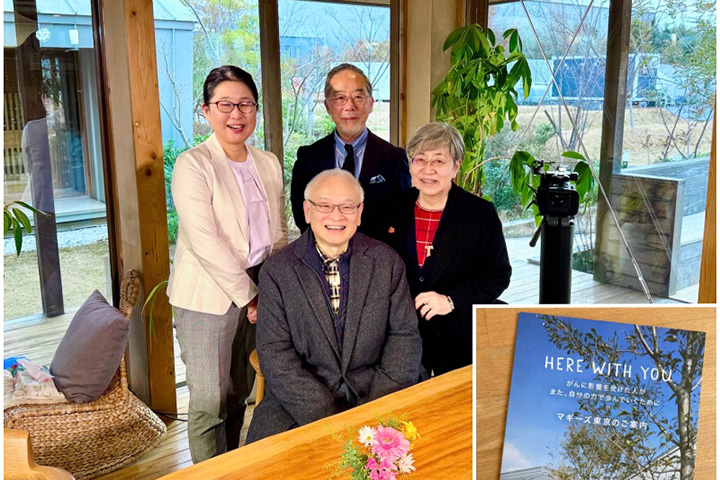▲向こうからこちらをみると、どうみえるんだろう。ふとそう思うことってありますよね。連続する風景がどこかで反転して、こちらがみられているという感覚。あれってなんだろう。自分の存在を意識する時・・・
いつだかの新聞に、俳優のイッセー尾形氏の出身母校の思い出が載っていた。
ある若い古典の教師が、窓の外を眺めながらふと「向こうからこっちをみたら、どう見えるんだろう」とつぶやいたという。イッセー尾形氏にはその年若い教師のつぶやきが、その後もずっと耳に残っているという。なるほど、これがあの一人芝居の新天地を確立したイッセー尾形氏の原点の風景のひとつだったのか。
「向こうからこっちをみたら、どう見えるんだろう」
そんなふうにして、この日常を見たら、どう見えるのだろう。
私たちは当事者性であるとか、共生社会であるとか、そしてそのための思考基点としての「自分ごと」をしきりに言い交わしている。
しかし、それはどことなく借り物の観念であったり、何より「自分ごと」を「他人事」のように手軽に語ったりしてすませている。
私たちはいつも誰かの大きな言葉からこの社会を眺めようとしている。眺めさせられているといってもいいかもしれない。共生社会とは、超高齢社会とは、新しい認知症観とは、とか。それはこっちから見た窓の外の風景であって、向こうに見える窓の外には私やあなたはいない。
「向こうからこっちをみたら、どう見えるんだろう」
この言葉には、ドキリとするようなリアルがある。それは、このつぶやきには自分を見つめられている視線を感じるからだ。
「向こう」とはどこか。実在の風景を突き抜けて、自分の知らない世界なのか。あるいは、そう、あるいは、そこにいるのは「自分」なのではないか。
向こうのどこかにもうひとりの自分がいて、その自分が、窓の中のこちら、クラスで頬杖ついている高校生の自分を見ているのである。自分を見ているもうひとりの「自分」がいる。そんな感覚を持つことがある。
向こうに広がる景色は、当たり前の街並みだ。手前に高校のグラウンドがあり、向こうにはくすんだビルや家々が雑然と並ぶ。その日常性の只中から、あなたを撃つ声が発せられる。向こうからみたら、あなたはどのようにみえるのか。
ドキリとするのは、自分の感覚のどこかが、今この瞬間に「自分」を発見しようとしている、そのことに気づくからだ。自分が「自分」を発見しようとしている。
そこに見るのが、「自分ごと」ということなのではないか。
「自分」とは何者かとする哲学的命題はここでは軽やかに開かれて、自分とは、もうひとりの自分から見た自分である、という発見をする時が来る。
自分は、人とのつながりの中にある。さらに言えば、「人はひとりでは生きていけない」ということへの回帰と確認である。そのことの発見が「自分ごと」なのである。自分に関わることであり、自分が関わることがこの世の中にはある、それが「自分ごと」だ。
「自分ごと」とは、今や共生社会や認知症基本法を考える上での重要なキーワードでありながら、その位置づけ、意味づけはずいぶんとおろそかであるとしか言いようがない。
例えば、認知症基本法の施策推進基本計画の前文には、「誰もが認知症になりうる(ので)、誰もが自分ごととして考える時代へ」とある。
私はこれがどうもしっくりこない。
誰もが認知症になりうるから「自分ごと」として考える、というのは確かに認知症の将来推計値からしてその蓋然性は高いとしても、あなたも認知症になるから「自分ごと」とせよ、という安直な言い回しは、それは窓の向こうの風景を怯えの中に描くようなものである。
そこにあるのは、認知症をリスクとして捉え、「自分ごと」が対策に閉じている。
認知症基本法が共生社会の実現を謳っているからにはそれは、認知症であろうとなかろうと、認知症は「自分ごと」であるはずなのである。「自分ごと」とは、単独アイテムの解決手段ではない。
「自分ごと」というのは、もうひとりの自分から見た自分の姿である。
「自分」というのは、自分ひとりでは見えてこない。自分とは他者との関係性で浮かび上がる。私たちは人とのつながりに生きている。もうひとりの自分というのは、自分の中に他者性を育むことだ。
よりよくありたいとする自分であったり、悩みや不安の中の自分であったりするのが、もうひとりの自分である。
誰もが我知らず経験的にやっているのが、もうひとりの自分との対話なのではないか。
「どうしたらいいのだろう」と呟く時、その相手はもうひとりの自分なのである。こうしようか、いやそうではなく、と際限なく自分と対話を重ねることで自分の意思決定を鍛え、自分を変え、自身の輪郭を描きあげていく。
いうまでもなくこれは、認知症当事者が辿った道なのである。当事者にとっては、まさに認知症は、寸分違わず「自分ごと」である以上、ひたすらそこに向き合う経験を重ねて新しい自分の人生に歩むことができた。「自分ごと」とは、リカバリー、回復であり、取り戻す力でもある。
認知症基本法の策定過程での市民の語り合いの場では、「自分ごと」とは「認知症を見る」のではなく「認知症から見る」視点だとされた。認知症を支援の対象、課題と「見る」のではなく、認知症から見れば、この社会はどうあったらいいのかが見えてくる。基本的人権の不在も検証できたのである。向こうから見るとこっちはどんなふうにみえるのかということは、自分ごとであると同時に、自分に当事者性を獲得することにもつながる。
「自分ごと」は、自分を小さく確かに変える。そのことはこれまでの社会を大きく変える力だ。
共生社会も地域福祉、社会福祉も、そして民主主義もまた「自分ごと」でなければ機能しない。
「自分ごと」という自分に関わることを、自分が関わることとすることで、新たな社会が創造される。誰かがやってくれる社会ではなく、畢竟、社会の成員一人一人が「自分ごと」の一歩を歩み出すことでしか、この社会は変わることはない。
もうひとりの自分との対話と言っても、それは特別なことではないはずだ。それは自分で「自分ごと」とはなんだろうと素直に問うことで始まる。
「自分ごと」というさりげない親密さに満ちた語感は大切にしたい。あくまでも日常の感覚を捨て去ることなく、私の自分ごととあなたの自分ごとを持ち寄って、私たちのまちが動き出す。
日常の中のことばだからこそ、このつぶきには自分の声を聞くことができるような気がする。
改めてつぶやいてみないか。
「向こうからこっちをみると、どう見えるんだろう」
|第310回 2025.3.19|