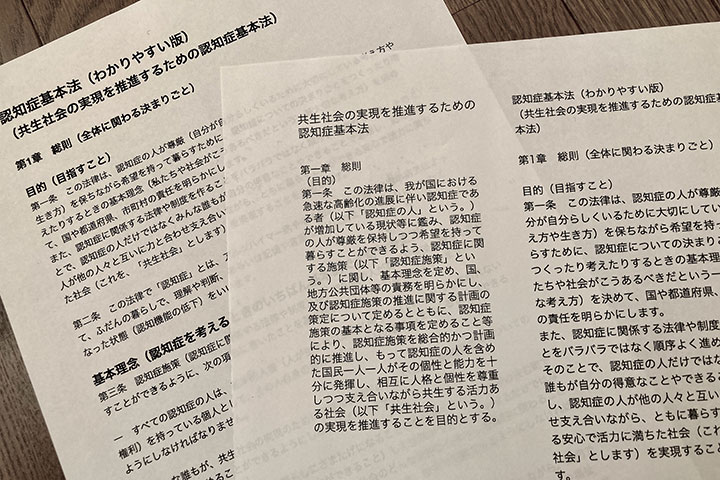▲「支え合う」とか「つながる」と言った言葉は、このコロナの時代の私たちの拠り所だ。それをそれぞれが自分の内にある力としての動態が「共振」だ。共振には自分の中に響く自分の気づきと力が込められている。写真、北海道医療大学名誉教授、中島紀恵子さんと。
共感する力がこの社会を創ったというのは、長年、霊長類を研究し、そこから人間社会を洞察する京都大学総長だった山極寿一さんの論である。
人類が、霊長類とは異なる家族と共同体という二つの構造体を両立させることができたのは、「身体的なつながりを超える「共感力」というコミュニケーション能力を育て、他人とのつながりを拡張し、仲間の事情や気持ちを理解して問題を解決することができるようになった。(共感革命・日本フィランソロピー協会)」からだとする。
共感は高揚の気分には端的に表れる。言い換えればそれは感動がつながっていくさまといってもいい。ひとりの感動が他者の感動とつながるときに豊かな共感に育つが、時として他人の感動が自分の感動とは重ならない場合もままある。
誰かが演奏会の帰りのタクシーの運転手さんに、聴いてきたベートーベンの第7交響曲のアレグレットの感動をいくら語ったところで(場を考えろよ)、相手が運転席のラジオから流れる鳥羽一郎の唄いあげる「兄弟船」の陶酔に(いい唄ですが)、はためく大漁旗をイメージしている限り、たぶん、互いをわからない奴だとして、感動を分かち共感とすることは無理だろう。
感動は個人のもので、共感は他者との関係性に生まれる。
個の尊厳と自立といった概念が他者とつながって共生になるのと同じ構造なのだ。
そんなふうに考えていたら、今度は「共振」という言葉にゆきあたった。言葉は連鎖する。
老年看護研究を確立し、認知症ケアの教育と実践者である中島紀恵子さんは、教え子たちとの著「老年看護の縦横な語り」で、認知症ケアでの「共振」というものを「すべての関係性は情的交流からはじまる。この流れを起こすもの、かつまた、この流れをうまく活かすもの、これが共振です」と語っている。ふーむ。
中島紀恵子さんは、看護や介護の分野で中島山脈というべき多くの教え子を持ち、そのそれぞれが全国でリーダー的研究者や実践者の峰々に育っているが、教え子の間では「中島先生の文章は難しい」といわれているようだ。
確かにそうかもしれないが、私にとっては中島先生の簡潔で、噛み締めがいのある含みを持ち、かつ抽象性をたたえた語りの文章は、まさに自分に多義的な共振を引き起こして理屈ではない感覚として響き合うところが大きい。
中島紀恵子さんの「共振」をたどってみよう。
著書のそのあとの、認知症ケアのケーススタディでは、共振と洞察は深く関係するとして、「共振は、ケアする人が受ける人の知覚・感覚に反応する知覚・感覚体験だから。そこにケアの読解力が強化されるし、コミュニケーションはそれに導かれつつ意図ある関係を築く中で情緒的交流に活性化されるでしょう p108」とある。ふーむ。
ここでの「読解力」とは、認知症の人の世界を読み解くことである。認知症の人の世界は、私たちと同じ環境でも、違う世界にいることがある。過去と現在を行き来したり、この地点に座っていても、別の地点にいて全く別のものを見ていたりする。
そのことをどう読み解くのか。それが認知症ケアの読解力なのであり、それは理解しようとか、ケアする側からのコミュニケーションといった能動では読み解くことは難しい。
どうすればいいのか。認知症の人との相互の知覚感覚のレベルで感じ取るもの。共振。それはどんなものなのか。
中島さんは、まず、たっぷりとした意味合いの問いかけをし、それから徐々にヒントになる語りを思考の道筋に置きながらその先に導いてくれる。「環境を読む」とする語りでは、こんな風に認知症の世界を物語る。
「認知症の人の行動をよく観察しつつ関わっていると、動作行為で触れる(作用する)人物、道具、空間などは、そのつどの新しい知覚体験であるようで、その体験の一つひとつが意味のある環境になっています p101」ふむ。なるほど。
語りが積みあがり、世界を拓き、そして、ついに思考を広々と解き放すようにして、環境を読むことを次のように語るのだ。
「行動空間の中で彼ら(認知症の人:町永註)が体験しているおびただしい質量の知覚・感覚をなぞることができる位置を探し求めつつ、傍にいること、必死に解ろうと思って “そっと”いること。“そっと”待つこと。彼らを困惑させているノイズをこばみつつ環境を修繕する行動力のある関わり方に集注すること、です。p101」
認知症の人の世界とそのケアを描いたなんと美しい語りの文章なのだろう。
人と人の間を描く「人間」の文章である。認知症の人の知覚・感覚体験を「おびただしい質量」に満ちた豊かな世界と捉え、そこに注意深く集中して(集注なのである)、ただ身を寄せながら自身の共振に耳を傾けるケアの姿は、何か感動的な光景だ。
「そっといること」「そっと待つこと」、祈るような言葉のくりかえしに、息ひそめ、まなざしを全体に柔らかに注ぎ、焦点を絶えず調整し、小さく震えるような共振を、知覚と感覚を研ぎ澄まして待ち構えている、そんなケアが浮かぶ。
この語りが描くケア世界の広さと深さをもう少し分析してみよう。
例えば、世間に「寄り添う」という言葉がある。大切な言葉ではあるが、ここに張り付いている既成の価値観を中島さんは因数分解する。
それは「傍(かたわら)にいること」というさりげない言葉にある。もちろん、「傍にいること」はただボーッとして佇んでいることではない。
ここでの「傍にいること」というひとつの言葉は、その両翼にガッチリとしたケアする人の意思と行動倫理を引き寄せている。まず前段で、ケア環境を読むためには、「知覚・感覚をなぞることができる位置を探し求め」なければならないのであり(これだとて、物理的位置のみならず心的位置でもあるはずだ)、さらにその右翼に続く言葉としては、「必死に解ろう」としつつ、身体的には「そっと」しており、認知症の人を何より困惑させないようにしつつ、「修繕する関わり方」をせよ、と決意と覚悟がつながっている。
「傍にいる」という「受動」に埋め込まれた凄まじいまでの「能動力」なのである。読み込んでフーッと大きく息をつく。
ここにあるのは究極の人間原理への共振だ。
そもそも「共振」とは物理用語で、辞典によれば、「物体に外から周期的な力を加えるとき,その振動数が物体の固有振動数に近いほど外力のする仕事が有効に吸収されて物体の振動が激しくなる現象(世界大百科事典第2版)」とある。ふーむ。
これはあれだな。重い釣鐘を指ひとつで、小さく小さく揺らしていくと、固有振動数が同期しやがて大きく揺れ動くというのと同じで、そこに共振が起こったということだ。
これを、私なりに人間の関係に置き換えれば、いきなり大きい力で動かそうとするのではなく、小さく小さく認知症の人の環境を細心の知覚と感覚で読み解いていくうちに、どこかの地点でそれぞれの固有の振動数がピタリと周期し、そこから共振し響き合ってケアの力が活性化していく、ということになる。共振とは、双方の固有振動数が響き合うことだから、ケアする人受ける人、どちらも主体意思なのである。
「共振」は、この新型コロナで傷ついた社会を癒していく力だ。誰もが自分の中の固有振動を響かせ、小さく小さく共振を引き起こし、やがて大きく人間の社会を揺り動かし覚醒させていく。
誰もが身の内に備えている自分の固有振動数を、どう共振させていけばいいのか。
中島さんは、それは「人権感覚を磨くこと」に尽きるという。
中島紀恵子さんは、今から25年前の1996年の第一回の老年看護学術集会の会長を務めたとき、老年看護における人権をテーマに掲げた。
その時のことをこう語っている。
「人権感覚って、最も高い共振能力だって解った。憲法25条や倫理教育だけではダメだね」
人権感覚とは、最も高い共振能力。
ウイズコロナの社会、共振する力をケアの社会だけのものとするのはあまりにもったいない。