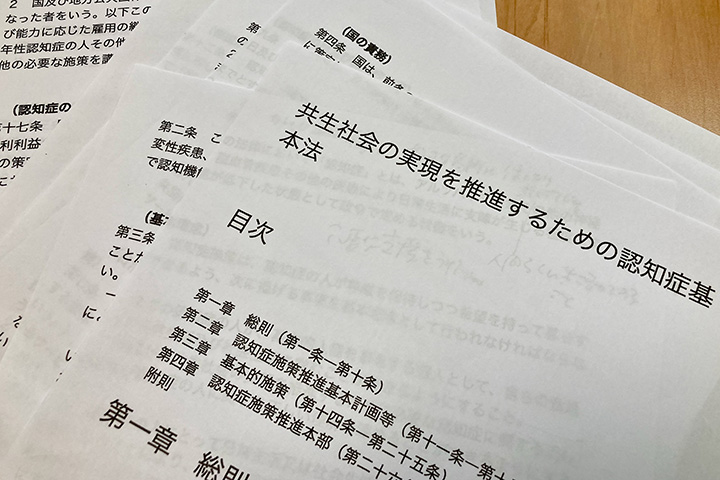▲昼下がりのガランとしたカフェというのは絶好の対話の生まれるところだ。梢のそよぎ、コーヒーの香り、ビル・エヴァンスのピアノ。「さあ、キミから話してごらん」
「マチナガさん、先日の「対話する認知症」のコラムを読んで、ボクも関係者会議資料の認知症施策推進基本計画の素案を読んでみました」
「ホー、それはエライじゃないか。それもまたキミ自身の言葉を獲得する一歩だからね。他人の言ったり書いたりしていることを鵜呑みにするのではなく、自身自身で1次情報にアクセスすることはまず持ってエライ」
「デヘヘ」
「基本法というのは与えられたものじゃない。これまでの認知症の人や家族や、関わる人々の10年以上の声や行動が生んだものだからね。ま、キミを含めた市民の側に「製造責任」の一端がある」
「で、読んでみて思ったのですが、内容的にはずいぶんガンバッタなあというのが第一印象です」
「ホー、それはどんなところかな」
「エート、(自分のメモを見ながら・・)まず前文でこの認知症基本法の位置付けを改めてしているのですが、そこに、この基本法はそもそも「認知症の人が主語になっている」と記してあって、これを踏まえて認知症施策の立案などを行うと書かれているんですね。
この手のお役所の作文としてはとても素直で明快だし、何より、認知症の人が主語であるって冒頭に宣言されていて、ちょっと感動した」
「なるほどなあ。やはり若い感性というのは弾力性に富んでいるんだなあ。
とかく今は、社会のメジャーな動きはなんであってもとりあえず、クサスことで自分の値札を高く見せかけようとする人たちが多いからね。
素直で明快だというキミの受け止めは、そのままキミの美質なんだと思うぞ。ふむ、「認知症の人が主語の社会」、いいね。で、そのほかには?」
「これはマチナガさんがコラムでも触れていましたが、基本計画の素案には「新しい認知症観に立つ」という項目がありますね。そう、素案にはこんなふうに書かれていました。
「新しい認知症観に立つ」を国民一人ひとりが自分ごととして理解し、「新しい認知症観」に立って施策を進めることが重要である。
ボクもその通りだと思います。でも、これもマチナガさん、コラムで触れていましたが、「認知症の人を主語とする」であったり、「新しい認知症観に立つ」にしても、もっと関係者会議で話し合うべきではないのですか」
「そうだよなあ。私もこれは各委員それぞれに、あなたの考える「新しい認知症観に立つ」とはどういうことですか、と訊いてみればいいのに、と一瞬思ったのだよ。
でもあのコラムを書きながら考えた。そうした意見の合意をすぐ求めることに走るのは、「共生社会の実現」を推進することとはちょっと違うのでは、と思ったのだよ」
「聞いちゃダメですか」
「ふふふ、オヌシ、若いのう。
聞いてもいいんだけどね。でも、そうしていつも誰かの意見でしか、自分の考えが立ち上がらないのはもったいない。
だったら、まず、改めてキミに聞きたい。キミの考える「新しい認知症観」とはどんなものかな」
「えっ、そんな・・
いきなり言われてもなあ・・・」
「いいから、ゆっくりでいいから。キミ自身、話し合うべきではないかと言った以上は、「新しい認知症観」については当然、何かあるのではないのかな。話してほしい」
「えーとえーと、そうだな。認知症になっても何もできない人ではない。わからない人ではない。できること、やりたいことはある、とかかな」
「ひたいに汗が浮いているぞ。ホレ、そこのティッシュで拭くといい。
うん、いいね。その通りだね。いい答えだと思うよ。つい汗かいてしまったのはキミ自身がなんとなく自分の言葉ではないと感じているからなんだろうね。
確かにキミの言ったことは、丹野智文さんが言ってきたことの受け売りだ。でも咄嗟にでもその言葉が浮かんだのは、認知症当事者の声と思いを受け入れて、キミの中の「認知症観」がこれまでであってはならないということの意思の表明なんだから、それはそれでいい反応だと思う」
「褒めてくれているんですか」
「褒めているのさ。でもね、ここでのキミとの話は、褒める、褒めないと言ったこととは切り離したほうがいい。だいたい私自身、他人を褒めるとか褒めないとか言える立場ではない。
つまりさ、誰かに大上段に問いかけて、直ちにその答えを求めることの反復はほとんど何も生み出さない。それはどちらが正しいのかの議論の荒野でしかない。
もっとも世の中には問う側は安全地帯にいて、厳格な審問官のようにして「答えよ」という感じの問答が多いよね。あれは一種の暴力だぞ。
ヒトに「問う」ということは、その問いを、聞く側と聞かれた側が共有することなんだ。ちょっと抽象的かな。
問う側、つまり私は問うことでまた自分の中の考えをキミに検証されることになるし、そして問われた側、キミだ。キミはその「答え」を即答するのではなく、問いを自分の中に響かせることになるはずなんだ。
さっき、「えっ、そんな、いきなり」とキミがうろたえたのは、自分自身に直面させられたからなんだ。問われることで、改めて自分を発見しようとしたと言ってもいい。そこにあるのは、問う側と問われる側との間に新たな関係性が生まれることだ。関係性は必ず何かを動かす。
問うことと問われること、それは互いに入れ替わりながら上昇していくイメージで、それが対話なんだと思うよ。
ついでに言えば、「わからない」と答えることにもとても大きな意味があると思うぞ。
誠実に「わからない」と言えるというのは、問われたことへの答えがわからないということではないんだな。それは、たぶん、自分がわからないということなんだ。わからない自分を見出すってすごくないか。
だいたいさ、と言いながら私の話はすぐに横道に入ってしまうのだが、そもそも、自分ってわからない存在じゃないのか。私はいまだに自分で自分がわからない。だから、私も含めて大人がいつも「エラそうにわかったようなことを言う」のは、わからない自分への必死の抵抗なのだな。
幼い子供がすぐ「わからなーい」と言うのは、もちろん問われたことへの「わからない」なのだろうが、その深層には我が身に余るほどの自分の豊かな育ちに、自分が追いつけないもどかしさがそう言わせているのだ。可能性の伸び代が「わからなーい」、と。
「新しい認知症観」とはなにか。「わからない」ってありなんだよ。簡単にわからないでほしいね。そこに対話を重ねていく。「新しい認知症観」ってわからないと言える対話こそが、「新しい認知症観」を生むのだし、それはやがてきっと「新しい社会観」や「新しい人間観」に育つ。わからないけど」
「確かになあ、ボク自身、「わからない」と言うことはマケだと思い込んでいました。わからないと言う時って、何か新しい自分に向きあおうとしているのかもしれないなあ」
「だろ。だいたい「新しい認知症観」って構えの大きな言葉すぎるんだよ。だから、すぐに「生産性や効率ではなく」とか「能力主義からの脱却」とか言うすげえ立派な「正論」が横行するんだ。硬質な論考の文脈としてはありうる表現ではあっても、日常な感覚での対話にはそぐわない。
もっと、自分の日常のふるまいや些細な思い込みの一つひとつを検証するようにして「新しい認知症観」を探り当てた方がいいんじゃないか」
「もうひとつ、「認知症の人を主語にする」というのもあります」
「あるな。でも、これはたぶん、ほとんどの人が解説はできちゃうと思うんだな。
認知症を対象化、課題化するのではなく、医学モデルから社会モデルへ、とか、あるいは全ての認知症の人は基本的人権を享有する個人として、自分の意思で暮らすことができる、とかね。じつは今はこの不毛な「解釈合戦」ばかりだ。
こうしてお勉強してしまうとかえって基本法を自分から遠ざける。「わからない」と言えないしね」
「いまや、認知症の人を主語にするとか言うと、そんなのあたりまえだろと言われそうですね」
「あたりまえとか普通というのも用心した方がいい言葉だね。あたりまえとか普通から排除されてきたのが認知症の人だぞ」
「・・・・・」
「まあ、前向きの対話であってほしいが、この「認知症の人を主語にする」を語る時には、この社会が認知症の人から主語を奪ってきたことを忘れるなよ」
「・・・ハイ」
「まあ、私の悪いところなんだが、こんなふうに間口をやたら広げてしまうと、一体どこから取りかかったらいいのか、かえってわからないよな。すまない。
大体、「認知症の人を主語にする」とか「新しい認知症観」と言った語句だけを意識化すると、どこか自分と切り離されてしまいがちだ。評論的になってしまう」
「じゃあ、自分の感覚に引き寄せるようにした時の「認知症の人を主語にする」とは、どういうことなんですかね」
「それはね、人のいる風景を思い浮かべることなんだ。キミが認知症の人と話し合ったり、呑んだりした時のことを思い浮かべればいい。だからと言って、それをすぐに「認知症の人を主語とする」と言う言葉で考えないことだ。風景の中のその人の笑顔や声音から「認知症の人の主語」が浮かんでくるはずだ。
わかりにくいかなあ。キミは頭がいいので考えすぎだ。
隣近所の人たちとどう接しているのかな。え? あまりお付き合いしない?
それだな。「認知症の人を主語とする」よりも、ご近所に朝、挨拶することから始めた方がいいぞ。
まだわからないか。うーむ。この辺りは説明が難しい。ま、暮らしの実感からしか生まれてこないものがあると言うことだ。キミの場合、人間が人間と出会っていなんだな。
これもまた私の「わかったようなことを言う」とキミは受け止めるのだろうが、「認知症の人を主語」をするって言うことは、キミがキミ自身を主語として暮らして考えているのかということに尽きる。
「基本的人権を享有する個人」と言うことは、自分を主語にする社会だ。こんなふうに結論的に言ってしまうのは良くないがね。
結論ついでに言ってしまえば、「認知症の人を主語にする」とか「新しい認知症観に立つ」と言うのは「認知症の問題」ではない。
ここにあるのは、この社会は変わらなくてはならないと言うメッセージだ。と言うことはね、私もキミもまた変わらなければならないと言うことなんだ。
どう変わらなければならないのか。そうそう、そのことが問われている。この社会で大切なのは、「答え」を出すことではなく、「問い」を立てることなんだ。
だから、認知症基本法には答えはなく、問いが並んでいる。
いやいや、話しすぎた。こんなのは忘れていいからね。まずは自分で自分と対話してみることだ。
で、どうよ、ここまでの私の話?」
「よくわからないけれど、わかるような気もします」
「おお、素晴らしい。すっかりよーくわかりましたって言われたら、それはきっと何も伝わっていないのだな。キミを一ミリも動かしていない。
だから、今のキミの言葉はきっと私の言いたいことが伝わったんだと勝手に思うことにする。じゃあね。またおいで」