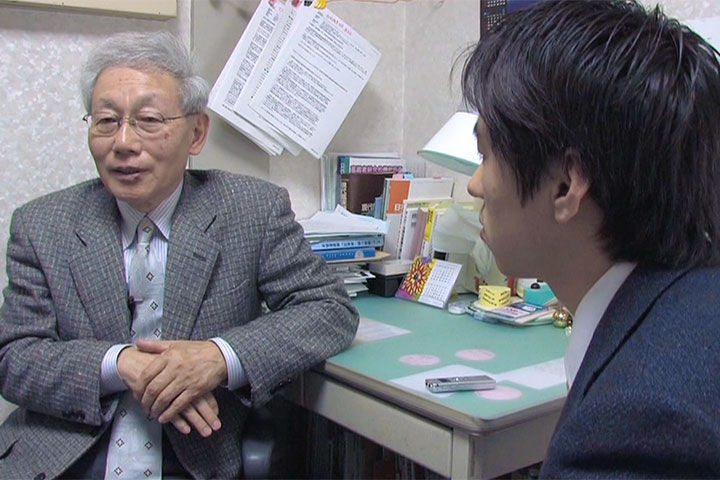▲東京で桜が開花した14日、渋谷のさくらホールでフォーラムを開いた。桜の花が咲き、私たちの心も広々と花開くようなフォーラム。下段、左から、町永俊雄、東京大学老年病学の小川純人准教授、広島からのオンライン参加で家族社会学者の春日キスヨ氏、NPO法人農スクール代表理事の小島希世子氏。
「汗を流して畑仕事をするようになって、将来の不安が減ったような気がする」と郊外の貸し農園に来る高齢者が言ったという。
渋谷で「超高齢社会を生きる」のオンラインフォーラムを開く。
超高齢社会といえば、いつもこの社会に重くのしかかる現実である。それは常に少子とセットにして少子超高齢社会を課題として、ただ膨張させてきた。それは逃れることのできない切実な響きをいつも伴う。
今回のフォーラムはそんな少子超高齢社会を、いつも不安と怯えの中で語るのではなく、グイッと視点を転じた。超高齢社会を高齢者の課題ではなく、むしろ高齢者と若い世代の力を引き出す可能性を論じようとした。
その取り組みは、このコロナの日々の中に生まれつつある私達の力の確かな芽生えのようにも思える。
まずフォーラムで提起をした社会学者の春日キスヨ氏は、これまで高齢者や家族への聴き取り研究の中で実感したのは、この超高齢社会の中で、当のお年寄りの多くは自分の老後への具体的な備えをしないままに、「成り行きまかせ」としていることだという。
元気なうちは、「子供の世話にはなりたくない」「子供に迷惑はかけたくない」と言いながら、いざ介護が必要になった時には、結局子供に丸投げとなる。
丸投げされる子供にはたまったものではない。まだ子供がいればなんとかなるかもしれないが、丸投げできる子供のいない人の場合はどうなるのか。
春日氏は、多くのお年寄りはピンピンコロリを願うが、現実にはヨロヨロドタリなのだと、なかなか辛辣なのである。
確かに「超高齢社会」と打ち出せば、何やら人智の及ばぬ大問題の設定となってしまいがちだが、そこにはまず一人ひとりが、この人類未踏の人生百年時代への「覚悟」を持つことなのだと春日センセイはおっしゃる。
では、私たちは、果たしてこの超高齢社会にどう覚悟し、そして備えることができるのだろうか。
横浜市都筑区、そこでは、ユニークな配食弁当の取り組みが始まっている。
取り組むのは地元のNPOロクマルのメンバーである。ロクマルというのは、60代以降の人生を、地域と共に主体的に過ごそうと名付けられた主婦を中心としたグループだ。もともとコミュニティ食堂の取り組みをしていたが、コロナ禍で活動は休止せざるを得なくなった。
そこで始めたのが、自分たちの手作り弁当の配達サービスだ。ただ配達するのではない。そこに必ずメンバー手書きの手紙を添える。手紙はさりげない日常の会話のような気遣いと温もりを届ける。

▲お手紙弁当の取り組み。弁当はすべてメンバーの手作り。添える手紙が、地域を行き来して、コロナの時代の新しいつながりを創る。
受け取る高齢者にとっては弁当もさることながら、手紙が何より、待ち焦がれるような楽しみなのである。食べ終わった弁当には、今度は返信が添えられる。道で出会ったご近所さん同士が交わすような近況や季節の思い出も多い。
しかし、中には三年で外出したのはたった一度、花見に出かけた時だけだという返信もあった。地域に孤立がうずくまっている、ロクマルのメンバーには衝撃だった。
ロクマル代表の有澤厚子さんはこう語る。
「これは福祉の専門家とかそういうわけでなく、普通のおばさんたちが、普通のおしゃべりのようにしてやってきた。それがかえって良かったのかもしれない。ここから互いの日常生活につながりと言えるものが育っていけばいいなって思っています」
実はこのロクマルの取り組みが展開されている横浜市都筑区というのは、ニュータウンが広がって、横浜市でも平均年齢が最も若い地域である。若い地域であるからこそ余計に、ロクマルのメンバーには、忍び寄る超高齢化のリスクがまざまざと予見されるのかもしれない。
また同時に若い地域というのは、ニュータウンといった街の機能性が、高齢者にとってはどこか住みづらく、孤立に傾いてしまうところがあるのかもしれない。
ロクマルの主婦を中心にしたメンバーの生活感覚はそうした地域の気配を敏感に感じ取りながら、自分の人生と地域の高齢者の老いの人生とを、同じ線上の、その時間差の中で結びつけている。自分の老いへの備えと地域の備えとが、同期しているようである。
もうひとつは、農の力がこの超高齢社会を実り豊かな姿に育てていく取り組みだ。
神奈川県藤沢市に、0歳児から80代まで多世代が集う貸し農園がある。体験農園コトモファームである。この活動はこれまでも農林水産大臣奨励賞の「人間力大賞」を受賞した他、ユニークな起業モデルとして様々な受賞歴を持つ。
そしてこの活動の代表が小島希世子さんという溌剌とした女性で、自らを「農家です」と名乗る柔道二段なのである(!)。柔よく剛を制するようにして、この社会の課題の襟をグッと引き寄せ回復させていく。

▲神奈川県藤沢市の貸し農園。子供から高齢者まで多世代のコミュニティ農園だ。「農の力」は、何か不思議な力で人間を回復させていく、という。
もともとホームレスやひきこもりの人などの就農支援だったが、今、新しい動きが加わっている。高齢者の参加が増えているという。
フォーラムの映像リポートには、5年間の夫の介護の日々に押し潰されそうだという84歳の女性が、日曜ごとに農園にやってきて農作業をする姿を描く。かつて農家で育った女性のクワさばきは鮮やかだ。
「ここの空気吸って体を動かしていると、いいことばかり思い出す。あの頃は楽しかったなあ、って」
ここで自分を取り戻し、女性はまた生き生きとした自分として、夫の元に帰っていく。
小島希世子さんによればこの農園で野菜作りを覚えたことで「将来の不安が少し減った気がする」と言う人が少なくないという。コロナの日々、ここには三密はなく、ただ土に向き合って黙々と作業をする。
畑での作業というのは、土やそれを取り巻く自然との対話であり、何より自分の中の自分とのつながりの濃密な対話なのだろう。
一粒の種がやがて芽を出し、茎を伸ばし、多くの種をつける収穫をもたらす。土と空気と水、自然と、そこにいる「私」という実感。私もまた「育って」いく。
それは単に農福連携という支援の枠組みを超えた人間力を育てる取り組みだ。
今回のフォーラムは、この超高齢社会をフレイルという視点からも見つめた。
ほとんどの人は、老いの道をたどることは、衰えの下り坂を転がり落ちるイメージを持つ。が、登壇した老年病学の小川純人東京大学准教授は、フレイルと自覚的分析的に取り組めば、フレイルには可逆性があるという。つまり、一方的な下り坂ではなく、老いの坂を登っていくことが可能なのである。
フレイルを虚弱の下り坂とするのではなく、自分の人生への確かな備えとするためには、運動、食事といった身体フレイルに加えて、社会のフレイルを改善することが大切だと小川教授は提唱する。
コロナの日々で、社会のつながりが途切れ、社会は傷ついた。しかし、私たちは途切れたつながりを嘆くしかないのだろうか。
つながりとは何か。もともと都合よく用意されたつながりは、もろく途切れやすい。
地域の中を行き交う1通の手紙のつながりの力。土にクワを入れながら自分と大きな自然とのつながりの感触。それはどちらも自分の中に潜在していた新たな力の発見であり、そうした人々同士のつながり直しでもある。
手紙や農作業、これこそがいいと言うつもりはない。出来合いのお手本ではなく、つながりとは何か、自分の中のつながる力はどこにあるか、それぞれの発見に満ちたフォーラムだった。
私達の人生百年時代を生きる覚悟とは、このことを言うのかもしれない。