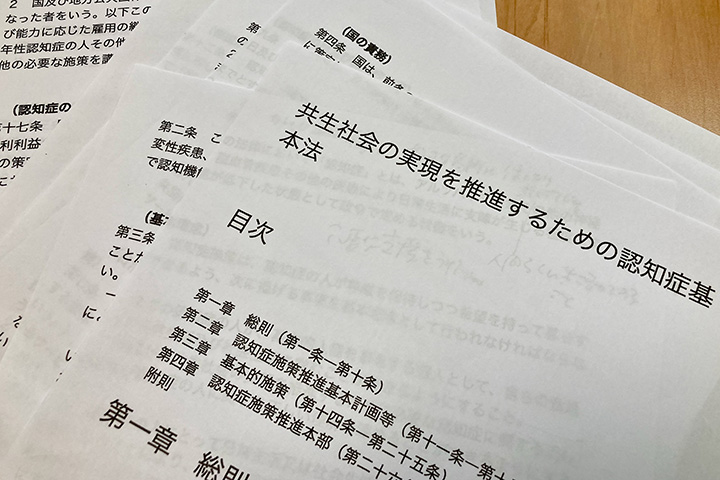▲高原で出会ったアサギマダラ。群れとなって一面に羽ばたいていた。この蝶は晩夏、海を渡って南西諸島、台湾にまで渡るという。生きていくのは苦難に満ちているのか、輝きなのか。高原は秋の気配だ。
コロナの日々というのは、積極的な活動に制限がかかる分、どこかこれまでの取り組みや自分自身を振りかえると言った内省の時間を誰もが持ち、それはこれまで前のめりに突っ走ってきた社会を一旦立ち止まらせる体験につながったのかもしれない。
少なくとも、私自身には、そんな時間が自分の周りを取り囲んでいた感覚がある。
今のこの社会のキーワードといえば、たとえば、共生社会とか多様性といった言葉がある。
こうした時代性を一言で括る言葉というのは、その背景のじっとりとした重みの現実から生まれたはずなのだが、言葉が広まるにつれ、次第にそうした重力から解き放たれてゼログラビティの空間に漂いはじめ、とにかく言説にこの言葉を散りばめれば、それだけで、エイヤッと何かしらの問題意識のある人になれちゃう、という便利な呪文になってしまった。
いうまでもなく、それぞれの言葉自体は記号性を内部にはらむ重層する意味があり、こうした言葉は常に私たちの側が問われていることを指し示している。呪文は魔法の「解」であるが、共生は、社会現実での多義の「問い」なのである。
「共生」の問いのひとつに「自分ごと」がある。2016年に国が打ち出した地域共生社会には、「我がこと・丸ごと」とされて、支援と被支援ではなく互助の形成という「我がこと」と、市町村自治体の縦割り行政を超えた連携としての「丸ごと」をセットで呼びかけたことから、急速に広まった。
しかし、認知症に関していえば、2009年のイギリスの認知症国家戦略にはすでに「Everybody's Business (誰もに、誰もが、関わること)」が謳われていた。認知症に焦点化することで、より切実で広範な人々の能動を呼びかけたのである。その意味では、「認知症」は現在に至るまで常に、世界の社会システムの更新を呼びかけてきたといえる。
さて、「自分ごと」である。地域共生社会では、これまでの福祉政策を転換し、地域課題はいわば「ご当地システム」といったもので「自分ごと」、つまり住民主体で取り組むことになった。しかし、その根底には、住民それぞれが「自分ごと」をどう捉えているか、そこのところから確認し転換していかなければかけ声だけに終わってしまう。
では「自分ごと」とはどういうことか。この設問に以下に30字以内で答えなさい。という正解を求めること自体がそぐわないのだが、とりあえず、どういうことだろう。
「自分ごと」とは、さまざまな課題を自分のこととして引き受け取り組むこと。
これで32語で、間違いではないとしても、なんだかわからない。でも多くの人の「自分ごと」とは、この次元にたたずんでいるのではないだろうか。ここには、「自分ごと」という言葉自体が、「自分ごと」になっていないというトラップが潜んでいる。
よく教育現場などで、「相手の気持ちになって考えましょう」と言う。
障がい理解の授業などで、子どもたちがアイマスクをしたり、車椅子体験をして、視覚障害や身体障害体験をするわけだ。これは社会の側のバリアフリー感覚の必然には大きな意味があると思うが、えてしてこうした体験を通して、「障がいのある人は、こんなに大変なのだから、手を差し伸べてあげましょう」と誘導したりすることも(一部では)あったかもしれない。
これは、実は健常の側、マジョリティの側の価値観で見た障がい理解にとどまる。ここにはどこかに「かわいそうな人たち」と言う対象化の見方がうずくまっていて、共生モデルというより無意識に、健常と障がいの間に壁を作りかねない。
相手の気持ちと言っても、それは自分のこれまでの経験に基づいた推測でしかなく、それは自分の気持ちでアレンジされた相手の気持ちなのである。
ここには、共生も自分ごともない。
「相手の気持ちになって考えましょう」と言う言葉は大切な言葉であるのは間違いない。しかし、同時にこれは大変に難しい。一歩深く考えれば、相手の気持ちになって考えるということが本当にできるのか、他者存在はわかるのか、と言う問いが立ちはだかる。
日本社会はすでに多様な価値観と文化背景を持つ人々との共存社会である。
法務省によれば、2021年の在留外国人はコロナの感染拡大の影響を受けて若干減ったものの、276万人で、総人口の2.18%、30年前の2.15倍で今後、その増加は加速することが見込まれている。すでに外国人は、ガイコクジンではなく、地域の隣の生活者なのである。
となれば、共生とは、私たちの均質同質の社会の中だけでの、わかり合える人々との心地よい関係性ではなく、互いにわかり得ない中で、どう生きることを共にするのかと言う新たな問いかけになっている。
その時出てきたのが、シンパシーからエンパシーという考え方だ。
シンパシー(sympathy)とは主に同情、共感とされて、相手の気持ちになって考えましょう、という私たちの共生観は、このシンパシーが大きな役割を果たしている。
対して、今出てきているのが、エンパシー(empathy)という考え方である。
エンパシーはフィンランドなど、多文化圏のヨーロッパの国々で強調された概念で、そこには、互いの価値観がバラバラの中でどうコミュニケーションを成立させるかという問題意識がある。
元外交官の北川達夫氏と劇作家の平田オリザ氏はその対談で、これからの社会での対話にはエンパシーという考え方が重要であると、その導入をいち早く提言していた。
エンパシーの定義としては、「自他の区別を前提としたうえで、意識的、能動的に他者の視点に立ち、他者の立場に置かれた自分を想像することに基づいた相手理解のこと」とし、従来のシンパシーは「感情移入」であるのに対してエンパシーはそれとは異なる概念で「自己移入」という訳語をあてている。(ニッポンには対話がない・2008 三省堂)
「自分ごと」を、相手の気持ちになって考えましょう、といった従来の共生観とするには限界がある。それはその自分は善意の持ち主であることを前提とし、その発動は、常に「弱者のために」という正義の側に立つことになる。
私は、自己移入というエンパシーにあるのが「自分ごと」なのではないかと思う。
エンパシーから見れば、「能動的に他者の視点になって、他者の立場に置かれた自分を想像する」こととは、自分の徹底した再検証を促すはずである。
自己移入であれば、自分の感覚や思考をどう変革し押し広げていくか、自分を問い続けながら、相手の立場に立とうとする。となれば、自分ごととは、自分の中の他者を発見し、自分の依拠する安全圏を解体し、ひたすら自分自身に向かっての問いかけになっていく。
認知症である人とまだなっていない人の間には、明確な「自他の区別」が存在する。私たちの「認知症と共に生きる」はその区別をあえてうやむやにしてきた。あるいは、高度な次元からの「共に人間である」という互いの存在承認を引き合いにし、観念の架け橋でしのいだ。
理念的には燦然としているが、暮らしの感覚では、「なんのこっちゃ」なのである。
だから、「認知症と共に生きる」とは、エンパシーの起動なのである。
別の言い方をすれば、エンパシーとは、自分の中の当事者性(認知症と言ってもいい)を見出す作業である。当事者の声を「自分ごと」とするためにはエンパシーを自分の中に響かせることになる。
シンパシーとエンパシーは、実はなかなかわかりにくい。が、その定義を解きほぐすのではなく、私たちは、エンパシーの前提での、わかり得ない他者であるとか、自分自身の中のわからない部分に向き合うことこそが共生の問いなのだと感じ取ることはできる。
正しいこと、答えのあることばかりの追求ではなく、わからなさに満ちた世界に、豊かな可能性や秘められた力があるはずだ。
そういえば、第一に自分自身がわからない。だから自分ごとなのだ。
「あー、わからないことばかりだ」とつぶやくあなたは、今、共生の扉の前にいる。