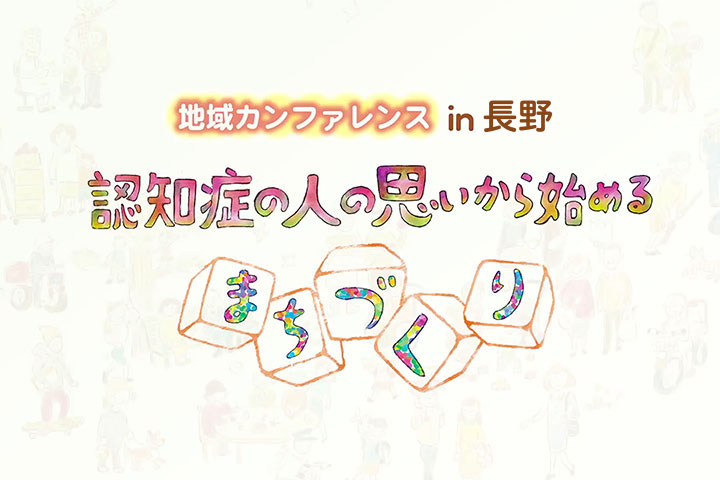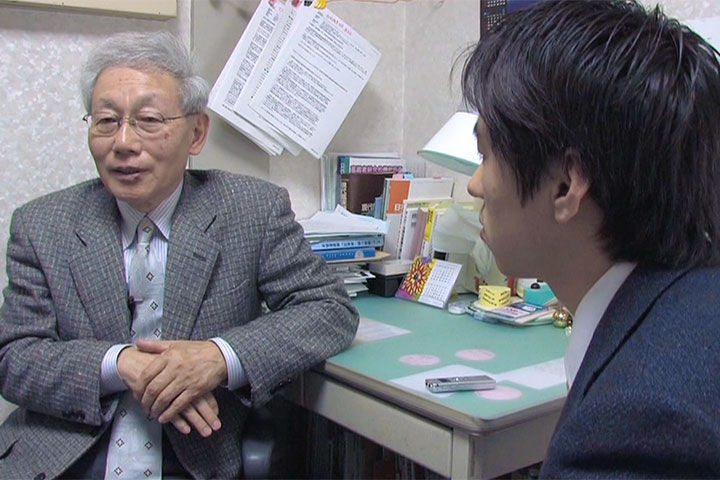▲2017年4月の京都ADIでは、認知症当事者のケイト・スワファーは、認知症の人の権利擁護を語った。その時のプレゼンで示したのが「認知症を見るのではなく、人を見よ」。力強いメッセージは、会場を圧した。(撮影:町永俊雄)
「認知症とともに生きる」ということは、改めてどういうことなのでしょうか。
何か、同じことをひたすらくりかえし問い直しているようですが、大きな岩も指先で小さく小さく突き動かせば、やがて地響きたてて転がるかもしれません。それが、私たちが出来る社会を変えること、なのでしょう。
「認知症とともに生きる」、こうしたフレーズには、必ずそれを生み出した背景があり、それを抜きに「認知症とともに生きるっ!」と呪文のように唱えても、アラジンのランプではないので、全能の魔神が出現するわけではありません。
この言葉は、私たちの共生の言葉というより、まず当事者の切実な決意が生み出しました。そのあたりは日本認知症本人ワーキンググループの「認知症とともに生きる希望宣言」を読めばいいと思います。
読めば分かるようにこれは認知症の本人の側の決意表明なのです。
認知症患者、あるいは介護される人という医療や介護の側のレッテルを引き剥がし、自分の認知症を受け入れ、自分を取り戻す宣言です。与えられた希望ではなく、つかみとった自前の希望が語られています。
この連載コラムは、どちらかといえばまだ認知症になっていない私たちが、どう認知症を内面化するか、といったあたりを焦点としていますので、そうした私たちからすれば、どうもこの「認知症とともに生きる」を、心のどこかで「認知症の人とともに生きてあげる」としてしまっているんじゃないか、と思うことがあります。
希望宣言の主体は、認知症の本人です。それは、あえていえば、認知症とともに生きることを引き受けざるを得ないことの宣言です。「認知症とともに生きる」を前提とするしか自分の「現在」を歩むことができない中で同じ当事者に向け、互いにしっかりと顔を前に向けようと、その先を呼びかける宣言となっています。だから、宣言文のタイトル以外にはどこにも「認知症とともに生きる」という文面はありません。
対して、私たちの「認知症とともに生きる」は、ア・ポステリオリ(後天的)の学習的な理念とならざるを得ません。
認知症ではない人にとっては、どうしても認知症は他者性を帯びています。だって、なっていないのですから。理屈では自分ごとであるといくら自分に言い聞かせても、認知症でない以上、それは理屈の上だけを滑り、なおかつ心の底深いところでは、なりたくないとする心情がうずくまっています。
でも、私はそれは仕方がないと思います。むしろ、認知症にはなりたくないとする自分を否定しようと思い込むことには無理があります。そうした自分自身を認めた上で考えることが、「認知症とともに生きる」ということだと思います。
としたら、ことさら認知症だけを切り出すのではなく、自分の内面や自分の属する社会の側を探ることというふうに方向転換してみてはどうでしょうか。
少し脇道にそれますが、現代の学問、知的作業というのは要素還元主義にのっとってどんどんと深く細密な方向に進んでいます。医学などのサイエンスやテクノロジーの世界です。私たちの身体自体が、精密部品のようにして限りなく細分化されています。
対して、私たちの暮らしとは、還元主義に対置する社会構成主義からすれば、全てが溶け込み関わり合うような人文科学領域のマクロな全体性の中に機能しています。
近年、日本でも大学院改革などでリベラルアーツ軽視の傾向に一部から批判が出ていますが、あのアップル創業者のスティーブ・ジョブズは、「テクノロジーとリベラルアーツの交差点に立つ」と宣言し、次々と革命的な製品を生み出してきました。
同じようなことでは、心理学者で文化庁長官だった河合隼雄は、「医学は科学、医療は物語」と語ったことがあります。
何が言いたいのかと言いますと、私は、「認知症」というのは、こうした専門性と暮らしという統合性との深い谷間をつなぐ交差点、あるいは回廊になりうるのではと思っています。
認知症を語ることは、医学とは何かを問うことであり、振り返る同じまなざしで自分自身とこの社会全体のありようを問いかけることなのです。認知症は、混迷する社会の総合知として存在しているとも言えると思います。
認知症をそのように見るためには、何か仕掛けが必要です。認知症を語らずに、認知症を考える、といったひねった角度が必要です。
それには格好のテーマがあります。誰もの属性としての「老い」です。
認知症になることは、一般には加齢リスクの要因が大きいとされています。ま、年を取るほど、認知症になりうる、ということです。となると、なぜ社会の側にネガティブな認知症観が根深く居座るのかは、認知症ではなく、誰もにやってくる老いについて考えることで引き寄せられるはずです。
それはエイジズムです。世界の三大差別と言われるものがあって、ひとつが人種差別(レイシズム)、そして性差別(セクシズム)、そしてこれが最も深刻な差別であると言われているのが、アメリカの老年学の父、ロバート・バトラーが提唱した年齢差別・老人差別(エイジズム)というものです。
バトラーは、エイジズムを「年をとっているというだけで高齢者たちをひとつのステレオタイプにはめ差別すること」と定義しています。
なぜエイジズム、老人差別が最も深刻なのか、それは誰もが持っていて、意識しないで差別しているからです。エイジズムは、私たちの幸福の図柄であった「長寿」をおびえの中に落とし込んでいきます。
高齢化率が跳ね上がるたびに、社会全体がビクッと怯えるように大きく報道され、超高齢社会とは来てはならない社会で、高齢者が増えることを問題とする記事で報道は溢れていきます。
この社会は「年をとることは問題だ」と喧伝している社会なのです。
老いていく自分は、生産性が落ち、衰退していく自分であり、社会に無用で、社会の負担となっていく。意識、無意識にかかわらず、そう思い込みます。いや、思い込まされています。
エスカレーターで高齢者を駆け抜き、レジに並ぶ高齢者の後ろで舌打ちし、電車の優先席で眠ったふりする若い世代、これは単にモラルの問題というより、もっと根深いところがあります。
それは若い人々自体が、高齢者たちは時間差での自分の姿だという感覚を誰もがあえて遮断しているのです。そこに自分を見ないようにしています。
実はそれは、未来の自分を「問題化」し、否定していることに気づかないのです。この社会の根本的な貧しさは、若い世代もまた、自分の未来を閉ざしながら今を生きていることなのです。
街角で、あるいは電車の中で、老人を見るまなざしがいつも衰退した人として眺め、ついに豊かな人生の人と見ることがなくなってしまったのなら、そのことがどれほどこの社会を傷つけているのか。
実はこの世間に根深く居座るネガティブな認知症観というのは、このエイジズムによって底支えされているのです。何もわからなくなる、何もできなくなるということは、ほとんど、エイジズムでの老いの姿を踏襲しています。
高齢化への怯えのほとんどは社会の側で作られています。それは認知症を「何もわからなくなる。何もできなくなる」という烙印(スティグマ)を焼き付ける社会の悪意が、常に社会の底でうごめいていることと連動しています。
さて、ここまで誰もの未来としての「老い」をたどった上で、改めて「認知症」を考えてみると、どうでしょうか、ずいぶんと違った風景が現れてはこないでしょうか。
当然ですが、私はここで何かの答えを出すつもりも、また出すこともできません。ただ、エイジズムも旧来のネガティブな認知症観も、同心円的に仕組まれた社会の深層意識です。その呪縛を解きほぐすことではじめて「認知症とともに生きる」への道筋が見えてくるような気がします。そしてその道筋の先にはどんな風景が見えてくるのでしょうか。
ピーブルファーストと呼ばれる世界的な運動があります。
1973年、アメリカのオレゴン州のひとりの少女が、知的障害の人々の集会で、「障害者ではなく、まず人間として扱われたい( I want to treated like PEOPLE FIRST)」と発言し、そこから世界にピープルファーストの団体と活動が広がっていきました。
2017年4月、京都で開かれた国際アルツハイマー病協会国際会議(ADI)で、オーストラリアの当事者、ケイト・スワファーは、「認知症を見るのではなく、人を見よ(SEE THE PERSON NOT THE DEMENTIA)」の言葉を大きく掲げて、認知症の人の権利擁護を講演しました。
「認知症」も「障害者運動」も、今一度、この社会を「人間」の地点にまで引き戻して考えようと言っているのです。ピープルファーストなのだと。
この社会は「人間」の社会となっているのか。認知症にまとわりつく一切合切も含め、それを突き抜けて立ち戻る地点は「人間」であると、絶えず「認知症」は呼びかけています。
つづく
|第210回 2022.5.13|