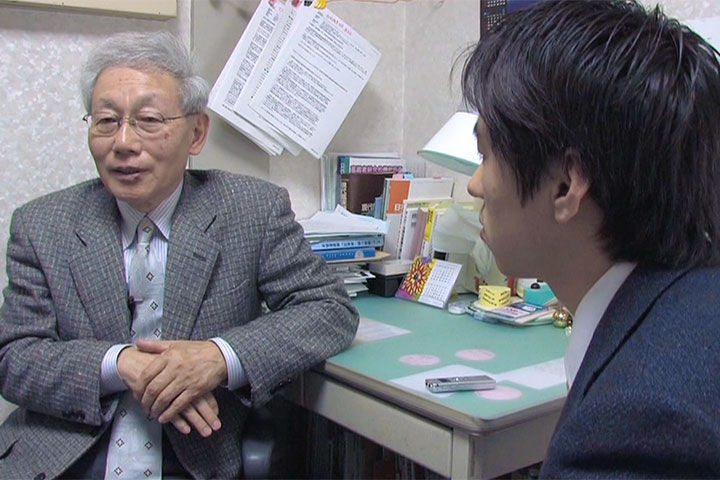▲2年前の誰もいない横浜の港の風景。誰もいない風景をじっと眺めていると、いつしか、自分自身の内面を眺めるような視線になる。喪失を見ないで、この2年間を過ごしてしまったのだろうか。
喪失の時代である。
私たちのこの社会は、ひたすら喪失し続けている。
繁栄を失い、人口を失い、若さを失い、子供を失い、地域を失い、未来を失うという喪失の社会の中に私たちはいる。
私たちは喪失を語らない。私たちは言葉を失っている。それは、喪失する社会を見たくないからである。
経済の衰退は歯止めが効かない。1990年代には世界の競争力ナンバーワンだったこの国は、それからの失速で2020年には34位と急落している(IMD世界競争力年鑑2020)。
あの経済繁栄はすでに幻想の彼方だ。
さらに繁栄を支える日本の総人口は、2050年には、2004年のピークから約25.5%の減少と4分の一の人口を失い、その内訳の生産年齢人口では約3500万人が減少、14歳までの若年人口は約900万人が減少すると推計される。
この間の高齢者の増加は1200万人だから、その約4倍近くの大人と子供がごっそりと消えていく。高齢者が増える以上に際限なく現役世代が消えていき、これが高齢化率を押し上げていく。
この社会は、若さと労働と、子供の姿を失っていく(国土交通省「国土の長期展望」)。
暮らしの舞台が消えていく。全国の896の市町村区が消滅可能性都市といういささか乱暴な指定が日本創生会議でされたのは2014年のことだ。しかし、それ以前から言われ続けている日本の過疎化は今や全市町村の47.8%を超え、すでに自治体の半分である(総務省「過疎対策の現状と課題」2017)。ふるさとは、ノスタルジアの中の唱歌にしか存在できない。
すべての数値は、私たちの社会は喪失の社会であることを指し示している。
手に掬い取った浜の砂が指先からこぼれ落ちていくようにこれまでの社会の姿を失っていく。そのような時代を生きていく。
喪失の社会を止めるのは難しいだろう。それは宿命であり、所与の社会の姿と言ってもいい。そのことの典型として、私たちは少子超高齢社会の中にいる。
しかし、この社会の喪失とは、一方的に誰かがこの国の資源を奪っているわけではない。この国の構造的体質が、抱えてきたものを維持できなくなった経年劣化の膨大な蓄積がもたらしたものなのではないか。
喪失は、この社会の枠組みの更新もせずにここまで至ってしまった結果なのである。
誰もがこの社会は変わらなければならないと口にする。
変わらなければならない社会として、「ともに生きる」共生モデルと多様性の社会を掲げるが、そこには、希望やつながりといった口当たりの良い言葉の表層だけをまとわりつかせ、それに伴う痛みを引き受けることに踏み出せない。
共生社会も多様性もつながりも、目指すというほどの時間の猶予はなく、すでにこの社会は維持できない今ここにある現実の課題なのである。
SDGs、持続可能な開発目標にしても、今あるこの社会の枠組みの持続と勝手に読み替えて、この世界の根本的な問題から目を逸らす役割となっていると警鐘を鳴らす人もいる(*1)。
ひたすらの喪失は、この社会に新しい姿に生まれ変わることへの要求なのである。もう元の姿には戻ることができないことの最期通告なのである。
これまでの価値観に執着していては、新たな姿は見えてこない。これまで抱えきれないほどに掴み取ってきたものを手放さなければ、新たなものを生み出すことは出来はしない。放下(*2)である。
なぜ私たちは、この喪失を語らないのだろう。無感覚なのだろう。
それは、どこかでこの喪失の時代を、自分だけは「逃げ切ること」ができると思っているからだ。
地球温暖化にしても、その未来予測の時間軸の多くは今世紀末に置かれている。だったら、逃げ切るには十分だ。そのように思い込んではいないだろうか。
すでにあなたの周辺の喪失は進み、あなた自身も喪失に包まれているのに。
喪失に真っ向から向き合っている一群の人々がいる。
認知症とともに生きる人々である。認知症と診断されることは、自分の喪失を突きつけられることになる。認知症の人は、自分の喪失から逃げることはできない。すべてを手放し喪失を見据えるしかない。
では、喪失とはどういうことか。
喪失とは、その心理過程での「喪の作業(モーニングワーク mourning work)」(*3)の4段階をたどることになる。それは、麻痺するほどのショックに始まり、否認から絶望に落ち込み、そしてやがて立ち直りに至るとされている。もちろんこれはひとつの概念に過ぎないが、私の知る認知症の人々の多くはやはり、この道筋をたどっているように感じる。
喪失とは、とかくネガティブな文脈で語られるが、喪失から逃げることなく見据えてきたのが、認知症当事者の人々である。ネガティブという弱さを、自身の力としたと言っていい。
ポジティブであることだけが求められ、常に答えを出すことを課してきたこの社会は、喪失という不可解で不確実な状況を読み解くことはできない。
ネガティブ・ケイパビリティ(*4)という言葉が今、注目されている。
「答えの出ない事態に耐える能力」とされるが、能力とは通常、この社会では何かを成し遂げる力とされる。しかし、そうではなく、それをしない能力、問題解決や解ろうとすることをしないという状況の中にいられる能力こそが、コトの本質に迫ることができるというもので、それがネガティブ・ケイパビリティなのである。
実際は深くて広範な概念を含むのだが、世の多くの精神科医や哲学者が、この言葉に惹かれるのもわかるような気がする(性急にわかろうとしないでいるのも、この能力なのだが)。
私は、これは認知症の力、かもしれない。そんなふうにも思った。認知症が見出す喪失の本質、といったふうに…
この力は、そのまま喪失に向き合う力なのだ。引き受け、逃げない。耐える。
認知症の人は、このネガティブ・ケイパビリティとともに、自身の喪失を見据えてきた。
喪失を見据えよ。そこから生まれる新たな何かがある。喪失の時代に、認知症の人々はそのことを指し示しているように思えてならない。
*1…東京大学大学院准教授の斎藤幸平(社会思想)は、SDGsでの、マイバッグやマイボトルといった小手先の行動は資本主義が内包する根本的な問題から目をそらす「大衆のアヘン」の役割をすると警鐘を鳴らした。
*2…放下(ほうげ) 禅の言葉。物事に執着せず、迷いを捨て去ること。解脱。
*3…喪の作業(モーニングワーク mourning work) フロイトが提唱した概念。その心理過程は四段階で、1. 麻痺/無感覚(激しいショック) 2. 否認・抗議 3. 絶望・失意 4. 離脱・再建(喪失の受け止め、立ち直り)とされる。
*4…ネガティブ・ケイパビリティ(Negative capability) 19世紀のイギリスの詩人、ジョン・キーツの残した言葉。後世になって精神科医や哲学者によって再発見され注目される。定訳はないが、作家で精神科医の帚木蓬生は、自身の著「ネガティブ・ケイパビリティ」のサブタイトルに「答えの出ない事態に耐える力」としている。