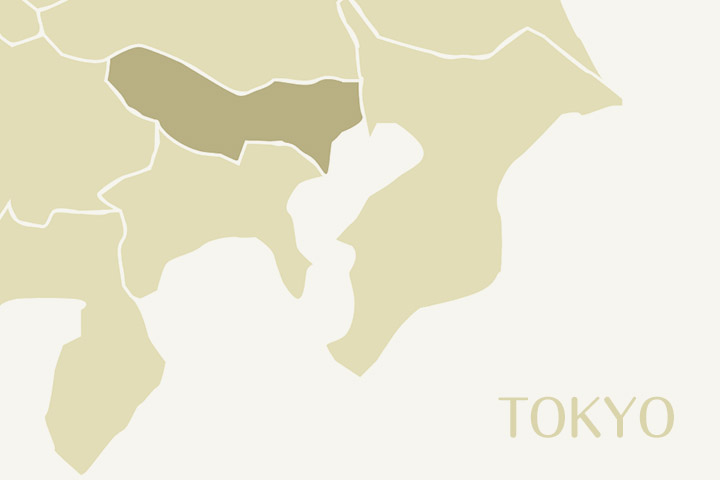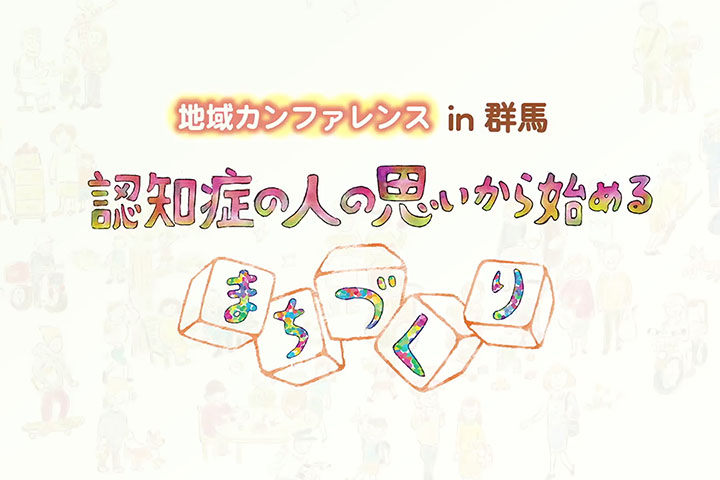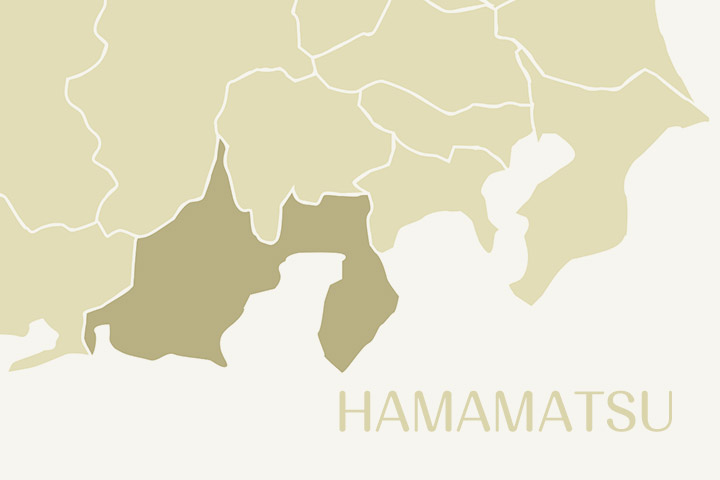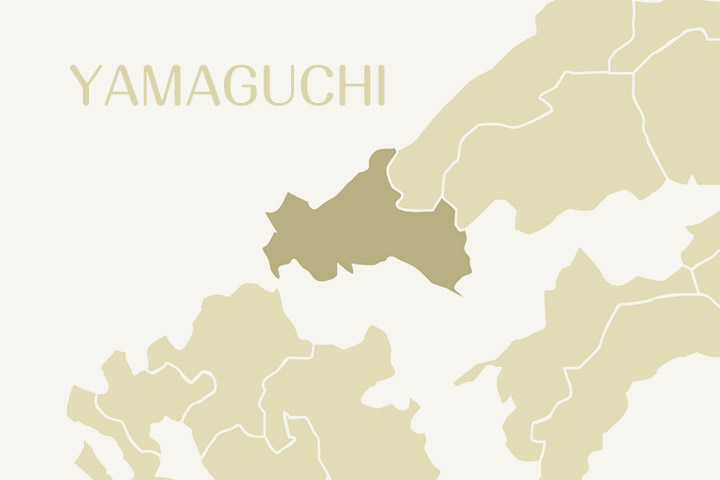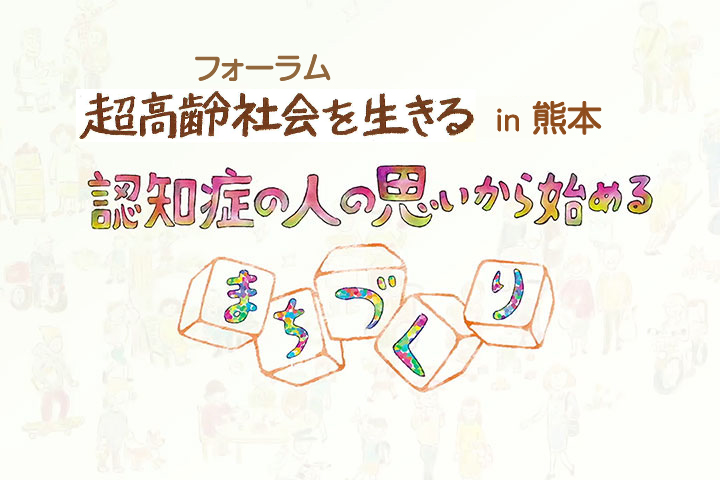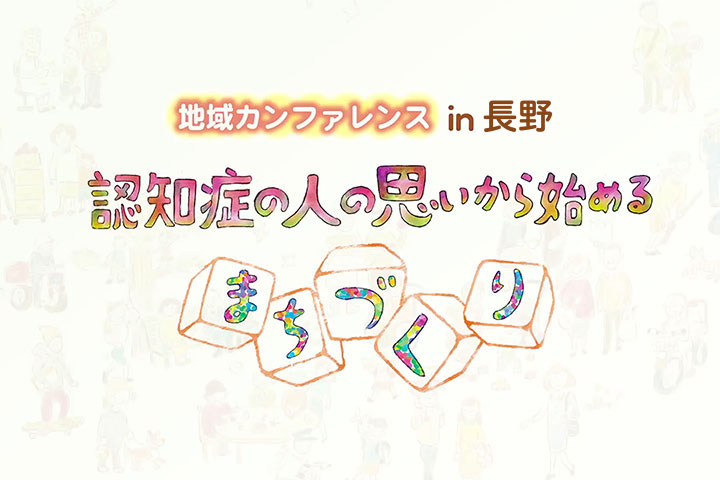▲この本の表紙の色合いはなかなか写真では伝わらないかもしれない。この本の対話は理解するより、心に響かせるものかもしれない。誰もの胸に音叉の共鳴のようにして伝わるだろう。
今、二冊の本を手にしている。認知症の精神療法の本である。
しかし、この手の医学本にしては、その不思議な本の雰囲気になんとも魅了される。先ほどからためつすがめつして表紙を眺めているのだが、まず、その装丁である。フランス装によくある端正な無線綴じで、軽快なようで同時に、シンとした知性のたたずまいがある。
くりかえすが、認知症の精神療法の二冊なのである。が、その表紙の色合いが、静かに心情を写し取るような印象を醸し出す。アースカラーとでも言えばいいのか、一冊は、芽吹く春の土の色、あるいは老木の木肌を思わせるマットなブラウンに、同じ色合いのやや濃色で「アルツハイマー型認知症の人との対話」と明朝体のタイトルが置かれている。
そしてもう一冊も同じようにくすんだオリーブグリーンの表紙に、同色で「認知症の人の家族との対話」のタイトルが刷り込まれている。
あえて目立たせるよりもむしろ、色の諧調にタイトルを沈み込ませるような「認知症」の装丁になっている。そしてそこに、この本の著者である「治療者」の静かに語りかけるようなメッセージが浮き上がる。
認知症をこのように語る。「認知症」だけを際立たせるのではなく、同じ色彩に溶け込ませて認知症を語る。私とあなたが溶け合うようにして、認知症を語る。語り合う。
そのような本である。
この本自体は重層的な構成となっているのだが、主たるコンテンツとしては認知症の人や家族と、専門性を備えた治療者との対話集と言っていい。
対話といえば、フィンランド発祥の、精神疾患の人とのオープンダイアローグが注目されている。当事者と当事者に関わるネットワークの人々が集まって対話する。それだけで大きな治療効果をもたらすと言われている。
この本に収められている認知症の人との対話もそうした療法と通底しながら、しかし、その対話の密度はあきらかに、それとは違う。
登場するのは、「治療者」と「本人」「家族」と言った記号的匿名で記された人々との対話である。ここにあるのは、それぞれの対話ごとに何かの成果、効果、改善といったものを目指すものではないらしい。
実際、対話自体にどんな意味があるのか、精神療法としての役割とはどこにあるのか、といった説明的な解説は、それぞれの対話の後の治療者のコメントには明示されない。対話後の治療者のコメントは、補足的な感想であったり、時に内省的であったり、同席した若い研修医との見解の違いに、治療者自身が考え込んだりしている。
治療者が目指すのは、直線的な医療効果や、治療への適正解を回避することでここでの対話を成り立たせている。精神療法の知見はむき出しには表面化しない。それをはるかに後退させながら、まっすぐに人と向き合う対話となっている。
例えば、72歳のアルツハイマーの女性は、治療者に自分の状態を伝えるために大学ノートに記したことを話そうとするのだが、どこに何を記したかわからず、ほとんど何も伝えられない。その短い対話が載っている。そのある部分だけを抜き出すのは、あるいは治療者の本意ではないだろうが、その対話はこんな風景を見せている。
治療者 焦らなくていいです。時間はあります。ちゃんと話そうとしなくていいです。話の内容が矛盾していてもいいです。私もそう。
本人 ・・・・・
治療者 差し当たり思いついたことを何か言ってくれればいい。そしたら私が何か言うから。それが診療の目的。言葉は大して問題ではないです。どんな思いで話すかが大事。
ここに治療者の考える対話の真髄がある、そんな思いがする。
この対話ではほとんどアルツハイマーの女性は喋っていない。文字起こしされた対話の活字を追う限りでは、治療者の側が懸命に語りかけているようでもある。しかし、ここにあるのが対話なのだ。治療者はどのように語りかけているか。改めてその言葉を繰り返し記す。
「言葉は大して問題ではないです。どんな思いで話すかが大事」
言葉という表意手段ではなく、思いで、こころで話してほしいと治療者は語りかけている。
治療者だけが語りかけているのではない。そこには「・・・・」で記される本人の無声が、治療者の語りかけと同じ質量の、未生の言葉として、あふれる思いとして、確かに聴こえてこないだろうか。治療者は、その声になる以前の思いを聴き取りながら対話している。
この対話集の一番の特徴というのは、記されている対話の活字に、読む側が確かに本人や治療者の声を聴く体験をすることにある。活字でありながら、対話が聴こえてくるのだ。
この書籍は、哲学概念の「バロール(音声)はエクリチュール(文字)に優越する」とする階層的二項対立を脱構築している。エクリチュールとしての活字となった対話が、逆に実際に交わされたであろう対話の音声、バロールを侵食し、そこでの対話者の声や息遣い、思い、こころの全てにその意味を付与し、新たな視点の交差を深いところから再構成している。
実際に治療者は、対話にのぞむ際には一切事前に質問などを用意することはない。全て本人や家族の語ることにその場で反応し、自分の見識、思いを語るようにしているという。
だからこの対話を読む人々は、時にさりげない対話の、その水面下の治療者と本人との凄まじいまでの葛藤に満ちたやりとりに息を呑む思いがするはずである。そこまでが聴こえてくる対話なのである。
この二冊の対話に収められているいくつもの対話の起伏、振幅は大きい。
対話によって互いの共感が生まれる場合もあれば、認知症の妻を虐待する夫との対話も緊張感と共に収められ、あるいは、何を言っても「諦めろっていうことでしょ」と繰り返す本人との対話もある。その対話のコメントには、こうした陰性感情を発露させたことに大きい意味があったという治療者のコメントが添えられている。
私はこの対話のひとつひとつを読むたびに、眼を虚空にさまよわせてしまう。それは今読んだ対話を自分の中で再生させるようにして響かせるためである。わかろうとするより、その対話の場の自分の臨場感を思い起こさせるための時間である。
例えば私は、この対話を読むことでこんな錯覚を覚える。
本の中のひとつの対話が閉じると、それは今度は読んでいた私に開かれる。
それはまるで、対話していた本人と治療者が、椅子をずらして私の方に向き直り、「あなたはどう聴いたのか」と問われるような感覚だ。
問われるのは、認知症のことを突き抜けて、すべてのつらさや困難の中にいる人々に、あなたはどのような言葉と思いを持っているのか、といったことであったりする。
私だったら、どのように対話するだろう。
同時にこの本には、対話の海を航海するための羅針盤も記されている。対話の合間に組み込まれた治療者による「補稿」とする考察は、いくつもの対話を俯瞰するようにして、「認知症とともにある」ことを精神療法の視点から指し示している。
さまざまな読み方があって然るべきなのだろうが、私はまず対話を読み、そのあと「補稿」を読み込むと、世界が目の前にひろがっていく思いがした。
ある「補稿」には、こんな記述が置かれている。
アルツハイマー型認知症の人は体験した内容の多くを思い出せないかもしれない。しかし体験に伴って生じた楽しさや悲しみといった感情は、認知症のない人と同じ時間持続させることができる。
沸き起こった感情は私達同様に余韻を残しながら痕跡を残すはずだから」
改めて、この治療者が向き合うのは、認知症の向こうの一人ひとりの「人間」なのであり、その人間存在へのひたすらの敬意なのだろう。
この対話は、精神療法という医学用語に満ちた教本ではなく、つらさや困難の中の人々の声に向き合う治療者自身のもうひとつの声と、読むものとの間に新たな対話が始まっていく、そのような本である。自分自身と出会うことができる本である。
本の帯にはこの治療者の「思い」が載せられている。
話すに値する相手へ思いが
自分にあるかどうか」
共感してくれる人がいれば
受容できるかもしれない」
ちなみに、この本の治療者とは、繁田雅弘先生のことである。
|第275回 2024.3.27|