-

「認知症大綱」 予防と共生の車の両輪は成り立つか
コラム6月18日に認知症の大綱が決まった。大綱案では、予防の数値目標に対する反発などから修正を余儀なくされたのはご存知の通りだ。
-

「認知症予防と共生」、見るべきものは何か
コラム政府の認知症大綱案の目玉とされた「予防」の数値目標が取り下げられた。認知症の人や家族団体からの猛反発があったことが修正につながったとされる。
-

「認知症予防」と「共生」
コラム政府が5月16日に認知症の大綱案の目玉とした予防の数値目標を取りやめると、6月3日、各紙が報道した。
-

「認知症医療」に何ができるのか
コラム6月15日に都内で開かれる認知症当事者勉強会の案内が届いた。今回の報告者は、認知症医療の木之下徹医師である。案内文にはこうある。
-

「認知症」は、わかるはずがないのか
コラム「おしめを替えたこともない人に、私のこのつらさはわかりっこない」はるか以前、番組で育児うつをテーマにしようというブリーフィングの時に同じ思いを持つ女性ディレクターが、男性スタッフにこう言い放った。
-
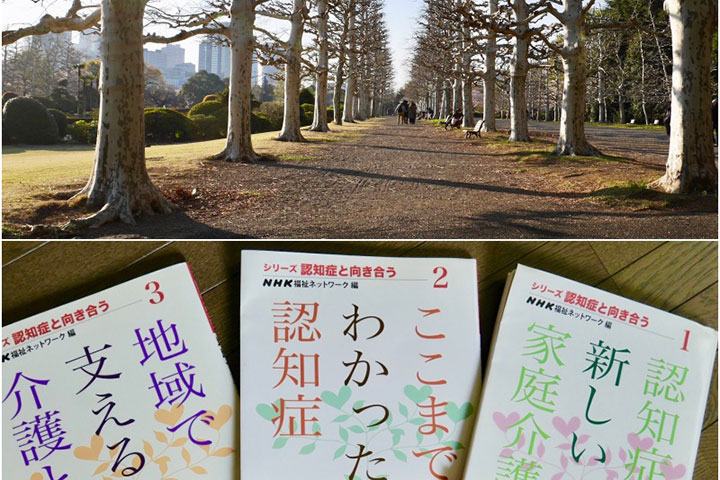
令和の時代の認知症
コラム実は、元号が決まる前、ノーテンキに、新元号は「認知」で決まり、などと友人にメールしていた。一部で認知症のことを「ニンチ」と記号的に使う風潮にかなりの人が違和感を抱いていたはずだが、疾患名を離れて「認知」という単体の言葉をしげしげと眺めれば、これはなかなか味わい深い熟語である。
-

「認知症バリアフリー」と認知症官民協議会
コラムこれからは「認知症バリアフリー」なのだそうだ。どうも「認知症にやさしい社会」が出たと思ったら、「認知症とともに生きる社会」だったり、「認知症でも安心なまちづくり」とか、看板が次々と変わる。
-

認知症を語るのではなく、わたしを語る
コラム私のコラムも、なんと100回を迎えた。イメージとしては、今、私の頭上でくす玉が割れて紙吹雪が舞っている。ひとり祝賀会。
-

映画「長いお別れ」を観て あたりまえの日常に「認知症」を描く
コラム映画「長いお別れ」を観てきた。認知症がテーマの映画だ。試写会のポスターには「だいじょうぶ。記憶は消えても、愛は消えない」というコピーが添えられている。
-

認知症の「総論」と「各論」をつなぐ
コラム認知症に対しては、「総論」と「各論」がある。例えば総論としては「認知症にやさしい社会」であったり、施策的に言えば「地域包括ケア」や「地域共生社会」といったことだろう。一方で、認知症の「各論」というものがある。
-

認知症に「寄り添う」とはどういうことか
コラム「寄り添う」と言う言葉が嫌いだと言う人がいる。あるいは、「向き合う」がしっくりこないと言う人も。「希望」と言う言葉さえ出せば、誰もが納得すると言うわけではないと拒否感を持つ人も。
-

認知症当事者発信と「分断」
コラムよく言われることだが、「聞く」と「聴く」はちがう。自然に耳に入る音は「聞く」だが、しっかりと耳傾けるのが「聴く」と辞書にある。
-
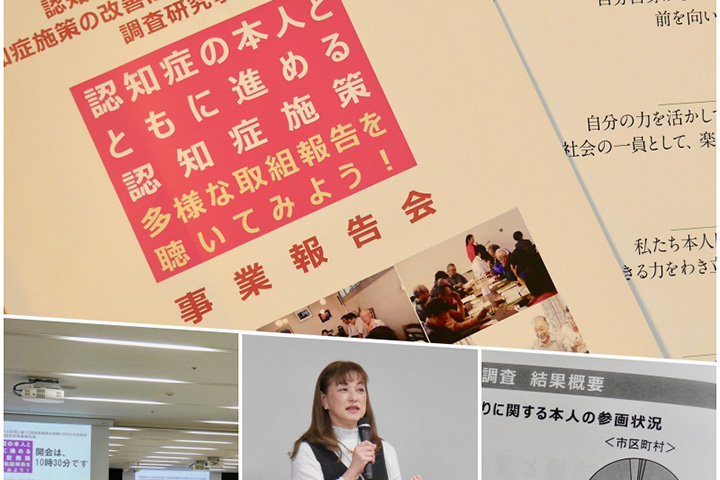
「認知症の本人の声を聴く」 施策に声は届いているか
コラム「認知症の政策の立案に認知症の当事者が参画できない状況があれば、それは異常なことだ」そう言い切って挨拶したのは東京都健康長寿医療センター研究所の粟田主一氏である。
-

「認知症の本人の声を聴く」 私たちは本人の声を聴いているのか
コラム先日、定期的に持っている認知症当事者勉強会で「当事者発信は何を語ってきたのか」という世話人会を持った。報告者は、東京大学文学部准教授の井口高志さん。
-

八千代座で語る「認知症」
コラム熊本県山鹿市で、熊本県の介護専門職の研修会に参加してきた。こうしたイベントなら、普通、公共施設のホールなどが一般的なのだろうが、今回は会場が山鹿市にある明治の芝居小屋、八千代座である。国の指定重要文化財だ。
-

「認知症 5.0」 すぐそこの未来
コラムソサエテイ5.0(Society 5.0)というのをご存知だろうか(社会5.0とも呼ぶ)。この国がめざす未来社会で、超スマート社会のことなのだそうだ。
-

前田隆行 認知症の人とともに「素になれる」あたりまえの社会へ
コラム町田のDAYS BLG! の朝は賑やかだ。迎えの車から続々とBLGのメンバーが集まってくる。(前田さんは認知症の人ではなく、仲間としてメンバーと呼ぶ)ここからここでの1日が始まるのだが、そうそうことは簡単には進まない。
-

認知症の「希望」を語る
コラム新しい年である。新しい年の初めには希望を語るべきだろう。と言いつつ、考えれば、希望を語る、というのは、この新年のいっときしかないのかもしれない。それほど、「希望」の肩身はせまくなってしまった。
-

早川一光 認知症へのまなざし
コラム12月15日、京都の立命館大学朱雀キャンパスで、全国から続々と人が集まって、ただひとりの医療者について、朝10時から夕刻5時まで語り継いだ。
-

「認知症にやさしいまち大賞」
コラム「認知症にやさしいまち大賞」の表彰式が行われた。晴れやかで楽しく、出会いと思いが交錯し自然に笑みが湧いてくる。どこかなつかしい共同体の匂いのするとてもいいイベントだった。