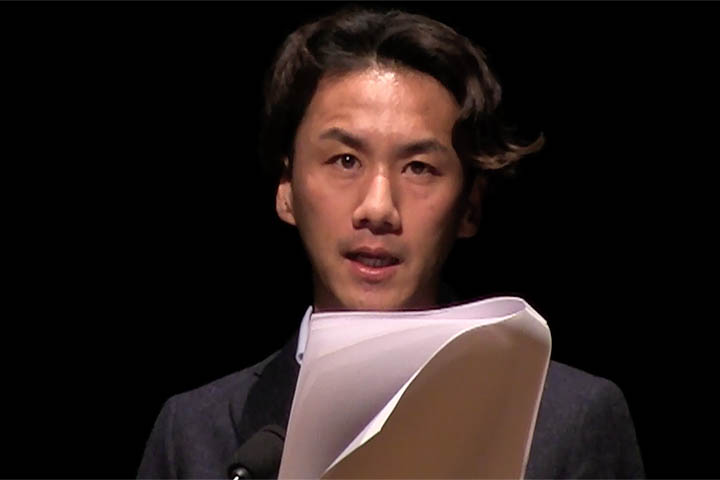▲ 未来に続くプラタナス並木のベンチそれぞれにそれぞれの人が並び、それぞれの人生の物語がたたずむ。高層建築を仰ぐ眼差しは同じでも、思うことはそれぞれ。わかり合えるのは、わからないそれぞれがいるから。(新宿御苑にて)
「おしめを替えたこともない人に、私のこのつらさはわかりっこない」
はるか以前、番組で育児うつをテーマにしようというブリーフィングの時に同じ思いを持つ女性ディレクターが、男性スタッフにこう言い放った。
「わかりっこない」と投げつけるように発せられた言葉は、拒絶なのだろうか。あるいはそれはそのまま、言われた側への人格も含めた徹底的な批判なのだろうか。
もちろんその時は、私を含めた男性陣は誰もがシュンとうなだれるしかなかったのだが、しかし、それは男性の育児参加の不全を突く言葉である以上に、この社会に横たわる本質的などこかを告発した言葉として、今もなお私の胸に刺さっている。
ある人のつらさや困難は、それを経験していない人にとってはわかるはずもなく、共有不可なのだろうか。
これにどう対応するかは、大まかに言っていくつかの類型がある。
ひとつは、「いや、わかる」という共感を寄せる立場。
ひとつは、「わかるはずもないが、わかろうとしたい」という折衷型というか混合型の態度。
ひとつは、「経験していない以上わかるはずもない。わかるとするのはどこか偽善だ」と突き放す立場。
さて、あなたはどの類型に当てはまるのだろうか。どれが正解というわけではなく、どれもが正しく、どれもが物足りない気がする。
例えば、「いや、わかるよ。あなたのつらさはよくわかる」ときっぱりと言って共に手を取り合い涙するというのは、心ひかれる美しい風景だ。己の人生でのつらさや困難の体験をかき集め、その人のつらさの近似へ想像力を駆使し、自分の共感を構築する。
当事者にとって、自分のつらさをわかってもらえるのは一番の大きな励みになる。しかし、これは同時に自身の経験値の押し付けにもなりやすく、同じ経験を持つ人同士のピアサポートとは違う役割をどう持つのか。
もうひとつの「そうだ、わかるはずはない。しかし私はわかろうとしたい」という立場は、どこか冷静で自分自身の納得のためのようであり、はぐらかしているようでもある。
同時にこの立場は、結論ではなく、その人のつらさを自分の側のソーシャルアクションにつなげて行こうとする行動宣言とも聞こえ、誠実の言葉とすれば、今時点での模範的回答かもしれない。
三番目の、「経験していない以上わかるはずもない」というのは、傍目での捉え方でずいぶん違う。わかるはずもないと途方にくれるのか、あるいは、わかるはずもない地点を見据えることの無力感を自分自身のつらさと困難に織り込むかでは、ずいぶんと違うはずである。
「わかるはずもないが、わかろうとしたい」という即答的な自己弁護の匂いが「わかるはずがない」にはない。むしろ絶望や諦念に近い。
繰り返すが、三つの類型のどれが正解ということではないだろう。人間に向き合うのに類型で対応できるわけもなく、誰もがこの三つの類型を縦横に往復しながら自分自身の問いと検証につなげている。
ただ、私自身は、最近この三つ目の「わかるはずがない」という立場を改めて考えることが多い。実は認知症の人を介護する家族や、最も誠実にケアする現場の人々は、少し口ごもりながら「認知症と共に生きると言ってもねえ」と、この切ないまでに冷厳な現実を語ることも多い。
家族の絶望、ケアラーの諦念、そうした思いをないまぜにして「どうしたらいいのか」「なにができるのか」と歩みだす。そこから積み上げていく中ではじめて、「心は生きている」「その人らしさ」を獲得しているような気がしてならない。
近代自我の社会は「わかりえない他者といかに共生するか」ということから始まったとも言われる。政治や経済システムは、制度や組織によってそれに対応してきた。社会福祉という分野こそ、最も求められる共生システムだが、福祉財源が行き詰まるとなぜか「支えあい助けあいましょう」と、誰もがわかりあえるという口当たりのいい「やさしさ」にドドっと雪崩をうった。
そもそも「あなたにわかりっこない」とビシリと言われることに対する怯えを交えたような衝撃はなぜなのか。
恋人から「あなたにわかるはずないわ」と言われるのは恋の終わりを告げる言葉だし、子供が親に「どうせわからないくせに」と言うのは、それは見事な反抗期宣言であると同時に子離れ親離れの到来なのである。
それは言い換えれば、関係性の再構築を求める声だ。
私は常に「わかってもらう」ためにいて、あなたは常に「わかってくれる」ふるまいをする。それってちがいませんか、ということを「あなたにはわかりっこない」と、いらだちと怒りを込めた叫びで表現する。
「支援被支援の関係ではなく」という、わかったようなあなたの側の造語で言われたくないから、「あんたにわかるはずがない」と当事者の魂の叫びをぶつけるしかない。
私たちは「わかりえない他者」との関係性の構築を前提にするしかない。
これまでの共同体の、誰もが同じと言う家族的な均質社会は、異質を排除することで成り立ち、会えばヘラヘラと笑顔で肩叩き合う居心地の良さに甘え浸りきってきた。
やすやすとわかりあえるという幻想社会は、言説を持って自己表現する必要も、志を持って熱議することもなく、ぶつかり合うことを回避し、だれもが同じであれば安穏な日常だと錯誤し、ひたすら民度を下方修正し続けていく。
「認知症と共に生きる」と言うのは、お気楽な「みんな仲良し」であるはずもなく、実はこの「関係性の再構築」の覚悟である。
認知症の人はまず私たちの眼前に「わかりえない他者」として現れ、自身のつらさや困難を自分の内部にしまい込むのではなく、同じわかりえない他者としての私たちの前にひとつひとつを明らかにしていった。
「わかりえない他者」というのは孤立し分断する個を示すのではなく、異なる存在が結節する靭さを生む可能性である。それが「希望宣言」であり、「共創」と言う概念だろう。
そのとき、ふと思うのだが、認知症の人が「あなたにはわかりっこない」と叫ぶ印象が、私に希薄なのはなぜだろう。
すでに周囲の環境で「関係性の再構成」が進み、認知症最適値の地域が整っているのかもしれない。あるいは、周囲の家族、ケアの人、地域の支援者などが緩衝材となって、その叫びは吸収されてしまっているのかもしれない。
私たちは、ひょっとして、すでに葛藤を整理した「正しかるべき認知症の人」の類型だけを目撃していて、「わかりっこない」と叫ぶ、あるいは呟く認知症の人の生の声をどこかで聴きのがしてはいないだろうか、そんな小さな不安が胸よぎるときがある。
|第103回 2019.5.9|