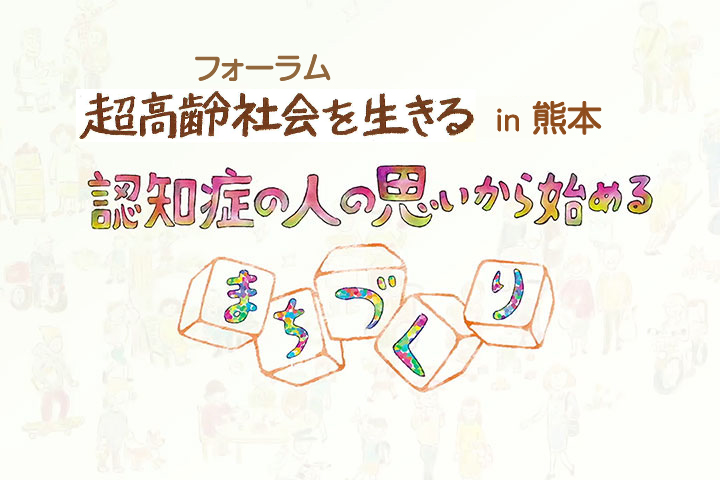▲ NHKが「認知症キャンペーン」を展開し、番組でも集中的に取り上げたのが2006年頃からだった。当時は介護にあたる家族の困難に応え、医療知識を伝え、そしてようやく地域での暮らしまでにたどり着いた。今、中心軸に本人、家族といった当事者の声を据えて令和の時代を牽引していく。(写真上段、新宿御苑。下段、NHK編「認知症と向き合う」2007年旬報社)
実は、元号が決まる前、ノーテンキに、新元号は「認知」で決まり、などと友人にメールしていた。
一部で認知症のことを「ニンチ」と記号的に使う風潮にかなりの人が違和感を抱いていたはずだが、疾患名を離れて「認知」という単体の言葉をしげしげと眺めれば、これはなかなか味わい深い熟語である。
認知。「認める」は、互いの承認であり、「知る」は、互いの理解の交換ということだろう。そこには相手をよく知り、その多様な個性や違いをかけがえのない存在として承認するというインクルーシブな意味合いもまた込められている。
「認知」という元号も捨てがたかったのではないか。誰も言っていないが。
「痴呆症」が「認知症」と呼称変更したのが2004年、ちょうど平成の半ばだった。それから平成の時代は大きくうねり、リーマンショックがその4年後で、日本の繁栄に終止符が打たれた。沈降する経済から交差するようにして「認知症」が立ち上がり、世に押し出されていったのは、どこか民心の本能的な危機感と復元力が反応したところもあったはずだ。
思い返せば、平成のはじまりはグローバル経済が世界を呑み込み、マネーという制御不能な怪物が跋扈した時代からだった。リーマンショックが世界に壊滅的な打撃を与えた荒廃の中、この極東の心やさしい国の人々が「認知症」に向き合うようになったのは、誰もの意識の深層に、確かな存在としての「人間」への認知と回帰があったとは言えないか。
さて、そのようにして私たちは令和を迎えた。
元号が時代を規定するものではないが、それでも時間の流れに区切りをつけて考えるには、いい機会である。
令和の時代に「認知症」をどう捉えるか。
確かに「認知症」への関心は高まった。ただし、関心の高まり自体が何をもたらし、どこを変えていったのか、そのことはいまひとつ実感できていないのではないか。
「認知症でも大丈夫」「認知症でもできることはある」「認知症でも安心の地域」とか、いろいろなキャッチはあふれ、誰もが耳にしたことがあるはずだ。
言葉が最初に世に出ると、そのとき周囲に摩擦を生む。その摩擦が熱を帯び、解釈の幅と修正が重ねられ、世に定位置を持ち、言葉の力となる。
「認知症でも大丈夫」ということが言われた時には、周囲の偏見や差別の中を斬りこむようにして、その言葉に託す人々の思いと実践がその言葉の背後に積み重ねられた。
が、関心の急速な高まりは、同時に言葉から密度を奪い、再生されすぎたレコードのように、どこか変質する。
パソコンのワープロ機能を使えば、魑魅魍魎とか侃侃諤諤とか薔薇の憂鬱だって、すぐさまジャンジャン出てくる。ふつう書けるか。こんなの。
今、これと同じようなことが起きている。「認知症」とインプットすると、すぐさま「認知症でも大丈夫」と変換されてアウトプットされるようなものだ。そこには思考回路の中抜きが起きている。この言葉を生み出した人間系のプロセスが、消滅している。
そこにあるのは空疎なキャッチフレーズの響きだけになり、「認知症でもダイジョブなわけないだろっ」という本音からの論点の取り込み機能も失われた。
同じ文脈で言えば、認知症を「自分ごと」と考えるということもよく言われる。
しかし、果たして本当に「自分ごと」ということはどういうことか。
「認知症は誰もがなりうる。だから自分のこととして考えましょう」
ここに潜む陥穽はなにか。誰もが認知症になるのだから、自分のこととして考えようという呼びかけには、どこか恫喝が響く。そこには、「認知症になると破滅的なことになる」というのが暗黙の前提としてあるからだ。
お前も認知症になるんだぞ、と脅しをかけて、だから「認知症にやさしい社会」にしましょうというのは、前提の脅しとしての旧来型の認知症観と、目的とする「やさしい社会」の共生モデルとがねじれている。いわば恐怖システムで人々を動かそうとしている。
それは「自分ごと」のはき違えである。
識者や施策者はデータを駆使する。いわく、2025年には高齢者の五人に一人が認知症で、その社会的費用は年間14.5兆円などなど。こうした客観データの重要性を否定するものではないが、そのすり込みの中で、認知症が社会の大きな負担であるというささやきが常に再生産され、ここに脅しの根拠が生まれる。
認知症当時者の話を聴いた人ならお分かりだと思うが、彼ら彼女らはほとんどこうしたデータに拠らない。私は彼らがこのデータを使ったのを聴いたことがない。
それは当事者は、真正の「自分ごと」としてまっすぐに認知症を捉えているからだ。
「自分のこととして考える」というのはどういうことか。
それは、自分が自分自身から見てどういう人間であるかを探り続けることである。外からのデータやキャッチフレーズに依拠するのではなく、自分自身を見つめ直す作業だ。
「自分がどういう人間であるか」、それはかなりつらく厳しい道のりだろう。が、その道のりを歩んできた人々が、認知症の当事者である。
自分の身に起きたことへの膝が崩れ落ちるような感覚から、涙を振り払い自分自身を取り戻し顔上げて、自身の人生を新たに歩むしかなかった。
どうすればいいのだろう。私は、それはひたすら「問い」を立てることだと思う。答えを求めるのではなく、認知症当事者のように、ただ自前の「問い」を立てるしか、自分が見えて来ず、自分ごととも捉えられない。
世界は複雑で不協和に満ちていて、自分でも自分がわからないほどに「人間」はとらえどころがない。こうした社会では、つい、切れ味の良いわかりやすい出来合いの論考に惹かれる。その気持ちはわからないではないが、それは「問い」の放棄であり、そこに「自分」はいない。
令和の意味は、英語ではBeautiful Harmonyだそうな。
この春から社会人になった若い世代は、「認知症」というとどうしても「高齢者」を連想するかもしれない。しかし令和を生きる人にとってはより切実に「認知症」は「自分ごと」なのだ。
2010年の時の1億2800万人のこの国の人口は、今後どんどん減少し2060年には8600万人あまりに縮みこむ。この国の姿は全く別のものなるだろう。
令和の時代を生きる現在の若い人は、今後、この国の1億3000万サイズの社会の制度やインフラを8000万人台の人口で運営していくことになる。(総務省人口推計)
社会システムをすっかり入れ替えなければならない。
これまで「自分ごと」と考えなくても済んできたのは、経済繁栄での財の再配分がジャブジャブとあったからで、「景気さえ良くなれば」と、世間のおばさんまでが無限に続く経済成長の幻想の中、福祉も地域社会も「誰かがやってくれること」としてうっちゃってきてしまったのである。
「自分ごと」として引き受けるというのは、この共同体への参加表明でもある。認知症当事者が、自立と自己決定を言い、共に地域を創りましょうと繰り返すのは、新たな時代の共同体再生の提言だ。
出来ないことより、「私だからこそできること」をそれぞれが持ち寄ることで、この社会を今より少しでも住みやすくすることができると確信を持つしか、令和のBeautiful Harmonyの風は吹きはしない。
令和の時代になったからといって明るい未来が拓けるわけもない。相変わらず、生きていくことは大変なことの連続だろう。
「認知症」はいつも困難の中から歩み出す。「認知症」を、福祉や政策や社会保障の中に分断し潜り込ませるのではなく、私たちの暮らしの中の認知症を、誰もの「自分」という統合した視点に据えれば、令和の風景がどこかくっきりとした輪郭をもつ。
それが「認知症」が指し示す「希望の作り方」というものである。