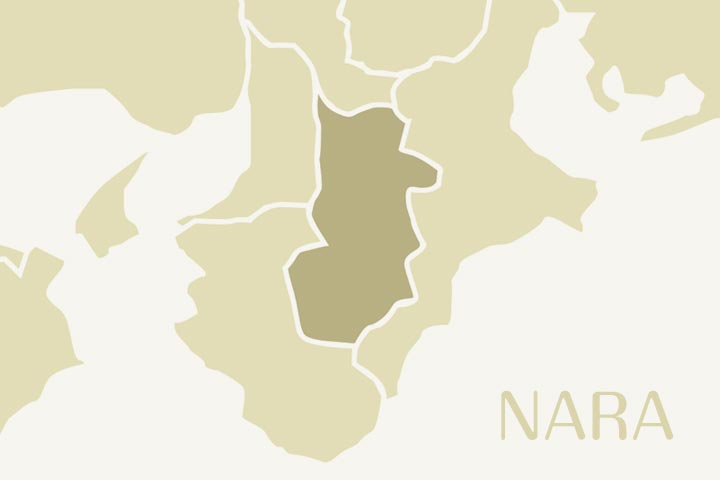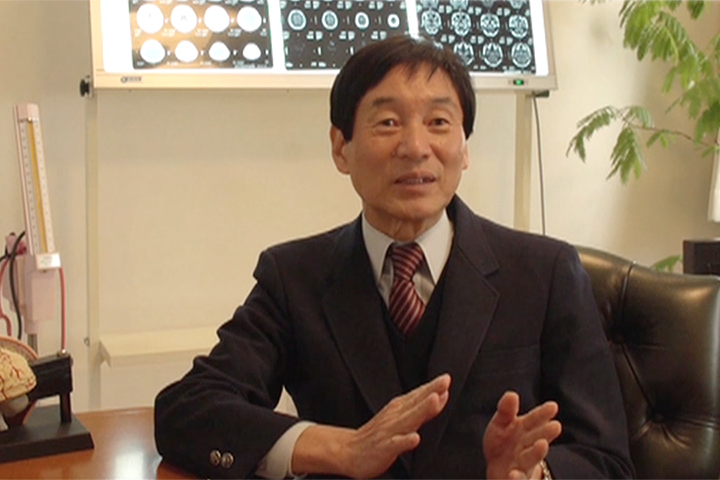認知症といえばアルツハイマーを思い浮かべるだろう。確かにアルツハイマー型認知症が割合としては一番多く、認知症の原因疾患の半分を占める。
最近、レビー小体型認知症が「第二の認知症」とも呼ばれて注目されている。このレビー小体型の特徴はその症状にある。幻視、幻聴である。
とりわけ、幻視は「ありありとした」という形容がつくほどまことにリアルなのだそうだ。「ホレ、あそこに子供がずらっと並んで歩いている。ね、ホレあそこ」とレビー小体型認知症の人はしっかりと指差すが、当然隣の介護家族には見えるわけがない。子供がホレ、あそこ、と言われても家族にとっては見えるはずなく、その戸惑いは大きい。否定すると、より症状が悪化すると言われたりするのだが、はてどうしたものか。
東北に今も伝わる「座敷わらし」の民話がある。
そのいわれには諸説あるのだが、共通して言われているのは、座敷わらしがあらわれた家は栄え、いなくなった家は衰退するという。
私はレビー小体型認知症の幻視の症状の話を聞いた時、すぐにこの座敷わらしを思い出した。民話に現れるいたずら好きの童子は、ひょっとして、レビー小体型認知症の幻視だったのではあるまいか。
旧家の奥まった座敷に絣袖の童子があらわれて、その家のお年寄りが「ホレ、あそこにワラシコが遊んでいるなス」と、ニコニコと指差して言う。
民話世界では、当然ながら認知症の症状としての幻視という捉え方はない。「幻視」を否定や当惑、疾病観の中に置くのではなく、くらしの中の素朴な想いで包み込むようにして、
「ほうほう、そうですか、きっと座敷わらしでありますなあ」
「いやいや、ババ様、ウチにも座敷わらしが来なすったですかなあ」
周りの人々は、そんなふうに、受け止めたのだろう。
ここには私たちは持っていた豊かな風土の反映がある。
なぜ、民話の中に「座敷わらし」が登場するようになったのだろう。
そこには高齢になることのおおらかな受容がある。歳を重ねていくこと、長寿を寿ぐ人々の思いが、「座敷わらし」を生み出しのではないだろうか。
高齢者との共生こそがその共同体の豊かさであり、強さであることを誰もが知っていた。だから、「座敷わらしが見える家は栄え、いなくなると衰退する」という民話の形をとることで、時代をくぐりぬける普遍の意思として地域に伝承させてきたのではないだろうか。
「うちのババ様が座敷わらしを見たそうな」
その誇らしさ、嬉しさ、ねぎらい。ババ様がね、童子がえりをして一緒に座敷わらしと遊んでいなさった、と言い合う豊かな地域社会を、たしかに私たちは持っていたのだ。
「認知症と共に生きる」その原点はここにあったのではないか。私はそう思う。
|第13回 2014.5.30|