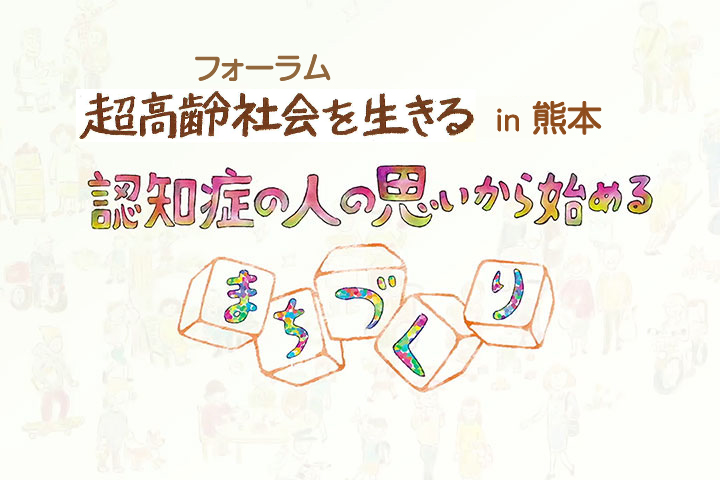▲この写真は、ある介護施設からの風景だ。なんということもない雪原が広がる風景。しかしこの景色を、このコロナとの日々の中で、心に誓うようにして、想いを込めて見つめていたひとりの介護職員がいた。それは・・・(撮影:柴田錬磨氏)
緊急事態宣言の緊急事態とはなにか。
その一つが医療の逼迫だ。医療が逼迫すれば、高齢者施設の利用者は感染してもすぐに入院できず、そのまま施設での療養を続けざるを得ない。
感染の急拡大の中、全国の介護事業所などの高齢者施設でクラスターの発生が相次いでいるのも、その背景にこうした「緊急事態」がある。
緊急事態は、いつも感染者数、死亡者数、重症者数、そして病床の使用率といった数値で伝えられる。連日跳ね上がる感染者などの数値は確かにあまりに厳しい。
しかし、数値だけでは、現実に何が起きているのかをうかがうことは難しい。
介護施設で一人の感染者が出れば、職員にも濃厚接触者が出る。濃厚接触の職員は現場を離れ二週間の待機となる。介護現場はたちまち深刻な人手不足に陥る。手薄になればさらに利用者同士の感染リスクも高まる。クラスターの発生につながる。重症化リスクの高齢者は命の危機だ。介護崩壊である。
この介護崩壊をなんとか食い止めようと、法人の枠を超えての応援体制の構築に取り組んでいるところがある。感染者が出て介護体制が危うくなったところに他の施設からの応援職員を派遣する。応援者を出した施設はその手薄になった分を、また他の施設からの応援職員で補填する。前者を直接応援、後者を間接応援とし、こうした組み合わせでなんとか介護崩壊を食い止めようとするものだ。
この取り組みはある医療福祉法人が呼びかけ、施設関係者だけでなく、医療者、行政、家族、認知症の当事者などを交えて去年6月から議論を重ね、県や市など各方面に働きかけて来た。
去年の暮れ、感染者を出した施設にこの清山会グループから職員が応援派遣され、その介護職員たちの報告が、この議論のためのメーリングリストに掲載された。
そこにあるのは「現場」で介護崩壊を防ぐための緊迫の報告である。
一週間から10日間の応援に入った職員は、当初一様にすさまじい緊張感の中に身を置く。真っ先に浮かんだのは「怖い」という感情だったと吐露する職員もいた。
応援先の施設では、そこの介護職員がほぼ全員濃厚接触者に該当し自宅待機のため、介護経験のない事務職員までもが動員され、不休で連日対応していた。
現場は混乱し疲弊し、感染リスクへの対策も機能していない。みんな殺気立っていた、報告にはそんな記述もある。
こうした感染施設ではゾーニングが重要だ。
感染者のいる区域はレッドゾーン、清潔区域をグリーンゾーン、脱衣場所などはイエローゾーン。しかし施設内は生活の場でもあり、現場ではどうしても明確に分けることは難しい。
応援職員は、PPE(Personal Protective Equipment)防護具と呼ばれる不織布ガウンに、N95の医療用マスク、二重手袋、ゴーグル、フェイスシールドというフル装備である。
緊張感に加え、このPPEが時間が経つにつれ体力を消耗させる。医療マスクで酸欠状態になり肌が荒れ、ワイヤー部分があたって鼻は真っ赤になり息苦しさに襲われる。呼吸を浅くすることでしのげる、窓の近くでマスクをずらすだけでも生き返る、そんな工夫も応援の職員間で共有された。防護具に包まれた身体の発汗は想像を超え、Tシャツ一枚でも汗だくになる。
介護職員には暑くても、室内は頻繁な換気のためかなり冷えている。暖を取るため、エアコンでしのごうというときにそのエアコンが不調になる。業者を手配するが断られたという。エアコンは、職員たちの再起動などの作業によってなんとか回復した。
施設の高齢者には発熱者が続いた。
応援の介護職員によれば、その熱は誤嚥による発熱なのか、果たして感染による発熱なのか判断が難しい中、常時ではないが医療者、看護師が共に施設に入り、伴走するようにして助言、指導があったことが、職員たちを絶えず励ました。
職員たちが感じたのは感染リスクの中での日々状況が変わる困難だけではない。
報告に記されたのは、応援での介護そのものの難しさだ。
例えば食事介助は、一人ひとりの状態に応じて口を開くタイミングやひとくちの量、嚥下しやすい角度、全てが違う。介護とは、そうしたきめ細かい手順の集積と共有とで成り立つ。それを応援というかたちで初めて利用者に向き合う難しさ。一人ひとりの利用者を、防護具と医療マスクとフェイスシールド越しに見つめながら、その人のケアを探り当てていく毎日だったのだ。
応援から5日目あたりから、現場の混乱は目に見えて落ち着きを取り戻していく。
職員間のコミュニケーションが取れ始め、互いに談笑したり、何より利用者のお年寄りがよく来てくれたと涙ながらに言葉をかけてくれ、それは職員の疲れを「ぶっ飛ばした」とある。
ある職員は、こんなふうに記す。
「お年寄りには逃げ場がない。我々はフル装備して感染対策する中、レッドゾーンの利用者は施設内でいつも通りの暮らしを送る。レッドゾーンが日常であり、生活の場だ。
我々の非日常と、利用者の日常。相反するものが同じ空間で成り立っていることになんとも形容し難い感情が湧いた。だからこそ、我々がしっかりと日常を支えるんだと強く思った」
彼らの報告は、自身の奮闘ぶりを「がんばった」こととして伝えているのではない。
彼らは事前に応援時の綿密な研修を重ねて現地にやってきている。しかしそれだけではない貴重な経験をし、多くの課題に直面し、そのことを今後の応援体制に生かしていくための提言をいくつも記している。本来の介護専門職、関係者には、その報告事項の方が重要だろう。
しかし、現場を持たない私は、社会の側に伝えたいことがある。
それは彼らがこの事態の中でも誰もが底流させている一つの「想い」である。
ある職員は、まず応援先の施設の玄関に飾られている写真をじっくりと見ることから始めた。そこには習字にいそしむ利用者、施設の夏の流しそうめんの行事、ボランティア活動の施設職員の姿などがあった。
彼は「この法人の大切にしていることがわかる。話し合いがよく交わされ、ご本人主体のあたたかい取り組みを感じた」と記す。
玄関でその確認をして、それから彼はPPEに身を包み、医療マスクで防護して「現場」へと踏み入った。
またある職員は、報告に自分で撮った一枚の写真を添付している(コラム冒頭写真)。
施設の窓から見える雪原だ。なんと言うこともない冬の光景。
彼はこの写真にこう記す。
「外にも出かけられない中、ひとりぽつんと寂しそうに景色を眺めている利用者さんを、私はこれから先もずっと記憶していることでしょう」
改めて写真を見れば、この景色は春が来て夏になれば広々とした快活な草原となる。そこで多くのお年寄りが、陽光のもとで寛ぎ、にぎやかに職員との交流を楽しんだのだ。
守るべきものは何か。彼が心に誓った取り戻したい光景は、彼にはこの雪景色にすでに見えているのである。
緊急事態の中にあって見るものは何か。
彼らは緊急事態の、まさにそのさなかにあって真っ直ぐに「人間」を見続けてきた。医療マスクや防護具の尋常ではない負荷にあっても、彼らはそこの利用者という「人間」を見つづけ、その人との関わりに自分を取り戻すようにして応援の日々をやり遂げた。
事態とは巻き込まれるものではなく、彼らは自分たちで新しく「人間」のための事態を作り上げたのだ。介護とはそういうものだとして。介護の力。人間の力。
応援を終えた彼らは自宅には戻れない。そのまま借り上げたホテルで二週間の健康観察という待機に入る。
そのひとりのメッセージ。
「今後も応援を必要とすることがあるならば、介護という命の現場を守るために真っ先に手をあげさせていただきます。
まずはホテル待機期間中に体重を増やします! ありがとうございました」
激務で、すっかり体重が落ちてしまったらしい。いたましくも、だが誇っていい彼の勲章だ。
この報告は、今この事態の中で起きていることのリアルであると同時に、誰もが老いていくこの国の超高齢社会に何が必要なのかを問うている現場からの声である。
私は彼らの「想い」をたどりながら、この稿を書いた。
|第164回 2021.1.14|