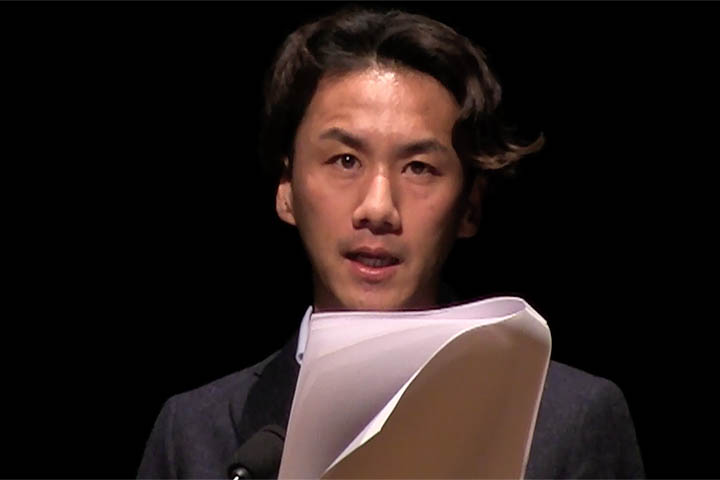▲これは3年前の横浜、山下公園のバラ園。誰一人いない中でバラが咲いている。失われた物語だ。私たちは「平時に戻る」のではなく新たな時代に歩み出す。バラはいつだって新たに咲く。
コロナの日々をくぐり抜けた開放感もあって、この大型連休はどこも大賑わいだったようだ。マスク外して笑顔あふれる各地の行楽地の様子がニュースに映し出された。でも、どこかその底にかすかな不安が流れているようにも思えてならない。
それはなぜなのだろう。
それは、この3年間で私たちは、暮らしの中に物語を失ったのだ。
私たちは、物語を取り戻すことができるのだろうか。そんな思いからの、小さな町の小さな物語・・・
古くからの商店街の中程にその郵便局がある。かつての特定郵便局の面影を色濃く残す局舎の昼下がり。
そこにベビーカーを押した若い夫婦が入って来た。むずかり始めた赤ちゃんを妻はベビーカーから抱き上げると夫に手渡した。よしよし、とおざなりに夫は赤ちゃんを揺すりあげながら、夫婦は通帳を開いて額を寄せ合う。ひそひそ声の相談と小さな口論の末、小さく深くため息をつくと意を決したように妻はカウンターに向かう。
ローンの支払いだったのだろうか、それを済ませると妻は夫の前に行き、これから近くのスーパーで夫の昼の総菜弁当と夕食の材料を買いにいく旨を伝える。
今日は夫が夜勤明けで、入れ替わりに妻がパートに働きに出るのだった。
「ここで待ってて。すぐ戻るから。赤ちゃんをお願い」
「ああ」 と夫は答え、無精髭に疲労をにじませながら赤ちゃんを抱いて待合室のベンチに座った。
夫婦の互いの乾いた表情は重くのしかかる暮らしのせいだ。
カウンターで長々と年金の相談をしていた老人が去ると、小さな鯉のぼりが飾られた待合室は急に静かになった。かすかなエアコンの作動音。
徹夜明けの夫はベンチに座るや睡魔に襲われる。眠りを吸い取られたのか、今度はだっこの赤ちゃんがパチリと目を開け、不思議そうに辺りを見回す。
ゆっくりと身体をずらし父親の膝からベンチ、そして床にと足をおろしていく。おしめのお尻を振りながらゆらゆらと、しかし確実にベンチに手をつき、伝え歩きを始めた。
「あらあら」
離れてベンチに座っていた老夫婦の妻が気づく。
ちいさな顔をしかめるようにして懸命に覚束ない足取りを運んでいた赤ちゃんは老婦人の丸々とした膝に到達すると、びっくりしたように老婦人を見上げた。
「あらあら」
ためらいなく老婦人は赤ちゃんを柔らかく抱き上げ、赤ちゃんはマジマジと婦人の顔を見つめる。
「あらあら、ネ、あなた、おっぱいの匂い」
隣のいかめしい表情の夫はそのままの顔つきで「ウム」と答えるが、所在なくベンチに座っていた老夫婦は、今や思いがけない不思議な生物の訪問にすっかり心奪われている。この老夫婦も、かつて新しい生命を真ん中にして二人の人生をスタートさせ、ここまでなんとか歩んで来たのだ。
そのむこうに座っていたのは文庫本を読んでいた若い女性だ。先ほどから老夫婦と赤ちゃんの光景をチラチラと見ながら心の中で念じていた。
あの赤ちゃん、こっちに来ないで。私、子供嫌いだもの。赤ちゃん、来たらどうしよう。どうすればいいの。シッシッ。
赤ちゃんは犬ではないから、そんな事で進路は変更しない。眉をしかめ口を尖らせて赤ちゃんの大冒険は今度は着実にその女性に向かっていた。
ワー、きたきた、どうしよう。
女性の膝に手をかけたところで赤ちゃんは小さくよろめいた。
「あっ」
思わず手を出すそこに赤ちゃんの手。
赤ちゃんの手。
なんて、なんて、
柔らかいのか小さいのか、可愛いのか、しっとりなのか、とにかく女性の手に赤ちゃんの手はすっぽりと包まれて、赤ちゃんは女性を見上げてにっこりと笑った。
凍てつく大地に射し込む春の陽射し。新緑の木漏れ日にラベンダーの香り。レースのカーテンを揺らす初夏の潮風。
赤ちゃんの手を自分の手に包み込みながら、女性はまずぎこちなく笑顔を浮かべ、やがてそれは自然の笑みとなって、こわばっていた顔と心と身体全体の筋肉をほどき、そして今度は女性の胸いっぱいに、懐かしくあたたかなものがゆっくりと満ちていった。
手を取りあい、赤ちゃんと見つめ合う形になった女性は両の手を赤ちゃんの脇に差し入れ、ヨイショッと抱き上げた。嬉しいようなわくわくするような不思議な感覚。
こんな思い切った事、私にも出来るんだ。いつも自分に自信が持てなくて、うつむいて他人の視線ばかり気にしていた私。
赤ちゃん、可愛い。
気づくと、みんながこちらを見ていた。
ベンチの老夫婦、カウンターのむこうの二人の局員。みんな微笑んでいる。
いつもならそんな他人の視線に凍り付くようになってしまうのに、その時は何故か自然に軽い会釈を、微笑みとともに返す事が出来た。
そっと赤ちゃんを抱き寄せる。赤ちゃんだあ・・・
そのとき、小走りに赤ちゃんの母親が戻って来た。手にスーパーの袋を提げた妻はベンチですっかり眠りこけている夫を見て、キャッと声をあげそうになった。赤ちゃんがいない。
「あなたっ」
はね起きる夫。
「あなたっ、赤ちゃんっ」
尖った声が待合室に響く。
「大丈夫ですよ、ほら」
老婦人が女性の膝から赤ちゃんを抱き上げると、母親に近づいた。
「大丈夫ですよ。赤ちゃん、もう伝え歩き出来るのね。今、この町にデビューしたところ、はい」
老婦人から渡された赤ちゃんを抱きとめながら、母親はようやく訳が分かって来た。
「固太りね、しっかり育ってますよ」 老婦人は微笑んだ。
そう、抱いた赤ちゃんはズシリと重い。しっかりと育ってくれているんだ。母親は気づく。これまでこの重さは育児と生活の辛さにしか結びつかなかったのに。
しっかり育ってくれているんだ。
「大丈夫ですよ」 にこにこと老婦人は何度も繰り返した。
不意にそれまでこわばっていた母親の気持ちのどこかが溶け出していった。
「大丈夫ですよ、大丈夫」
母親は老婦人と向き合いながら、赤ちゃんを身体全部で包み込むようにしてしっかりと抱きしめると、その時、ポロポロッと涙がこぼれ落ちた。
「大丈夫」 穏やかに老婦人は赤ちゃんを抱く母親の腕に触れ、若い夫は妻の背中に手を回した。
涙のあとの吹っ切れたような晴れ晴れとした表情で赤ちゃんを抱いた若い夫婦が、何度も振り返り頭を下げて帰っていくと、待合室には妖精が粉を振りかけたようにやさしい沈黙が舞い降りた。
「大変だな、あの二人」
ぽつりと言う夫に老婦人は「大丈夫ですよ」と自分に言い聞かすように何度もうなずいた。
何が大丈夫なのだろうか、あの年若い夫婦の事なのか、それともこれからの二人きりの老後の事なのか、多分その両方なのだろうと無口な老いた夫は考えた。
老婦人の声はベンチの若い女性にも届いた。
女性は背筋をピンと伸ばした。「大丈夫」、 これからはちゃんと顔を上げて生きていこう。
カウンターのむこうの年配の女性局員はもの思いにふける待合室の空気に、声をかけていいものかためらっていた。
「28番の方、どうぞ」 そっと声を出した。
「はいっ」
自分でもビックリするような勢いで返事をして、女性は背筋を伸ばしカウンターに向かって一歩を踏み出した。