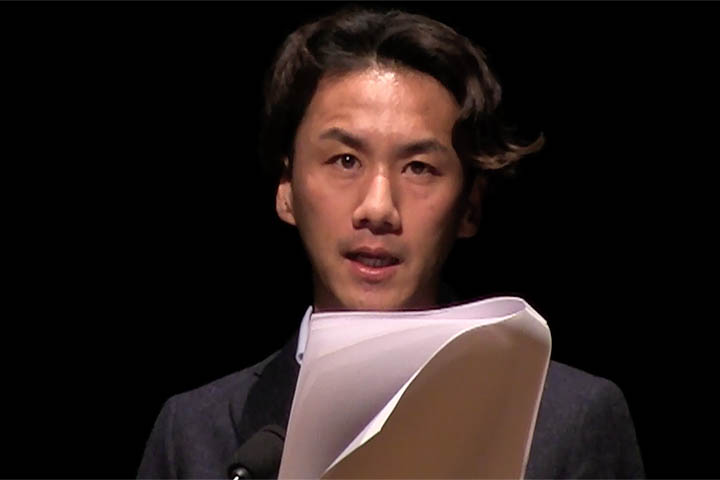▲箱根芦ノ湖と冬富士。大きな自然は私たちを癒すと共に、時に苛烈な牙を向く。それはまた私たちの日常の危うさとあたりまえのかけがえのなさを思い知ることでもある。
新しい年になったからといって我家の内を見渡しても、別段新しくなったものはこれと言ってない。この夫婦自体、年々古びていくだけだし、それにつきあうように家の建て付けも軋んだりしている。
ただ一点、毎年新しくなるものといえば、リビングの片隅のカレンダーだな。
最近はもっぱらスマホやパソコンと連動するアプリのカレンダーばかりを使っているから、以前ほどカレンダーの出番は少なくなっている。
「えっと、今日は何日?」とか「今日は何曜日だったかしら」といったやりとりがめっきり多くなった夫婦でも、スマホの一瞥で事足りる。便利になったものだ。
それでもやはりカレンダーというものが家の中の目立つところに貼られていることが必要なのである。あれはなぜなのだろう。
私は、カレンダーは日付だけの予定を書き入れることができるシンプルなものを愛用している。
新年のまっさらなカレンダーに、夫婦それぞれの予定を書き込む。スマホのアプリのカレンダーを見ながら記すのだから二重手間なのだが、やはりこれがないと年の初めにならない。
かつて、友人に手帳の予定が埋まらないと不安になるとこぼした人がいたが、それはちょっと働き方に問題ありの人生かも知れないぞ。
考え込んでしまうのは、自治体など組織からの仕事の依頼は年度ごとの計画ということもあって、秋頃には翌年の9月や11月の依頼が入ってくる。一年先である。
この歳になるとそうした依頼を受けるときに、「生きていればお受けしますよ」と言ったりして、まあ当然、冗談めかしての前置きだから、「いやいや、まったぁ、そんなことぉー」といった陽気な反応をどこかで期待しているわけだが、中には「そうですねえ・・」とまともに考え込むような反応もあってこちらもドキリとする。余計なことを言って律儀な自治体職員を悩ませてしまってすまないことだ。
カレンダーというのは、人生という暮らしの未来図である。
そこに書き込むべき予定を立てるというのは、現在の私の意思を未来に反映させることだ。未来はただ茫漠とした空白ではない。私たちは予定を立てることでそれぞれの未来を生み出していると言える。
無人島にひとり流れ着いたロビンソン・クルーソーは、毎日柱にナイフでしるしをつけることで日数を確認し、その作業で自己の生命と存在を支え、無人島に未来を刻んだのである。
だから、多くの家庭ではリビングか冷蔵庫の扉あたりにカレンダーを掲示する。
あれは予定表の体裁の向こうに、それぞれの未来の可視化と確認のためなのである。そうしてそれぞれのこの一年をどのように生きていくかの決意表明をするわけだ。
ただし、カレンダーの予定というのは、予測不能な事態というのを規定しないことで成り立っている。予測不能なことはカレンダーには書き込めない。
書き込むことはできないが、しかし、カレンダーを見つめることで、私たちの日常には予測不能な事態というものが埋め込まれていることを私たちは心のどこかに意識させる。
どういうことか。
毎年暮れになると、ささやかな家庭内行事のようにしてカレンダーを新しいものに取り替える。そのときに古いカレンダーをめくり返しては、記された予定から、あそこに行った、こんなこともあったと子供達が小さければ賑やかな成長記録のようにして語り合うひとときがある。
と同時に、そこには予定されなかったこと、子供が病気になったことや、身内の不幸なども浮き上がるのである。
カレンダーの未来は、過去の予定の検証から生まれている。その余白には必ず予測不能な事態があって、そのことで私たちがあたりまえとしている日常には、実は予測不能の事態、つまり、日常とは「どうなるかわからない」ことを考える修練を積んでいく。
「どうなるかわからない」ことを考えるというのは、未来への怯えではなく未来への備えだ。予定を立てるというのは、予測不能の事態を考えるということを含んでいる。
2024年1月1日、午後4時10分ごろ、能登半島地震が発生した。
輪島や能登地方の甚大な地震災害は、今なお続いている。
正月を襲った大震災の傷はあまりに深く、時間が経つほどに被災した人々の暮らしと心と身体を侵食していく。被災地での暮らしの困難はいかばかりだろうか。
ただここで一旦深呼吸するように冷静に見渡せば、この震災に向ける全国の人々の反応に、どう説明すればいいのかわからないのだが、ひたすらの思い寄せるまなざしを感じる。
それは例えば、輪島朝市に象徴される豊かな暮らしの風土を育んできたその土地柄のせいかもしれず、あるいは、正月睦月と呼ばれ人々が睦まじく集い合う、その月始めを襲った痛ましい災害のせいでもあるかもしれない。
能登地方の厳しい冷え込みの中で過ごす家族や子供、お年寄りの映像に、誰もが我が身を切るような痛みを感じ、そしてそこに心寄せる全国の人々の思いを感じるのは私だけだろうか。
何か、災害に向ける人々のまなざしの奥深いところに変化が生まれている気がしてならない。
誰ものカレンダーに、予測不能だった阪神大震災や東日本大震災の記憶が刻まれている。そして3年半のコロナの事態での、虚しい空白も見えないペンで記されている。
「惨状」の向こうの被災した人々への想いが、自分の無力感といたたまれなさとがないまぜになって、心中に熱く溢れようとしている。
「誰かいませんかあ」、倒壊した家屋の奥に向かって救助隊員が声を枯らし、映像を見る人々は手を握り締め、隊員の呼びかけに必死に息遣いを合わせ、「直ちに逃げること!」と、大津波警報に避難を呼びかける女性アナウンサーの切迫した声に、「逃げて!逃げて!」と心中を波打たせ、寒中の避難所のテントで、熱い汁椀を口にして互いに顔合わせて微笑む親子の姿に、どうしようもなく瞳が潤んでいく。
世の人々には、揺るぎないものが潜んでいる。これだけは人として譲れないという心情がある。人を想う。心寄せる。人を想うことで、自分を思う。そのことから立ち上げる社会システムというものがあるはずだ。それを共生社会と私たちは語り合っている。
大災害にはいつもただちに防災施策の充実が叫ばれる。しかし、その基盤には、私たちの「共に生きる」ことへの想いが流れていなければならない。
災害時の医療や防災の充実は当然だが、それは、他者への身を切るような想いの集合から練り上げなければ、施策に体温が通わない。有事の時こそ、私たちの共生の社会が試される。
想いを寄せる、と言ったことはいつも、そんな甘いことばかり言っても何の役にも立ちはしないと言った現実論に駆逐される。そうだろうか。私はむしろ、素朴な人の想いを信じられない社会の方が、よほど痛々しい社会のように思えてならない。
カレンダーの最初の日付に、「令和6年能登半島地震」を記して、この一年を歩み出す。
|第269回 2024.1.12|