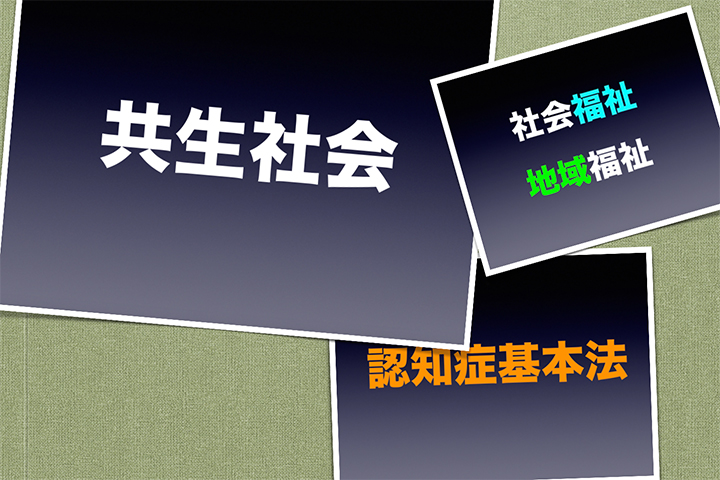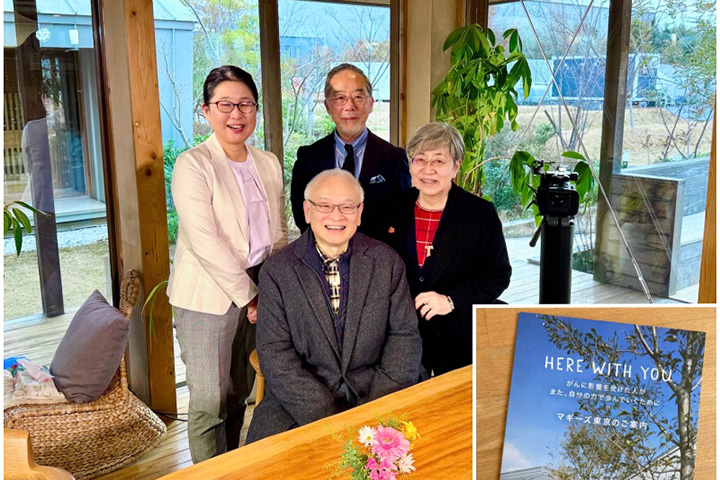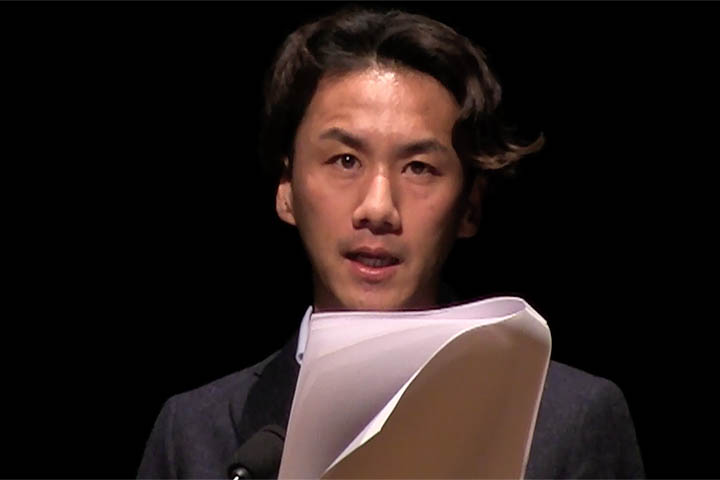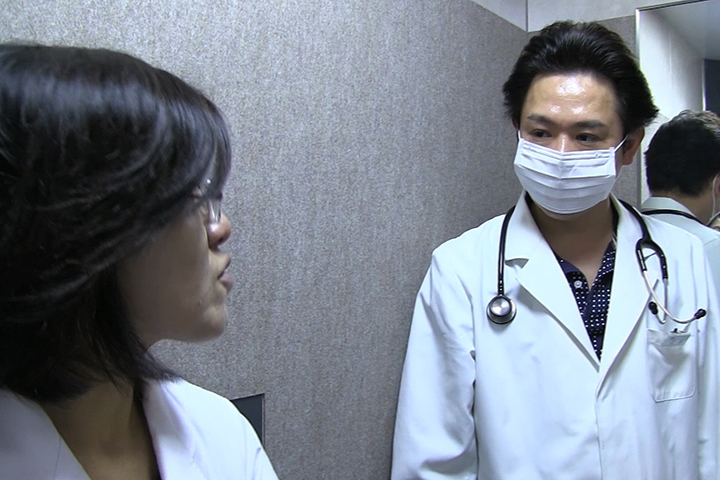▲生きることには喜びもあれば悲哀もある。哀しみに、横に一筋を加えれば「衰え」になる。老いること、失うこと、「生きる」ことの弱さと強さ。先日のBSの放送を見ての想いなどこもごも。(写真はNHK BSのHPより)
春分の日の朝に、BSで放送された「妻亡きあとに ~近藤正臣 郡上八幡ひとり暮らし~」という番組を見た。俳優の近藤正臣が、互いに「ヒロさん」「臣(おみ)さん」と呼び交わしてきた小学校以来の幼馴染の伴侶、裕子(ひろこ)さんを亡くしてからのほぼ一年を描いたドキュメンタリーである。
ドキュメンタリーとは言っても記録性より、人の想いを深いところから汲み上げていくような番組だった。
近藤正臣といえば、私にとっては大河ドラマ「龍馬伝」で、時代の狂気を見据える土佐藩主、山内容堂を演ずる彼の、舌なめずりするような鬼気迫る演技に強い印象をもっていた。
だが、趣味の渓流釣りを極めたいと伴侶の「ヒロさん」と岐阜県の郡上八幡に8年前に移住した彼は、あくまでも物静かで内省的な佇まいだ。
おととし、伴侶の裕子さんは認知症で入居していた施設で亡くなった。「ヒロさん」がいない暮らしが映し出されていく。「不在」とは、いないことなのか。
番組でしばしば登場するのは、小さな写真立てに収まる伴侶、ヒロさんのモノクロのスナップだ。和服姿に伏し目がちのヒロさんはほのかな笑みを浮かべ、その控えめな表情だからこそ、彼女の愛情の深さがリビングのたたずまいのそこここに溢れている。
広いリビングにフローリング、革張りの大きなソファ。そこに近藤正臣、臣(おみ)さんはひとりで暮らす。
その写真立てにはいつも、臣さんが手ずから摘み取った山荘近くの野の草花が手向けられている。モノクロのヒロさんの写真は、想いこもったなんと美しい表情なのだろう。現在83歳の近藤正臣と青春をともにし、56年を連れ添い、そして亡くなってなお、彼の老いと孤独に寄り添っている。目を伏せた穏やかな顔に笑み浮かべて、「私はここにいます」と言うように。
番組では彼の「老い」や「孤独」の寂しさや悲しみをナレーションで説明することはない。どこか沈潜する映像の中に辿るのは、妻を亡くした近藤正臣、臣さん(おみ)さんの一人暮らしの日常である。
ひとり食事を用意し、ひとり食べ、ひとり片付け、そして愛猫の「やっこ」と対話しながら、その日の出来事と想いを小さなノートに書き記す彼の日々を淡々と描く。
伴侶の裕子さん、ヒロさんは郡上八幡に移住してから認知症になった。
認知症になったヒロさんと近藤正臣、オミさんはどのように過ごしていたのか。役場の介護福祉士がその二人の関係性を語っている。
その介護福祉士は介護保険の申請に訪問した折、裕子さんの認知症はすでにかなり進行していると見ていた。ただ臣さん、近藤正臣はそのことはあまり意に介していないようだった。それよりも、ヒロさんになんでも絶えず語りかけていることに、訪ねた介護福祉士は驚いた。
臣さんは、「今晩なに食べる?」と言うことにもいちいち裕子さんに聞いていく。介護福祉士の彼女には裕子さんになんの反応がないように見えても、臣さんは、ヒロさんの夕飯について語りかけていく。
なにを食べたいのか。どういう料理がいいのか、美味しさだとか自分の思いも含めて、裕子さんからはなんの答えも返ってこなくても、臣さんは丁寧に時間をかけ説明し、間をおいてひとつひとつ話しかけていたと言う。
「在宅での認知症の人との、ああした光景は見たことがなかった」、介護福祉士の彼女はそう語る。
ヒロさんの認知症は進行し、やがて物忘れや夜に家を出てしまう事態も起きた。街中とは違う真っ暗な里山である。近藤正臣は、それを受け入れた。「いいんです、それでも、」
最期まで在宅で共に暮らすと決意していた近藤正臣だが、無理がたたって腰を痛め、ついに施設入居に踏み切る。
ヒロさんの施設を近藤正臣は連日のように訪ねてはベッドサイドで二人でジャニス・ジョプリンを聴いて過ごした。その様子に介護福祉士の彼女は、もはやなんの反応も示さないヒロさんであっても、二人は明らかにジャニス・ジョプリンを聴いている互いをわかり合っている、とつぶやく。
ヒロさん、裕子さんが亡くなったのは、一昨年のことだ。
ヒロさんを亡くした臣さんの悲哀はいかほどのものか。
しかし、この番組では彼のその悲哀や喪失をあえて語らない。心情の解釈や解説は一切排除され、ノーナレーションでの情報は、字幕で最小限の客観的な時間経過を伝えるだけだ。
想いは語らない。想いは描く。
随所にインサートされるのは、郡上八幡の自然のたたずまいだ。四季折々の郡上八幡の風景が、彼の想いに応えるかのように描かれていく。吉田川の清流、点景に鮎釣りの竿を振る人がいて、山々に湧き立つ雲が流れ、木立越しの郡上八幡城と、その物言わぬ天守が語りかける。紅葉の山々とハラハラと風に舞う楓の葉。
懐かしい風土。風と土に、彼、臣さんの想いを描いていく。
実際この番組の全体の起伏は極めて穏やかで、番組案内ではそのテーマは、老いと喪失からの回復の物語といったニュアンスも解説されているが、視聴する限りではそのメッセージは解体されて、風景、風土の中に溶け込まされているようだ。
日常の暮らしの近藤正臣の言葉もほとんどが断片的で、彼の心情の道筋を辿る仕掛けも外されている。つまり、この番組の最大の特色は、彼の想いをどう見るかは、見る側に全て託されているのである。
だからこの番組を、思い描いていた老後の穏やかな暮らしが、認知症に侵食された悲しみの物語と見ても、あるいは、認知症であっても互いに思いを交わし合う愛情物語としても、さらには絶望からの回復の物語として見る人がいてもいいのだろう。
どのように視聴してもらってもいいとする語り口が、番組の奥行きとなって見る側に絶えず問いかけ、心に沁みてくる。
見る側の年代や死生観、大切な人を失った体験など、その境遇によってそれぞれがどう受け止めるのか、あるいは全く別の感慨をもたらすのかもしれない。
ただ、このコラムの執筆者としての私は、ここでの認知症の描き方が印象に残った。
この番組の通奏低音は、ヒロさんの認知症である。ただし、その認知症の語り口や描き方はこれまでの「認知症」とは明らかに違っている。
ここでの認知症は、課題や試練といった認知症観を超えている。むしろ番組では、認知症を語ることで二人の互いのかけがえのない想いをよりくっきりとさせているようである。
臣さんは、認知症を見るより何より、ヒロさんを見つめ続けた。認知症にヒロさんを奪われることを拒否したのである。それは人生の伴侶、ヒロさんのひたすらの「人間」を見つめ続けたのではないか。
介護福祉士の女性は、近藤正臣の、妻、裕子さんとの接し方に「このような認知症の人との関わりの仕方は見たことがない」と呟いたそうだが、私は、近藤正臣は認知症を弱みとして見るより、その弱さに老いの中で目を逸らすことなく向き合い、その弱さを受け入れる強さにしていったのではなかろうか。
限りない弱さを実感することで、むしろ自身の生きる強さを見出した。認知症に生きるヒロさんと共にあることで、それが生まれた。弱さが、つよい。
春分の日の朝のうららかな陽射しのリビングで、私はこの番組をたまたま妻と一緒に見たのだが、普段はいらぬ感想を挟んだり、ツッコミを入れる妻が、ほとんど何も喋らずに見入っていた。番組が終わるとふっと息つくようにして、それからキッチンで洗い物にとりかかった。どこか物思いに沈みながら。
わが夫婦もすでに老境、共に70代半ばだ。いつかはどちらかがどちらかの伴侶を失うであろう。
これまでの歳月よりこれからの日々を共に歩き、やがて必ずひとりで歩むことになる。
郡上八幡の吉田川の流れに互いの想いを、互いが確認するような時間だった。