総人口に対して65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率といい、世界保健機構(WHO)や国連の定義によると、高齢化率が7%を超えた社会を「高齢化社会」、14%を超えた社会を「高齢社会」、21%を超えた社会を「超高齢社会」という。
平均寿命が長くなり、少子化が進むにつれ、社会の中で高齢者の占める割合が増え、将来に向けて大きな課題となっている。
【参考】内閣府ホームページ
こうれいかしゃかい
総人口に対して65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率といい、世界保健機構(WHO)や国連の定義によると、高齢化率が7%を超えた社会を「高齢化社会」、14%を超えた社会を「高齢社会」、21%を超えた社会を「超高齢社会」という。
平均寿命が長くなり、少子化が進むにつれ、社会の中で高齢者の占める割合が増え、将来に向けて大きな課題となっている。
【参考】内閣府ホームページ
[ 高齢化社会 ] 関連記事一覧

認知症が進行したゆみ子さんの日常を通して「介護のあるべき姿」を考えるシリーズの3回目。

認知症が進行したゆみ子さんの日常を通して、「介護のあるべき姿」を考えるシリーズの2回目です。

長寿の未来フォーラム 記憶の見方が変わる 〜高齢者心理と認知症治療からひも解く〜

群馬発 長寿の未来フォーラム 人生100年時代への処方箋 〜最高齢化率の村に学ぶ“健やかな暮らしと生きがい”〜
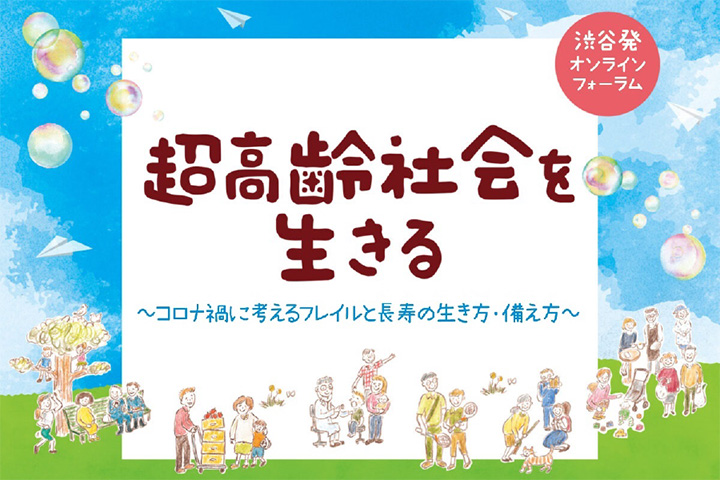
2021年3月14日、東京渋谷でフォーラムが開催され、インターネットでライブ配信されました。

石川県発オンラインフォーラム 超高齢社会を生きる ~コロナ禍で考える 認知症とともにあるまち~
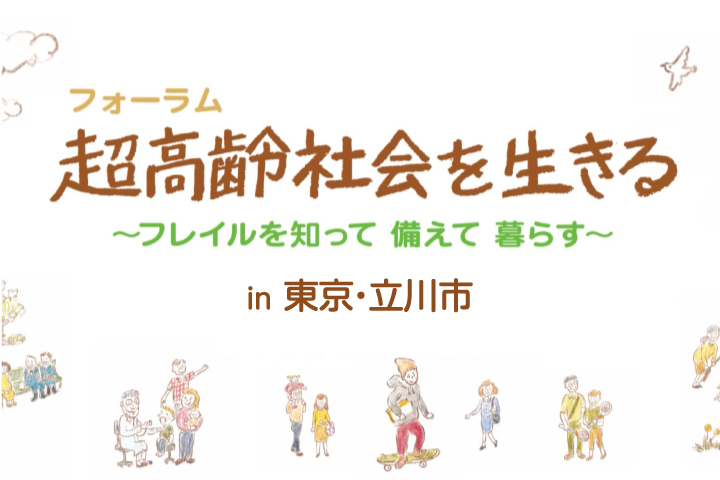
フォーラム「超高齢社会を生きる ~フレイルを知って 備えて 暮らす~」(東京・立川市)

日本人男性との結婚を機にアメリカから来日し、認知症とともに生きるスーザンさんの日常を描いた第3弾。
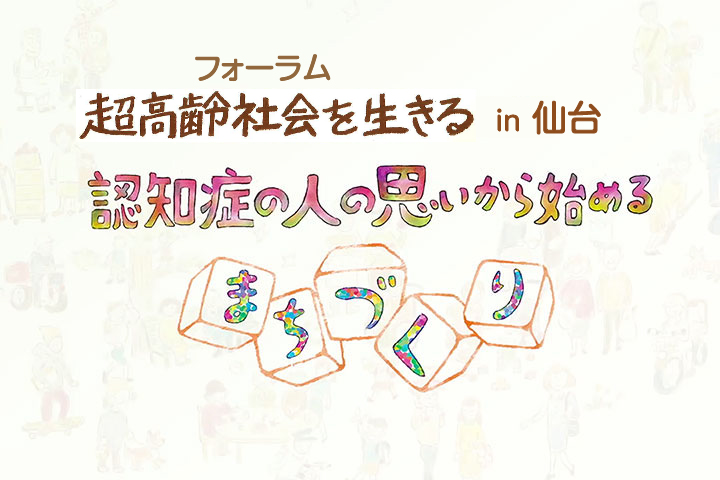
フォーラム超高齢社会を生きる in 仙台〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜

青森県八戸市内の県道沿いに、「無添加お弁当『二重まる』一番町」がオープンしました。二重まるが提供しているのは、共生型デイサービス(通所介護)。

「コトバで語らなければ、カタチにならないのよ。もっと語り合ってコトバを探すの」中島紀恵子さんは頬を紅潮させ、そう語った。

熊本県球磨郡あさぎり町では、2009年から行政主導で薬草栽培による町おこしを進めています。

熊本市北区にある八景水谷地区では、マンションの一室で「八景水谷4丁目認知症カフェ」が開催されています。
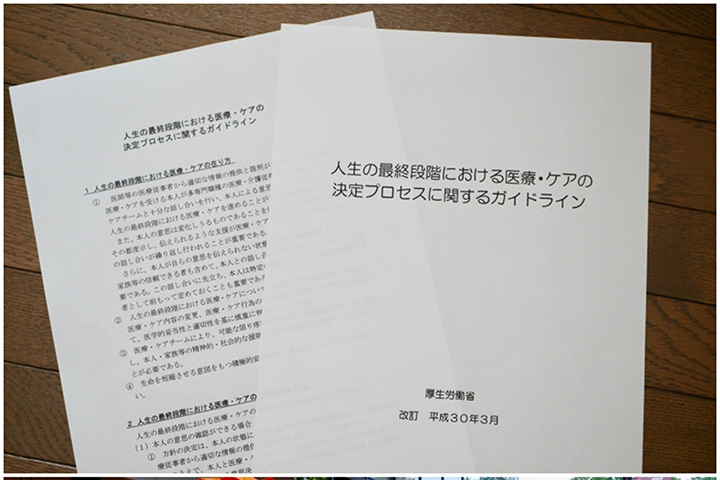
「認知症と共に生きる」、その最大の実践者は言うまでもなく「家族」だろう。これはいろいろなところで言っているのだが、この国の現在の認知症の環境は、認知症の人と共に暮らしてきた家族抜きにしては語れない。
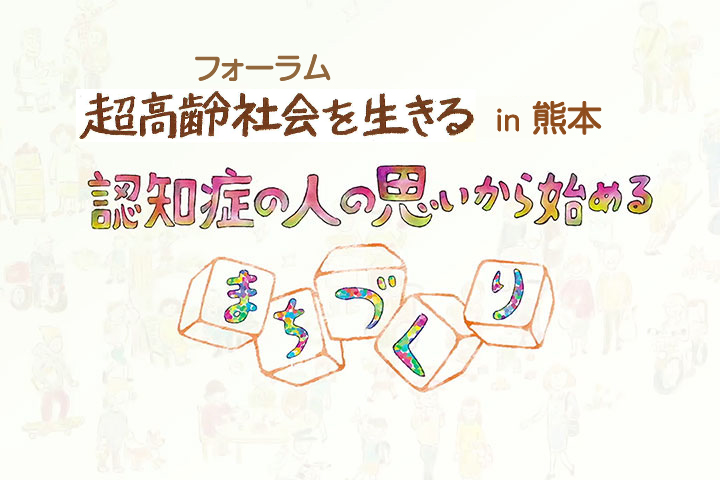
2019年3月3日、ホテル熊本テルサで「フォーラム超高齢社会を生きる in 熊本〜認知症の人の思いから始めるまちづくり〜」が開催されました。

2018年10月28日、認知症の人と家族への援助をすすめることを目的とした「第34回全国研究集会」が福井市で開催されました。
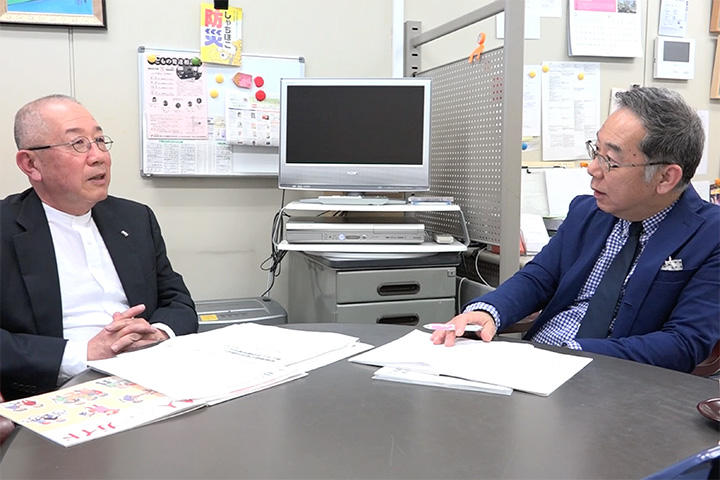
2017年6月に公益社団法人「認知症の人と家族の会」(本部・京都市)の新代表に就任した鈴木森夫さんに、福祉ジャーナリストの町永俊雄さんがお話を伺いました。

Mrs. Toshiko Yamasaki (85 years old) immigrated to the US when her husband Katsuo (87 years old) was transferred there.

山﨑利子さん(85)は夫の勝男さん(87)の赴任をきっかけにアメリカに移住。長年アメリカで暮らし、二人の孫たちの世話も引き受けてきました。
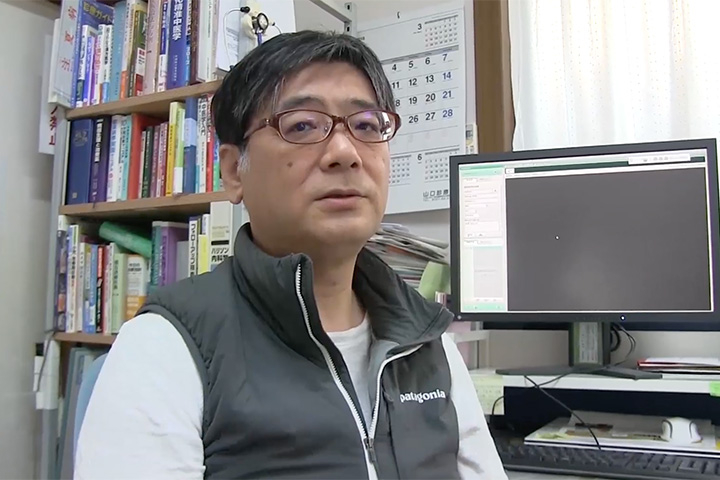
河内長野市の自宅で一人暮らしをしている西井享子さん(88)は5年前に認知症と診断されました。診断当初は介護を拒否して体が徐々に衰弱し、もともと仲の良かった娘の広美さんとの関係もこじれてしまったそうです。