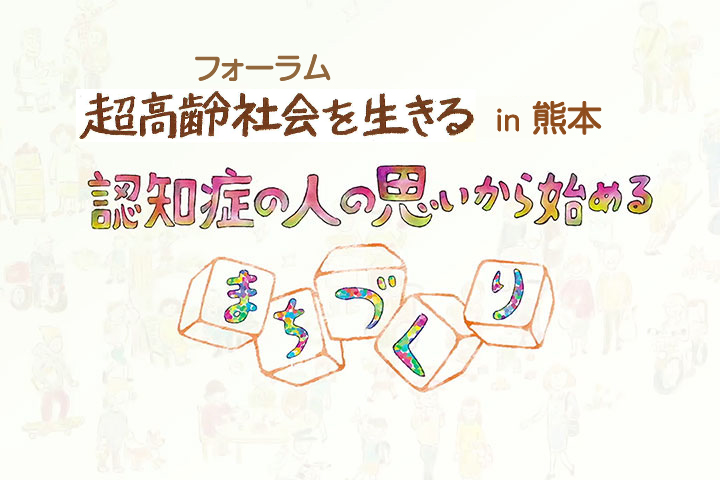▲ 「認知症と共に生きる」には社会の理念的側面と、現実の在宅での暮らしとがある。在宅で認知症の人と共に暮らすためには、「家族支援」の充実が必要だ。それが「本人支援」でもある。そして、人生の最終段階を共に暮らす。それは家族だけが担えるわけがない。その時、社会の理念としての「共に生きる」が機能するか。
「認知症と共に生きる」、その最大の実践者は言うまでもなく「家族」だろう。
これはいろいろなところで言っているのだが、この国の現在の認知症の環境は、認知症の人と共に暮らしてきた家族抜きにしては語れない。
かつて、「ボケても心は生きている」と、一番身近な家族からの声が集まり、認知症の医療を動かし、ケアを変え、そして今の当事者の誕生につながった。
一方で認知症当事者の発信が盛んになるにつれ、しばしば家族の支援のあり方が問い返される。何かをしてあげたいという家族の優しさが、本人の自立、自己決定を奪うことになりかねないと。これは確かに家族の痛点であったろう。
認知症を巡って家族と本人の間にズレがあるとしたら、それは当事者同士の課題ではなく、この社会構造のどこかが、互いの不適合を生んでいる。
とはいえ、家族の中のことはセンシティブである。そのことが密室化した家族関係に閉じているとも言えるのだが、だから、それを「家族の闇」として糾弾するのか、その関係性を解きほぐし、共に暮らす家族の再生につなげるのか、一括りにはできない。
では、その時、家族の思いはどこにあるのだろう。
友人が、認知症の家族の思いを語ってくれた。
彼は私たちの認知症に関わる活動にも参加し、認知症への確かな洞察を持つ人である。彼の義母が認知症で、だいぶ進行しているらしい。その人の語る家族としての思いと悩み。
「認知症の人と接していると、現実的なケアのことももちろんあるのだが、一番気にかけるのは、本人の意思決定支援をどうするかと言うことだ。認知症の人と暮らすと言うことは、これをどうする、何をしたいのか、といった、日常の細々とした意思の確認の連続なのだ。
その多くは、これまでの暮らしの中でのルーティンワークで処理できる。現に妻はそうしてうまくやっているのだろう。
しかし、認知症の人の意識の状態には変動がある。明瞭で、以前と変わりない晴れやかな受け答えができる時もあれば、ふっと雲間に意識が隠れるように、無反応にたたずむようになるときもある。
そんな時、何か視線を虚空に泳がせたり、ここがどこかわかっていないような不安をにじませている時、一体、本人は、何を思っているのだろうか。
そんな時、私は大抵、何かをうながす。「お母さん、トイレ?」、あるいは、「座って一休みしましょうか」、確信ないままに何かを言う。言うだけでなく、顔を覗き込み、手をそっと引いてみたりする。十分、時間を待つようにしているのだが、その時、私の中にあるのは、私の不安と当惑と、そして、微かな苛立ちだ。
そして、ふと、本人は今気づいたようにして、私に目を合わせ、「はいはい」とうなずきながら、リビングの椅子に向かい、腰をかける。
やれやれ、私はホッとする。
しかし、後になって考えこむ。あれは本人の意思を確認したことになるのだろうか。
彼女は、単に私に合わせてリビングの椅子に座ったに過ぎないのではないか。
しかし、私に何ができたろう。あの時、年老いた義母は、時間も空間も超えたどこかに思いを遊ばせていたのかもしれないのだ」
彼はここまで話して、テーブルの水割りを一口飲んで、照れ臭そうに言う。自分はそんな誠実で立派な介護者であるわけでもなく、普段は、そんな意識もなくただ介護を「こなすように」しているに過ぎないのだ、と。普段から、こんなにひとつひとつのことに考え込んでいたら、介護などできるわけないだろ、と笑う。
で、言いたかったのは、次のことであると、彼は言葉をつなげた。
「そうそう、言いたかったのは、認知症の人の意思決定支援の事だ。
家族が認知症の人と共に、これからの暮らしのことを話し合うとする。その時、よく聞く話なのだが、当の本人が、「私は施設に入ることにするよ」と言う場合がある。
これを家族は、どう捉えればいいのだろう。無論家族の置かれている事情は全てちがう。
「そうしたいのね」とため息と共に受け入れる家族もいれば、「何言っているの。ここでみんなで暮らしましょうよ」と、ひきとめる家族もいるだろう。どれが正解とは誰も言えない。
ただね、これは、本当に本人の意思なのだろうか、その一点にどの家族もためらいを見せる。本人は、本当に自分の意思で施設に入ると言っているのか。私たちに迷惑をかけたくないと、ああ言っているのではないか。それはつまりは、自分たちがそう言わせているのではないか、とね。
私のところでも、やがてそうなるかもしれない。ではその時、私は、「施設に行きたい」と言う本人の意思を、否定できるのだろうか。
本人の、家族を思う気持ち、それを否定して在宅の暮らしを続けることが、果たして本人の意思決定支援になるのだろうか。
本人の、家族に迷惑をかけたくないと言う思いをも、その全部を含めて、本人の意思として尊重すべきなのではないか。
もちろん、本人の意思決定支援という名の下に、家族の都合に誘導するようなことがあってはならない。だが、こうした現実にやがて私も直面するかもしれないのだ。
でね、飛躍するようだが、ふと「姥捨山」伝承を思い出した。
そう、姥捨山。あの言い伝えもいろいろなバリエーションがあるのだが、あれだって究極の高齢者本人の意思決定支援だと言えないだろうか。
おそらく、あの当時の貧困や飢饉の中で、村の老人自身が家族のために捨てられることに同意する。どの民話でも無理やり老人を捨てに行く設定にはなっていない。
親の思いを知りながら、親を捨てにいく子、子の悲しみを知りながら、その背に負われる親。確かに理不尽だ。そんな理不尽を家族に押し付けられてはたまったものではない。
しかし、そんな切なさ、厳しさは、形を変えて現代にも繋がってはいないか。
つまり、これは家族だけにかぎらないのだろうが、人は誰もが人生のどこかでそうした究極の切なさとか哀しさと向き合わなくてはならない、ということなんだ。
人生の最終段階で、自分のことより家族のことを優先して思う親の気持ちを、家族の側が、まるごと確かに受け止めたと伝え返すことしか、家族にはできない。
その時、言葉にできないほどのあふれるような互いの感情が行き交う。
そしてそれこそが実は老いた親への、家族の側の意思決定支援なのではないのだろうか。
家族の絆はいいものだ、というノーテンキな合唱が続くが、そんな側面だけを見るのではなく、実は家族というのは、順繰りにそうした喪失の哀しみといったものを伝えていく役割があるのかもしれない。
姥捨山の言い伝えは、実はそのことを語っているのではないのかな」
途中で途切れたりしながら、だいたい彼はこんなことを語ってくれた。全ての家族の思いというわけではなく、こういう思いを持つ家族もいるということだろう。
家族というのは、本来、そこに赤ん坊や年寄りという「社会的弱者」を包みこむ、共同体の最少単位の「共生の場」だった。そうした家族が連なって地域を構成していた。
しかし、その家族の形態は急速に変わった。
核家族はそのまま高齢者世帯にスライドし、老々世帯と単独高齢者世帯に変貌し、そしてそれぞれの世帯は共同体からも切り離され孤立していく。
人生の最終段階で、その意思決定プロセスを通じて本人と家族の互いの深い感情の確認をすることができる家族がいつまで残るのか。それとも、そうした家族の機能も失われて、意思決定支援なき「親捨て」の荒涼とした姥捨山の風景を現代に見ることになるのか。
確かなことは、これは家族の問題というより社会の問題だということだ。
(今年春に改訂された「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」では、医療やケアなどのチームが、そうした意思決定に際しての、本人・家族を十分支援する体制を作る必要性が盛り込まれている)
|第111回 2019.8.1|