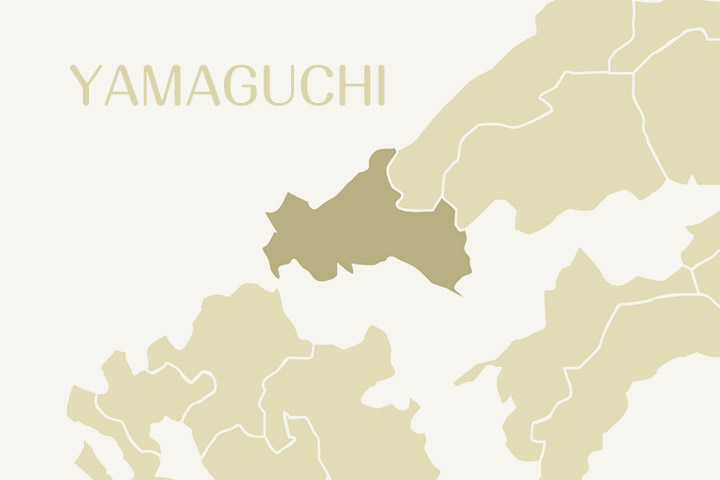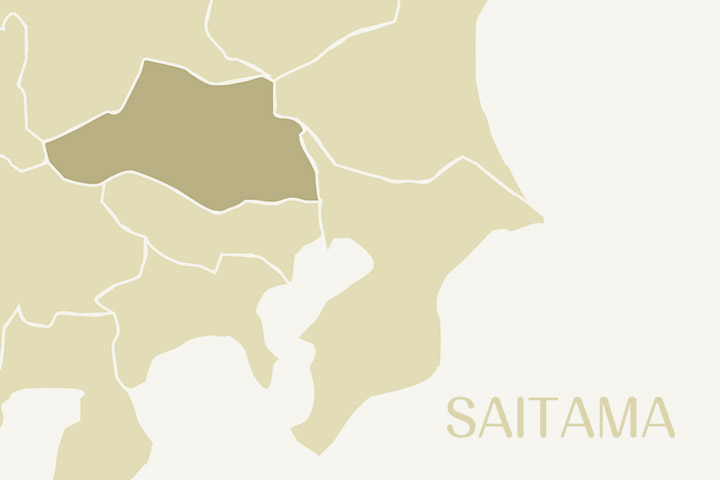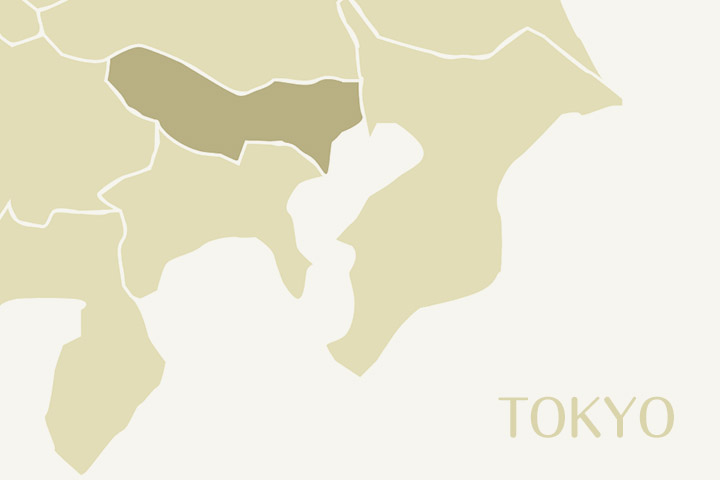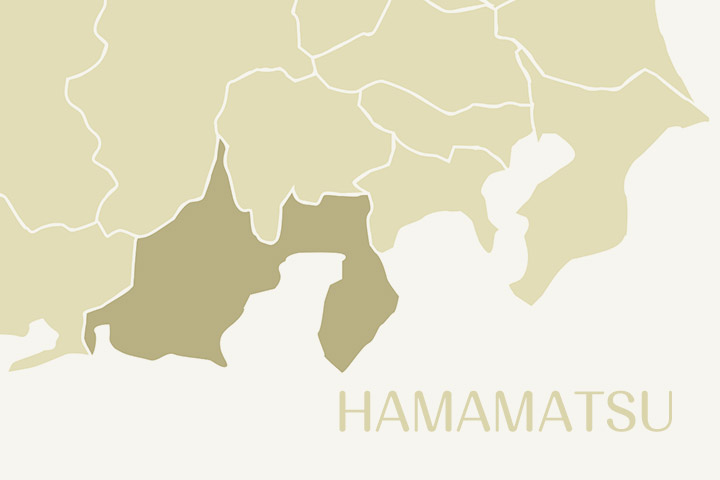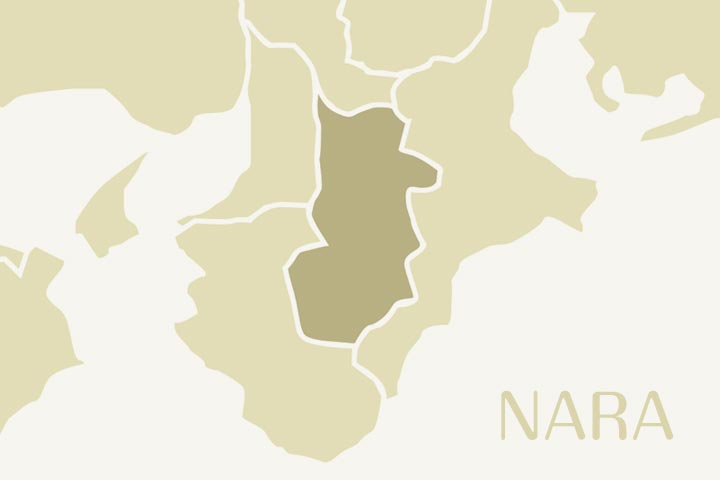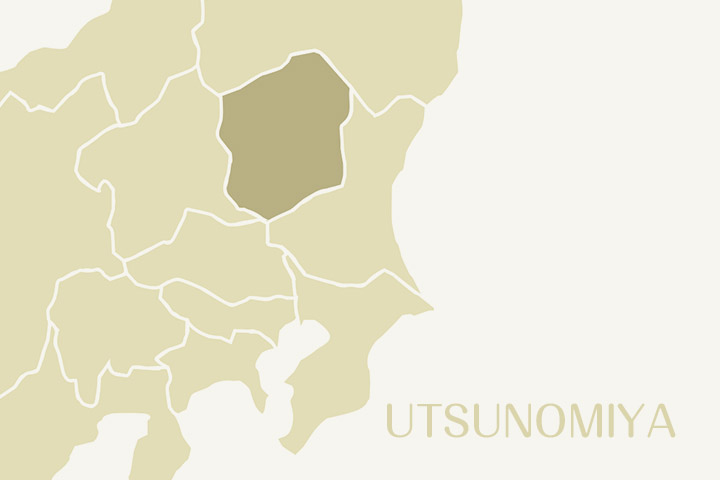▲去年11月、金沢でのフォーラムで地域の取り組みとして「聞き書き」が語られた。高齢者や認知症の人の人生の聞き書きは、新たな地域やケアを生み出す力がある。右が聞き書きの実践を語った「かがやき在宅診療所」院長の野口晃氏。
認知症の当事者をはじめ、様々な人とお会いし話し合い、そのことをコラムにしたり、また講演などで話したりする。
誰かに会って話を聞くときに、私はほとんど取材ノートもICレコーダーも使わない。いや、確か現役の時にはノート片手だったし、ゴトリと録音機を(最近のICレコーダーははるかに小型で高性能になっている)机の上に置き、「録音してよろしいですか」と断って取材活動をしてきた。取材というのはまず持って正確を旨としなければならない。周囲からも言われたし私もそう思っていた。
フリーランスになって、認知症の人とは随分とお会いするようになった。それなのに、なぜか逆にノートもレコーダーもほとんど使わなくなった。なぜだろう。
そのあたりについては、以前(2020/6)のコラム「私が認知症の人にインタビューしない理由(わけ)」に記したことがある。よろしければ。
フリーランスになって、そのあたりが自由になった。取材というお仕事ではなくなったのである。ふんふん、なるほどと聞くほどに開かれた言説空間に行き交う認知症の人の語りが、とにかく面白い。
そんな話を聞いても、私は詳細なメモを取るわけではない。そのあとの電車や車の中で、その内容を反芻するようにしながら帰途につき、食事をし風呂に入り、書斎でCDを聴きながら、そのやりとりが再現され、くりかえされ、そこには絶えず、その人の声音やリズム、表情が浮かび、部屋の日差しや光景、周りの環境のノイズ、笑い声や食器の音なども混じり、その中を人間の声が、浮き上がるようにして明確さを増してくる。
時間の中に洗われ、それでもなお私の記憶に残るその人の言葉があって、初めて私はその言葉に励まされるようにして、ワードソフトを立ち上げる。
すでに書くべき言葉は、そこにある。その人の表情とともにその人の語り口を再現するように言葉を置きながら、そこに私の思いを寄り添わせ、思考が立ち上がっていく。そのようにして、文章が生まれる。
だから、そこに記される認知症の人の言葉は、語ったそのままが記されるわけではない。テープから書き起こしてみたことがあるが、一字一句正確なその言葉からは何の思いも思考も浮かんでこなかった。その言葉は正確ではあっても、プリントされた書き起こしの文章からは、人の声やぬくもりといったものがかき消えていた。
私が獲得したいのは、私の感覚や思考を通して私の言葉となったその人の言葉なのである。正確さで言えば、この方が私の感覚には、より正確なリアリティとして迫ってくる。
多くの場合、認知症の人は認知症を語るわけではない。言い方が難しいのだが、認知症を語らないことが、紛れもなく認知症を語ることなのである。
それは聞く側の価値観の中の認知症ではなく、その人の認知症とともにある人生という物語が語られるからだろう。
例えば、以前にこんな私の原体験を記したことがある。
「認知症の取材を始めた十数年も以前、とりあえず施設やグループホームに行って、認知症の人の話を聞くことにした。しかし、何を聞けばいいのかわからない。
だから、一緒にお茶を飲んでは、そのまま所在なげに座っているしかなかった。
そのうち、初めて私がいることに気づいたように、その人が話しかけた。
グループホームの庭の向こうを指差して、あの山の向こうに住んでいた、とその人は語り始め、若い頃のこと、大工だったこと、「かかあ」のこと、かかあ、というのはお母さんですか、と聞いたら、うんにゃ、かかあだと答え、妻女のことだった。かかあとの話はずいぶんした。
話はいきなりあちこちに飛んだり、黙り込んで流れる雲を一緒に眺めたり、つながりがよくわからない話も多かったが、帰りの道すがら不思議に、私は確かに「認知症」と出会ったのだという感覚が残った。」
今、介護や福祉の分野で「聞き書き」の取り組みが注目を集めている。
去年、金沢で開催した認知症のフォーラムで聞き書きのことを熱込めて語ったのが、地元のかがやき在宅診療所院長の野口晃氏だった。
野口氏は聞き書きというのは、単に高齢者や認知症の人の言葉を転記するのではなく、録音素材をそれこそ徹底的に聞き込んで、情景を思い浮かべ、まるで「憑依」するかのようにしてその人の人生を生きる体験をするところまで自分を追い込むのだという。
憑依とはなんとも迫力ある言葉だが、それを野口晃氏は、まことに楽しげににこやかに話すのである。誰かととことん出会うことができる体験なのだ、と。
野口氏の「聞き書き」は、氏の在宅医療の基盤と深いところで繋がっている。患者である前に、まず人が人と出会うことの確認として「聞き書き」が据えられているようである。氏の話を聞きながら、私もまた認知症の人の話を自分なりに「聞き書き」していたことに気づかされた。
この聞き書きには、特別のルールがあるわけではない。ただ、こちらが聞きたいことより、本人の語りたいことを起点にするなどの原則的なところを踏まえ、各地でボランティア活動として行っているところが多い。以前参加した石川県小松市の「とことん当事者」をモットーとする認知症ケアコミュニティマイスター養成講座では、この「聞き書き講座」が必須科目だ。
私は「聞き書き」は、認知症ケアの本質と深いつながりを持つと思う。
認知症ケアそのものの概念は変化してきた。
これまで言われていた「支援と被支援」の関係を組み直し、同伴するケア、パートナーシップと言われてきた認知症ケア。しかし、それは常に理念的な傾斜の中で語られることで、対して、現実の現場はそんなに生やさしいものではないとする声も常にあがった。
認知症の「ご本人さま」が不穏な状態であれば、そこにケアの力を駆使し状態を安定させ、認知機能の低下を食い止め、改善することを求められるのがケアの現場である、と。それは言い換えれば、理念と現実の交差しない中での消耗戦のようでもある。
この理念と現実の乖離をどうつなぎなおすのか。
それがこの聞き書きなのではないだろうか。高齢者や認知症の人の聞き書きとは、まず持って、その人の話したいことに向き合う。こちらから質問を矢継ぎ早に繰り出す尋問ではない。その姿勢はそのままその人の存在を受け入れることだ。老いのプロセスを受け入れることだ。
進行を食い止めるとか、改善させるといった成果主義を一旦は振り落として、その人の話に耳傾け、その物語を自分に移植するように自分のものとする。それはそのまま当事者であることの実践で、それは「支援と被支援」といったケアの次元を超えて、いつのまにか物語と対話の場となっていく。
聞き書きは物語と対話の記録なのだ。
その人の物語をあなたが引き受ける中で、対話が生まれる。その人の話に相槌を打ちながら、あなたは自分自身と対話しているような不思議な空間に身を置くかもしれない。
聞き書きとは、文字通り、聞いて、書く、ということだ。
他人の人生を自分の中に取り込み、その息遣いや思いを自分の中で再構成させて文章化する。書いている間は、その人の物語がひたすら書く人の中を流れていく。
それはたぶん、書く人の深いところの変化を生む。認知症の人の失われていくものを食い止めるケアではなく、互いに生み出していくケアへ、と。
それは、当事者であることの確認と新たな認知症ケアの創出への実践だ。
認知症ケアをどうするか、ではなく、あなたはどうありたいのか。
よく言われる「支え合う」というケアの狭義から解き放たれて、聞き書きの体験からは、「分かち合う」や「与え合う」といった新たなケアの姿が拓けていくようだ。
ノンフィクション作家の柳田邦夫氏は日本聞き書き学校の校長も務めるが、氏は「一人の人間の人生の内実は文庫蔵一つに相当する」と記している。
確かに、一人の高齢者が亡くなるということは、地域から図書館がひとつなくなるようなもの、とはよく言われていたことだ。
コロナの時代に、この地域の記憶の継承を誰がするのか。それもまたケアの力だ。ケアの力とは、社会を持続させる力でもある。
シンプルでそれでいて奥深いだれものケアの力、それを生み出すのが聞き書きなのだろう。
|第174回 2021.4.22|