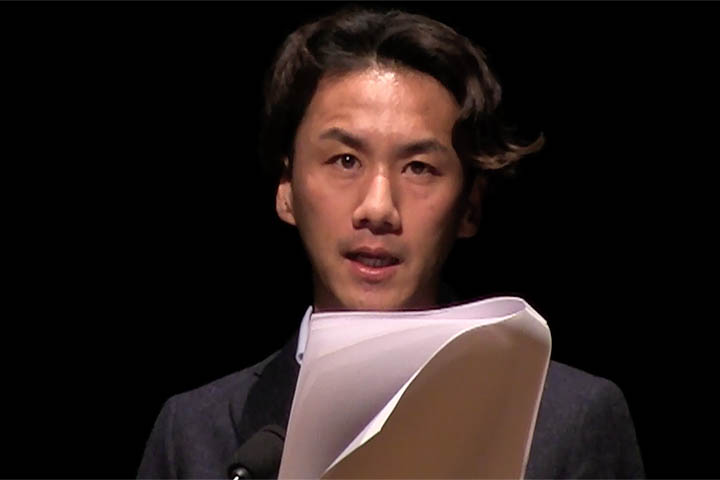▲かつて、姉が嫁いでも春になると母は必ず雛人形を飾った。気がつけば、同じことを我家でもしている。ケースに入った木目込の人形はしまったままだが、手元に置く小さな雛人形の方が、なぜか春を感じることができる。
仕事部屋に、コトリ、春を置くようにひとつの雛人形を置いた。
まことに小さな手のヒラにのる素朴な造作の土人形である。造り手がこねて彩色し、細く小さく眉目を引いた可憐なお顔をしている。どこかの土地の土産だったはずだ。
春に生まれた娘が初節句を迎える頃、私は全国を飛び回るような仕事についていた。仕事も親業ともにおぼつかない新米の父親だった私が、出張の帰り際にふと思いついて、慌ててその土地の土産物屋で買い求めた雛人形だったと記憶する。
春になると、妻はどこからかこの小さな雛人形を出してくる。この夫婦がたどり着いた人生航路を彩る小さな春である。
今年もまた、春は誰とも分かち合えないまま、訪れる。
北京オリンピックはさまざまに言われながらも、アスリートの競技そのものは手に汗握る感興を十分に呼び起こした。しかし、その閉会式となるとなぜかその大掛かりな仕掛けや華やかさに素直に入り込めない。
実況の「楽しげな光景です!」の連発や、スタジアム・スタッフの大きく手を振り回しながらの盛り上げる様子にも、どこか作為的なわざとらしさを感じてしまうのは、多分、こちら側の感覚の何かが外れてしまったからだろう。
世紀の祭典のような巨大な夢は、もはや、私たちの共同幻想だ。新型コロナウイルスのもたらしたのは、ともにひとつの夢を見ることが難しい時代なのかもしれない。
春は必ずやってくる。それはどんなにつらく厳しい冬の中にあってもきっと明るい未来が訪れる、と言った揺るぎない思いを育む私たちの精神風土となってきたはずだった。
桜の花は、いつもそこに一緒にいた人との記憶に咲いた。ともに飲み交わしたり、風に舞う花びらを眺めた人がいたこと、それはつながりを生きることの承認だった。
かつて、ともに桜の下にいた人がこの春にはいないという喪失もある。悲しい記憶の中にも桜は咲く。東日本大震災の春に、この国のどれほどの人々が涙と痛切な思いで、桜の花を仰いだことだろう。
梅は咲いたか、桜はまだかいな、私たちは桜の花の咲くことをひたすら待ち望み、そして桜の開花に共同体の再生を確認してきたのである。春はそのようにして、冬を生き抜いた安堵と祝祭の季節として私たちの歳時記に語り継がれている。
そのような春がやってくるのだろうか。祝祭の春ではなく、我慢の春としてそれぞれがひっそりと桜の花の下にたたずむしかない春だとしても、春を嘆くのではなく、私たちの共同体の覚悟として、私たちが、私たちの桜の花を咲かせなければならない。
新型コロナウイルスの2年というのは、ほとんど感染対策の中に明け暮れた。そして感染対策で前面に出てきたのは、専門的知見でありエビデンスの裏付けがあるかということだった。
専門的な数値の数々が対策の根拠、エビデンスとされ、感染者数、重症者、死亡者数、病床逼迫度などの数値で蔓延防止や緊急事態の対策が語られた。
その際に目立ったのが「専門家会議」なのだが、この役割や位置付けはひどくわかりにくい。
専門家と言っても、専門家会議、クラスター対策班、有識者会議、諮問委員会と主要メンバーが重なる組織が複数存在しており、各自治体も専門家会議を持っているから現時点でどうなっているのかよくわからない。
メディアでの露出でよく知られる尾身茂氏は、新型コロナウイルス感染症対策分科会の会長で、専門家として必要なことは「サイエンスをベースにした社会的応用」だと語っていた。
要するに、科学の知識を役立ててこの事態の中、困難はあってもより良い社会的決定につなげていく、ということだろう。
大切なことだ。どうしていいのか右往左往する中で、科学の知見というものしか私たちは頼るものはなかったのだ。
以来、科学的エビデンスに基づく知見というものがいつも専門家から語られ、そのことで暮らしは右へ行ったり左に傾いたりしてきたのである。およそ、これまで私たちの経験したことのない事態とも言える。「エビデンス」という、これまで全く馴染みのなかった専門用語が暮らしの隅々までを規定し、施政者が新たな対策を発出するたびに専門家会議に諮問し、そこでの見解は水戸黄門の印籠のようにしてサイエンスの威光を放ち、私たちは、ただ、ハハァーっと平伏するしかなかった。
この稿はこのことを論評するものではない。難しいのは、エビデンスというものがどれほどの成果に結びついたのか、一般人には検証できないということだ。今私たちが手にできる一番確かな対策の指針がエビデンスに基づくものであることは、なんとなくわかる。なんとなくわかるということは、解釈の幅があるわけで、となるとそこにさまざまなメディアやSNSや井戸端会議的な手前勝手な解釈が入り乱れ、せっかくのエビデンスが混乱を引き起こす。あるいは、私たち自身もそこに示される数値自体を、重大な意味をもつご託宣として受け止めたりする。
多分、こうしたことのほとんどは、専門家の側からすればきちんと説明しているのだろう。こうした一般人の無知に舌打ちしたい専門家が多くいても不思議ではない。
しかし、一般の高齢者も含めた人々に伝わらないのであれば、専門家が機能していないということではないのか。あるいは機能させていないのは、私たちの側のリテラシーにあるのかもしれない。
しかし、もっとも課題とすべきは、専門家の知見をあたかも便利に施策対策の裏書きにつまみ食いするように「使いまわしている」ように見える政治過程にある。我慢を強いるような自粛策には専門家の知見を前面に出し、経済を回すことを優先したいときには、専門家の見解は奥に引っ込める。それはないんじゃないか。
専門家会議の見解が、最も影響を受け役割を果たすべき生活者の側の実感とつながっていない。そこを説明し納得させ、つないでいくのが政治の役割のはずである。
いうまでもないことだが、私たちの暮らしはエビデンスを元にして成立するものではない。暮らしというのは、変数に満ちた日常の中で、さまざまな価値観を持つ人々の間を行き来する関係性の中で築かれていくものだからだ。暮らしの根拠というのは与えられるものではなく、地域の中で作り上げていく。だから、地域の生活者は、まぎれもない暮らしの専門家なのである。この事態の経験専門家であり、主権者であり、当事者なのである。
今、医療や介護の現場では、当事者である患者や高齢者との対話は欠かせない。エビデンスベイスドメディスン(根拠ある医療)とナラティブベイスドメディスン(物語に基づく医療)は両輪となって初めて機能する。
感染対策に、地域の専門生活者の感覚や声はどこに組み入れられているのだろう。コロナ対策専門家たちと生活者との対話の回路はあまりに希薄だ。
雛人形を飾る桃の節句は、いうまでもなく子供の健やかな成長を願うものだが、その源流は平安時代からの流し雛の伝承にある。物忌みの行事で、ヒトガタである形代(かたしろ)に穢れや災厄を託し、川に流すというものだったと言われる。
子供が無事に育つかどうかは現代と比べようもなく難しい時代だからこそ、人々は子らの育ちを共同体の未来としてともに願って、雛を流した。
春とは、そのような季節でもあった。いのちの育ちと作物の成りを願い、祈るようにして花の下に暮らしの物語を編み上げてきたのである。みずから桜の花を咲かせるような物語を。
「春よ、来い」は、北京オリンピックの羽生結弦選手のエキシビションに流れた松任谷由実の名曲である。「春よ 遠き春よ」の調べはよく知られているが、もうひとつ、相馬御風が作詞した童謡の「春よ来い」がある。
春よ来い 早く来い
あるきはじめた みいちゃんが
赤い鼻緒の じょじょはいて
おんもへ出たいと 待っている
そう、私たち誰もが輝く陽光の「おんもに出たいと待っている」、早く来い、と待っている。
私たちに、どのような春が訪れるのだろう。