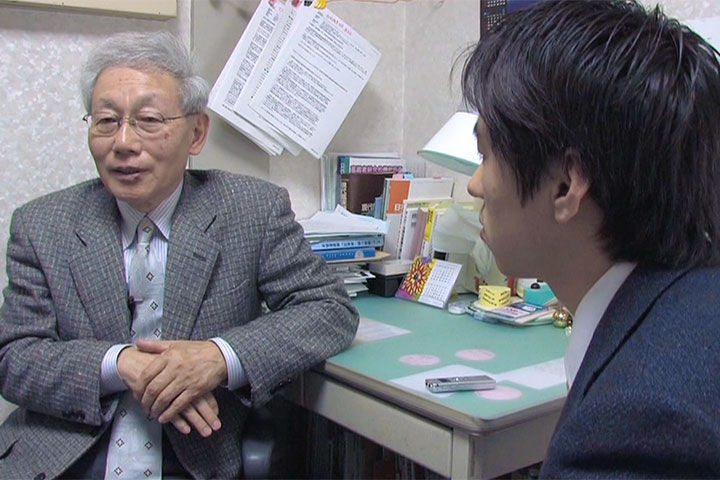▲時間は容赦無く過ぎていくが、私たちの暮らしは先を見はるかすようにして一歩一歩進むしかない。この道ははるかな未来の光に続くのか。時代を拓く「認知症学」のススメ。
秋が日毎に深まって庭の木々の葉が散っていく。
ふと、「認知症学」といったものを提唱できないだろうか、そんなふうに思ったりする。
日本社会は世界に冠たる超高齢社会である。ということはコトのほぼ必然として、認知症社会である。
だから、世間ではそのことを「認知症と共に生きる」として引き受けようとしているわけだが、シニカルに見れば、どうもその引き受け方の片隅に、「しぶしぶ」といった感じが滲まざるを得ない。
まあ、そうだろうな。大歓迎で引き受けるわけにはいかないのはよくわかる。しかし、冷静に見れば、この超高齢社会というのは認知症社会であるということも、紛れもない現実だ。
認知症社会であるのなら、「認知症と共に生きる」というよりいっそ、「認知症と生きる」といいきってもいいのだが、そこはまあ、ちょっとね、といった具合に小指で眉を掻く小さな間合いを置いて、「共に」を挟み込む。
自分とちょっと距離をおいて、「共に」の言葉に、自分は認知症ではない側の設定を確保する。
「認知症と共に生きる」には、見方によれば、なりたくない自分となるだろう自分との切ない思いが交錯している。
「認知症学」を創ろう、といったことをどこかに書いたことがあるなあと探したら、11年前の2011年2月のこのコラムに書いていた。ほんの思いつきのメモだったが、実はその発想は「水俣学」にあったとそのコラムに記していた。
「水俣学」というのは、水俣病研究の第一人者で患者の救済に半世紀にわたって取り組んだ熊本の医師、原田正純氏が提唱したものだ。
水俣学については、原田正純氏は2005年のシンポジウム「なぜ今、水俣学か・現場からの学問の捉え直し」の講演で静かな凄みを湛えてこう述べている。
「(水俣病という)これほどの政治的、社会的な事件を最近まで、 医学の症候学という狭い枠に閉じ込めてしまったことは不幸であった。
したがって、「水俣学」は水俣病の医学的な知識を普及、啓蒙するための 「水俣病学」ではない。 専門家や学問のありようから、この国の政治や行政のありよう、そして個人の生きざままでさまざまな問題を水俣病事件に映してみて何が見えてくるかを探るエキサイティングな知的作業である」
原田正純氏とは、水俣を語る番組でご一緒したが、その前日の打ち合わせでは、眉間を広々とくつろがせ、際限なく焼酎を喉に流し込みながら水俣の美しい風土を語ったのだった。その美しい風景を踏みにじったのは誰か。ミナマタを考えることについて、原田氏は水俣学の講演ではこうも語っていた。
「私にとって、 水俣病をつうじて見た世界は、 人間の社会に巣くっている抜きさしならぬ亀裂、 差別の構造であった。 そして私自身、 その人を人と思わない状況の存在に慣れ、その差別の構造のなかで、自らがどこに身を置いてるかもみえた」(保健医療社会学論集16巻2号 2005)
知られているように原田氏は徹底した現場での医療活動と、当事者の声から患者救済に取り組んだ。そこで専門家、非専門家を超えて広範な市民、支援者、当事者と共にあることが必要だったとし、そこから学際的な「水俣学」を未来社会への指針とすべく立ち上げた。
もちろん、ミナマタは、深く息吸い込むような鋭角の問題性を持つテーマであるから、一概に認知症とは同列に論じることはできないかもしれない。しかし、より広範な当事者社会の性格としては、認知症はむしろより濃厚な自己への問いかけとして響くはずである。
原田正純氏が、「抜きさしならぬ差別の構造の中で、自らがどこに身を置いているかも見えた」とミナマタの声をひたすら厳しい自己検証に受け止めたように、実は認知症をめぐる環境は、このコロナの日々で苛烈さを増している。当事者発信の一方で、声をあげられない認知症の人々、孤立する本人と家族の姿が見えなくなり、また介護保険制度からも見捨てられようとしている。
私たちは、この抜きさしならぬ現実の中で、どこに身を置いているのだろう。
もはや、他者性のあいまいな「理解と共感」で認知症を語るのではなく、明確な意志として、認知症の人が人間として奪われた権利を取り戻すためには、私たちはどこに身を置くのか。
認知症学は、その道筋を探る。
「認知症学」が、私の記憶の深層から再び浮かび上がってきたのは、もうひとつ、映画評を書くために改めて接した盲ろうの研究者、福島智氏の論考にあった。
それは「障害学」である。
障害学(Disability Studies)は、1980年代にアメリカで始まったとされるが、最近上映された福島智氏と母親の実話をもとにした「桜色の風が咲く」でも、物語の智が「見えへん、聴こえへんとはどういうことか」と問われるシーンがあって、そのことは現在の福島智氏の「盲ろう者と障害学」の研究テーマにつながっている。
福島智氏は、自身の障害については、「障害」を持つ人が「障害」にどういう意味を見出すか、その人の生き方や人生における「価値」とどう関わるのか、といった実存的なレベルでのアプローチが大切であるとし、「障害」という切り口で、社会や人生について考える営みすべてを障害学と呼んでよいのではないかと述べている。
元々、認知症を障害とする捉え方は、障害者権利条約のパラレルレポートに認知症団体の参加や記述もあって、障害学とは極めて親和性が高く、障害学の「障害」を「認知症」と置き換えても違和感はない。
福島智氏は障害学の取り組みとしては、大きな二つの側面があってそれは、「文化論的戦略」と「能力論的戦略」であるとする。文化とは、障害を否定的に捉えるのではなく、それ自体を独自の文化であると見ること、能力論とは、能力差による差別への抵抗を示すこととしている。
ここでの「文化」と「能力」はそのまま認知症学の柱となるだろう。
認知症を文化として捉え直す。能力主義からの脱却を目指す。
老いていくこと、それぞれが弱い個の集合である社会の姿にはどのような価値があるのか、できる、できないの選別にはいかなる意味があるのか、そして、認知症の自分が存在することの実存的な意味とは何か。認知症学の歩む道筋だろう。
認知症学を考える時、認知症を包摂する領域に老年学(gerontology)がある。
日本は世界に突出する超高齢社会であることから、高齢社会のアカデミアもまた世界のフロントランナーであると考えがちだが、実はこれは大きな錯誤なのである。
日本の老年学の目覚めは世界的にも遅かった。その立ち遅れは、アメリカと比較すると顕著だ。
アメリカでは1965年にアメリカ高齢者法(the Older American Act)が成立して以来、全国の主要大学に老年学の研究や教育の重点投資が行われ、現在アメリカには老年学修士課程を持つ大学は40近くあるが、わが国には、桜美林大学の一つしかない。
代わりに日本に目立つのは老年医学の講座で、全国医学部80のうち23にあるが、アメリカでの老年医学講座は3つしかない。(公益財団法人長寿科学振興財団・老年学とは)
わが国での老年学は医学に傾くばかりで、高齢者の増加は常に社会保障財源圧迫の恐怖におののくばかりで、ついにそこから老年学という新たな社会の姿と可能性を見ようとはしなかった。
老年学を特色づけているのは、学際的、分野横断的であるということだ。
老年医学が医学的な視点が核であるのに対し、老年学は医学はもとより、心理学、社会福祉、哲学、歴史、文学や芸術、宗教学も含むとされる。要するに「文化」的考察が大切な柱なのである。
だとしたら、より市民社会に開かれた認知症学があって当然ではないだろうか。
私の構想する認知症学の起点には、認知症当事者の視点がある。
それはこれまで健常の側から認知症を見るという方向性しかなかった医学や社会のあり方を逆転させることだ。認知症からこの社会を、人の存在を見つめ直す、そうしたベクトルをつくり出せないか。
思えば、認知症学の下地はすでにこの社会に芽生えている。
認知症医療や介護にあたる現場では、知識や技量だけにとどまらず、人間存在そのものを捉え直す実践や見識を磨き上げている。中島紀恵子氏のケアの専門書が人間論としての考察に満ちていたり、あるいはすでに古典とも言える小澤勲氏の「痴呆を生きるということ」などは、ほとんど認知症文化論と読み直すことができる。
認知症学の芽生えは、認知症をテーマにした出版、アート、まちづくりといった日常と地域にすでに種蒔かれている。ニーズがシーズ(種子)となり、地域社会の土壌にすこやかな育ちさえみせている。
こうした個々の芽生えを体系化して、「この社会はどうあったらいいのか」という認知症学を編み上げていくことはできないだろうか。
私は、自身のささやかなネットワークを見渡しても認知症学を講義してほしい人々の顔が、次々と浮かぶ。当事者はもちろん、研究者、医療者、アーチストや作家、ジャーナリストなどなどの学際的な連続講義があり、それを受けて海外のネットワークとも結んで対話を重ねていく。
水俣学も障害学も、膝から崩れ落ちるような圧倒的な絶望や悲劇から、渾身の思いで立ち上がり、自らを見つめ直し問い直すことで、未来を拓こうとしている。
この社会のどこかに、もしも認知症学の扉があるとするなら、それを多くの人によって押し開く時、何かが変わる、何かが動く、そんな夢想に駆られている。