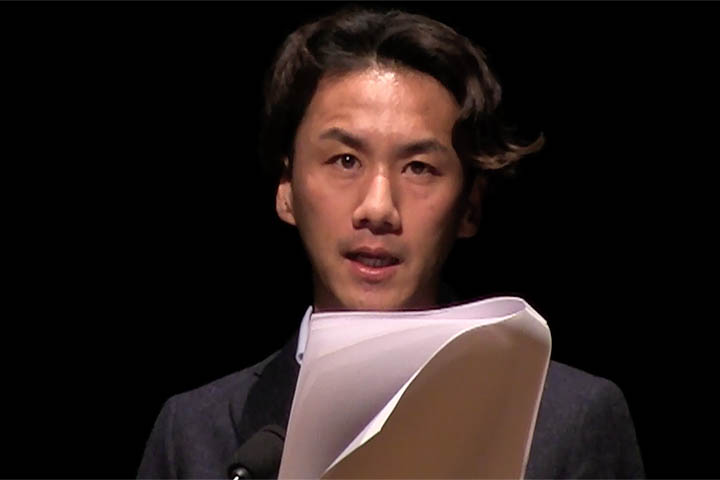▲2020年2月の町田市の「まちだDサミット」の様子。今は全国各地で多彩なまちづくりといった地域活動が展開されている。こうした取り組みがつながり広がるのが共生社会の実現だろう。
認知症をめぐる変化の質量は、その起点をどこにするかによっても違うだろうが、とりわけここ20年は、質的にも大きな変化を見せている。
「痴呆」が「認知症」と呼称変更されたのが2004年だから、今年でちょうど20年だ。私がメディアで認知症を本格的にテーマとし始めたのがこの頃だった。そこから多くの認知症当事者をはじめとして、認知症に関係する人々と会い、話し合い、現在に至る。そこで気づいたことがある。この20年の変化は実は認知症を超えている、ということである。
どういうことか。
とかく、この国の認知症の変遷を語るときには、例えば2000年の介護保険から始まって、ゴールドプラン21、国家戦略としての認知症新オレンジプラン、認知症大綱、そして今回の認知症基本法といったふうに制度政策を連ねることで論じられている。たしかに制度や施策の観点は社会変換の論証としては欠かすことが出来ない。
しかし、現在の「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」という認知症史のエポックに立って振り向けば、これまで見えていなかったもうひとつの流れを目撃することができる。
その流れとは、ほとんど初めて、この社会に市民性の存在とその躍動が生まれたことである。
ここでいう市民あるいは市民性というのは、教科書の中の、近代社会を構成する自立的個人、政治参加の主体といった死語ではない。平凡な日常を暮らし、しかしその日常のかけがえのなさを愛し、互いに肩叩き合うようにして過ごす健全な生活感覚を持つ人々のことである。私たちの地域の隣人であり、どこにでもいるような凡庸な人々のことだといってもいい。
アカデミアの文脈での市民とは、いつも眉間にシワ寄せて「この社会はどうあったらいいのか」とか「我ら、何をなすべきか」といったモラルの探究があり、ストイックな自己否定と検証の責務に自分でおののきながら、ひたすら未来に生きる意味を求めるといったイメージの市民像だったところがある。
今、巷に立ち現れている市民はその風貌からして違う。
夏空に流れる雲を眺め、暑熱の日中を、宵方のビールを楽しみにしのぎ、現実の人生のありのままを心ゆくまで生きる人々である。自分たちの愚かしさや騒々しさや軽薄さと言った人間臭さを誰もが共有し、それを認め合い楽しむ、そのような市民性の誕生である。つまり私たちである。
そうした市民性は、認知症がもたらした。あるいは市民の側が認知症を見つけたのである。
10年以上前からの認知症当事者発信は、当初は一定度の覚醒した専門職や医療者、メディアが先導したところがあったろう。しかしそれはすぐに新しい市民性に受け継がれた。
「認知症とともに生きる」「認知症フレンドリー社会」「認知症とともに生きるまちづくり」と言った理念の言葉はたちまち、自分たちの生活感覚で暮らしの言葉に翻訳され受け入れられた。
そのことを示す好事例がある。
東京郊外の町田市は2018年度から「まちだDサミット」という町あげてのイベントを開催している。「D」は、ディメンシアのDである。
私は2019年度のイベントに参加したのだが、その日は一日中、認知症の人とともに講演会や映画上映、トークや演奏会などがびっしりと続く。しかもそこには地域の駅長さんや郵便局長に書店員、コンビニマネージャーといった福祉以外の町の人々もこぞって参加した。
運営には大学生や高校生など若い世代があたり、お揃いのオレンジTシャツを着て、目撃した人によれば「笑っちゃうくらい大勢のオレンジシャツの若者が駅頭に立って、やってくる認知症の人や家族を絶対迷わせないようにと案内していた」とのことだ。
実際、大勢の認知症の人や家族がやってきた。これは祭りなのである。地域の祭りの主役はお年寄りだ。自分たちがいなければ祭りは成り立たない。そんな感覚だったのかもしれない。それは認知症の人がいなければ成り立たない地域社会の風景だった。
このイベントの中心人物の一人が町田市の松本礼子さんだった。松本さんによれば、やってくる認知症の人たちは誰もが連れてこられるのではなく、自分の意思で来たのだという。
その松本さんは、詰め掛ける認知症の人や家族を見てこんなふうに語った。それは今も私には鮮やかな印象を残している。
「私はね、認知症のご本人があまりにたくさんやってくるのに初めは感激して、すごいすごいを連発していたのね。でもふと、本人が参加したくてきているのに、それを「すごい」と捉えてしまうのは、やはりどこか認知症の人を特別扱いしているのではないか。自分はまだまだだと思ったの」
松本礼子さんはこんなふうに反省の弁を語ったのである。地域の認知症の取り組みを立ち上げた中心的な立場の松本さんにして、自らの成熟の視点を常に更新する。暮らしの中の市民性の強みだ。
また、若者達に指示を出し、取りまとめをしてきた市役所の担当者は、これまた意味深い感想を寄せた。
「このサミットに集う若者はぶっちゃけ物珍しさかもしれない。あるいは、良かれと思ってのお世話ばかりで認知症の人を戸惑わせているのかもしれない。でもね、みんなホントやさしすぎるくらいやさしい若者ばかりだ。私はね、最初は認知症のマイブームでもいいと思っている。そこから認知症の人たちと出会い、何かを学ぶ。そのことに期待している」
若者たちへのやさしいまなざしはおそらく認知症の人のまなざしから学んでいる。「ともに生きる」ということは、そこに間違いや錯誤、失敗を含んでいる。失敗できるとする若者の育ちを見守る包摂こそが、市民性の萌芽なのである。
ここに記したのはもう4年前の町田市の取り組みである。町田市では今も、認知症の人たちとより広範で柔軟な認知症の取り組みを続けている。
そして、たまたまここでは町田市の取り組みを挙げたが、全国各地で同じような、そしてユニークな活動は展開されている。そこにあるのは、認知症だけにとどまらない地域を底上げするような生き生きとした市民性に満ちた活動だ。
私はこれまでの20年に及ぶ認知症の歴史と本人発信を受け継ぐ正統性(オーソドクシー)というのは、今の新しい流れとしての市民性にあると思っている。そうでなければならないとも思っている。
確かに現在の認知症状況は、これまでの認知症施策の成果を受け継ぐようにして認知症基本法に至ったと輝かしい言い方もされるが、法制度の連続性から言えば間違いではないとしても、それではそこに、はるかな時代の痴呆の人々、認知症の人々はどこにいるのだろう。
収容と隔離と拘束の中に捨て置かれた認知症の人々の無念と絶望は、どこに記されているのだろう。そういう時代だったとして、それだけで認知症の新しい時代に歩み出せるのだろうか。
かつての認知症の人から、名前と人生と存在を奪ったのは誰なのか。
私たちはその告白を僅かに2012年の厚労省の内部文書の一節に読み取るだけである。
「かつて私たちは認知症を何もわからなくなる病気と考え、徘徊や大声を出すなどの症状だけに目を向け、認知症の人の訴えを理解しようとするどころか、多くの場合、認知症の人を疎んじたり、拘束するなど、不当な扱いをしてきた。」(今後の認知症施策の方向性について 2012年6月)
誠実な見解であっても、ここにあるのは公的な謝罪ではない。告白であり懺悔である。
ただ、このことの責任の所在を問うているのではない。なぜなら、そのような社会をつくっていたのは私たちでもあるからだ。認知症の人をこの社会は見えない存在として、それを家族や施設に押し付けてそのままにしてきたのである。その意味ではともにうなだれるしかない。
私は、認知症基本法が成立したときに、やはりその立場の人、誰かがこの認知症の歴史に触れてほしかった。新たな認知症の時代はそのことから出発すべきだった。
なぜなら今なお、この社会には認知症に対する根深い差別と偏見が居座っているからだ。あからさまな形でないだけに余計に深刻といってもいい。私たちが引き受けるこの社会の現実の確認はしておかなければならなかった。
だから、市民性なのである。
認知症基本法は、周知の通り「共生社会の実現」を掲げている。そして、そのための推進力として実は「参画」の二文字を埋め込んだ。これが私たち地域社会の市民性が基本法を受け継ぐ正統性の証なのである。参画とは、新たな市民性の誕生への期待につながっている。
認知症の人の想いは今、認知症を超えて、共生社会の実現へと日々の暮らしの感覚にダイレクトに手渡されようとしている。そして、共生社会の実現とはそうした人々の参画でしか推進しない。
身近な私たちの地域社会の底力が試されている。