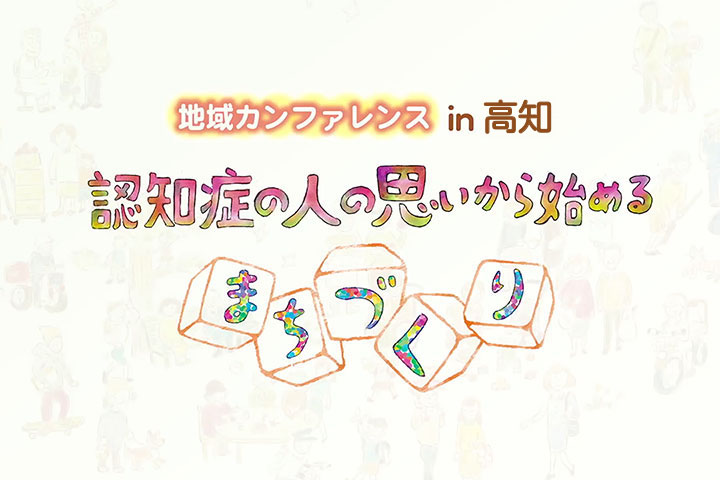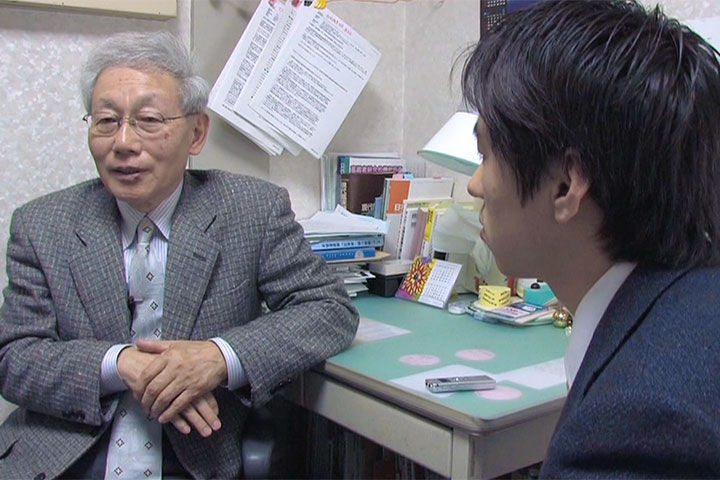▲上段は、庄原市の文化会館のロビーと住民の皆さんが詰めかけつつある会場。下段右、左から町永氏、大阪大学大学院医学研究科、日本老年精神医学会理事長の池田学さん、なぜかベトナムの服を着た介護福祉士の和田行男さん、聖仁会戸谷医院の戸谷修二さん。
広島県の庄原で「認知症講座」に参加してきた。
庄原市は、広島県の一番奥、北に鳥取、島根に接し、山に囲まれた近畿以西では最も広大な地域である。広島空港から車でも1時間半近くかかる。
早くも木々の梢の先が色づいて、ソバの花が白く清潔な花をつけ、まだ刈り入れ前の稲穂が揺れ、彼岸花が対照的な鮮やかな赤い群生となって沿道を縁取っている。
いつもこの道筋を通りながら、どこか「ああ、帰ってきたなあ」という感覚になる。それはいつもの場所にやってきたと言うより、どこかもう少し内側の、私たちの「帰るべきところ」としての原風景なのである。
どこと言って特別な景勝というのでもない。山々が周りを囲み、田や畑が広がり、農家が点在すると言ったあくまでも穏やかな「ふつうの」田園風景が続く。
司馬遼太郎は「古代史と身辺雑話」の中で、弥生時代の水田農耕というのは、田を開くために水平の土地にする農業土木を伴っていて、私たちがふるさとといった時に思い起こす景観はここに生まれたと語っている。そして、弥生時代の最大のうつくしさは、そうした農業土木的景観であったとし、主観的にはそれは世界一の景色であったろうとも記している。
空港からの車窓に流れる景色は、「世界一の景色」なのだ。
原初、稲作による暮らしの定住に深い安堵を覚えたであろう先人が作り上げた農業土木的景観とは、手付かずの自然におずおずと畏敬と調和を感じとりながら創作した風景で、今、私たちがそうした風景に「いいなあ」となつかしく安らぐのは、われらの古代人のはるかな記憶の継承なのかもしれない。
それが今、人と自然との共生の里山となって、眼前に広がっている。
私が庄原に通い始めた頃、ここは水も空気もきれいで、地元の産物も川のもの、山のもの、畑のものどれもそれは美味しい、いいところですよねえ、来るたびにそう言うと、それは外からの訪問者の気楽でノンキな感想で、ここに住み暮らす者にとっては、ここでの高齢化や過疎の現実はずしりとのしかかってそれどころではないのだと言う本音がつぶやかれる。訪問者の私はただうなだれるしかなかった。
ところが毎年通うようになって最近、それがどこか変わった。地元の人が、「ここはいいところでしょ」と言う人が多くなったような気がする。特産の山野の豊かな食材を自慢し、高台からの広々とした眺めをあちこちを指さしては季節の移ろいの喜びを語る。
庄原の高齢化率は44%を超える。加えて過疎地であり、さらには人口減少が加速している。国立社会保障・人口問題研究所によれば、庄原の人口は2060年には、2015年時の人口の45%にまで減り続けると推計している。とりわけ痛いのは、年少人口生産人口という子供と働き手の世代の減り方が著しいことだ。
しかし、ここで深呼吸するようにして改めて見なければならないことがある。
地域の現実はいつもこのような数値で語られる。確かに数値は客観的な現実の反映であろう。しかし、それは地域に暮らし続けている人の思いや、地域の景観がもたらす安らぎや喜びは反映しない。人々が住み暮らす中で培ってきたつながりや取り組みといった地域の力を算入することはない。
「ここはいいところでしょ」、地域に暮らす人々が実感込め誇らしげに、外からの訪問者である私に語りかける時、それは何か地域の力そのものが頭をもたげたようなそんな息遣いを感じる。
それはなぜだろう。
それを成り立たせるひとつに、今回の庄原市での「認知症講座・自分のこととして」がある。
地域の人々が自分たちの地域の良さとその力に気づいてきたとしたら、その背後には、地域の人々の安心の暮らしのための「医療と介護」がしっかりと備わっているからだ。
もちろん、課題は山積している。その確認と話し合いのためにこの「認知症講座」が、まるで年に一度の地域社会の祭りのようにして開かれている。そして必ず多くの住民がこの「認知症講座」にやってくる。
庄原が過疎地で高齢化率が高いと言うのは、見方によれば住民誰もが「認知症と地域医療と介護」の当事者であるということだ。だからここでの認知症も地域医療も介護も全て、「自分ごと」が単なる標語ではなく切実ないのちと暮らしの継続のための心音として響いている。
「今頃は、グランドゴルフを楽しんでいるお年寄りが集まっていて、みんな元気でね、それを見てもらいたいなあ」
庄原の医療法人で診療している医師であり、今回も講演会のレギュラー登壇者の戸谷修二さんは、私と山合いにポツンとある不思議な魅力あふれるお好み焼き屋(絶品だった)の昼を食べながら、そんなことを言った。
この何気ない言葉にも、医療者として、診察室の中だけで高齢者を診るのではなく、暮らしの中の高齢者の力を見つめ、そこから地域医療を組み立てようとする姿勢がうかがえる。
庄原の「認知症講座・自分のこととして」は、新装になった庄原市民会館大ホールで開かれた。
続々と人々が集まってくる。何かの歌謡ショーと間違っていないか。
やはりこの講演会のレギュラーである介護福祉士の和田行男さんは以前、会場に詰めかけた満員の住民にむかって、「あのな、この市民会館がいっぱいということは、人口密度の比率からすれば、東京ドームが超満員ということや。えらいことやでえ」と会場の爆笑を誘っていたが、考えてみれば、この人口3万2千人の過疎の町で、こうした「認知症講座」が20回を重ねているということ自体が、ちょっと全国的にもありえないことだ。コロナで4年ぶりだから、本来なら24回、四半世紀続いているのである。
今回の庄原の認知症講座には、大阪大学の池田学さんに講演してもらった。
いうまでもなく、池田学さんは認知症医療の第一人者なのだが、同時に認知症医療を地域のケアと暮らしにつなげなければ、といち早く、その新たな取り組みを各地で提唱し、しかも先頭切って実践している人である。だから、10年ほど前にも、この庄原の現実を話したら「オッシャー(とは言わなかったが)」と、この認知症講演会にもきていただいている。
池田学さんの講演は「ひとり暮らしと認知症」というものだった。
今、地域では高齢者世帯と同時に単身高齢者世帯が増えている。庄原だと、高齢者夫婦のみの世帯とひとり暮らしの高齢者で、人口の半分を超える。
だが、池田さんはこのことをすぐにリスクとして「問題化」しない。
池田さんは、新オレンジプランでの「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会」から説きおこす。
高齢者がひとりになっても認知症になっても、馴染みの土地で「自分らしく暮らし続けること」を支える医療でなければならない、と。
大阪大学の池田学さんのチームは、ひとり暮らしの認知症の高齢者がいれば、作業療法士と医師がタッグを組み、そこに看護師などのスタッフも加わって、その暮らしを1週間ほどにわたって綿密に観察し、どのように暮らしたいのか、何がリスクとなりうるのか、本人と語り合い、その上でその人らしいひとり暮らしのための支援プログラムを作成していくという。
残念ながら、池田さんの講演についての詳細を語る紙幅にすでに余裕はない。というより、こうした話はそれぞれの地域の現実の中で語り合うことで、専門医療の汎用が浮かび上がるものだろう。
その後が恒例の「市民参加広場」で聴衆の質問を受け付けるのだが、なんとまあ、全員が質問用紙に記入したのではないかというほどにドサっと質問が寄せられた。
認知症治療薬のこと、物忘れのこと、車の運転について、あるいは「共生社会とは」という質問もあり、壇上の3人はそれぞれが違った視点から答える。いや、答えというより、そのことに触発された自分の思いを語ったのである。つまり、正解などはない、一緒に考えよう、ということに尽きる。
壇上の専門家が優位性にたつのではなく、むしろ住民こそが暮らしの主体であるとして、その地域の専門家である住民から問われたのである。積み重なり答えきれなかった質問用紙は、来年また来るまでにしっかり考えておいてね、そのように庄原の人たちに問われて、そして、今年の庄原の認知症講演会が終わった。
「またな」、そう言い残して和田行男さんは1960年代のモーリスミニクラブマンの愛車で名古屋に戻って行った。スピード出しすぎるなよ。
思えば、「自分のこととして」語るというのは、「庄原って、いいところでしょ」とつぶやく地元の人のその言葉に全てが集約されている、そんなふうに思いながら私も帰途についた。
また来年。