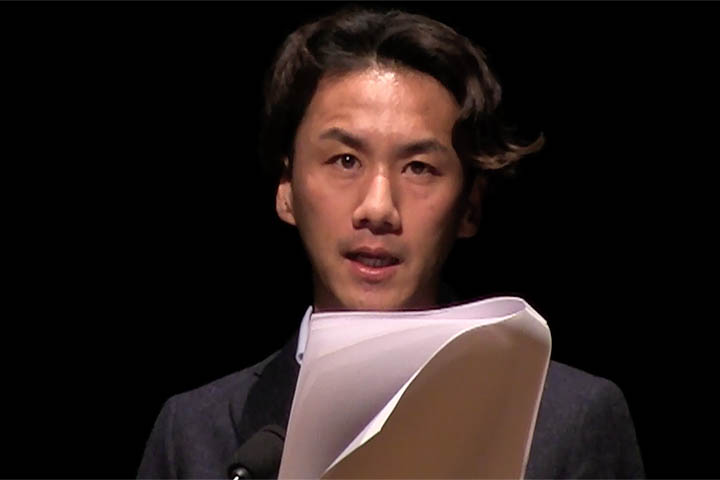▲桜が咲いた。開花する、というのは新しい時代への形容でもある。桜が咲くように、ときめくように、認知症を巡る新たな時代をどう構想できるのか。新たな時代は待っていてもやって来ない。花開く季節に時代を拓くために。
認知症が治る時代が来る。
といったことを話した。それも、よりによって認知症医療を担う医療者たちとの研究会でのことである。
私はいつも認知症について話をするとき私自身の立場として、医療者でも専門職でもなく、たまたまメディアの世界に長くいた経験と感覚から、社会変化のいわばエンドユーザーと位置づけられている生活者の側からお話するといったことを、まずお断りしている。
というのも、この社会には専門性への偏重があり、しばしば一般生活者はそこに揺さぶられてしまいがちなのである。だから私自身、専門性を拓く、ということをほのかに私の責務としているところがある。
そういえば、過日、ある講演会で医療ジャーナリストの市川衛さんとご一緒した。医療ジャーナリストと福祉ジャーナリストの講演というのもどこか怪しい感じがしないでもないが、その医療ジャーナリストの市川衛さんは、自らを「医療の翻訳家」と名のっているのである。なるほどなあ、医療というのは専門の牙城だからね。流石である。
私にも「福祉の翻訳家」といった気分がある。しかし私自身は誤訳だらけの翻訳家であろうし、第一、福祉というものを生活者の感覚に届けるのが翻訳だとすれば、それはどのように受け止めても構わないという地平に置かれるのが福祉なのである。
仮にその受け止められ方が違うとするなら、その福祉構築になにかしらの問題がある。福祉は送り手ではなく、常に受け手の側で機能する。福祉の翻訳家とするなら医療とは違って、生活者の感覚を福祉に手渡すように逆翻訳する必要があり、そこが難しいといえば難しい。
横道にそれた。
そうそう、認知症医療者を前にして「認知症が治る時代」をぬけぬけと語ったということだった。どのように語ったのか。
認知症の新たな治療薬が登場した。専門医療者の見解では、新たな治療薬はその最大の特性としては、疾患のメカニズムに直接働きかけるものであり、5年、10年ではそのメリットは一般には明らかに見えてこないとしても、将来的には、アルツハイマーを含む神経変性症の治療を変えるブレークスルーの可能性があるとされている。
ということは、やがては「認知症が治る時代」が現実のこととして視程に入ってきたと言える。もちろん「認知症が治る」とすっぱり切り替わるはずもないのだが、5年、10年なりのスパンで展望すれば、時代はある確度をもって、これまでの認知症を取り巻く状況と意識は様変わりすることを示している。
そして新薬の登場は、認知症基本法の成立施行と重なり、そこに当事者の社会参画という新たな動きも加わって、不思議な必然に導かれるようにして時代は大きく動いていく。
となれば、認知症基本法がたかだかと掲げた「共生社会の実現」へと、医療や福祉という枠組みを解体するようにしてどのように練り上げていくのかが私達のこれからの使命となっていく。
おおむね、そのようなことをおぼつかなく話した。
研究会では、グループでの討議もあった。そこでは、私が語った「認知症が治る時代」についての異論も出たという。認知症を含む慢性疾患などの治療というのは主にコンディション調整であって、だから「認知症が治る時代」とは言えないのではないか、ということだった。
いかにも私の言葉足らずだったのだろう。
一応発表スライドには、「認知症が治る時代?」と保留のクエスチョンをつけておいたのだが、でも「認知症が治るとは言えない」には、実は私がここで言いたかったことの本旨との若干のズレがある。
ここでの「認知症が治る時代とは言えないのではないか」とする医療者の発想には、今の自分たちの認知症医療世界が変わってしまうことへの無意識の怯えといった反射的な自己防衛から来ているのかもしれない。
実は現今の医療も福祉も「認知症は治らない」ことを前提に組み上げている。
地域福祉での「認知症とともに生きる」とは、認知症は治すことはできない、しかしそれを個の不幸ではなく、地域社会の誰もが自分ごととして受け入れ、社会に潜在する偏見や差別を乗り越える福祉的な意思表明を「ともに生きる」としている。
認知症医療もまた「治すことができない」と「敗北の医療」とまで言われた苦渋を呑み込むようにして「治す医療」から「支える医療」として歩みだし、ケアと連携し、診断後支援の拡充を図り、認知症の当事者発信を裏支えしながら「認知症とともに生きる」とする社会性に満ちた医療を形作ってきた。
では、認知症が治る時代とは、こうした「治らない」ことを前提としてきた医療や福祉にどのような影響を与えるのだろう。
それは、新しい治療薬が早期のアルツハイマーを対象にしたあくまでも進行抑制薬であるといった作用機序などの医療専門を問うているわけではない。
まず、「認知症が治る時代」とする想定を置いてみることだ。そうした未来のある地点から逆照射して、現在の認知症社会を洗い直す。
そこでは、新治療薬の登場に加えて、同時期に成立した認知症基本法、さらにはそこを貫く認知症当事者発信の動きを統合し、立体化する新たな構想力が問われることになる。
「治る」「治らない」というほとんど同語反復を超えて、医療と地域福祉、施策政策といった分野を個別とするのではなく、その共通と独自を織り上げて一枚のタペストリーを社会に敷きつめる。それが、専門を拓く共生社会の実現だ。
そもそも「治る」とはどういうことなのだろう。
「認知症が治る時代」とは、認知症がなくなる時代ではない。とすれば、医療や福祉にはこれまで以上に「支える医療」や「ともに生きる」ことの必然を濃厚にしなければならないと言っていい。それはなぜか。
新しい治療薬の登場は、「治すことができない」としてきた単色の分野に複雑な変数を投げ込むことになる。たとえば「治る」と「治らない」が混在することにもなりかねない。となれば医療は審問官のようにして、診断で「治る」と「治らない」に選別する審判を下す立場になるのだろうか。
それは誰にとっても望ましい事態ではないだろう。それはひとつには、「治る」ということを医療の枠の中だけで捉えることの限界がある。
「治る」ことを医療の成果、勝利とするのではなく、治ろうと治るまいと、ともに生きる社会に流し込む医療と社会との合意が必要だろう。
それは、地域社会がようやく到達した「認知症であろうとなかろうとともに生きる」とする共生社会への医療参画だ。
改めて、認知症が「治る」とはどういうことだろう。
法律の用語に、「瑕疵の治癒」というのがある。行政行為に違法状態があるとされても、後続する別の行為などによって元の法の趣旨にかなう状態になることを、その瑕疵(法的なキズ)は治癒した、元の本来の状態に治ったとみなすこと。それが「瑕疵の治癒」である。
法理から離れて想像を跳躍させれば、認知症と診断されても、そこにピアサポートと言った「ともに生きること」によって認知症当事者は新たな自分の人生に歩みだす事ができる。では、診断で本人が抱いた不安や絶望は誰が治したのか。それは医療の「治療」によってではなく、後続する別の行為としての当事者や地域社会が生み出した「治癒」によるとみなしていいはずである。
更に援用すれば、認知症が「治る」とは、「癒る(なおる)」に変換することができる。「認知症が癒る時代」が来る、と。
「治す」とは「治療」といった疾患への限定的な用語だ。対して「癒る、治癒する」とは、「癒やし」と読まれたり、原義に本来の状態に戻すとあるようにその包摂範囲は社会にひろびろと拓かれている。「治る」から「癒る」へ。認知症の医療モデルから社会モデルへの転換を今こそ、概念にとどめおくのではなく実態化する構想力が求められている。
端的に言えば、「癒る」とはリカバリー(recovery)である。
リカバリーとは「回復」ともされるが、もともとは精神医療での当事者に対して言われている。パーソナル・リカバリーとされ、主には、他者とのつながり、将来への希望、アイデンティティ、エンパワメントなどをその構成要素としている。
リカバリーは、医療や福祉に任せることはできない。ピアサポートと言った当事者の側の治癒力に負託して初めてリカバリーが立ち上がる。
とすれば、「認知症が癒る時代」とはそのまま「認知症が癒す(なおす)時代」と読み替えることができる。
癒す主体は医療や福祉、行政ではない。主体は認知症という存在であり、その当事者である。認知症は、膝を屈して深く傷つき、不安に満ちたこの社会をリカバリーする。
「認知症は社会を癒す(なおす・本来の人間の社会に回復させる)」、それが私達の目指す「認知症が治る時代」と言っていいのではないか。
|第276回 2024.4.11|