認知症では、中核症状とBPSD(行動・心理症状)に対して薬物を用いた治療を行うことがある。
中核症状の治療で主に使われているのは「抗認知症薬」で、認知症を根治させることはできないが、進行を抑えることが期待できる。現在は、1999年に発売された塩酸ドネペジルだけでなく、2011年にはガランタミン、リバスチグミン、メマンチンの3剤が新たに加わり、4剤が使えるようになった。ただし塩酸ドネぺジルはアルツハイマー病とレビー小体病、後から発売された3剤はアルツハイマー病にしか効果は期待できない。なお血管性認知症には、脳血流改善薬などが使われる。
一方、BPSDには抗不安薬や抗精神病薬、抗うつ薬、睡眠薬などが使われることがあるが、近年は薬で症状を抑え込むのではなく、環境調整や適切なケアで症状を改善しようという流れに変わっている。こうした流れの中、作用が穏やかで副作用の少ない漢方薬の活用が広がりつつある。
薬物治療
やくぶつちりょう
[ 薬物治療 ] 関連記事一覧
-

長寿の未来フォーラム「認知症のこれから ~本人と家族で考える“幸せ”とは~」
長寿の未来フォーラム「認知症のこれから ~本人と家族で考える“幸せ”とは~」
-

「認知症が治る時代?」 どう考えればいいのか
認知症が治る時代が来る。といったことを話した。それも、よりによって認知症医療を担う医療者たちとの研究会でのことである。
-

「影を慕いて 男性介護者の喪失と葛藤 」〜お父さん ありがとうを支えにして〜
正楽忠司さんが、若年性認知症と診断され5年前に亡くなった妻との日々を振り返ります。
-

「認知症予防と共生」、見るべきものは何か
政府の認知症大綱案の目玉とされた「予防」の数値目標が取り下げられた。認知症の人や家族団体からの猛反発があったことが修正につながったとされる。
-
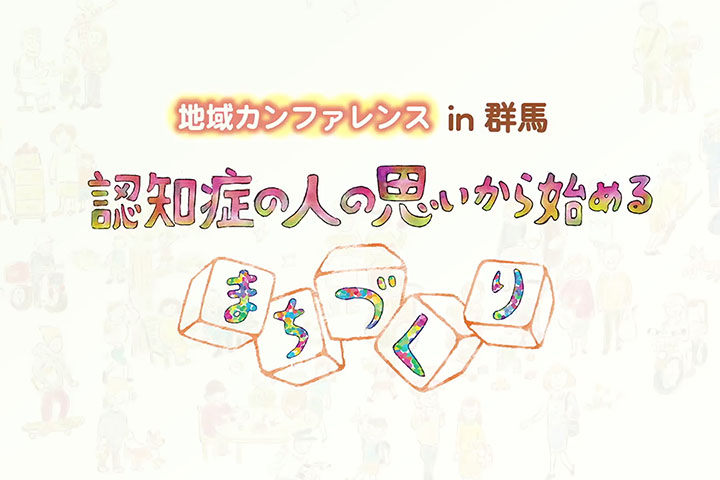
地域カンファレンス in 群馬 認知症の人の思いから始めるまちづくり
2016年3月に群馬県前橋市で開催された「地域カンファレンス in 群馬」の様子を紹介します。”人とつながり、ともに暮らす”。認知症の本人の声、思いから地域を見つめ、私たちのまちづくりについて語り合いました。
-

大分県佐伯市 まちなかカフェに集う ~役割があれば いつまでも自分の家で 地域で暮らせる~
大分県佐伯市で毎月開催される「まちなかカフェ」。ここを利用する武田キミエさんの姿を追いながら、どうすれば認知症の人が地域で生き生きと暮らしていけるかを考えます。
-

若年認知症 ~ともに生きる夫婦の日々~「彼女の言葉を待っている」 Part 3
若年性認知症になった田中裕子さんと介護をする夫・圭介さんの日々のリポート。
3回目は薬の調整で症状が好転した裕子さんの様子を紹介します。 -
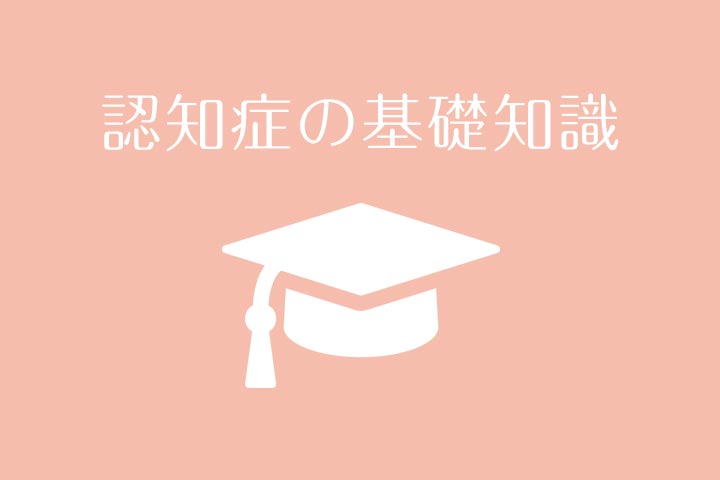
認知症とアルツハイマー病はどう違う?
「認知症」は病名ではなく、認識したり、記憶したり、判断したりする力が障害を受け、社会生活に支障をきたす状態のこと。この状態を引き起こす原因にはさまざまなものがありますが、「アルツハイマー病(アルツハイマー型認知症)」もそのひとつ。…
-
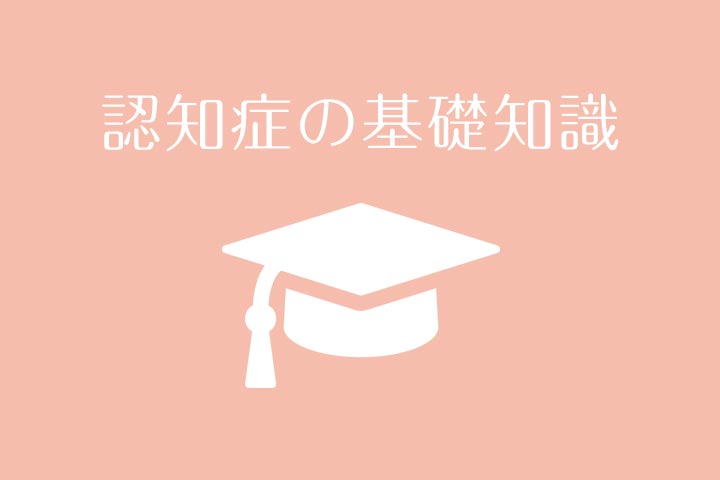
認知症って、どんな病気ですか?
脳は、呼吸や睡眠といった意識せずに行っている活動から、学ぶ、運動する、創造するといった高度な活動に至るまで、人間のあらゆる活動をコントロールする「司令塔」の役割を果たしています。…
-
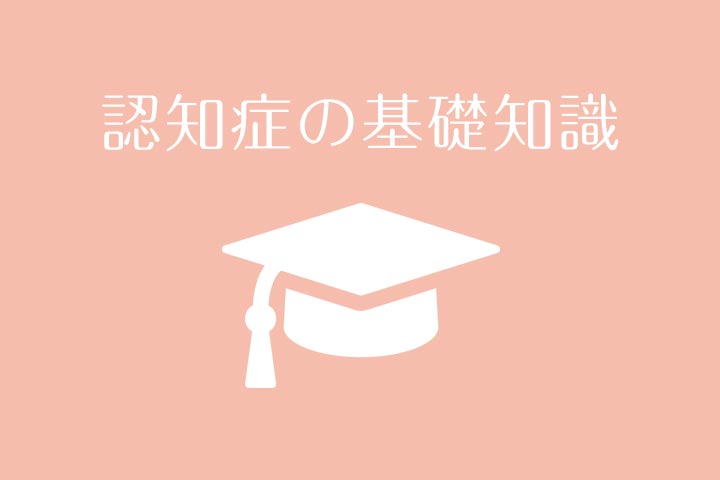
認知症は治りますか?
認知症を引き起こす原因によっては、手術や薬物療法によって症状を完全に解消したり、改善できたりするものがあります。例えば、慢性硬膜下血腫は、血腫を手術で取り除くと認知症の症状がなくなります。…
-

若年認知症~ともに生きる夫婦の日々~ 「彼女の言葉を待っている」 Part 2
58歳で若年性のレビー小体型認知症と診断された田中裕子さん(65)と夫の圭介さん(68)の日々を追った後編。新たな人生を穏やかに歩んでいこうとする2人の様子を紹介します。









