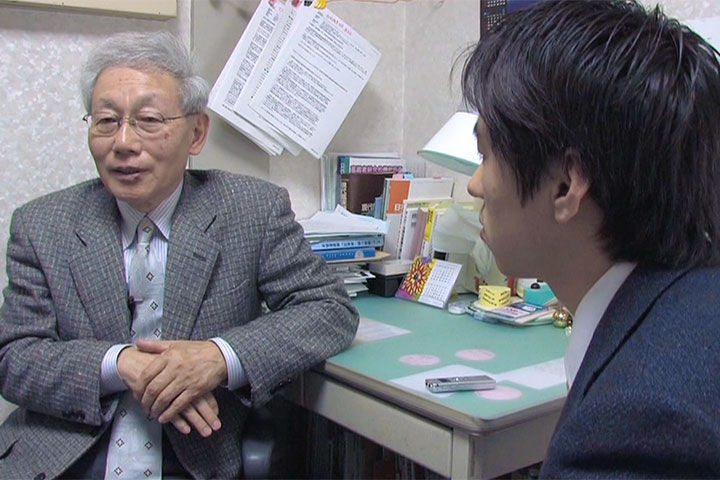▲ 厚労省は以前に厚生労働白書を「日本の1日」「100人で見た日本」というポスターで示した。なかなかお役所らしからぬ体裁で、日本の福祉の現場が一目でわかる。ただ、そのわかりやすさで、どこまでこの国の現実に向き合えるかは読み取る側次第でもある。
二人に一人ががんになる。
高齢者の五人に一人が認知症になる。
こうしたデータを何度目にし耳にしたことか。いや、私自身だって、こうしたデータを枕に語り始めることがある。
データ自体は、客観の凝縮であり、無機の数値である。しかし、私たちがその数値を読み解くとき、それぞれの願いや希望、そして思惑や絶望さえもが織り込まれて、一つの数値が耳元で悪魔のようにささやくこともある。
二人に一人ががんになり、2020年には高齢者の五人に一人が認知症になるという時、さて、このデータからどんな物語を始めればいいのか。
多くの場合、だからこれは誰もの課題であり、他人事でなく自分のこととし、ともに生きる共生社会の構築に向かおう、というロジックが展開される。
「みなさん、高齢者の五人に一人が認知症になる。あなたもなる可能性は高い。だからこそ、あなたの問題であり、認知症にやさしい社会なのです」とか言うわけだ。
他者のつらさ困難を思うとき、それを対象化するのではなく、自分のこととして引き受けることができるかは、共生と福祉概念の基本動作である。だからこのロジックに間違いはない。胸張って語っていい。
ただ、それを言うときに私自身、まるで教科書の活字体のようなよそよそしさも感じてしまうのはなぜだろう。私の修練見識が足りないのだろうとは思う。そうは思うのだが、福祉が現実に屈するのは、この教科書的な建前の中に閉じているからではないのか。
当事者発信が盛んになり、多くの当事者の声と接するようになった。
あるがん患者が言った。
「二人に一人ががんになると言いますがね、しかし、その確率は50パーセントです。丁半で言えばどっちの目がでるかで、大違い。賭場ですっからかんになるか、転がり込んだあぶく銭でニンマリするか、なんて比べ物にならないほどの違いなのです(うーむ、いかにも例えが不適切なような気がするが)。誰もの課題なんて、軽々しく言って欲しくないですね」
私はうなだれるしかない。
ここには、データ上の数字はあくまでも等量同質の単位とみなされるが、そこで示される人間の感情は同じ一単位の数字で考量できるものではあるまい、という糾弾が響く。そのとおりだ。
データの数値から溢れ出るヒトの感情の行き先が見えない時、「どうせ、誰にもわかってもらえない」「あなたに私のこのつらさがわかるものか」という他者に向けた負の感情が、実は当事者自身を孤立に追い込んでいく。
実はデータで語ること自体に、ある錯誤が潜んでいる。データは客観的な裏付けとして引用され、説得力を後押しするとされている。番組でも多用されるのはこのせいだ。しかし、当事者の多様な声を聴き取ったまなざしで見ると、実はこのデータ主義というのは、ある意味、健常モデルでの発想なのではないだろうか。誰に向かってデータの効力を発揮させているのか。
二人に一人、と言い、五人に一人という時、それはがんになっていない人、認知症になっていない人達に向かっての「なるかも」という蓋然の説得材料として使われているだけだ。この危険なところは、蓋然性、確率が高いほど、そうなった人を「不運の人」として位置付け、たまたま逃れた人を「ラッキーな人」とし、両者を醜悪な深さの谷で隔てさせてしまう。
これが世間の本音の衣をまとったスティグマを生み、「自分のこととして考えましょう」という建前の福祉は、この谷に一本のロープを掛けることさえできないのである。
深い谷を繋げるのは、やはり想像力しかない。二人に一人だから自分ごとで、希少がんのように10万人に一人だったら、埒外なのか。そのような社会を次の世代に引き渡すのか。そうではあるまい。
データは数量の多寡で、想像力の範囲に線引きし出し惜しみさせてしまう。
それは私たちがデータに馬鹿にされているようなものだ。私たちの想像力の及ぶ限りの世界の力があるのではないか。愚直なまでに私たち自身の想像力を絶えず検証し鍛えるしかない。
認知症社会は、私たちの想像力の広がりと交差の中に描く。