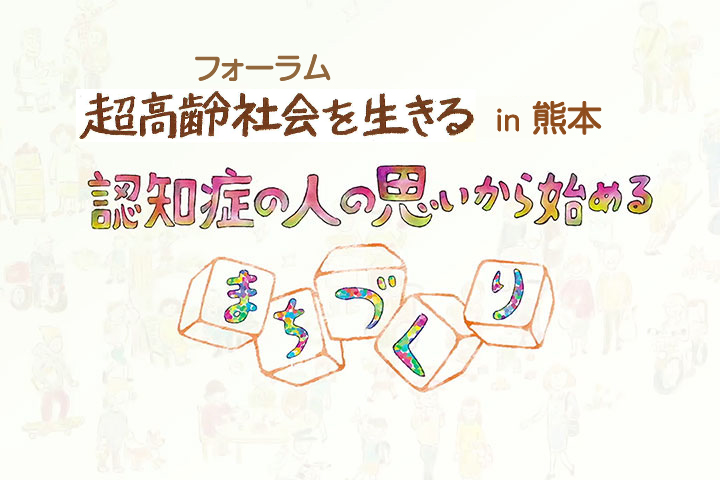▲ 語るべきことはあるか、を語り合った仲間。上段、朝日新聞記者、生井久美子氏。下段左、NHKディレクター、川村雄次氏。上段左は、ご存知、ロダンの考える人。国立西洋美術館の「地獄の門」の上で考える人は何を考えるか。ダンテの「この門をくぐるものは一切の希望を捨てよ」、寓意に満ちた「考える人」である。
NHKラジオ深夜便の「認知症カフェ」に出演した時、ディレクターの佐治真規子が、最後にひとつお伺いしたいのですが、とちょっと改まって聞いた。
「町永さんは、どうしてそんなに認知症に熱心なのですか」
虚をつかれた感があった。いやいやとんでもない。熱心というには私はいかにも不似合いで、熱心さで言えば、あの人、かの人と様々に地域や施設で懸命に活動している仲間の顔がたちまちに浮かぶ。
とは言え、この番組自体は、幅広い聴取者が対象の深夜便である。ここで押し問答をしても始まらない。その時は、この社会のこれからの少子超高齢社会を不安とおびえの中に描くだけでなく、認知症を視点に眺めれば、向き合う課題もくっきりと見えてくる。だから、認知症こそが新時代を拓くのだと、少しの気負いの中、そんなことを話した。
あとになれば、多少なりともメディア体験があったものだから、番組のシメに調和的な一般論でまとめてしまったなあ、と反省した。
決して間違ったことを話したわけではなかったが、何か、もやもやが残り、マイクの前で喋るのは、いやはや難しいものだ、などと久しぶりの感慨にふけったりした。
その時、ふと思い出したのが、だいぶ以前の仲間との雑談だった。
二年ほど前、都立大学近くで「認知症当事者」の催しがあり、そこで出会ったメディア仲間と会場を出たあと、なんとなく近くで話そうということになった。
その仲間とは、NHKで認知症をテーマに意欲的な番組を次々に送り出していたディレクターの川村雄次と、朝日新聞記者で、当時、認知症の人々の暮らしと声を取材した「ルポ・希望の人びと」の出版をした生井久美子、そして私の三人だった。
三人が、その日参加したのが、町田BLG!の前田隆行が5人の認知症の人と語り合うというものだったから、言ってみれば、認知症の現在地に立ち会ったという昂揚感もあり、そのまま分かれるのも物足りなく、ちょっとそこらで、ということになったのだが、まだ陽は空に高く、駅に向かってゾロゾロと歩きながら、通りの中程に見つけたのが、創作中華料理とカフェを兼ねたような歴史的味覚的不安定な雰囲気の小さな店だった。
「もうやっていますか」と誰もいないガランとした店に入ると、「オマエたち、食事あるか、よろし」といった中国人ではなくて、テレビショッピングの司会者のような妙にシャキシャキのマスターが出てきて、とりあえずビールと、マスターの薦める小皿を頼んで席についた。
それから、イベントの感想などあれこれを話し、どうしてそういう流れになったのか、「語るべきことは何か」といった話になった。
こういうのを話すのが好きなのだ、メディア人というのは。
夕暮れ近しとは言いながら、昼のビールのせいもあり、その時、私は二人にこんな話をした。
「語るべきは何か、と言うが、そもそも私たちは語るべきことを持っているのだろうかね。
いや、私自身、そう思う時があるんだ。
私自身の生活はこれまで、それはまあ、盛大に幸福であると言い切ることはできないにしろ、では不幸だったかといえば、そんなに過酷な不幸にも遭遇していない。
むろん金持ちではないが、そうかといって飢えや貧困の厳しさの中にあるわけでもない。
振り返れば、確かに仕事につまずいたり、悩んだり、組織に呪いの言葉を吐いたりもした。しかし、そんなことはコップの中のことで、シニカルに見れば、毎日をそのまま受け入れ、そして送り出すような日常を過ごしてきたとも言える。
幸福でもないが、不幸せでもなく、金持ちではないが、貧窮でもない。起伏はあっても日常は同じように流れ行く。思えば、ごくごく平凡で、中途半端な人生だ。
こんな私に語るべきことはあるのか、と正面切って自問すると、そこがあやふやなのだな。
この世の現実を切り裂くような、自分の生命かけるような語り方を、私はしたことがあるのだろうか。
いや、それなりに厳しい現実も経験はしているのだよ。でもそれがどうだと言うのだ。仕事なのだから、といえばそれまでだ。
今、ふと思うことがある。私は語るべきことを語っていたのだろうか。
職能の義務感の中で、それを使命感で言いくるめ、何とか自分の語るべきこととして、世に送り出してきただけではないのだろうかと、今現場を離れて、そんなことも考える」
私はぬるくなったビールを飲み、川村雄次はなぜか日本酒で小籠包をつまみ(日中友好なのだろう)、生井久美子は少女のように瞳をくるりとさせて、アイスティーを一口飲んだ。
店の前の通りを行き来する人が多くなり、陽が向こうのビルに傾いている。
「語るべきことを、私は持っているのだろうか。
私が認知症の人々に関心を持つのは、彼ら彼女たちが語るべきことを持っているからなんだ。彼らは、これまでの自分、現在の自分、そしてこれからの、つまりは未来の自分までを、統合的に、自律的に、そして意識的に見つめ、語る。
それは、時間軸にそって進行形の現在の自分を、絶えず検証しているようなものだ。
彼らは語らざるを得ない。
でもね、語らざるを得ないと言うのは、それはすでに私たちの側からの他者のまなざしなのだ。
彼ら彼女たちは、自身の深いところの内圧に突き動かされて、自分の語るべきことを、ただ語る。もちろん、この場合の「語る」と言うことは、別に言語性を持たなくていい。「存在が語る」、といった具合にね。
語ることをやめた認知症の老人のたたずまいは、とても雄弁だ。
そのような、私は語るべきことを持っているのだろうか」
西陽が店の中に差し込んできても、相変わらずこの小さな中華カフェに客は誰も訪れない。
二人とも、自分の中の何かを見つめているように黙っていた。その沈黙に励まされるように、私はまたビールで口を湿らし、話した。友よ、この話はもうすぐ終わる。
「だから、彼らが語らざるを得ないのではなく、そこにあるのは、私の語るべきことなのだ。
あなたの言葉は、私の言葉であり、私のやり過ごしてきた無自覚な時間と現在の私と、そして未来の私を、あなたは語ってくれている、そう思う時がある。
彼ら彼女たちは、絶望と希望を、誰かの言葉ではなく、自分の言葉で語る。そのように私も、私を語ることができるだろうか。
絶望は、「私」が与えてしまったことであり、希望は、「私」とともに創り出すものであり、そして、あなたは「私」なのだと、告げることができるか。
中途半端な人生の私が語るべきことは、彼らの言葉にあるような気がする」
店を出ると、夕暮れのメトロポリスのいつもの光景だ。店にはついぞ、一人の客も来なかった。今思うとあの店は、次元の違うパラレルワールドの空間だったような気がする。
さ迷い込んで垣間見たのは、なんだったのだろう。
しばらくして、川村雄次から「いい話だった」とメールが来た。
(文中敬称略)
|第108回 2019.7.3|