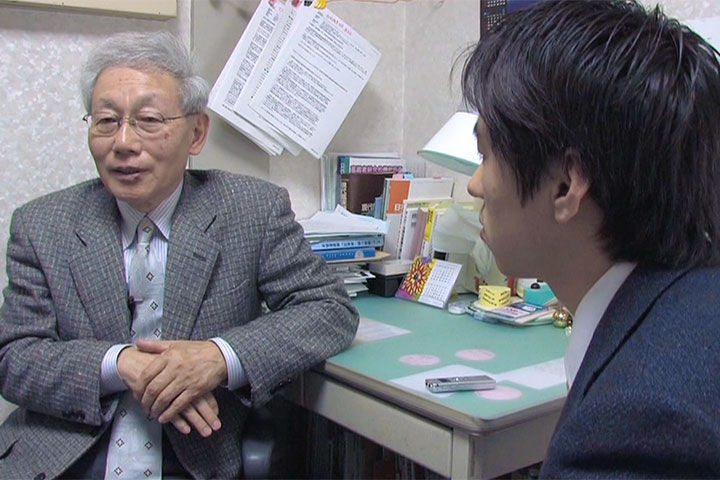▲これまで10年以上にわたって市民フォーラムを開催してきた。何を語り合ってきたのか。つまるところ、それは「安心の社会」についてである。コロナの時代の不安の中、改めて「安心の社会」への転換が求められている。くらしの原点としての「安心の社会」を語る。
コロナの時代はこの世の中に何をもたらしたのか。施策や新しい生活様式など様々な側面が取りざたされているが、その騒擾を突き抜けて人心の底に横たわるのは、不安ではないだろうか。
何かつかみどころがなく説明のつかない不安が、誰もの心に沈殿してしまった。
その正体がわからないことが不安なのか、逆に情報過多が、混信して何も映らないテレビのホワイトノイズのような不安を生み出してしまったのか。
東日本大震災の時、原発事故の被災者のつぶやきが今も記憶に残っている。
「国は安全だというが、私たちは安心できない」
「安全」はデータの指し示す基準であっても、「安心」は、そこに暮らす人々の実感でしか成立しない。安心は文字通り人の心の状態だから、安全は安心のひとつのてがかりであっても保証にはならない。
コロナの時代の底知れぬ不安は、単に見えないウィルスの侵攻がもたらしたというより、実はこの社会の現実をあらわにしたことにある。少子超高齢社会のこれからを誰もまともに向き合うことなく無策なまま手をこまねいていたことを、ウィルスは暴いてしまったのだ。
とは言ってもこの超高齢社会のこれからについては散々議論され、社会保障の重要議題ではないかと見る向きもあるだろう。もちろん、その通りだ。しかし、それで私たちは安心できるのだろうか。
安心の社会とはどんなものか。
認知症を語る時、「認知症になっても安心の社会」とする共生理念が掲げられてきた。今それを進化させ、「安心して認知症になれる社会」とされている。
共に「安心の社会」を語っているわけで両者の正誤の問題ではないのだが、ここに本質的なヒントがある。
そのことはこれまでも記してきたのだが、このコロナの時代を語るときに大切な視座になると思うので、今回はそれをもう少し丁寧に辿ってみたい。
「認知症になっても安心の社会」というのは、とてもわかりやすい。すっと誰もの心に染み込む。しかし、わかりやすさにはあやうさもあって、実はそれは、誰もの共有している「常識」に響くからである。その常識とは何か。それは「認知症になっても」という前段の字句に潜む「認知症になると大変であり、つらく困難な暮らしになるはず」という思い込みだ。この「常識」を前提にして、この標語は語られている。
少しシニカルにこの標語の根底を探ってみれば、それはこんな通俗の思いなのかも知れない。
「誰だって認知症にはなりたくはないだろうが、仮になったとしても、大丈夫、私たちがきっとなんとかしてあげよう。だから、安心してね」
そう、ここにあるのは確かに馴染み深い地域共生の合言葉であり、素朴な善意である。
が、こうした心やさしい人々の心情には実は、認知症になると大変なのだという負の側面が刷り込まれていることに当の本人が気づいていない。そしてこれが社会の常識、通念としていつまでも温存されていく。
「認知症になっても」という言葉に潜むもの、それは多少意地悪く探れば、今施策としても打ち出されている「認知症予防」の徹底との表裏の関係にあり、予防にも関わらず認知症になってしまっても(医学的には予防にエビデンスはないのだから)、その受け皿として「認知症になっても安心の社会」が用意されているのかと、勘ぐりたくもなる。
そこにあるのは、「認知症になってしまった人」という他者性へのやさしさの擬態である。この言葉には、「認知症にならずにすんでいる」側の無意識のマジョリティと健常性の優位が感じ取れる。
それでは、これを当事者の視点から語るとしたらどうなるか。
それが「安心して認知症になれる社会」なのである。同じようなことを言っているようだが、ここにあるのは社会の側のパライダイムシフトを目指すものだ。認知症であろうとなかろうとユニバーサルな「安心の社会」を打ち出し、ここでの「認知症」は問題化される社会の重荷ではなく、社会のパラダイムシフトをうながす駆動力としての位置付けであり、確かな包摂の社会を描く。
認知症当事者の発想から、改めてこの社会を捉え直す機運は、そのままこのコロナの時代を解き明かす視点である。
この新型コロナウィルスの感染拡大は、より根深くはこの社会の脆弱を浮き彫りにしている。
感染者を出した企業や施設は、今なお「多大なご迷惑を」と謝罪し続け、そこに中傷や差別が集中するのはどうしてだろう。
それは認知症になった人がその最初に、迷惑をかける、申しわけないという感情に襲われるのと、構造的には同じである。認知症もコロナ感染も、誰もがなりうるとされ、誰もが当事者と言われながら、受け入れられていない。
それは常に認知症もコロナ感染もひたすら「なってはならない」と問題化される文脈でしか語られていないからだ。もちろん公衆衛生での感染予防の手立て、新しい生活様式の徹底は必要だろう。しかし、医療や介護体制の備えが万全であることの証明が、毎日の感染者数の数字の変化でしか語れないのなら、感染することの負の側面だけが肥大する。
「ウィズ・コロナ」という以上は、感染予防だけでは、どうしても排除が前景化する。それと同等の力を込めて感染した人々との共生意識を呼びかける必要があるはずだ。
それが「安心して感染できる社会」というものである。
先行モデルとしての「認知症」は、「認知症とともに生きる社会」という共生モデルを打ち出し、そして今や「リビング・ウィズ・デメンシア」をさらに「リビングウエル・ウィズ・デメンシア(認知症とともによく生きる)」と深化させている。よく生きる、なのである。
では、リビング・ウィズ・コロナは安心をもたらすのか。
施策者の記者会見のツボは、明日の新聞の見出しになるような「おいしい」フレーズを打ち出すことだと言われる。ウィズ・コロナはその意味では大変うまいことハマったわけだが、その意味するところの社会転換の取り組みはどこにも見られない。どうもウィズ・コロナは単なる枕詞だけに消費されてしまっている。
安心の社会というのは、これまでの社会を組み替えることだ。
「安」という文字は、家の中に女がいるという象形で、「安心」とは暮らしの場が安らぐということだ。つまりは、安心の社会とは「女性の論理」で組み立てられる社会のことだ。
対して、これまでの私たちの経済社会は、いわば男の論理が貫いてきた。それは言ってみれば「大きくて強くて早い」ことに至上の価値を置く論理である。この国の奇跡の経済成長は、まさにこの男の論理の成功体験の蓄積だった。
一世を風靡したテレビの「プロジェクトX」が常に、「男たちは」というナレーションで始まる「男たちの物語」だったことは、そのことをよく表している。
しかし、この男の社会はとっくに行き詰まっていた。誰もがそのことには気づいていながら強力な惰性に引きずられて弥縫策を重ね、生産と効率から外れた認知症の人や弱者をスカスカのセーフティネットから振り落とし、そしてこのウィルスはいとも容易にこの強いはずの社会のあちこちの綻びから侵入してしまった。
思えばこの新型コロナウィルスの事態の当初、この国の指導者たちは口々に制圧、国難、戦いに勝利と、勇ましい軍事用語を連発して既成の社会体制の防衛を叫んでいたのだ。
コロナの時代の私たちの抱く不安は、この社会の仕組みをどう組み直していくかその展望を誰も示していないことにもある。
コロナの時代の適合モデルとは、それは言ってみれば、安心の「女性の論理」の社会システムへの転換である。
それは「小さくても弱くてもゆっくりでも」認め合う社会であり、それが、しなやかに強靭な「安心の社会」と言えないだろうか。
それは巨大な建設と開発に象徴される男の論理に対しての、「はぐくみ、いつくしむ」くらしの社会の姿だ。
どのようにして「安心の社会」に組み直すのか。
ウィズ・コロナというのであれば、予防対策を徹底した上で、失われ途切れた地域の人と人とのつながりを回復する手立てを考えていい時期ではないか。一方で経済対策としてのGo Toトラベルのキャンペーンがあるのなら、今もっと必要なのは地域の関係性をつなぎ直すための地域活動の振興策なのではないか。
それこそが、ウィズ・コロナであり、「安心して感染できる社会」というウィルスに対する社会免疫を持つしなやかに強い新たな市民社会システムというものである。
「安心して認知症になれる社会」
「安心して感染できる社会」
正しい不安は、その向こうの安心につながる道でもある。