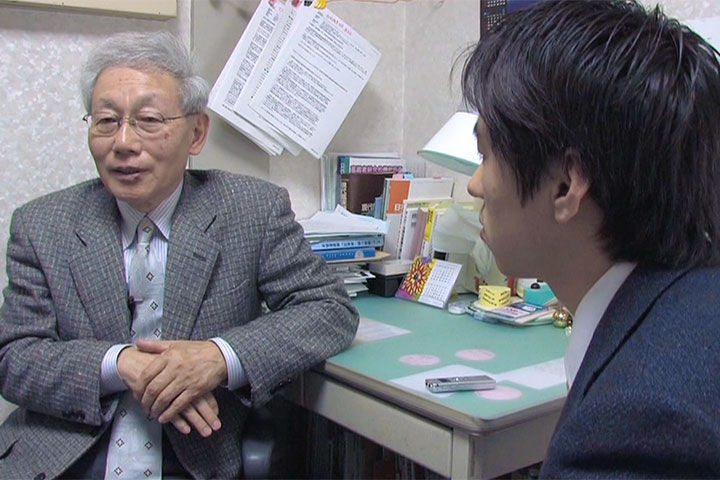▲「福祉」を語って気づいたのは、真っ向から福祉の現場に向き合っていると、かえってその現実に縛られてしまいがちなことだ。この先の新たな「福祉」とは、やはり当事者のまなざしを自分に重ねることで見出すしかない。下段左から町永氏、迫田朋子氏、内多勝康氏。
福祉を語ることに皆さんはどんなイメージを持つだろうか。
私が現役の頃、番組で「福祉を語る」というタイトルで各界の著名人にインタビューするコーナーを企画した。今から20年以上前の話だ。
さっそくディレクターと手分けして出演交渉である。
ところがこれが難航した。お相手は名だたる実績を持つ作家、学者、文化人といった人々である。あえて、福祉が専門でない人に日頃の思いや言論から福祉を語ってもらおうというものだった。断られるパターンは大体同じである。
「いやいやいや、私ごときが、」なのである。
つまりここには福祉を語るという事は、とにかく立派で正義で揺るぎないものという思い込みがある。もちろん謙遜なのだがそこに、間違ったことを語ってはならないとする感情が「いやいや、私ごときが、」となったようである。
その福祉の語り口が変わってきている。
そんなことに気づいたのは、先日、NHK厚生文化事業団の企画で、福祉の過去、現在、これからを語り合ったときのことだった。
NHK厚生文化事業団は去年、創立60年を迎えた。
60年前、この国は空前の成長と繁栄のとば口に位置していた。
福祉事業を展開する社会福祉法人であるNHK厚生文化事業団がそうした時代にできたことには意味がある。
事業団ができた1960年は所得倍増でお馴染みの池田内閣ができた年である。
あるいはどこかで、のちに世界の奇跡と言われる成長路線を駆け上っていく中で、直感的にその危うさを感じ取っていた一群の人々がいたに違いない。均衡を図るためにも、この社会への新たな福祉の投入が必要だ、そうした人々の想いによって、放送と連動する社会福祉法人、NHK厚生文化事業団が生まれた。
そこには、事業団を生み出した公共放送のNHKで、戦後からの日々の暮らしを伝え続けてきた放送マンの感覚が生かされたのかもしれないし、60年安保という生々しい権力へ対峙するようにして、人間へのまなざしが強かったのかもしれない。あの頃は、そうしたメディアの初々しい健全さがあった時代だった。同時に、その時の思いから今の公共放送をえぐるように検証することも必要だろう。
その厚生文化事業団が、60周年の記念誌を出すことになり、かつて放送の現場で福祉に関わったOB、OGの鼎談を企画した。迫田朋子氏、内多勝康氏、それに私の3人である。今はそれぞれが放送の現場を離れて独自の活動に関わっている。
鼎談内容については、後ほど冊子になるのでそれに任せるとして、ここではあらためて福祉をこのコロナの時代相に考えてみたい。
私が思ったのは、「福祉を語る」というこの設問の立て方が既に違っているのかもしれない、ということだ。
福祉という発想から入ると、そこに待ち受けているのは制度や政策、あるいは資格といった枠組みなのである。書店で福祉のコーナーに行けばよくわかる。そこに並べられているのは福祉六法や介護保険制度の解説本、福祉士資格教本などだ。そうではなく、より良く生きる力や糧としての福祉はどこかと探し回れば、それは人気作家の人生読本やエッセイということになる。
福祉から語り始めると、どうしても事象を対象化してしまう。貧困であり、障害であり、認知症であったりする。むろん、制度政策はそのことから始めていく。誰が貧困者であり、障害の困難を規定し、認知症の診断から支援につなげていく。大切なことであるのは間違いない。しかし、そこに「私」はいない。冷ややかに対象を見るまなざしだけが残ってしまう。
以前、やはり番組を担当していた頃、毎年新たなディレクターが福祉番組班にやってくる。当時、そしてたぶん今も福祉番組は志望者が多い狭き門だった。じかに人間にとことん向き合って番組が制作できる、そんな思いもあったろう。実際優秀な才能が集まる部署だった。
その新人ディレクターの歓迎会で、それぞれが抱負を述べた。
あるディレクターは頬を紅潮させてこう言った。「弱者の側に立った番組を作りたい」
まっすぐな志であろう。が、そこに意地悪なキャスターがいた(私である。すまない)。
「ふーん、弱者のために、ネ。するとキミは何者?」
毎年の洗礼なのである。弱者を語るその自分が、知らず強者の側に立っているかもしれない。ある意味、メディアは権力である。だからこそ、常に自分を繰り込んだ当事者として社会を見ないと、福祉は描けない。
介護福祉士で、認知症ケアの実践者で知られる和田行男氏は、認知症への偏見は専門職に根深いところがあって、市民の側の方が共生意識では先行しているところがあると述べている。
また、「このゆびとまれ」の富山方式と言われる福祉の革新をした惣万佳代子氏との語り合いでは、なぜこうした革新が実現できたのかという私の問いに対して、「それは、私が福祉を学んでいなかったから」と微笑んだ。
むろん両者とも福祉への信頼と愛情があるからこそ、こう発言できるのである。私はむしろ、こうしたことを語ることができる「福祉」の底力と復元力を羨望した。
両者にあるのは、「福祉」が常に「良きもの」としての前提から発想していることへの批判精神である。
よく言われる「目の前の人のための支援」といった美しい言葉も、それはどこかで、この社会に可視化されず声にならない声を振り落としていることに気づくはずなのだ。
目の前には見えない隠されたニーズを探り当てる徒労に近い営為がなければ、新たな福祉は形作られない。
年若い専門職の「笑顔とありがとうがやりがいです」といった無邪気な抱負はまことに微笑ましく、そのことを社会の希望としたい一方で、どこか、本来の「困難な人々の自己実現のための支援」が逆転し、自分の自己実現のための福祉支援となってはいないだろうか。
当事者の側から見るということは、生易しいことではない。絶えざる自己検証というイバラの道かもしれない。しかし、そのことで自分と社会を大きく変えていく本来の福祉観が生まれてくる。
福祉の概念は大きく変わっている。
NHK厚生文化事業団のような社会福祉法人はもともと、戦争孤児や戦後の困窮者の救貧活動を、篤志家からの経済援助や教育支援を元手として始まっている。当初から行政の手が届かないところに,篤志家と言う、いわば人の思いを結集させるようにして手を差し伸べてきたのである。
そのNHK厚生文化事業団は、60年を迎えてシンボルマークも変え、ホームページの体裁もひきこもりや認知症、うつなどを個人の課題としてではなく、社会の側の課題だとして当事者の声で問いかけるスタンスで社会への提言性を高めている。
「福祉とは」と言う大上段から語ればたちまち行き詰まるが、当事者の声を聴き取りながら共に生きる道筋を見つける新たな福祉像を創造しようと社会に呼びかけている。
社会を強くするのは、それぞれの「弱さの公開」がされることだという。
「福祉を語る」ことが「私ごときが、」と、間違うことを恐れ、正しいことのみを言わねばならない「福祉の強者」の社会は、実は何か後ずさりしていく社会かもしれない。
長く続くこのコロナの時代は、誰もが自分の「弱さの公開」の日々だった。
その共通体験の中、私たちは弱者のまなざしでこの社会を見つめ、そのもろさと、そしてだからこそ人は一人では生きていけず、共生への道の必然に否応なく気付かされた。
福祉の再定義が必要だ。
認知症の人が認知症を語るとき、ほとんど常に「私は」と語り始める。
医療者や専門職の人が認知症を語るとき、「認知症とは」と語り始める。
「福祉を語る」とは「私」を語ることである。
心優しい強者ではなく、思い惑う弱者である人々こそが、内発する自身の力に気づき、
あらたな福祉の発信を生み出すことができる。
60年前と同じように私たちは今、ウイズ・コロナと少子超高齢社会の中で、時代の分岐点にいて、同時に東日本大震災から10年を迎えた。
私たちは、「私たちの福祉」の時代の交差点にいる。