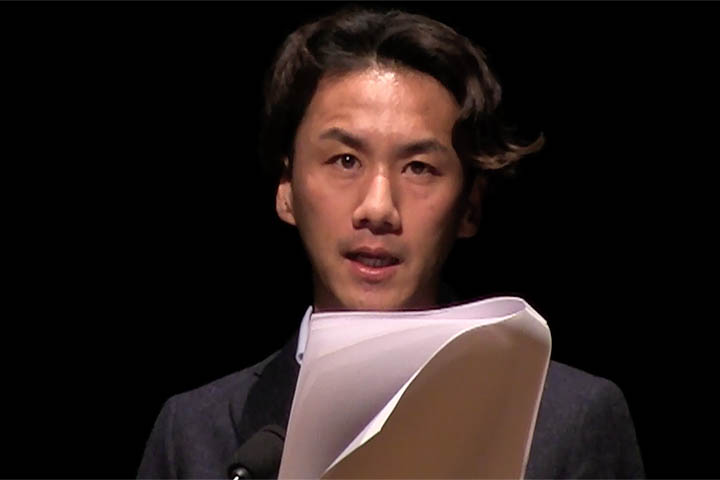▲新型コロナウイルスの日々は確かさが失われたことでもある。誰もいない公園の日時計は、確かな時を映す。曇りの日、雨の日には時を示す日射しはないが、確かな「時」が失われたわけではない。私たちの確かさとは何か…
新型コロナウイルスとの歳月がもう一年を超えて、なお収束は見えていない。
この事態に流されながら、どうも一人ひとりが同じようなものとして扱われているような気がしてならない。感染者、高齢者、若者、人流。名前や顔もある一人ひとりが消えていく社会。
認知症の人は、認知症というレッテルを貼られた途端、昨日までの自分と今日の自分に変わりはないのに、全てが奪われ「認知症」という別の人格とみなされ、自分でもこれから誰になっていくのかわからない不安に落ち込む、とこれまで語ってきた。
思えば、この事態が起きた去年の今頃は、不安や怯えもあったものの、どこかでこの事態に連帯感や高揚感を共にしたところがあった。
「今、私たちにできること」「ステイホーム」といった呼びかけに多くの人が応じ、この事態を懸命に切り抜けようとするそれぞれの社会意識が芽生えたところも、確かにあった。
この事態が起きた当初、こんなことがしきりと語られた。
新型コロナウイルスに誰もが感染しうるということ、それはまた、誰もが認知症になりうることと重なり合う。それは誰もが「当事者」であることで、ここに共生社会の基盤である「じぶんごと」が成立するであろう。
誰もが当事者化する社会とは、誰もがじぶんごととして認知症を捉え、共に生きる社会への確かな道筋になる。ポストコロナの方向性が見えてきた、とそんな思いも芽生えたのだった。
が、そうはならなかった。
それどころか、感染した人やクラスターが発生した高齢者施設、あまつさえ医療、介護にあたる人にまで、誹謗、中傷、差別が相次いだのである。
新型コロナは、じぶんごとの当事者を生み出すどころか、これまで「共に生きる」とか「地域共生」を掲げてきたはずのこの社会の脆さや醜さを一気に吐き出した。
どこでボタンを掛け違えてしまったのだろう。
それはどうやら、当事者性を引き出すのに、「誰もが感染しうるから」あるいは「誰もが認知症になりうるから」と言う不安を前に置いてしまったことにある。
感染するぞ、認知症になるぞ、と人々の不安感をあてにし、その不安を煽ることで、だから「当事者」であるべきだと言われても同意できるわけがない。それはある種、仲間にならないと感染しても認知症になっても知らないぞ、と恫喝しているようなものだ。
ひきこもりなど思春期、青年期の精神病理学が専門の精神科医、斉藤環さんは「パンデミック下の常識」とは、感染しないように行動するのではなく、「誰もが感染しているという前提でふるまうこと」とし、それを汎当事者性であるとした。
つまり、自分の前に他者を置き、その人に「感染させないこと」がパンデミックを乗り越えるための誰もの当事者としてのふるまいであるとしたのだ。
「感染しないこと」と「感染させないこと」、この二つの行動原理の違いには、あるいは、この社会を拓いていくヒントがあるかもしれない。
確かに公衆衛生の原則で言えば、感染拡大を防ぐには一人ひとりの「うがい、手洗い、ディスタンス」である。実際にその効果は大きい。
が、ここに怯えるような感染恐怖が貼りつく時、電車に乗っても周りの人が全て感染リスクに映り、それはそのまま他者を敵視する感情を湧かせ、マスクをしていなかったり、出歩く人を見ると、自分はこんなに我慢しているのに、あの人は自分ほどに我慢していないと攻撃的になっていく。他者との接触を避けるようにという呼びかけが排除に転化し、そして差別と中傷となっていく。
「感染したくない」が「感染は許せない」と、自分と他者とのつながりを自分自身で断ち切って、「感染予防」の見えないバリアーで「利己」を囲い込み、更なる不安に落ち込んでいく。
危ういのは、こうした人々がとりわけ性悪であったり反社会的人物ではなく、あなたや私のように律儀な地域の生活者であったりすることだ。
対して、「感染させないこと」とするのは、まず自分を感染者とする当事者と規定する。(ついでに言えば、自分が認知症であるとするまなざしでこの社会を見れば、ずいぶんと自分と社会が違った風景になるはずだ)
そして、そこからの自分自身の検討と変容の確認である。「自分が感染しているとしたら」どんなことを考え、注意し、行動するべきか。同じ「うがい、手洗い、ディスタンス」を励行してもそれは、させられる行動ではなく、能動的な自分の意思の反映だ。
ここにあるのは、まずもって他者への関心である。感染させない、というふるまいは他者と自分との関わりなのである。つまり、接触しない、つながらないという行動自体が、他人との関わりを、表面的には途絶えたように見えても、内面ではより深く維持させていく。
「感染させない」というのは、いってみれば利他の行動と言える。しかし、もうお分かりだと思うが、その利他というのは、めぐるようにして、あなたの新たな利己となって帰ってくる。
利己と利他というのは区別したり対立する概念ではない。それぞれ一人ひとりの中には、利己と利他というものが同居している。
最近、どうやらこの「利他」がさまざまな場で論じられている。徹底して道徳実利的な提唱もあれば、主義としての多義的な利他を立ち上げて論じ合ったりと多彩である。
大阪大学の経済学の堂目卓生教授は、アダムスミスの研究者としても知られるが、そのアダムスミスの国富論と並ぶ「道徳感情論」に教授は注目し、利己と利他の一致を述べている。
アダムスミスは「国富論」での、「見えざる手」で知られた自由主義を無条件に主張しているのではなく、「道徳感情論」では、人間の本性には、自分の利益だけでなく、他者に対する共感から道徳的な判断をする心の働きがあるとしている。
つまり、他者に対して共感する力が利己と利他を一致させるという。
例えば胸が苦しくなった人に共感すると、その他人の痛みが伝わってきて自分の胸も苦しくなる。なんとか治したいと思うが、原因は他人の側にあるので、「大丈夫か」とさする。そして他人が「はー」と息をつき楽になると、同時に自分も楽になる。
これ自体は利他の行動に見えるが、この行動は、相手の苦しみを取り除いているのではなく、自分の苦しみを取り除きたいという気持ちから生まれているので、利己でもあるとする。(共感革命/日本フィランソロピー協会)
ここで注目したいのは、利己と利他を区分するのではなく一致するものとし、利他の行動は、利己を含んでおり、それをつなぐのが「共感」であるという部分だ。
共感というと、今の、便利に使いまわされた「共感」しか思い浮かべないかもしれないが、ここでの共感は資本主義勃興期の不安定な社会相での人間回復の分厚な言葉であることには留意しておきたい。
この新型コロナウイルスのもたらした事態の中で注目された利他であるが、それは道徳でも戦略でも主義でもなく、私たち誰もに内在する「利他によってしか自分は存在していけない」という実感だ。
そして、論を跳躍させれば、利己と利他、あるいは利他から利己への往復は、この社会の舞台転換につながる可能性がある。
思えば、認知症の人は、自身の利己のために利他に歩み出した。
自分の奪われた自分や暮らしは、自分の力では取り戻せない。自分のことは自分で決めて暮らしていきたい、とする自己決定は、まずは利己の思いを凝縮させるようにして発信された。
その自己決定は、しかし、自分だけでは成り立たない。ひたすら利己としての自己決定を語りかけながら周囲を変え、自分も変わり、そして人々の共感の中、利他の発信に育っていった。
利他は利己を育む。
この社会のだれもが生きやすくならないと、自分も生きていけない。だから一緒にやりましょう、という認知症当事者の言葉に利己と利他が一致して共感を響かせ、今、コロナの日々とこの先の、私たちの地域社会の確かな流れとなろうとしている。